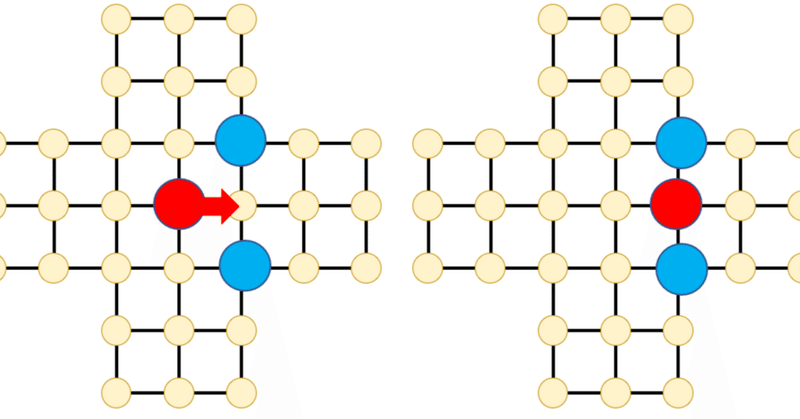
シーガっていう伝統的ゲームがありまして(4)
昨日からの続きです。
年代を追いかけながら調べなおしてみたところ、ハナヤマ社の創作ゲーム「シーカ」のルールは、長い年月をかけて、とってもゆっくりと変化していたこともわかりました。
ハナヤマさんの「シーカ」は、だんだん「シーンカ」してる・・・なんちゃって。
どうして「次第に・ゆっくり」ルールを変化させる必要があったの?
なぜに?と、私は思いました。
その背景事情は何だったのか?
想像してみるのって、面白いです。(後日、ラジくまるの考察を述べるつもりです。)
***
まず第一に1974年ごろのルールをご紹介します。
ハナヤマ社の創作ゲーム「シーカ」がはじめてこの世に出たのは、1974年ごろの事です。
PIECEというポケットゲームに収載されていました。
ルール詳細は、こちらの記事にまとめてあります。
要するに、ナナメにはさんだ場合も相手のコマを取れるという点において、伝統ゲームのSeegaとは、大きく異なっていました。
それから約20年後、再びシーカが販売されたのですが、ちょっとルールが変化していました。
HANAYAMA「ゲームクインテット・プラス1」添付のルールに書かれたシーカは、以下の通りです。(推定1989年ごろ)
***
シーカ 2 to 4 players
(1989年ごろのルール)
勝利条件:
自分のコマが1個以下になったら負け。最後まで自分のコマの個数が2個以上を保ち続けたら勝ち。
用具:
ソリティア盤。
赤青黄緑の4色、各8個ずつのコマ。

準備:
ゲーム盤に何も置かない状態からスタート。自分が分担するコマの色を決めた後、順番に1個ずつ任意の位置にコマを置いていく。
*必ず真ん中のマスは空けておくこと。
コマがすべて置かれたらゲーム開始。
遊び方:
コマはタテヨコの4方向に1マスぶんの距離だけ動かす。
*このゲームではジャンプなし。
自分の色のコマ2つで、相手のコマ1個を「タテ・ヨコ」いずれかの2方向ではさんだら取れる。


相手のコマ2個が、1マス空けて「タテ・ヨコ」に並んでいる時、その中心に割り込んだら、両側にある2つのコマを取れる。
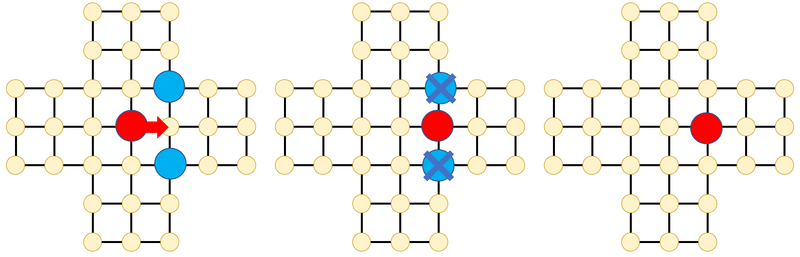
*「ナナメ」では、相手のコマを取れない。
*相手のコマ1個をはさんだら取れるが、相手のコマ2個をはさんでも取れない。
ゲーム盤のスミに対戦相手のコマ1個を追い詰めたら、それを取れる。

***
さて、さらに時は流れ、推定2013年ごろの事。HANAYAMA「ゲームスタジアムSD」添付のルールに書かれたシーカは、以下の通りになりました。
またしても、ちょっとだけルールが変化しています。
シーカ 2 to 4 players
(推定2013年~2024年現在まで)
勝利条件:
自分のコマが1個以下になったら負け。最後まで自分のコマの個数が2個以上を保ち続けたら勝ち。
用具:
ソリティア盤。
赤青黄緑の4色、各8個ずつのコマ。

準備:
ゲーム盤に何も置かない状態からスタート。自分が分担するコマの色を決めた後、順番に1個ずつ任意の位置にコマを置いていく。
*必ず真ん中のマスは空けておくこと。
コマがすべて置かれたらゲーム開始。
遊び方:
コマはタテヨコの4方向に1マスぶんの距離だけ動かす。
*このゲームではジャンプなし。
自分の色のコマ2つで、相手のコマ1個を「タテ・ヨコ」いずれかの2方向ではさんだら取れる。


*「ナナメ」では、相手のコマを取れない。
*相手のコマ1個をはさんだら取れるが、相手のコマ2個をはさんでも取れない。

ゲーム盤のスミに対戦相手のコマ1個を追い詰めたら、それを取れる。

またまた、明日に続きます。
ゲームシステムのデザイナーって、何なの?どういう意味? そんな疑問は、私の記事群によってご理解いただけるものと期待してます。 ラジくまるのアタマの中にある知識を活用していただけるお方、サポート通知などお待ちしています。
