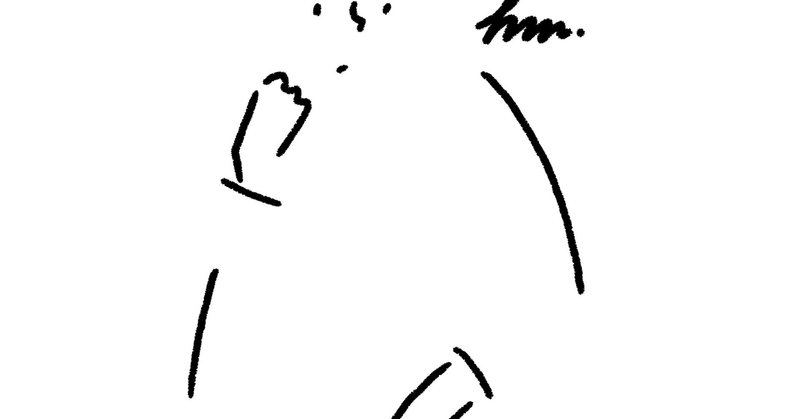
「捨て力」
心理学者のコリン・チェリーに提唱された
「カクテルパーティー効果」というものがある
「人はパーティーのような騒々しい場所でも、
離れていても自分の名前などはきちんと拾える。
つまり、意識の水面下で、人は常に周りを監視している」
といったもの
一方、生理心理学の授業では「注意」の視点から
「パーティーのような騒々しい場所でも、必要な情報以外は、すべて捨てることのできる人間の能力」
という形で取り上げられた。
私が上記との対比について質問すると
先生いわく、
「実際に聞こえる全ての音は、必ず鼓膜を震わせるし
映像も全て、網膜に写し出される。
そうした莫大な情報は全て意識化レベルで処理するわけではなくて
監視するというよりは、むしろ人間は情報を捨てる能力がすごいんだよ。」
とのことだった。
つまり、どんなにうるさいところでも
自分が注意を向けた声だけを拾うことができる。
そして他の多くの情報は、(顕在)意識にまで上ってくることはない。
注意を向けたものだけが、心と頭に焼き付くのだ。
◇
これからは、「情報の選択」がますます大切だという。
くしくも、「所有の時代」では
人、モノ、金、情報を
きちんと把握し
管理できる能力が求められていた。
今後はwithコロナ時代でも象徴されるように
「所有」という概念も薄まり
レンタル・シェア・ジョブ型
といった
新たな価値観が定着しつつある。
ユングのいう「集合的無意識」も
SNSのクラウドなどで具現化されているのが面白い。
今や断捨離は、世界共通言語となっているし
ブリッジズによるトランジション(転機)の考えでは
「終わり」を重要視している。
近江商人も「始末」の大切さを説いている。
つまり、「正しく終わって」こそ、新たな始まりがあるという。
人はつい「獲得」に目がいきがちなのかもしれないけれど
実は「捨てること」は
人体では同じくらい
もしかするとそれ以上に
多くのエネルギーを費やしているのだろう。
◇
2010年
第一次コンマリブームに乗っかった妊娠中の私は
2010個のものを捨ててきた。
2021年
あのときのお腹の子どもは10歳となり
UFOキャッチャーで獲得した謎の人形たちを
リビングルームに並べるようになっている。
今はそれらを
いかにバレないように捨てていくかに
細心の注意を払っている。
