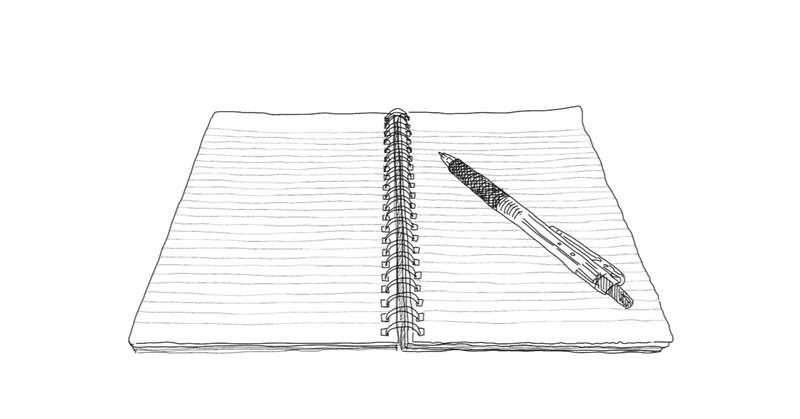
学びの意味
大学院でのまなびも1/4終わったね。どう?
友人から言われて、早いものだなぁ、と改めて思う。
授業はおおむねオンラインで
対面を好む主指導の先生がらみで週に3日は通学したが
大学内のWi-Fi環境が不安定なこと
我が家のリビングの方が快適だったり
夕食の準備をしながら学習できる等の理由で、院生室にもそう長居はしていない。それは他の院生も同じだ。
ちなみにゴリラの研究をされている
京都大学の山極教授は
「人間は、視覚と聴覚だけでもコミュニケーションをとったと錯覚できるが、やはり嗅覚、触覚も伴わなければ、本当の信頼関係は築けない」と述べられている一方
「今後は視覚と聴覚のみでも信頼関係が築けるよう、進化していく」可能性も示されている。
オンライン授業も、慣れてくると快適だ。
修士課程でのまなびも、前期にそこそこ単位をとったこともあり、2/3は終わった。
もちろん、これから本格的な修論の執筆が始まるので、本当に大変なのはこれからだ。
が、とりあえず思い返してみると
本当に実りの多い半年であった。
オンラインとはいえ
授業で意見を求められることも多く
そこで
「~について、改めて~な気付きがありました」
「~なことは、初めて知ったので興味深かったです」
なんて、お客様アンケートみたいなことを発言していたら、まるでその発言自体がなかったかのように
見事にスルーされてしまう。
やはりクリティカルシンキングで、ほんの少しでもモヤッとしたことがあれば
自分なりにきちんと言語化し、その原因の可能性や比較を示唆しながら、人に伝わるように発言しなければならない。
私はこれがすごく苦手で
普段いかに、いろいろなモヤっと感を流して生きてきたのか
再認識させられた。
そしてこれがひとまずの、大きな気付きと収穫だった。
思えば子ども時代から、分からないことは分からないなりにいったん頭を通過させ
もしくは疑いもなく落とし込み
後に全体像が見えてからまとめて考えるのが
私なりのやり方だった。
それでもあまり困らなかった。
そしてそのことを
そのままある先生に伝えてみたところ
「我々でも、私生活ではそんなにクリティカルに考えたりしない。いろいろ問題がでてくるし(笑)
なので、私生活と研究とで、スイッチで切り替える感覚を持っている」
とのことだった。
なるほどなー、、
いまだに私は、そんなに器用なことはできないが
最近気づけば
テレビなどのメディアを含め
無意識に多角的に物事を捉えている自分に気づく。
確かに以前から、そう心がけているつもりだったが
何て言うか
それまでとは質が違う感覚だ。
常日頃から、何かを調べ、ソース元の信頼性も考えながら引用をきっちり示すことの積み重ねが
知らず知らずのうちに
新しい自分の軸を作り始めていた。
と同時に改めて
何かの情報を鵜呑みにすること
すぐに効果のでそうな何かに飛び付くこと
一見魅力的でキャッチーな事柄など
人間の心情を揺さぶりつつ、それにとって都合の良い方向へ誘導していくものが
社会に溢れすぎていることを痛感した。
その、様々な「揺さぶり」で
一見新たな変化を感じたりもできるけど
それは皮膚の直下1㎝くらいまでしか深化しない感覚で
本当に内臓を通過し、「ハートや魂」まで届いたものは
これまでほとんどなかった気がする。
「自分の頭で考える」
使い古されたフレーズだが
ある意味、こんなに強力なツールは他にない、と断言できるようにもなった。
私のような人間でも
たったの半年で
見えてくる世界が変わる。
自分にとって
これ以上の学びの意味はない気がしている。
