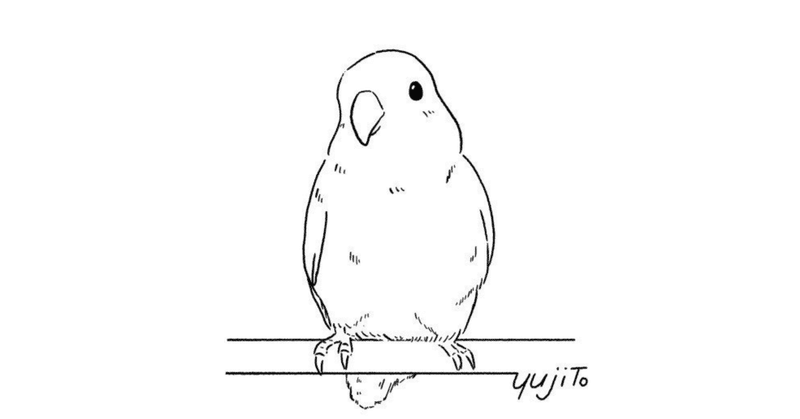
余白を考える
以前「スペクトラム」という記事で
色素の濃淡が移り変わるような変化について述べたが
それとは別に
ものごとには質的な変化を遂げる瞬間がある
いわば
生卵がゆで卵に変化する分岐点だ
人はいくつかの顔をもち
同時並行的にそれらの役割をこなす
それらが程よいバランスであれば
相互作用としてのリフレッシュ効果もある
しかしそれらのバランスが崩れたとき
一つの役割ばかりが肥大しすぎしたり
役割のページが増えすぎた時
ページをめくる指先もままならなくなると
たちまち心が固くなることがわかる
そのような
心が「ゆで卵化」した状態で
私の場合
ものごとの見方・捉え方は大きく変わってくる
例えば
とまり木のインコを眺めてほっこりするのも
心が固まっているとき
ゲージ周りの散らかりにしか目が向かなくなるし
季節の空気の移ろいや季節の花
その香りを楽しむ道のりは
車の往来と信号機の情報だけに留まってしまう
さらに、子どもの
「ねぇ、見て見て!」には
「別に今じゃなくてもいいのに」
という気持ちがざわめき
その瞬間の熱量だけが放つ宝物を
つい、見逃してしまうことにもなる
これらは
ストレージの空き容量が少なくなると
デバイスの動きが鈍くなる感覚に近い
個人的な体感では
あらゆることにおいて、4割程度の余白がないと
度々フリーズしてしまうようだ
◇
心の余白は
感性をふくらませる領域だ
そして
感性によってなお
心はふくらみ続ける
膨張した空気があたたかいように
ふくらんだ心には温かみがある
反対に
ちぢこまった心は固くて脆い
◇
時代は速度を増し
情報量は増え続けている
そこでは、合理性やスマートさが歓迎される
一方
人体や感情は相変わらずのアナログだ
最新のスマートツールを駆使しながら
半日おきには眠気がおそい
どこかにぶつかれば青あざをつくり
時々雑談をかわし
新陳代謝による排泄を繰り返す
こうした生理現象は
人類の始まりから進化を遂げることなく続いているし
そのようなムダや野暮ったさこそ
人間が生身である象徴と哀しみと愛しさに他ならない
◇
アナログな毎日は
SNSの切り抜きのような
分かりやすいコンテンツで溢れてはいない
余白という「ムダ」と「貴重品」を味わいながら
卵液を固め過ぎないよう
せめて半熟卵や温泉卵ぐらいであり続けたいと願う
だから今日もインコに癒されている
