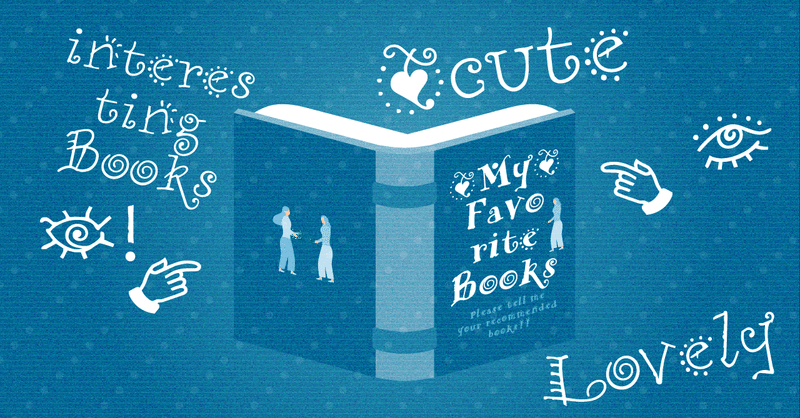
4月21日(木)2021年に初任者の先生へお勧めした本【らいざダイアリー#69】
みなさん、おはようございます。(こんにちは。)(こんばんは。)
本日、4月21日ということで、4月がスタートして3週間ということになります。
え?もう21日も過ぎたのかっていう感覚に陥っているくらい早いですね。
本題に入る前に、最近、反省したことを抽象的ですが書きたいと思います。
様々な情報が行き交う様子を目前にしていることもありますが、目の前が疎かになっていました。まずは、目の前をもっと丁寧にやっていきたいです。
(自覚しようとすると、やはり痛みを伴いますね)
さて、今日の記事は、2021年にカタリストさんに依頼されて書かせてもらった初任者の先生へのおすすめの本がテーマです。
こちらのnoteで、加筆・修正をして再投稿したいと思います。
『具体と抽象 細谷功』
今回、私がお勧めさせていただく本は細谷功さんの『具体と抽象』です。
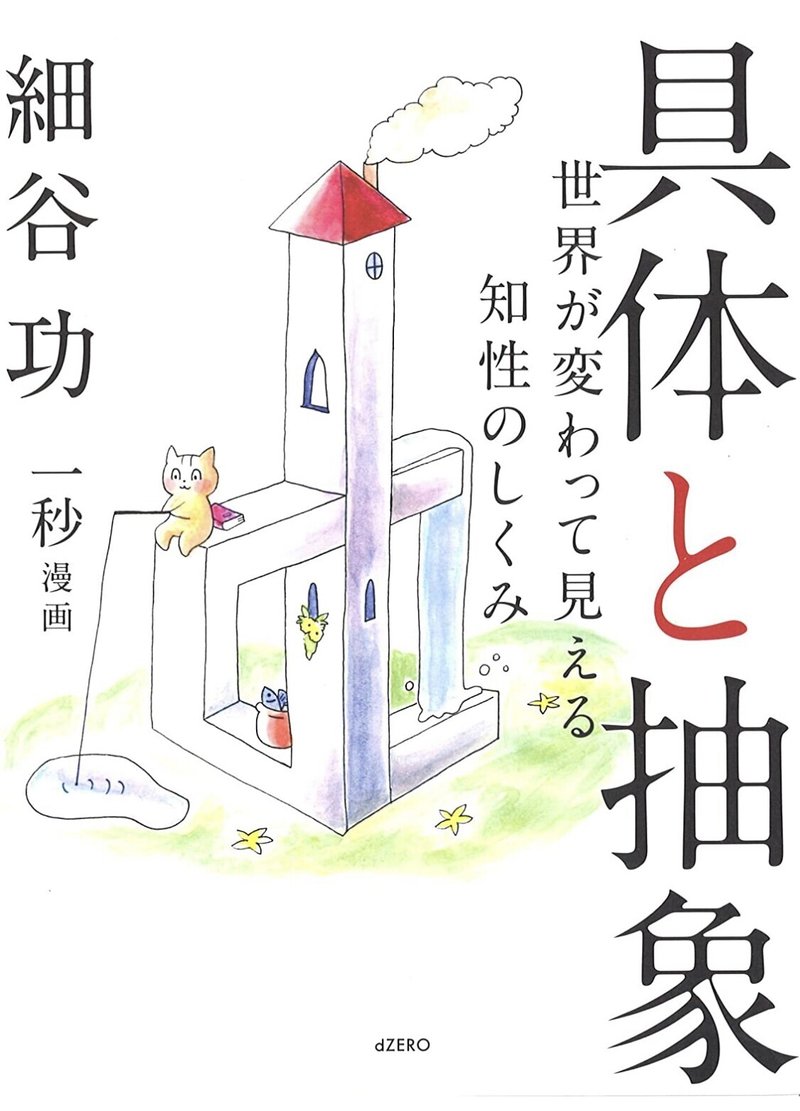
普段、あまり本を読まない人でも手を出しやすい約130ページほどの本で、漫画で表現している部分もあるので読みやすいです。
この本は、冒頭にも書いてありますが、分かりやすさとは逆行する本でもあります。
ただ、それが一番のポイントであり、教員として必要なことであると自分自身が実感したことがこの本をお勧めする本として選んだ理由です。
著者が一番に伝えたいことは、『具体と抽象を往復する』です。
これはまさに教育に関わる教師にとって、必要な視点だと思います。
4月も半ば、今年度から現場に入ったみなさんは、おそらく具体的なことに追われている生活でしょう。
また、残念ながらそれは暫く続いていきます。
始業式までも大変だったと思いますが、日々の授業に事務作業、行事の計画・準備・運営、校務分掌などなど、多くの具体が仕事として降りかかってきます。
必死に取り組むものの、余裕のなさから具体的なことは、いつしか作業となってしまい、本来の目的も見えづらくなっているのではないかと思います。
そんな中ではモチベーションも低下することでしょう。
そこで、この本でも紹介されている抽象化がプラスになります。
日々の具体的なことを全て作業のようにこなすのではなく、
その具体の目的がどこにあるのか?
そもそも、なぜこの具体が必要なのか?
というように、可能な範囲で抽象化してみましょう。
それで、作業だった仕事が目的をもって取り組めることもあると思います。
また、同じ目的を達成するための違う具体を自分なりのアレンジや工夫をして生み出す可能性も高まります。
もちろん、これは簡単でないことです。
しかし、これだけ教育界の問題がたくさんある中にもかかわらず、この職業についたからにはみなさんにも大きな目的や理想があるはずです。
その目的を達成するためにも、具体と抽象の往復が有効な手段の1つだと考えます。
最後になりますが、みなさんは、この教育界をともに明るくしていく仲間と思っています。
いろいろ大変なこともあると思いますが、自分の身体を労りながら、目的を見失わずにスモールステップで前に進んでいっていけたらと思います。
※2022年4月21日 加筆・修正済み
というわけで、今日の記事はここまで!
読んでいただき、ありがとうございました。
シェア(RT)バチクソに嬉しいです!
毎日更新してるので、フォローしてください!
記事を書くモチベーションになるので、あなたのスキ❤️を待ってます😘
お時間ある方は、昨日の記事や自分の記事で一番読まれている記事もついでにどうぞー!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
