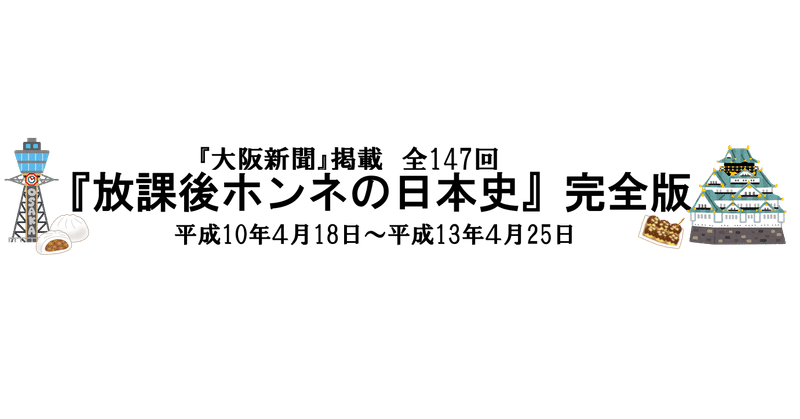
日本人の大発見⑨ 世界で最初に受像実験に成功した「テレビの父」・高柳健次郎
昭和10(1935)年、世界初のテレビ定期放送がドイツで行われました。翌年のベルリンオリンピックの中継や英国での正式放送の開始は、各国の研究者の意欲をかき立てました。その中に日本のテレビの父・高柳健次郎もいました。
高柳は明治32(1899)年に現任の静岡県浜松市に生まれました。工作が好きだった高柳は、静岡師範学校(現静岡大学教育学部)を経て、東京高等工業学校(現東京工業大学)付属工業教員養成所に進学しました。卒業後、工業学校の教壇に立つかたわら、自らのライフワークとなる研究テーマを見つけるため語学を学び、専門誌を読みあさりました。
ある日、洋書を読んでいた高柳は「テレピジョン」をテーマにした絵に釘付けになりました。そしてこれこそ自分か求めていたテーマだと確信しました。
まもなくチャンスが訪れました。大正13(1924)年、高柳は浜松高等工業学校(現静岡大学工学部)助教授に就任しました。まだラジオ放送すら始まっていないこの時に、「テレビの研究をしたい」と申し出た高柳に対し、校長の関口荘吉は研究費の捻出を快諾してくれたのです。
当時、1884年にパウル・ニプコー(独)が発明した「ニプコー(ニポー)円板」を用い、画を機械的に分解し、それを組み立てて受像する機械式テレビが登場し、1897年には、カール・フェルディナント・ブラウン(独)が電気信号を光画像に変える「ブラウン管」を発明しています。高柳は、画像の復元にブラウン管を用いる電子式を採用して研究を始めました。
ところが大正14年に関口が学校を去ると、研究費が止まり、やむを得ず高価な電子式をあきらめ、ニプコー円板を送像側に使った折衷式で実験を続けました。そして翌年、世界で最初のテレピ用ブラウン管を自作した高柳はそこに、イロハの「イ」の字を映し出すことに成功したのです。
高柳は昭和5(1930)年に「積分方式撮像管」を発明しています。これはロシア出身で、アメリカのテレビの父と呼ばれるヴラディミール・コスマ・ズボリキン(米)が1933年に発明した「アイコノスコープ」と同じ原理のもので、これまで弱点であった送像側の感度を上げる画期的なものでした。
国内の期待は大いに高まりました。すでに昭和7年に行われたある教育座談会で、「近い将来、テレピで公民教育を」という発言かNHK関係者の口から出ていたほどです。
昭和9年、欧米を禍察した高柳は、「他国と比べ基礎研究は90~95点。だが、実用化面では劣っている」と報告しています。他国に迫いつくため、さらに研究を進めた高柳は、訪米時にズボリキンと面会して得たヒントをもとに、翌昭和10年に全電子式のテレビを完成させました。
昭和12年に高柳はNHK技術研究所に移り、3年後に予定されていた東京オリンピックのテレピ放送の準備に携わりました。そして昭和14年、電波による準備放送に成功しました。オリンピック中止決定後も研究は続けられ、昭和16年5月には定期的な実験放送が開始されましたが、わずか2カ月で中止されました。そして大東亜戦争開戦後、実用化の一歩手前まで高められていたテレビの技術は、レーダーなどの研究に振り向けられました。
戦後、高柳は日本ピクターに移り、テレビ研究を再開し、昭和33年のテレビ本放送開始を感慨深く迎えました。高柳は昭和45年には日本ビクター代表取締役副社長、3年後には日本ビクター技術最高顧問に就任するなどテレビの改良や技術者の養成に努め、ハイビジョンの実験放送がたけなわとなった平成2(1990)年にこの世を去りました。
連載第126回/平成12年11月8日掲載
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
