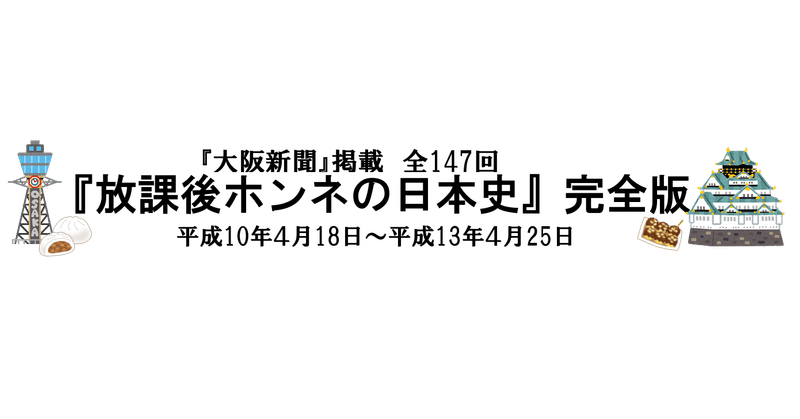
教科書が教えない軍人伝⑥ 宇垣一成(1868~1956年)
大阪市中央区にある高津神社の石の鳥居には、陸軍大将・宇垣一成の筆になる文字が彫られています。
宇垣は明治元(1868)年に岡山県の農家に生まれました。生後間もなく父を喪った宇垣は、小学校を卒業後、代用教員となりましたが、苦学の末に明治21年に陸軍士官学校に入学しました。明治33年に優秀な成績で陸軍大学校を卒業すると、田中義一の庇護を受け、長州閥の末席に連なるようになりました。
宇垣は 、田中軍務局長の下で軍事課長、田中参謀次長の下で第一部長、大正12(1923)年には田中陸軍大臣の下で次官となり、その手腕を発揮しました。そしてその翌年、清浦奎吾内閣に、宇垣は初めて陸相として入閣しました。
清浦内閣は第2次護憲運動によりあっけなく瓦しましたが、宇垣は次の加藤高明護憲三派内閣に留任し、懸案であった軍縮を断行します。世に言う「宇垣軍縮」です。
宇垣は陸軍内の猛反対を押し切って、高田(新潟県上越市)、豊橋、岡山、久留米の4個師団を廃止し、その費用を陸軍の近代化に廻しました。リストラされて余剰人員となった将校は中学校などに配属され、軍事教練の教官となりました。いわゆる「配属将校」です。この制度は、単に学生に単に軍事教練を施しただけではなく、一定時間以上の教練を受けた者に、幹部候補生となる資格を与えるというものでした。
宇垣の汚点は、極右のクーデター計画「三月事件」に関わっていたという疑惑があることです。
昭和6(1931)年3月、陸軍内の秘密結社桜会の橋本欣五郎大佐、右翼の理論的指導者大川周明らが、クーデターにより政権を奪取し、「宇垣内閣」を誕生させるという計画を立てました。 しかしこの計画は、宇垣自身の中止指令で頓挫します。宇垣がどこまで計画を知っていたのかは藪の中ですが、確実なのは、陸軍は、軍縮を行い、三月事件に乗らなかった宇垣に対する反発を強めたということです。
その後朝鮮総督となった宇垣は、農村振興運動を推進し、農村の食糧不足や負債を着実に減少させました。これは、戦後韓国で行われた「セマウル運動」の原形となりました。
昭和12年、広田弘毅内閣が総辞職すると、組閣の大命は宇垣に下りました。しかし陸軍は、自分たちの意のままにならない宇垣に対して、陸相を推薦しませんでした。軍部大臣現役武官制が前内閣で復活していたため、予備役の宇垣は陸相の兼任という手段をとれません。事態を昭和天皇に訴えることも考えましたが、それもかなわず、結局組閣できませんでした。ちなみに
昭和天皇は、三月事件のことで宇垣に対して警戒心を持っておられたようです。
その後、昭和13年に、第1次近衛文麿(改造)内閣に外相として入閣し、支那事変の和平工作に着手しましたが、結局それも果たせず、その後は政治の表舞台から姿を消しました。
戦後宇垣は、公職追放にあった後、昭和28年の参議院議員選挙でトップ当選を果たします。陸軍から阻害された「悲運の老将軍」のイメージが、国民的人気を獲得したのでしょう。
連載第68回/平成11年8月18日掲載
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
