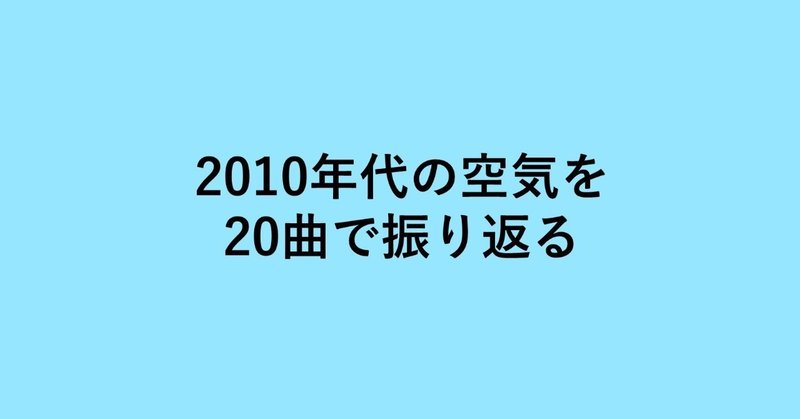
2010年代の20曲 _ ⑦SMAP 「Joy!!」 (2013)
※企画趣旨はこちら
みんなで踊れば怖くない
結果的にSMAPにとって最後の「世の中ごとになったシングル」となってしまった、という印象がある。赤い公園の津野米咲をコンポーザーとして抜擢するといういかにも「SMAPらしい」布陣で制作されたこの曲のサビに津野が放り込んだのは<無駄なことを一緒にしようよ>というエンターテイメントの真髄とも言うべきフレーズ。この言葉は20年以上にわたって日本のエンタメを更新し続けてきたSMAPが歌ったからこそ、その字面以上の輝きを放った。
そんなサビの歌詞のみならず印象的だったのが、この曲の振り付け。大サビの<自らJoy!! Joy!!>という歌詞を中居正広が<みんなでJoy!! Joy!!>と歌う(というか叫ぶ)のがテレビの歌番組での定番アクションとなったように、この曲の肝は多くの人たちをとにかく巻き込んでいく求心力にあった。2011年の震災以降、被災地に足を運んだり「SMAP×SMAP」でメッセージを発したりと「日本国民統合の象徴」とでも言うべき存在感を発揮してきた当時のSMAPにとって、「Joy!!」のメッセージはまさにぴったりだった。
おりしも、この曲と同じ2013年にはAKB48の大ヒット曲であり、アイドルシーンの枠を越えてJポップの歴史における重要な1曲となった「恋するフォーチュンクッキー」もリリースされている。多くの人たちのダンス動画がYouTube上を席巻することになったこの曲と合わせて、2013年は日本中が「一緒に踊った」1年でもあった。海外に目を向けても、ファレル・ウィリアムスの「Happy」のリリースが2013年11月。「Jポップのガラパゴス化」といった状況が語られ始めたタイミングで、「ダンス曲」に関して期せずして海外と歩調がそろっていたのはなかなか面白い(そのファレルは2014年に「SMAP×SMAP」に出演した)。2012年には中学校の体育の授業でダンスが必修化となるなど、日本人とダンスの距離が(表向きには)どんどん近くなっているタイミングでの出来事でもあった。
若い作家の起用、人々の価値観に訴えかける大きなメッセージ、そして多くのリスナーというか「国民」を巻き込むパワー。SMAPがやれることを存分にやりきった、とでも言うべき内容だった「Joy!!」。シングル盤にはデビュー曲から50枚分のシングル曲をつないだミックス曲が収録されるなど、パッケージとしてもメモリアルな1枚だった。この曲がリリースされてからたった3年後、彼らを取り巻く環境は急変する。
「さよなら」と「ご無沙汰」と
「公開処刑」。2016年1月18日の「SMAP×SMAP」で5人が並んだ姿は、後にこう称された。舞台裏のゴタゴタ、それもメンバー間の不和というよりはさらにバックにいる人たちのパワーゲームの帰結としてあんなものを見せられたら、その場から届けられる娯楽に対して素直に感情を預けることは難しい。2010年代後半はSMAPの一件を皮切りに、AKS、吉本興業と似たような案件が多数繰り広げられた(個人的にはここにハリルホジッチ元日本代表監督の解任劇も並べたい)。それは「時代を作ってきた」組織の裏側に実は蠢いていた(そして皆うすうすその存在に気が付いてた)ドロドロの発露であり、こういった案件がなぜか数年の間に立て続けに起こったことに「時代の移り変わり」を感じずにはいられない。
SMAPの解散については数多のうわさが駆け巡ったが、結局明確なファクトは「メリー氏が飯島氏を恫喝したこと」「SMAP×SMAPでメンバー5人が謝罪をしたこと」「SMAPが解散したこと」「中居正広と木村拓哉はジャニーズ事務所に残り、他の3人は<新しい地図>として再出発を果たしたこと」くらいだろうか。「確度の高そうな噂」はいろいろあったものの、それが「真実」かどうかを確認する術はもはや存在しない。
SMAPが思わぬ形で幕を引かざるを得ない状況に追い込まれた2016年、2010年を最後に「人間活動」に入っていた宇多田ヒカルが本格的な復帰作『Fantôme』を発表。ライフステージの変化に伴う言葉の変化のみならず、椎名林檎、KOHH、小袋成彬をフィーチャーした内容は「アーティスト間のコラボレーション」に関しても新たな地平を切り開いた。また、同年にはHi-STANDARDが新曲「Another Starting Line」をゲリラ発売。フィジカルでの販売にこだわるやり方には若干のズレたノスタルジーを感じてしまうところもなくはないが、自分も含めた多くの「現役キッズもしくは元キッズ」がCD屋に大挙した。
翌2017年2月には小沢健二がシングルCDとしては19年ぶりとなる新曲「流動体について」を発表。90年代の狂騒を<間違い>という言葉で表現しながら次の世代と自分自身、そして宇宙という大きな概念を接続していくポジティブなメッセージは古参オザケンファンのみならず「初めて“小沢健二の新曲”を体験する」という若い世代にも勇気を与えた。
巨星が不本意な潰え方をした一方で、「歴史上の人物」とされていたアーティストが続々と蘇った2010年代後半。音楽シーンの輪廻転生はこの先も続いていく。
もし面白いと思っていただけたらよろしくお願いします。アウトプットの質向上のための書籍購入などに充てます。
