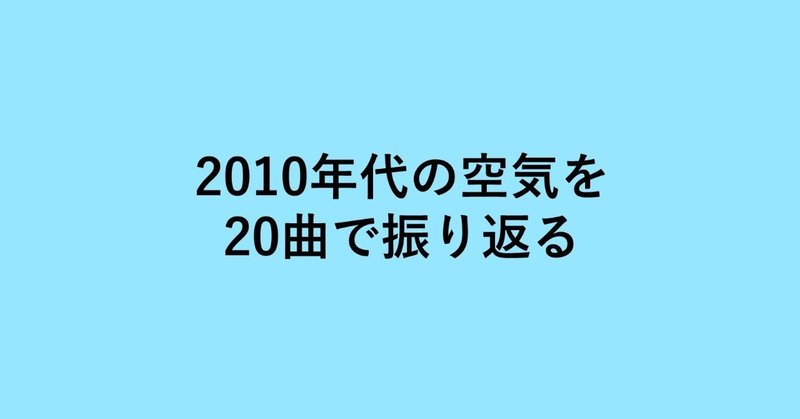
2010年代の20曲 _ ⑨BUMP OF CHICKEN feat.HATSUNE MIKU 「ray」 (2014)
※企画趣旨はこちら
必然だった「ロック」と「初音ミク」の邂逅
「今までならバンドをやっていたはずの才能が今ではボカロで曲を作っている」という話がよくされていたのは2010年代の前半くらいだろうか(ちなみに最近「今までならバンドをやっていたはずの才能が今ではラップをやっている」という旨の文章を読んだ)。おそらくハチ、後の米津玄師やwowakaといった存在を受けてそういった言説が出てきていたはずだが、フェスブームなどを通じてロックシーンに「一体感」といったキーワードが存在感を増していく中で内省的な表現の主戦場が移っていくような流れがあったと思われる。
そのような背景を考えると、ロックシーンの一つの側面を結果的に請け負っていった初音ミクというツールが改めてロックシーンと合流すること、そしてそのフロントを担ったのが日本のロックシーンの一つの精神性を象徴してきたBUMP OF CHICKENだったというのは非常に納得感がある。「ray」における初音ミクとのコラボレーションは、枝分かれした支流が再び本流に流れ込んでいくようなものだったのだろう。
「ray」にはバンプのみによるものと初音ミクも参加しているものという2つのバージョンが存在している。前者についても2014年7月13日のMステ初出演時、さらには2015年の紅白歌合戦でも披露されるなど彼らの代表曲の一つとしての地位を確立しているが、やはり重要なのは藤原基央と初音ミクの声が重なり合う後者のバージョンだろう。バンプが「デュエット」という形を取り入れている(しかもその相手が「生身の人間」ではない)こと自体の希少性のみならず、「男性と女性」「人間と機械」といった対比こそが喪失と再生の両面から人生を歌ったこの歌詞を表現するうえで最適なフォーマットであることを確信させてくれる出来映えになっている。
今の日本のロックバンドの大半が、その源流を突き詰めていくとバンプとアジカンにぶち当たるはずである。とかく「先がない」と言われがちなロックバンドというフォーマットにおいて、日本のオリジネイターは「ロック」の隣で新たに湧いていた表現の泉とがっぷり対峙することでロックバンドの新たな可能性を示した。
オタク文化上位時代との付き合い方
KDDIが行った調査によると、18歳~34歳の男性のうち約4割強、女性のうち約4割弱が「オタク」としての自覚を持っているという。その「オタク度合い」がどの程度かは確認できないし経年の変化もわからないので何とも言えないところはあるが、個人的な肌感覚としては「自分はオタクである」という形で自己紹介をすること、それに付随する形で何らかのアニメやゲームをフェイバリットとして挙げることがこの20年程度でよりしやすくなっているように思える。
「オタク=キモい」といったステレオタイプはおそらく世代が若くなればなるほど崩壊していっているはずだが、そういった流れの影響は音楽シーンにも当然ある。「アイドル戦国時代」を通じて「センスの良いアイドルソングを探すこと」に価値が見出されたことやアイドルグループがロックフェスに登用されるようになっていったのも、そういった社会の空気とリンクしている事象だろう。
「オタク」が市民権を得ることでアニメというもの自体が「大手を振って人前に出せる趣味」に格上げされていく中で、かつてはドラマとのタイアップで成し遂げられていたような作品との相乗効果がアニメにおいても多数生み出されるようになった。UNISON SQUARE GARDENのバンド最大のヒット曲であると同時に2010年代のロックシーンを代表する1曲となった「シュガーソングとビターステップ」も、もともとは『血界戦線』とのタッグによるものである。
文化のヒエラルキーというのは時間とともにどんどん変わっていく。ある時期までは日陰の存在だった「萌え」をコアの提供価値とするようなコンテンツは今では日本の中心的な文化になった。また、その過程において90年代には「娯楽の王様」だった音楽も今では「あくまでもいくつかある娯楽の一つ」となっている。2020年代が終わるころにはどんなパワーバランスが生まれているのだろうか。
もし面白いと思っていただけたらよろしくお願いします。アウトプットの質向上のための書籍購入などに充てます。
