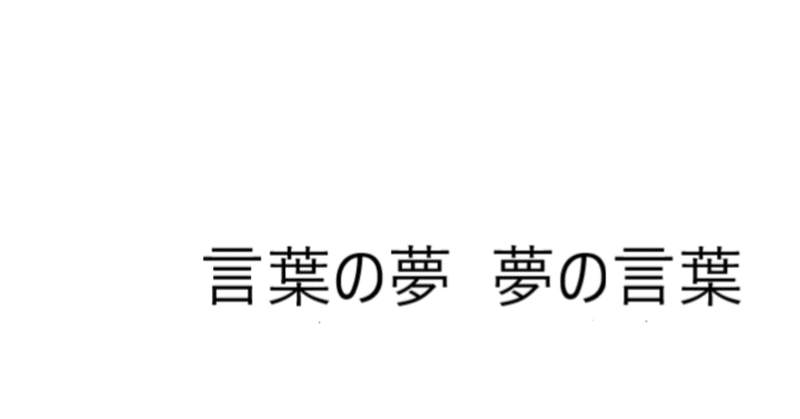
夢のからくり
うつる
川端康成作『雪国』の冒頭。汽車のなかの場面で、視点的人物である島村の思いとして「夢のからくり」というフレーズが出てきます。
この「夢のからくり」とは、一言で言うなら「うつる」ではないでしょうか。私にはそう思えてならないのです。
移る、映る、写る、うつる――。こう書くと、夢のからくりと言葉のからくりはとても似ているように感じられます。
*
具体的に見ていきましょう。
島村は移動のために汽車に乗っています。これが「移る」です。
闇を背景に汽車の窓が鏡と化して、通路を挟んで島村の斜め向かいの席にいる女を映します。これが「映る」です。
ただし、この作品では「映る」はほとんどつかわれず、「写る」という表記が選ばれています。
いずれにせよ、移動するガラスの鏡は完全な鏡ではなく、移りゆく外の景色と単調な車内の様子が二重写しになります。この「映画の二重写し」の描写について、小説ではくどいくらいの説明がなされています。
*
つぎに、二重写しの写しとは異なる「写し」と「写る」を見てみましょう。
ある女に会いに行く島村は人差指の匂いを嗅ぎます。人を「さす」指は島村の分身という意味での写しであると同時に、会いに行く相手の女性のある部分を「さす」写しであるともいえる気がします。これが「写る」です。
移り香、残り香――写しと写しの仲を取りもつのが、ありながら目に見えない匂いであるのは象徴的です。
【お察しのとおり、いまはエロチックな話をしていますが、「死人にものをいいかけるとは、なんという悲しい人間の習わしでありましょう。」ではじまる『抒情歌』に見られるように、川端における匂い(『抒情歌』では「香」にルビを振って「におい」と読ませています)は、現世の時空をこえたつながりさえ感じさせる要素でもあります。】
五指のなかでその腹がもっとも繊細かつ鋭敏であり、関節の動きにおいてしなやかで器用なのが人差指ではないでしょうか。人の分身だと言いたいゆえんです。
*
触角はいうまでもなく、生物の身体において、とがったものや突起した部分の多くには知覚機能が集中していて――だから面積がきわめて小さい、つまりとがっているのしょう――、文字どおりアンテナの役割を果たしているようです。
現在では人と世界をつなぐものとして、そして人が世界を触知するさいに大きな役目を果たしているのが指、とりわけ人差指と親指と中指です。なかでも人差指の働きは群を抜いています。パソコンやスマートフォンの操作のことです。
*
さす・差す・指す・射す・刺す・挿す・点す・注す。
こう書くと「さす」の多義性が匂ってくるようです。だからというわけではありませんが、まばらにまだらに読む癖のある私がこの作品を読むさいには、「差・指・射・刺・挿・点・注」という文字が目についてなりません。
【「写・射・斜・車」も気になるのですが、こうした私の習い性については「「うつる」でも「映る」でもなく「写る」」という記事に書いたことがありますので、よろしければお読みください。】
匂い(残り香・移り香)、形状、部分、器官、器具といった要素は、とりわけ文学作品において、「たとえる」いとなみを通して「写る」と重なります。「うつる」は「つなぐ」でもあるのです。
「さす」なしに、「うつる・うつす」も「つなぐ・つながる」もないと言いたいほどです。
*
汽車のなかの場面では、もう一つ写しがあります。汽車の窓ガラスに映る葉子は島村がこれから会いにいく相手の写し(コピー)であり、これも私にとっては「写る」なのです。
二人の女性が、かたわれ同士のように――まさにかたわれである場合もありますけど――男の目に映り、それが写しへと転じ(割れるのです)、男の視線がその二人のあいだを移ろう。
いま述べた目うつりと心うつりの展開は、川端の作品群でストーリーとしてあるいは細部としてさまざまに変奏され頻出します。
わかりやすいのは『古都』でしょう。冒頭で「樹上二株のすみれ」が登場する『古都』です。
われる、わかれる、うつる、うつろう。
「上のすみれと下のすみれ」(後の展開から「上」は「うえ」であって「かみ」でもあり、「下」は「した」であって「しも」でもあるでしょう)をはじめ、こうした動きと身振りが『古都』では図式的なくらいに出てきます。
*
写し、複製、コピー、レプリカ、片割れ、分身、模写、複写、再製。似ている、そっくり、ほぼ同じ。
同じや同一ではなく、あくまでも似ているのです。その隔たりが人をわくわくさせるのかもしれません。少なくとも私の場合にはそうです。
似たもの、似せたもの、贋もの、偽もの。
「似ている」を前にして人は目まいをおぼえ、惑乱におちいることさえあります。この私がそうです。
*
ここでは、さらにもう一つの写しを加えるべきだという気がしてきました。それは反復です。
窓に映る葉子と男の二人は同じ動作を「見ている島村がいら立って来るほど幾度も」くり返します。
ある情景がそれにつづく情景によって何度もなんども転写されていくものとして人の目に映る。こうした反復や模倣も写しといえるでしょう。
からくり
からくり人形を連想させる「夢のからくり」という言葉が、半ば鏡と化した窓ガラスに映る葉子と男の反復する身振りを受けて出てくることに、私は興味を引かれます。
(……)二人は無心に繰り返していた。
(……)二人は果てしなく遠くへ行くものの姿のように思われたほどだった。
(……)夢のからくりを眺めているような思いだった。不思議な鏡のなかのことだったからでもあろう。
(以上、川端康成『雪国』新潮文庫p.10・丸括弧は引用者による)
からくり、絡繰り、唐繰、機巧、機関。からくる、絡繰る。絡む、繰る。絡繰灯籠。絡繰眼鏡。
後述しますが、からくりに唐繰という漢字が当てられるのが、母語が日本語である私にはきわめて興味深く感じられます。まるで言葉のからくりを眺めているような思いなのです。
あてる、さす、うつる・うつす。
また「さす」を出しましたが、「さす」なしに「あてる」も「うつる・うつす」も「つなぐ・つながる」もありません。そもそも言葉は「さす」(なざす・さししめす)ものだからです。
*
移る、映る、写る。
どの「うつる」も二つのものや場所や時をまたぐ動きや働きであって、それが二重写しや移ろいや反復・模倣として人の目に映ります。
なお、「映る・映す」と「写る・写す」にかんしていえば、この小説ではほぼ一貫して「写る・写す」と表記されています。例外は「ふと火事が映っていると思わせたが」(p.162)と「天の河の光が映るかのようだった。」(p.170)くらいなのですが、見落としがあったら、ごめんなさい。
以上の表記の違いは『雪国』という作品の成立事情から来ているのかもしれません。1935年から1947年にかけて異なる雑誌で連作として掲載および改稿されたものが、そののちに単行本として刊行されたらしいのです。
このような作品の成立過程は川端康成の長編や中編でよく見られたと聞きます。たとえば、中編小説『死体紹介人』における表記のばらつきについて、「文字を見る」という文章でふれていますので、よろしければご覧ください。
*
「うつる」は、一方から一方への働きかけであるとは限りません。双方向的なつながりに見えたり(する・されるの関係)、逆方向の動きに見えたり(移動での進む方向と後ろへと流れる景色)もします。
いま方向という言葉をつかいましたが、夢のからくり(もちろんそんなものがあればの話ですけど)における「うつる」は、あくまでも人にどう見えるかどう感じられるかであり、うつつ(現実)の一部をなすと考えられている物理的な現象とは異なる文法(法則)にしたがっているようです。
*
こっちとあっち。これとあれ。いまとあのとき。いまといつか。するとされる。自と他。本物と偽物。異なると似ている。実物と複製。起源と引用。ものとかげ。闇と光。
うつつにおいて対をなすとされるものたちのさかい目やうつり目が不明に感じられるのが夢や夢うつつです。
夢では輪郭がくっきりしていながら――だからこそ「見える」のでしょう――、それでいて、さかいというものがまるでないかのように私には思えます。
*
夢とは、夢から覚めた思いが思い出したり思い浮かべたり、さらには思い描く「写し(おそらく、うつつのうつし)」でしかありません。そんなとりとめのない夢にからくりがあるとして、そのからくりがとりとめのないものであっても不思議はないでしょう。
とりとめられる夢。それはもう夢ではないはずです。
言うまでもなく、これまでここで述べてきたことは、ことごとく日本語とその表記にかぎっての話なのですが、日本語以外で夢を見られない私には、日本語以外の言語の修辞を弄しての夢のかたりはできないもようです。
まさに、かなわない夢でしょう。
似ている
移る、映る、写る。
「うつる」と口にすればたった一言なのに、文字にすると何通りかに書けます。これが文字のすごいところなのですが、この「言葉のからくり」の基本にあるのは、もともとこの島々にあったらしい話し言葉に、大陸から持ってきた文字を当てて分ける、という操作です。
私には、そのアクロバットもどきの操作が「夢のからくり」のように感じられてなりません。
大和言葉に唐(から)の文字を当てて分けたとはいえ、移る、映る、写るにさかい目があるとは思えないし、そもそも体感的にとらえられないのです。
当てても当たるわけではなく、分けても分かるわけではない。その意味では、うつつ(現実)もまた、からくりのある夢なのかもしれません。
からくる、からくり、からから、からまわり。
*
掻いても掻けていない。隔靴掻痒の遠隔操作。どんなに駆けてもぜんぜん駆けていない。移ったようでいっこうに移っていない。うつるといっても映ると写るばかり。
夢もうつつも、私にとっては、そのなかで、もがき、あがくしかない場です。なかなかいじることができないとか、思いのとおりにならないという意味で、まことにままならないものです。
いっぽう、思いや言葉は、たとえ思いのとおりにならなくても、とにかくいじることができます。夢うつつもそんな場である気がします。
*
庭のはずれに並んだ菊の末枯(うらがれ)が宿の燈か星明かりかで輪郭を浮かべ、ふと火事が映っていると思わせたが、その菊のうしろにも人が立っていた。(p.162・丸括弧内はルビで引用者による)
島村は自分の小さい影が地上から逆に天の河へ写っていそうに感じた。(p.163)
島村はやはりなぜか死は感じなかったが、葉子の内生命が変形する、その移り目のようなものを感じた。(p.172)
その必死に踏ん張った顔の下に、葉子の昇天しそうにうつろな顔が垂れていた。(p.173)
*
夢はたったひとりでうつろう夢。うつつはみんなでうつろう夢。
うつるがうつる。うつるはうつる。うつるにうつる。うつろにうつろう。うつろう、うつりめ。うつうつ、うつお。
夢のからくりと言葉のからくりは、やっぱり似ています。
※この文章は、「まばらにまだらに読む/書く」というマガジンにおさめます。
#川端康成 #夢 #言葉 #日本語 #和語 #大和言葉 #漢字 #文字
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
