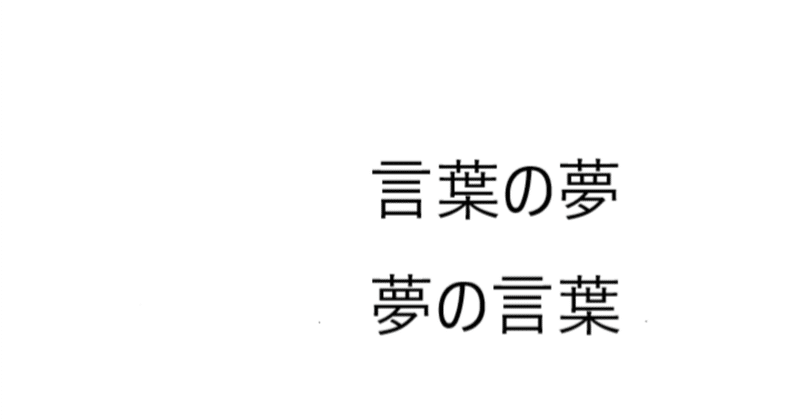
まばらにまだらに『杳子』を読む(11)
始まり、途中、終わり
『杳子』では、たとえば「左」「右」「上」「下」のように方向をあらわす言葉が、くどいくらいにくり返し出てきます。そうであれば、方向にこだわってみましょう。
小説は文字で書かれています。しかも、小説の文字列は線上に進んでいて、始まりと途中と終わりがあります。つまり、進行方向があるわけです。
私は小説の始まりと終わりだけを読むことがよくあります。これは癖と言うべきかもしれません。『杳子』も、「一」と「八」に目をとおすことが多いです。私には始まりと終わりは別格だという思いがあるようです。
*
私の印象では、「二」から「七」までは迂回だらけなのです。迂回は「一」と「八」にもありますが、「一」と「八」はまだましだという感じがします。
そうは言っても、「一」から「八」の8つの章は延々と迂回しつづけている ∞ なのです。無限でありメビウスの帯――。
これは単なる印象であって、検証はできません。だいいち、8 という数字は作品のどこにも書かれていないのですから。
あるいは、S(「七」p.133になって明らかにされる「彼」のイニシャルです)が、Sの字のように身をくねらす癖のある杳子といっしょになって、いわば似たもの同士として彷徨をつづけるから、∽ (相似 similarity をあらわす記号です)なのでしょうか。
それとも、SにSが引っかかったり、くっついて 、§ (セクション)とか。まさか……。
8から ∞ 、Sから ∽ や § だなんて、いかにも安易な連想ではありますが、こうした連想は私の偽らざる率直な感想でもあります。連想は私の大好物なのです。
*
というわけで、8つの章からなる『杳子』という作品は、「八」において ∞ が収束し終息するのでしょうか。
似たもの同士( ∽ )である、SとS( § )の延々と続く( ∞ )感のある迂回と彷徨と反復は終わるのでしょうか。
右、左
方向をあらわす文字では「上」「下」よりも「右」「左」が多いです。さらに言うと、「左」よりも「右」のほうがずっと多いです。不思議でなりません。
上、かみ、うえ。下、した、しも。
「かみ」「うえ」と「した」「しも」が異なるように、「回れ右をする」や「左折する」の右および左と、右大臣・左大臣の右および左とでは意味合いが違ってきます。
上座、下座、右翼、左翼の上下と左右も、なかなか感慨深いものがあります。つまり「深い」のです。これを追求すると、文字の向こうとか、文字の裏とか、文字の「深層」をさぐるという方向に行くでしょう。
ようするに、謎解きの方向へと傾いてしまいます。
文学作品を対象にして、そうした姿勢で研究をする向きがあるのかもしれませんが、私は知りません。
*
それにしても、この作品では「右」が目についてなりません。石ころくらいに右という文字が目につくのです。この作品のあちこちにあるという意味では、「右」という文字と「石」という文字は似ています。そっくりです。
右へ右へとまわって迂回するさいの「右」(方向)も気になりますが、次の「右」(右側)も気にかかります。
彼が右肩をさし出すと、杳子は自然に彼の右腕につかまってきた。
(p.24)
河原をしばらく下ると、沢が段々に左から迫ってきて、道は右岸の荒れた山肌を、人ひとりしか通れない細さでくねり上がりはじめた。彼は杳子の手を右腕からほどいた。
(pp.24-25)
上は「一」からの引用ですが、「彼」が杳子を右腕で抱いたり包んだりするという身振りは、「一」から「八」までほぼ一貫して出てきます。つまり、ふたりが並ぶと杳子はほとんどいつも「彼」の右側にいるという位置関係になるのです。
*
そう嘆いて、杳子は赤い光の中へ目を凝らした。彼はそばに行って右腕で杳子を包んで、杳子にならって表の景色を見つめた。
(pp.169-170)
作品の最後から二段落目からの引用ですが、最後の最後になっても杳子は「彼」の右側にいます。
右大臣左大臣という区別や、雛人形の並べ方、つまり右側と左側へのこだわりが、冗談には思えなくなります。
とはいえ、雛人形とか大臣について調べるのは面倒なので、漢和辞典(漢字源・学研)で「右」を調べてみました。
「右」という漢字の解説について、私が気になった記述は以下のとおりです。
・名付けに「あき・あきら」がある。
・「西、西のほうの」の意味がある。
・「みぎ。上位。上位の。」
・たっとぶ。大事にする。
・たすける。かばう。
・解字に「かばうようにして物を持つ手」「その手で口をかばう」とある。
なるほどと思ってしまいます。参考になりそうです。ただし、私は調べ物が得意でも好きでもないので、「だから何?」とは言いませんが、むなしさが残ります。
*
とはいうものの、どきっとする記述があります。収穫と言えます。
・名付けに「あき・あきら」がある。
・「西、西のほうの」の意味がある。
思いあたることがあるのです。
東、西、南、北
方向に注目するのであれば、方角や方位にも目を向けてもいいはずです。ただし、気をつけないと、古井先生が生前に風水に関心があったかどうかという下世話な話の方向に行きかねません。
(競馬通だっただけでなく(たとえば川端康成文学賞受賞作品の『中山坂』)、方角はもちろん地形や地勢を的確に見つめ描写していた(たとえば『東京物語考』)ことは先生の小説とエッセイを読んで知っていますが。)
そうしたアプローチもあっていいと私は思いますが、自分でやる気はありません。お勉強しなければならない複雑な体系は、大の苦手なのです。
*
さきほど、作品の最後から引用した箇所のシーン、つまり最後の最後になっても杳子が「彼」の右側にいる場面を詳しく見てみましょう。ラスト近くですし、きわめて大切だと思われる言葉が出てくるのです。
『杳子・妻隠』をお持ちの方は、ぜひラストのp.169とp.170、そして冒頭のp.8とp.9をご覧ください。
軀を起こすと、杳子は髪をなぜつけながら窓辺へ行ってカーテンを細く開き、いつのまにか西空にひろがった赤い光の中に立った。
「明日、病院に行きます。入院しなくても済みそう。そのつもりになれば、健康になるなんて簡単なことよ。でも、薬を呑まされるのは、口惜しいわ……」
そう嘆いて、杳子は赤い光の中へ目を凝らした。彼はそばに行って右腕で杳子を包んで、杳子にならって表の景色を見つめた。家々の間をひとすじに遠ざかる細い道のむこうで、赤みをました秋の陽が痩せ細った樹の上へ沈もうとしているところだった。
(pp.169-170・太文字は引用者による・以下同様)
上の引用箇所では、「西空」、「赤い光」、「明日」、「陽」、「樹」、「上」、「沈もうと」に注目したいです。以下に引用する、小説の冒頭と呼応する部分――相似する部分と相反する部分の両方――があります。
十月もなかば近く、峰には明日にでも雪の来ようという時期だった。
彼は午後の一時頃、K岳の頂上から西の空に黒雲のひろがりを認めて、追い立てられるような気持ちで尾根を下り、尾根の途中から谷に入ってきた。
(……)
谷底から見上げる空はすでに雲に低く覆われ、(……)
重くのしかかる暗さの底に、灰色の明るさを漂わせていた。その明るさの中で、杳子は平たい岩の上に軀を小さくこごめて坐り、すぐ目の前の、誰かが戯れに積んでいった低いケルンを見つめていた。
(pp.8-9)
上の引用箇所では、「明日」、「西の空」、「黒雲」、「谷・谷底」、「見上げる空」、「暗さの底」。「灰色の明るさ」、「すぐ目の前」、「低いケルンを見つめていた」に注目したいです。
*
この作品の冒頭の二ページと最後の二ページには、相似する部分と相反する部分の両方がある、つまり呼応しているのです。
対照と比較による図式化を促しているような細部に満ちていると言えます。共通点もあれば対照的な点もあるという意味です。要所のありようが対をなしていて、その作りは対称的とも言えそうです。
色
明(「あける」の「あけ」)と赤(あか)は同源らしいのですが、古井由吉の作品群では特権的な意味をもつと私は感じています。
「空ける」と「開ける」とも書けるところを、あえて「明ける」と書く表記を、古井は作家活動の初期から晩年にいたるまでほぼ一貫してもちいてきました。
古井の文章における「明」という文字は、「明ける」と「明日(あす・明くる日」と「赤・紅」とかかわる形でつかれているという印象をもっています。
*
明度という面から見ると、「一」の明度は低く、暗さをあらわす文字が頻出しています。それにたいし、「八」の明度は「一」にくらべればずっと高いです。
「一」の冒頭と「八」の終わりでは、共通して夕暮れ時の西の空が出てきますが、その明度はぜんぜん違います。
上、下
冒頭では、「彼」が山の頂上から下りて谷底の河原にたどり着いたところで杳子と出会うという設定になっています。上から下に降りた、明るい上から暗い下に降りたと言えそうです。
いっぽうの「八」では、「彼」が杳子の家の階段を上がり、二階にあって杳子がつかっている洋間に入ります。下から上へという動き、つまり移動が見られます。
下降と上昇です。
*
赤みをました秋の陽が痩せ細った樹の上へ沈もうとしているところだった。
(p170)
この箇所では日没の上から下へという動き(下降)があります。陽が樹の上へさしかかろうとしています。日が木の上に来るわけです。
このまま夕陽を見つづければ、日は木の下に沈むのがふたりの目に映るでしょう。沈んだ太陽は見えなくなりますが、残照があるかもしれません。いずれにせよ、木の下に日が来るのです。
杳
この文字を連想するなというほうが無理でしょう。私には無理です。「杳子」は、この小説のタイトルであり、この小説の冒頭の二文字でもあります。
杳、陽
杳、陽
「ヨウコ」はじつは「陽子」ではないか、「杳子」と明度が正反対の「陽子」だったのではないか。
そんな邪念が浮かびますが、「六」のp.117に杳子の手紙が引用されていて、「杳子」という署名らしき文字が見えることから、「ヨウコ」は杳子だと考えるのが妥当だと思います。
*
いや、そうかな、という思いもあります。杳子という署名はヨウコの書いたものだからです。陽子という女性が自分の名前の字を嫌って杳子と書く。そんなことがあってもいいし、似たような話を見聞きするからです。
「ヨウコさん、お茶ですよ」という声がして扉が静かに開き、敷居のむこうに杳子の姉が盆を支えて立った。
(p.157)
杳子とSのふたりにとって重要な位置を占めるであろう第三者の姉の発言のなかでの「ヨウコ」と地の文の「杳子」の書き分けが目につきます。
杳子とSのあいだだけで「杳子」とされてきたこの女性は、第三者にとっても「杳子」なのでしょうか。さらに作品の細部に目を向ける必要がありそうです。
*
いずれにせよ、小説の冒頭で、深い谷底で灰色の低い岩ケルンを目にしていた杳子は、最後にSといっしょに樹(木)の下へと降りていく赤みをました陽(日)を目にしているのです。「杳」のことです。
話は少し飛びますが、
睿は漢和辞典の解字の欄を見ると、「目+深い谷」とあり(漢字源より)、深い谷を見つめるさまが見えてきます。まるで『杳子』の冒頭ではありませんか。睿には「さとい、あきらか」のほかに「ひじり」なんて訓義もあるそうです。古井的な言葉とそのイメージを感じないではいられません。
(拙文「まばらにまだらに『杳子』を読む(08)」より)
なお、睿という美しい文字は、『古井由吉 文学の奇蹟』(河出書房新社)のインタビューをお読みいただくのがいちばんなのですが、講談社文芸文庫にある古井由吉の作品(集)の巻末にある年譜や、ウィキペディアの古井由吉の項をご覧になっても、その姿を見ることができます。作家古井由吉にとってというより、一人の人間古井由吉にとって、もっとも大切で愛おしい文字だったはずです。
*
樹・木、陽・日
赤みをました秋の陽が痩せ細った樹の上へ沈もうとしているところだった。
(p170)
「痩せ細った樹」にわざわざルビが振られているのに目が行きます。
わざわざと言うのは、このルビの前の「口惜しい」や「歓び」と、この後の「炙られて」にくらべれば、わざわざルビを振る必要はなさそうに思えるからです。
「痩せ細った樹」が「見て見て」と言っているように感じられないこともありません。「一」で「細」が出てくる箇所を以下に引用します。伝聞の形で出てくる杳子から見た「彼」(S)の様子です。
細長い軀の、背を獣みたいにもっさりまるめて、まるで薄い氷の上をそろそろと渡るみたいに、おさない目もとに不安を剥き出しにしている。
(p.22)
「八」では、「カーテンを細く開き」(p.169)、「ひとすじに遠ざかる細い道」(p.170)、そしてラストの一行にある「かすかな輪郭だけが細っていった」(p.170)というふうに、それほど隔たっていないところに「細」が三つあるも目について気になります。
もっとも気になるのは、やはり「秋の陽が痩せ細った樹の上へ沈もうとしている」にある「細」です。この「細」部が目についてなりません。
私にはこの樹がまるでSのように見えます。
日没である以上、この風景のなかで、陽と樹がどんどん遠ざかるのは確実です。明日という日があるにしても、です。
*
杳、陽
樹・木、陽・日
上、下、右、左、東、西、南、北
始まり、途中、終わり
色
「八」という章には、以上の要素がそろっている印象を受けます。
美しい
夕陽が沈もうとしているところを見つめながら、杳子は次のように口にします。
ラストの段落の直前の言葉です。
「ああ、美しい。今が私の頂点みたい」
杳子が細く澄んだ声でつぶやいた。もうなかば独り言だった。彼の目にも、物の姿がふと一回限りの深い表情を帯びかけた。しかしそれ以上のものはつかめなかった。帰り道のことを考えはじめた彼の腕の下で、杳子の軀がおそらく彼の軀への嫌悪から、かすかな輪郭だけの感じに細っていった。
(p.170)
「ああ、美しい。今が私の頂点みたい」は、「二」でのふたりのやり取りを思いださせます。
「山の頂上では何ともなかったのですか」
「ええ、とても幸福でした」
(p.34)
「山の頂上」では「とても幸福」だったと杳子は回想して「彼」に語ったのですが、ラストでは「独り言」のつぶやきである点が気になります。
「八」では、「繰り返す」と「反復」という言葉があれだけ繰り返され反復していたのに、反復とは正反対の言葉である「一回限りの」という言い回しが出て終わるのも気になります。
「一回限りの」は、「二度と繰返しのきかない釣合いを彼は感じた」(p.169)の「二度と繰返しのきかない」とも呼応します。
繰り返しと反復が終わったのでしょうか。
*
「ああ、美しい。今が私の頂点みたい」
(p.170)
最後の最後である場面でふたりが並んでいるのは確かです。ところが、作品内であれだけくり返され、つい数行前にもあった「右」という文字が、ここではなぜか見えません。
彼の目にも、物の姿がふと一回限りの深い表情を帯びかけた。
(p.170)
繰り返しと反復が終わったのでしょうか。同時に、彷徨による迂回が終わったのでしょうか。
最後の最後に来て、あれだけ冗漫なくらいに繰り返されていた「右」という文字が消えて作品が終わっているのです(この作品のなかでは、あってもいいところにないまま――これは私が反復に染まってしまったからの思いなのかもしれませんが)。
「右腕で杳子を包んで」(pp.169-170)いるはずなのに、次のように終わっています。
帰り道のことを考えた彼の腕の下で、杳子の軀がおそらく彼の軀への嫌悪から、かすかな輪郭だけの感じに細っていった。
(p.170)
彼の右側にあるのはもはや軀ではなく、細っていくかすかな輪郭の感覚だけのようです。
#古井由吉 #杳子 #方向 #方角 #色 #名前 #文字 #漢字 #連想
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
