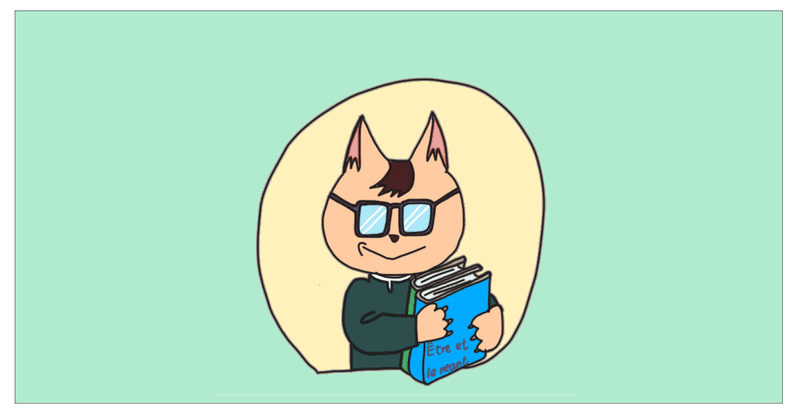
「芸術神学」批判序説 ~ 新しい公共劇場の在り方を模索するための省察 ~(3)
3.「芸術神学」、その礎石的「信仰」その2
~ 芸術には「真理」注入されている? ~
芸術作品の中には「真理」なるものが入っているのだろうか?
そう問う前に、そもそも「真理」とは何なのか?について考えてみる必要があるだろう。
「真理」、それは簡単に言うと、「神の〈ことば〉」だ。ちなみに、〈ことば〉を日本語とか英語とか、通俗的な意味での言語でイメージするのはよろしくない。たとえば、ピュタゴラス=ガリレオ路線でいうと、〈ことば〉とはむしろ〈数〉であり、「真理」を「神の〈ことば〉」と表現するよりは、「神の〈数式〉」とでも言い換えたほうが、彼らにとって違和感が少ないだろう。「神の〈ことば〉」を人間の言語と一緒にしてはいけない、とだけ指摘しておく。また、「神の〈数式〉」を求める運動である近代科学が西洋でこそ誕生したのは、アジアで誕生しなかった理由は、以上から、ざっくりと理解できるだろう。
この世界を造ったのは「神」である。しかも絶対「神」、超越「神」である、という「信仰」がすべてのベースにある。ちなみに、この西洋的絶対「神」について、超平易にその性質を説明するなら、さしずめツンデレとかいうやつだろう。いつも人間界のことを気にかけてくれるというデレ(人間大好き)ではない。むしろツン。たとえばプロテスタンティズムの予定説では、あらかじめ「神」によって救われる人間は選定し終わっているため、「神様、ぼくちゃん毎日頑張ってるよ」と今さら猛アピしたところで、神「そんなの関係ねぇ、そんなの関係ねぇ」としかならない。めっちゃツン。そのくせたまに(預言者を派遣するとか)デレてくれるから「信仰」は手放せない。
さて、「神」とは「完全」なる存在であり、全能者である。その「神」が造ったのがこの世界なのであるから、イッツ・ビューティフルワールド、世界はデタラメではなく、カオスではなく、秩序、がある。
秩序を注入!
そして、この秩序こそ、「神の〈ことば〉」「神の〈数式〉」であり、「真理」だ。
イッツ・ビューティフルワールド、「世界」「真理」は美しい。
ちなみに、昔から西洋では、イッツ・ビューティフルワールドであるべきところ、なんで「悪」なるものが存在しているのか?といった素朴かつ根本的な問題提起がある。ちなみに、プラトン(紀元前ギリシアの哲学者)はもちろんキリスト教徒ではないが、なぜ「神様が造った世界なのに、悪いものが混じっているのか?」という質問に対して、「神様は世界を造っているときに、つい、ちょっと、うっかり、よそ見をしてしまったからだ」と回答している。そう、なぜ「悪」が存在するのか? よそ見をしていたからである。
それで納得できる人は僅少だろう。ゆえに、キリスト教異端派が誕生することになる。簡単に言うと、「善」一元論ではなしに、「善/悪」二元論を導入しているのが異端である。正統派からすると、なぜ「悪」が存在するのか?について真面目にレスポンスするよりも、そういうことをほざくヤツは殺したほうがはやい、ということで、異端撲滅運動に邁進していく。共産主義に真面目にレスポンスするより潰したほうがはやい、イスラームに真面目にレスポンスするより潰したほうがはやい、「悪の枢軸国」は潰したほうがはやい、というのは、その伝統的戦術の亜型(現代の異端審問)とも言える。
さて、「神」は世界を造るとともに、「人間」もあわせて造った。しかも、自らの「似姿」として。この「似姿」というのは、わりと誤解を招くが、べつに「神」にも頭とか手とか足とかがついているわけではない。「神」と人間は似ている、というのは、そういう話ではない。ちなみに、日本人だと阿弥陀如来立像とか、普通に神様を偶像化(視覚化)してしまうが、キリスト教の「神」に対し、そんなことしたら、それこそ昔なら異端審問で火あぶりだろう。
人間が「神」に似ているというのは、身体が似ているということではなく、精神、もっと具体的に言うと、人間には「理性」が与えられている、ということに他ならない。
「理性」、仮にそれが「神」版「理性」の劣化コピー版(人間版「理性」)であるとしても、だ。
「神」は、人間に「理性」を授けた。
「理性」を注入!
ゆえに人間は、この「理性」を正しく用いれば、「神」とまったく同じものが見える、というわけではないが、それは言い過ぎだが、なんせ人間版「理性」だから、そこそこ同じようなもの、それこそ似たようなものが見えるようになる、ということになる。
じゃ、「理性」を用い、究極のところ、人間は何を見たいのだろう?
「真理」、言い換えるなら、この世界の真実、秩序、がソレである。
「理性」を用いれば、人間は「真理」に到達することができる、あるいは、せめてギリまで接近することができる、とする信念がこのとき誕生したのだ。
言い換えれば、これは「人間の〈ことば〉」によって「神の〈ことば〉」に迫っていくことであり、もっと言い換えると、その営みを、「哲学」と表記することができる。ちなみに、〈ことば〉をカッコよく「ロゴス」とでも呼ぶなら、哲学通には理解しやすいが、まぁそんなことはどうでもいい。
神学と哲学は大変相性がよく、近代に至るまで哲学は神学の相棒(あるいは下僕?)であった。
小括しておこう。
(1)哲学は「真理」に到達(またはギリ接近)することができる。
(2)なぜなら、哲学は「理性」を用いるからだ。
さて、いよいよ芸術について語ろう。
哲学が「理性」を用いるというなら、芸術は何を用いるのだろう。
「感性」、である。
ところが、「感性」は「理性」に劣る。ゆえに、長らく芸術は哲学に劣るものだとされてきた。
しかーし!
近代ドイツ思想(美学)の段階で、「いやむしろ芸術こそ(哲学よりも)真理を開示するんじゃないか」とかいう転倒した思想がでてきた。そのあたりの事情については、たとえば柄谷行人(1941-)が次のように語っている。
【一八世紀に「美学」という概念が登場したことは重要です。Aestheticsというのは、本来、感性論という意味であって、たとえば、カントは『純粋理性批判』の中で、もっぱらその意味でこの言葉を使っています。要するに、それは感性あるいは感情についての学問なのです。しかし、そこに、感性に対する新たな態度があります。感性・感情はこれまで哲学において人間的能力として下位におかれてきた。むしろそこから離れて、理性的であることが望ましかった。ところが、感性・感情が知的・道徳的な能力(悟性や理性)と密かにつながっていること、そして、それらを媒介するものが想像力だという考えが出てきたのです。想像力はそれまで、幻想をもたらすということで否定的に見られてきたものですが、この時期から、むしろ創造的な能力として評価されるようになった。】
『近代文学の終わり』(インスクリプト、2005)44頁
そういった考え方の到達点は、たとえばマルティン・ハイデガー(1889-1976)『芸術作品の根源』(平凡社、2008)などに見つけることもできる。ヴァン・ゴッホが描いた農夫の靴について、ハイデガーは「靴という道具が真実のところ何であるか」を知らせてくれるものだとし、そこでは「真理の生起が活動している」という。簡単に言うと、いくらリアル靴を眺めていても「靴という道具の真実」には到達できないが、芸術作品を通すことで、「真実」に到達することができる、ということだ。なぜなら、そこでは「真理の生起が活動している」から、ということだが、まだまだ何を言っているのか分からないだろう。説明が要る。さしあたり、「真理」にふれる専売特許が「神学-哲学」だけではなくなった、という点だけ、抑えておいてほしい。
そしてこの、なるほど神学は「神の〈ことば〉」=「真理」にふれるだろう、哲学もまたしかり、とはいえ、芸術もまたしかりなのだ!とかいう思想的土壌に咲いた花が、いわゆる「近代芸術」なのである。
「近代芸術」とは何か?
それは「真理」を開示するものである。
いや、前近代芸術だって、たとえば宗教画だって、「真理」(「神」の世界)を開示してるんじゃないの?とかいう反論はあるだろう。
それは違う。宗教画は「神」的世界をほのめかしているだけであり、いわば模造であり、「真理」を直接開示しているわけではない。
もっと言うと、ここに至って、芸術は神学から自律したのである。前近代的芸術は神学から自律できていない。
なぜか?
「近代芸術」が取り扱う「真理」とは、自己目的的に自律しているものだからである。
説明しよう。すでに述べたとおり、「神」が造った世界であるから、この世界には秩序=「真理」が宿っている。たとえば、リンゴは木から落ちる(=秩序)。寝て起きて、明日になってもやはり木からリンゴは落ちる(ここで、カンタン・メイヤスー(1967-)の思弁的実在論を持ち出されると話が超ややこしくなるので割愛させていただく)。
昨日も今日も明日もリンゴは木から落ちる、のであれば、いったん「神」がらみの話は棚上げしてもいいだろう。今や「神」がよそ見をしていても、やはりリンゴは木から落ちるのだから。秩序、あるいは法則と呼ぼうか、法則は、(もはや「神」が脇見運転していても)それ自体で自律的に在るのであるから、「神」云々はいったん括弧でくくり、法則それ自体を探求することができてしまうのだ。そして、これが、近代科学の誕生!であり、科学の神学からの自律、である。
それはべつに科学についてのみ言えることではなく、哲学も、そして芸術についても同じことが言えるようになった。
「神」の世界創造後においては、ポストでは、「真理」は自己充足的にそれ自体で在るのだ。「真理」は「自律的存在」なのである。
この「自律的存在」をつかむ芸術が「近代芸術」である。前近代的芸術とは根本的に異なる。また、「真理」=「自律的存在」を直接つかみにかかるため、「近代芸術」もまた何ものにも依存することなく、自律している。「近代芸術」が別名「自律的芸術」と呼ばれる所以である。
さて、ここで素朴な疑問が発生しよう。
(1)「神」が世界を造った。世界は「神の〈ことば〉」「真理」に満ち満ちている。
(2)人間は「神」から「理性」を授かった。
(3)「理性」を用いれば、人間は「真理」に迫ることができる。
(4)ちなみに「真理(神の〈ことば〉)」に迫ることは、神の意志に沿って(人間が本来あるべき姿で、人間らしく)生きることでもあるだろう。
(5)「真理」到達への道は、じつは「理性」オンリーではなかった。もっと言うと、神学や哲学オンリーではなかった。芸術も加えるべきだ。いやむしろ、芸術こそだ!
なるほど、そういう流れ(思想的展開)は分かった。
しかし具体的に、芸術はどのようにして、あるいはどのような理由で「真理」に迫れるというのだろう?
次回は、その話をします。
《またまた、つづく》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
