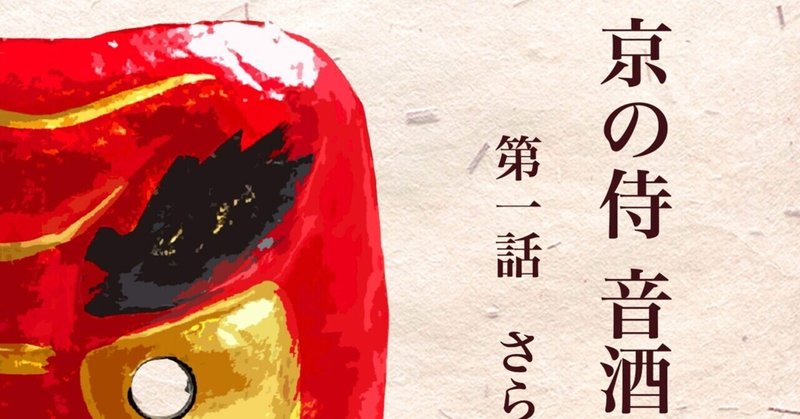
私が書いた物語のなかから(5)「ペンは剣より強し」
19世紀末、日本でいえば明治30年になる1897年に、ワシントンD.C.の合衆国議会図書館が開館し、そのトーマス・ジェファーソン・ビルの壁面に"The pen is mightier than the sword"という言葉が刻まれました。『ペンは剣よりも強し』と訳される言葉で、英国作家リットンの『リシュリューあるいは謀略』の一節に起源があるようです。この言葉は、ジャーナリズムを学んだ方なら誰もが知っている(はずの)言葉です。
2021年2月にデジタル発行した、拙書「音酒麒ノ介日乗第一話・さらば本坂丑之助」は、幕末の京都にふらりと現れた幕臣旗本の息子、音酒麒ノ介が主人公の活劇風エンタテインメント物語なのですが、第一話に登場する本坂丑之助を描くにあたり、どうしてもこの言葉を登場させたいと思い、ある人物がワシントンD.C.を実際に訪れ、この壁面を眺めたたずむシーンを入れました。
私も、出張の合間におれまで二度、この壁面の前に立ち、じっとこの言葉を噛み締めたことがあります。学生時代、海外で働くジャーナリストに憧れ、大学と大学院でジャーナリズムを学んだ者として、この言葉は心の支柱でもあり続けていたのもあります。もちろん、今でも、ジャーナリストではありませんが、心の奥深くにしっかりとこの言葉を刻みこんでいます。
作中で、ある図書館司書は語ります。
「…その言葉は我々の魂のようなものです。知りたい方には知ってもらう。いかなる武力もかなわない。司書という仕事に従事していると、これこそ我々の魂だな、と思います」
新聞やテレビだけがジャーナリズムではなく、図書館司書にとってもこの言葉はとても大切な言葉だと考えいて、図書館という機能も立派なジャーナリズムだと思っています。「言論の自由」には、何かを発言する自由だけでなく、知る権利もまた含まれていて、図書館という場は私たちにとり、とても重要な役割を担っているはずです。余談ですが、言論の自由の源泉にあるのは政治家の演説の自由で、英国の詩人で「失楽園」で有名なJ.ミルトンの「言論・表現の自由/アレオパジティカ」は、私たちの演説の自由を謳ったバイブルだと思っています。そして、政治家自らが言論の自由を否定するのは自殺行為なのだと気づいてもらいたいところです。
さて、幕末から30年ほど経った明治30年ごろ、ある白髪の日本人が、この壁の前にたたずみます。
その情景をある図書館司書が次のように語ります。
「…当時の司書の日記が何冊か、この図書館に保管されています。万が一と思って調べると、その人物の来館時の姿が描かれていました。わずか数行でしたが。あの壁の前にたたずみ、『ペンは剣よりも強し』の言葉を感慨深げにじっと見つめ、涙ぐんでいたようです。その人物は白髪だったようです」(拙書「音酒麒ノ介日乗第一話・さらば本坂丑之助」より)
250年を超える江戸時代という封建主義の歴史を終え、近代化へと向かう明治時代初期、気づけば専制主義的になり軍国主義の道をひた走り始めた当時の日本という国の様相に、白髪の人物は涙をこぼしながら、次の時代へと歩み始めたのかもしれません。希望に満ちた幕末から、希望が失われていく現実政治の荒波に立ち向かおうとする白髪の人物…。活劇風エンタテインメント作品ですが、数々の謎解きも楽しんでもらえればと願っています。中嶋雷太(本書は主要デジタル・ブック・ストアにて読むことができます。また、紙本はhttps://bccks.jp/bcck/168058/infoにて購入できます)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
