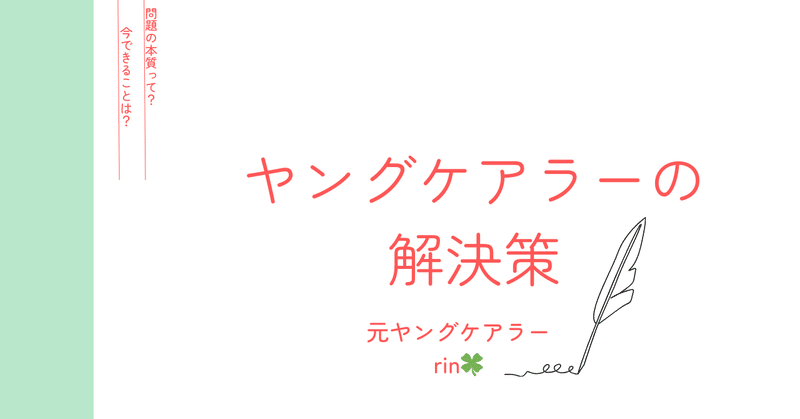
ヤングケアラーの解決策は?【過去ヤングケアラー7年行った私が書く】これが本質だと思います
「ヤングケアラーの解決策って何だろう」
「そもそも何が問題なの?」
「今すぐできることは?身近にできることはあるかな?」
こういった疑問についてお答えします。
私について
元ヤングケアラー。家事と学業の両立を7年続けました。
病気や苦労を乗り越え、現在はパートナーと二人で幸せに暮らしています。
①ヤングケアラーの解決策は、「大人と子ども、それぞれ役割が果たせる環境に身を置くこと」
私が思うヤングケアラーの解決策は、
「大人と子ども、それぞれの役割が果たせる環境に身を置くこと」です。
子どもは狭い世界で生きています。
本来の子どもの役割は、
大人がサポートしながら視野広げ、成長し、自立すること。
と、私は思います。
しかしヤングケアラーは誰かを支えるのに忙しく、
自分の成長を考える余裕がありません。
未熟の存在でありながら、誰かの気遣いで精いっぱい。
だから私は、ヤングケアラーの解決策として、
ヤングケアラーは子供らしく過ごし、
それを支える大人がいる環境が必要、だと思います。
「子どもらしくいられる」「大人から学べる」環境の具体例【過去ヤングケアラー7年行った私の意見】
ヤングケアラーを7年行って感じた、
私が大人(家庭)から教わりたかったもの/子どもが子供らしくいられる環境の、具体例まとめました。
大人(家庭で)から与えてほしかったもの/教わりたかったこと
社会とのかかわり方、社会とはどんなものか
その子にあった教育を受けられる
子どもの相談に乗る
子供の成長のサポートをする
子どもを守る(子どもが安心して過ごせる)
子どもらしくいられる環境
自分が感じたことを素直に表現できる
いろいろな経験を積める
生活の心配をしなくて済む
自分の心配ができ、それを周りに相談できる
見守ってくれる(過干渉ではない)大人がいる
② 【ヤングケアラーは家事や介護の支援だけでは解決しない】ヤングケアラーの本当の解決策は「子どもでいられる環境を見つけること」
私が思うヤングケアラーの本当の解決策は、
「子どもらしく生活できる環境を見つけること」です。
ヤングケアラーの問題は、
・学習時間が足りない、・休養の時間がない など、さまざまですが、
本質は家族という社会がうまく回らず、それが
子どもの健やかな成長の弊害になっていると、私は思います。
経験からお話しします。
私は15歳の時、交通事故で母親を亡くし、
そこからヤングケアラーになりました。
母が亡くなってから家庭は崩れ、
父も姉も荒れてしまい、顔を合わせることが少なくなりました。
その時私は、ご飯づくりや洗濯ものに忙しくしていましたが、
もしその時家事自体がなくなっていたとしても、
おそらく健康に育たなかったと思います。
心の面では、どこにも安心できる場所がなく、
食事は簡単なものや外食が多くなったと思います。
同じ悲しみの中、家族を責めるつもりはありませんし、
そういう事情になので、誰かがやるのは仕方ないと思っています。
でも、「誰か」ではなく、家族で協力し合い、
支え合える関係ができていたなら、
おそらく違う結果になっていたと思います。
親は親(大人)としての役割をはたし、
子どもは周りと自分を大切にして、自分の実力をつけていく。
ケアのサポートも大切ですが、
それができる環境が重要だと、
私は思います。
③ どうしたらいい?【今ヤングケアラーの方へ】【周りの大人の方へ】
【今ヤングケアラーの方へ】
大人と会話することを勧めます。
相談ではなくても、日常会話をするだけでも違います。
日常会話をすると、
自分がわからない(言葉にできない、整理できない)問題も、
大人が気づいてくれる可能性がある自分の状況が、客観的にわかることがある
逃げ場ができる可能性がある
などがあります。
また、本を読むこともおすすめします。
私がヤングケアラーの問題を乗り越えたのにも、読書の力がありました。
私は親に生活や生きることを教わることができず、
恥ずかしい思いや失敗を何度もしました。
そこで、本から教わりました。
おすすめは
お金の本 (投資/働くこと/社会保険/年金/納税/経済など)
健康についての本(食べ物/病気/女性は子宮・卵巣・生理なども)
生き方の本 (社会情勢の評論/心の持ち方/暦、年中行事など)
などです。
【周りの大人の方へ】
私が思うのは、
ヤングケアラーの子にただ寄り添うだけでも力になると思います。
例えば
「次の日曜日、運動会だね」
「朝早く起きてるの、知ってるよ」
「この時期は●●がおいしいよ」
など、
その子を認めたり、嬉しいことを話すなど、
普通に接してくれる人がいるだけで、安心すると思います。
ヤングケアラーは我慢のし過ぎで、
自分の気持ちや言いたいこともわからない可能性があります。
また、私の経験ですが
「あの子の家は苦労してる家だから」
「あの子はあまり話さない子だから」
という理由で。避けられた経験があります。
一般的な家庭の子と同じように接してくれただけで、
私はとても嬉しかったです。
また、募金やボランティアなどもあります。
ヤングケアラーの子に力を貸していただければ、嬉しいです。
今回もご覧いただきましてありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
