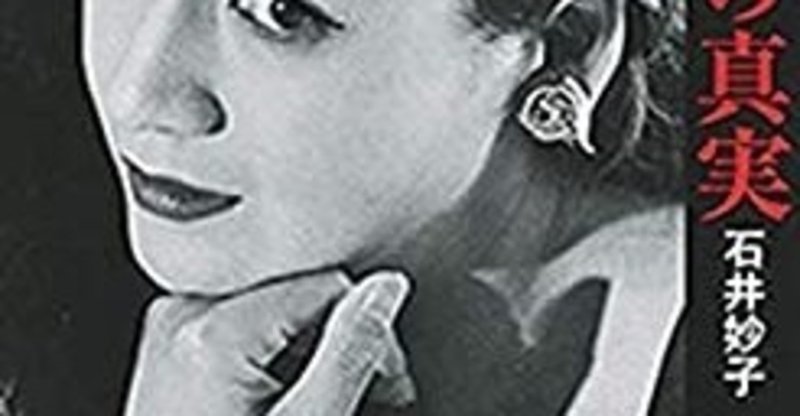
「ボランティア情報2020年8月号」市民文庫書評『原節子の真実』石井妙子著 新潮文庫(とちぎボランティアネットワーク編・発行)
『原節子の真実』石井妙子著 新潮文庫 定価(税込み)791円
評者 白崎一裕(那須里山舎)
コロナ禍の酷暑の中、75年前を振り返る映画表現をいくつか鑑賞した。自然災害と人災の入り混じったような現在の「事態」において、定まった対応もなく揺れ動く国民や国家の右往左往を自らのことに重ねて自己嫌悪に陥りながらの「8月15日」への回帰である。
今夏のコロナ禍社会であらためて考えさせられたのは、「戦後民主主義」とは何か、という課題である。ちょうど、昨年だろうか、作家の三島由紀夫が、1968年の東大全共闘とおこなった討論集会の記録映画が編集・公開されて話題になった。その三島は、おそらく戦後日本の在り方に反省を迫る意味で市谷の陸上自衛隊市谷駐屯地で割腹自殺を遂げた。また、戦後の民主主義進歩派知識人のスターであった政治学者の丸山真男が「戦後民主主義の虚妄に賭ける」と1964年当時自著のあとがきにおいて発言したことが、過去に話題になったりした。しかし、「戦後民主主義」を再考するときに、本書の主人公、原節子の映画界からの引退と半世紀におよぶ「隠遁生活」という事実は、上記の知識人たちの行動や発言をはるかに超える深さと重さをもっていたことが確信できるのが本書である。
原節子が最後の映画「忠臣蔵」に出演をし、この映画が公開されたのが、1962年(昭和37年)である(正式な引退は1963年とされる)。その後、マスコミ等の取材を拒否し、公の世界に登場することもなく2015年に95歳でこの世を去る。
原は、家庭の事情から当時新進気鋭の映画監督でもあった義兄のすすめもあり、14歳で映画女優としてデビューする。当時の映画女優の社会的地位は決して高いものではなく、彼女は、家計を助けるために、やむなく女優の道を選択した。その原節子が、国民的スターとなるきっかけは、ナチスドイツと日本との日独軍事協定締結を円滑に進めるために、アジア人種に偏見の強いドイツ国民向けの日独合作国策映画に出演したことであった。原は、この映画の宣伝のために、ドイツ・欧州を公演旅行して、その日本人離れした容姿などでドイツ各地において評判となる。ここから、アジア・太平洋戦争の「戦意高揚の女神としての原節子」が誕生することになる。彼女は、1942年の『ハワイ・マレー沖海戦』をはじめ『決戦の大空へ』、『勝利の日まで』、『望楼の決死隊』などの戦意高揚映画に数多く出演している。実際、原自身も、強い信念の「軍国少女」であった。
その原は、敗戦をどのように受け止めたのか。戦意高揚の宣伝として「利用」されてきた映画が再興されるとも思わず、彼女は、「地方に移住して畑仕事でもしようかと思う」と同僚女優の山田五十鈴に語っている。ところが、映画人たちは、実に変わり身が早く、占領軍のGHQの戦後の「民主化」に便乗して、戦後の「民主化啓蒙」映画を撮り始めるのである。戦争中、戦意高揚映画をとっていた監督が、自らの作品の「軍国的」な部分を差し替えて、米占領軍(GHQ)を刺激しないものとして再上映しようとさえする。原は、このことを批判的に考えていて、のちのインタビューで「―――8月15日一日を境にして、こうも器用に変えられるとするならば、そんな程度のものなら、「映画ッてなんだろう」と考えました」と言っている。そんな彼女も、戦前の家父長制的な職場(映画界)や社会から解放される「戦後民主主義」の息吹を感じている。そして、戦後民主主義のイメージを代表する作品である「青い山脈」などの映画に出演し、原は、「戦意高揚の軍国の女神」から「自由と民主主義の女神」へと変身をとげる。しかし、これは、けっして、原自身が望んでいたものとは違うのだ。それは、あくまでも、一般大衆の欲望が創造した幻影のようなものである。
小津安二郎と原のコンビによる世界的名作「東京物語」の最後のほうのシーンで、小津は、原節子扮する「紀子」に「わたし、ずるいんです」といわせている。このセリフには、中国戦線で辛酸をなめた小津と戦中の苦しい時代を生き抜いた原の本心が含められているといってよいだろう。戦後の大衆は、戦中の死者の思いを忘れ去り、ひたすら物質的な豊かさの上の幸福を追い求めている。それは、本当に戦後民主主義なのだろうか。そこにある戦後という時代そのものの「ずるさ」を自省する意味を問う「東京物語」であった。
原節子は、戦後を静かに告発すべく、テレビの勃興と共に消費社会的映像に変容する映画界を、ひっそりと去ったのだと思う。原が戦後すぐに感じた、かすかな解放を私たち戦後生まれは、本当に継承しているだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
