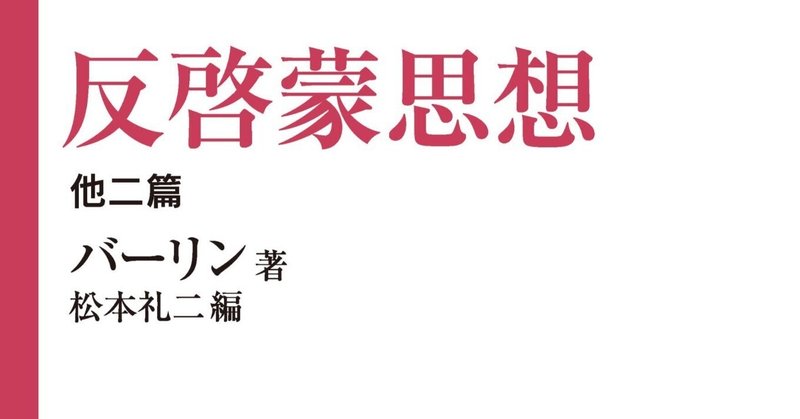
バーリン『反啓蒙思想』
アイザイア・バーリンの『反啓蒙思想』を読んだ。
バーリンは日本においてはそこまで有名ではない。事実私もこの本を読むまで彼の事を知らなかったし、Wikipediaに掲載されている以上の情報を知らない。バーリンの経歴を軽く紹介しておくと、1909年にラトビアに生まれたが一次大戦の戦火から逃れるべくロシアに移住し、最終的にはイギリスに移り住んで生涯をそこで過ごした。オックスフォード大学にて教鞭を取り近代政治思想を中心に著作活動を行っていたが、彼の最も有名な業績は自由主義に関する思想的貢献にある。著作「自由論」において自由という概念を"積極的自由"と"消極的自由"に二分したことは”自由”に対する新たなる議論を呼び起こした。
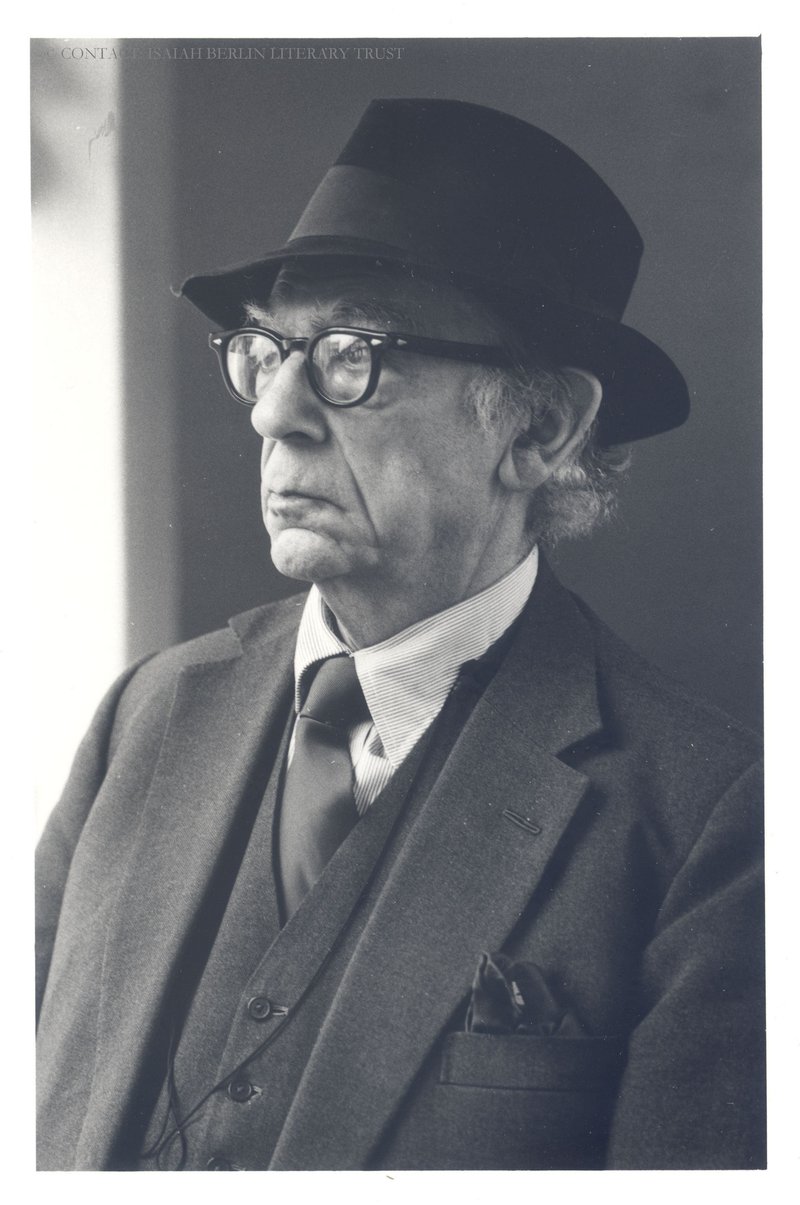
© The Trustees of the Isaiah Berlin Literary Trust 2000–2020
Isaiah Berlin Online(https://isaiah-berlin.wolfson.ox.ac.uk/node/2594)より
この本は『バーリン選集』のうち、「反啓蒙思想」(原題:"The Counter-Enlightenment")、「ジョセフ・ド・メストルとファシズムの起源」(原題:"Joseph de Maistre and the Origins of Fascism")、「ジョルジュ・ソレル」(原題:"Georges Sorel")の3つの論文によって構成されている。反啓蒙と題されているように、そのどれもが啓蒙思想に対する批判についての論文である。
バーリンは啓蒙思想に対する批判を検討していたが、あくまで彼は啓蒙思想を部分的に継承した自由主義側の人間である事を予め述べておきたい。すなわち、バーリンが行った啓蒙批判は改革・改善としての意味を持った批判であり、その点ではカントの理性批判と共通していると言える。
反啓蒙思想
第1の論文である「反啓蒙思想」では啓蒙思想に対する批判を総括している。啓蒙思想はキリスト教的ヨーロッパ社会からの脱却と科学的思考を元に人間社会を合理的に設計する事を目指していた。その思想が具現化したのがフランス革命である。フランス革命の市民革命としての意義は非常に大きかった。しかし、合理性を追求した急進的革命は混乱をもたらし却って失敗に終わった事は歴史からも明らかである。
科学の進歩は多大なものであった事は間違いない事は誰しもが認めているが、それを人間にも適用させようとする思想に対する批判というのは啓蒙思想と同じくらい古くから存在するという。ウィーゴを始めとした思想家による啓蒙思想の哲学的側面からの批判や自由意思の領域を狭める科学の進歩に対する反動として人間の創造行為の礼賛を行ったロマン主義が主にある。また人間の本質は暴虐的であると断定し、それを抑える手段として旧世界的な絶対的権威を是としたジョセフ・ド・メストルのような独創的な面からの批判もある。バーリンはド・メストルの独創性に注目していた。彼に関しては第2の論文にて詳しく考察されている。
ジョセフ・ド・メストルとファシズムの起源
ファシズム。自由や平等を否定し、国家の権威を高め全体主義の名の下において国民を服従させたこの思想は、ナチス・ドイツの台頭と20世紀前半におけるかの悲惨な第二次大戦を引き起こす事となった。バーリンはファシズムという恐ろしい暴虐的な思想の起源を、その200年程前に見出した。法律家の家系に生まれ、貴族の一員として列せられていたジョセフ・ド・メストルはフランス革命時代に生き、その変化を間近に観ていた。彼は合理性を酷く嫌悪し、非合理的なものとされ当時徹底的に排除されていた絶対王政、そしてカトリック教会の権威を大いに評価していた。人間とは生来的に暴力的でかつ無力な存在であると見なしており、世界とは全く楽観視出来るものではなく、悲観的であり、血生臭い争いや耐えがたい受難が必然的に降りかかるという。故に人間の統治は絶対の権威によってのみ可能であると繰り返し主張した。そして教会や王政のような絶対的権威を亡き者とした啓蒙思想は、徹底的に糾弾されるべきであって、その先陣を切っていた科学者、特に自然科学者は国家の敵であるとまで考えていた。またド・メストルは抽象観念を無価値であるとも考えていた。世界の文化は固有のものであって、それらの共通項を見出そうと抽象化し、隠された関係を見つけ出す事を嫌った。
ド・メストルはロシア帝国のサンクトペテルブルクで過ごしていた時期があった。ロシア帝国の政治顧問として招かれ、そこで彼はロシアが他の西欧諸国のような科学的自由主義の影響を受けていない事を称賛し、帝国の絶対的権威を維持するための様々な警句――自然科学的思想、自由思想の影響を排除し、農奴性はまだ維持すべきである――と助言した。実際彼の助言の一部は政策として実施され、大学教育から哲学、美学、経済学等が追放された時期があった。かの有名なドストエフスキーやトルストイにもド・メストルの影響を垣間見る事が出来る。
ジョセフ・ド・メストルは絶対的権威に取りつかれていた。彼のカトリック教会への賛辞の数々は信仰それ自体というよりかは教会が1000年以上にも渡ってその権威を維持し、ヨーロッパ社会を統治していた事にあるかもしれない。彼の主義や主張は全くの独断であり、非合理の塊である。議論の場において彼のような偏狂的な主張は無視される。しかし20世紀の動乱を経験したものであればその政治思想は人間の闇の側面を明確に浮き彫りにしたという点においては、啓蒙思想に代表される楽観的理性信仰よりかはずっと、人間の実態を正確に表現していたと言う。ド・メストルはある意味で次の時代に来る恐ろしい未来を予見していた、とバーリンは分析している。彼は人間の存在を血と闇に結び付ける事に固執していた。正しき、罪なき人間でさえも災難に遇う事があるのは、責任というものは個人ではなく集団が負うものであるからと考えていた。ド・メストルは他の反啓蒙思想家とは異なり、単なる保守的な神秘主義者ではなかった。明らかにその内にはファシズム的世界観の原型を有していたのである。
ジョルジュ・ソレル
3つ目の論文にて述べられているジョルジュ・ソレルはド・メストルとは対照的に、一般には一貫した思想を有していないと見なされている。レーニンを称え社会主義を擁護したかと思えば、ムッソリーニに連帯を示したりと、その思想には特異的な面が見られる。しかし、バーリンはソレルの隠された観念を明らかにし、彼の思想の根底には一貫した信念があったと述べている。
ソレルは人間の持つ創造的な自由を高く評価していた。人のありとあらゆる行為というのは自発的であり、論理的分析によって型に当てはめるようなものではなく、何者かによって使役されたりするものでもない全くの自由であると考えていた。人間は行為の主体であり対象ではない。自然法則を人間の領域にまで拡張しようとする啓蒙主義的世界観は人間の自由を妨げるものであり、生涯嫌悪した。人間らしさについて焦点を置いていた点ではロマン主義者と意を共にしていたと言える。
その一方ソレルはマルクス主義の労働により創造を行う人間という世界観を継承した。彼は労働者階級を共同体への連帯、自己犠牲、家族、愛といったものに価値を置く事のできる唯一の道徳的存在であると見なしていた。しかし彼は絶対的な道徳価値の存在を確信していたため、マルクス主義の唯物史観については否定した。プロレタリアートによる政治というのも結局は彼らが嫌悪するブルジョアジーの支配と何ら変わりないと考えていた。彼にとっては支配階級に対する労働者階級の闘争の過程こそが重要であった。それは道徳的正義の具現に他ならないからである。
ソレルはデモクラシーに対しても冷ややかな目で見ていた。民主主義とは妥協の極致であり、それは根源的な悪に対して対抗する正義の力を弱めるものに他ならないと考えていた。
彼はムッソリーニを「政治的天才」と評したり、レーニン達による社会主義革命を多大に評価した。特にレーニンに対して一層高い評価を与えている。しかし、ソレルは真のマルクス主義者でもなければファシストでもない。ファシズム批判を行っていた事からもそれは明白だ。本質的にはモラリストである。ソヴィエトの中央集権的政治体制は明らかに彼の思想とは相いれない。この点はマルクスも意を同するであろうが。ファシズムとの親和性についてもソレルの反自由主義、知識階級への反感、反ユダヤ主義に帰せられる。
彼の発言の支離滅裂さは多くの人々を失望させた。ムッソリーニはソレルの著書をファシズムの宣伝材料として利用したが、彼が大きな賛辞を贈ったレーニンについては終生ソレルを無視していた。彼は孤独であった。しかし人間の自由な意志と絶対的道徳の確信は合理主義に対する人々の不満を明確に言語化したという点で現代社会の政治・社会問題にも展開する事が出来るだろう。
総括と感想
バーリンは18、19世紀の思想家たちが持っていた世界観を20世紀に起きた諸現象に照らし合わせた。特にド・メストルとファシズムを結び付けた「ジョセフ・ド・メストルとファシズムの起源」は圧巻である。
ド・メストル、ソレルの思想は当然のことながら全くの非合理性に溢れている。しかし彼らが持っていた反啓蒙的観念は人間理性を楽観視した啓蒙思想よりもずっと現実的であり、人間の実態を表していたのである。
私は合理主義や自由主義に賛同し、これを擁護する立場の人間である。しかし反啓蒙思想の根源を分析する事で啓蒙思想の欠陥と失敗の原因を明らかにする事が可能になる。自由と平等に対する反感――ジェンダー問題やポリティカル・コレクトネスに対する批判、人文科学の縮小――こうした問題を大衆の過ちだけに起因しようとするのではなく、教師的立場の側――人文学者、急進的左派――、インテリの自己批判と再出発が必要なのではないかと思う。そうしなければファシズムや原始共産主義のような破壊的思想が、かつてのナチス・ドイツやクメールルージュの台頭のような恐るべき現実として具現化する事になるだろう。
参考
1) バーリン著、松本礼二編、『反啓蒙思想 他二篇』、岩波文庫、2021年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
