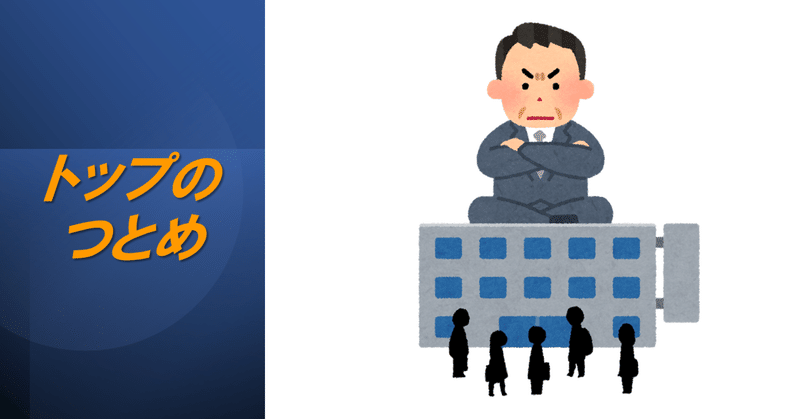
『稲盛和夫一日一言』 12月21日
こんにちは!『稲盛和夫一日一言』 12月21日(木)は、「トップのつとめ」です。
ポイント:企業のトップに立つ者は、自分の能力を企業に100%注入できてはじめてトップといえる。プライベートな時間すらとれないほど厳しいもの。
2016年発刊の『稲盛和夫経営講演選集 第5巻 リーダーのあるべき姿』(稲盛和夫著 ダイヤモンド社)の中で、「トップは無私の心でことにあたる」として、稲盛名誉会長は次のように述べられています。
西郷南洲の思想をまとめた『南洲翁遺訓』の最初にある言葉は、混迷を極める今だからこそ、たいへん大事なことだと思います。
【遺訓一条】
廟堂(びょうどう)に立ちて大政を為すは天道を行ふものなれば、些(ち)とも私を挟みては済まぬもの也。いかにも心を公平に繰(と)り、正道を踏み、広く賢人を選挙し、能く其職に任(た)ふる人を挙げて政柄(へいせい)を執らしむるは、即ち天意也。夫れゆゑ真に賢人と認むる以上は直に我が職を譲る程ならでは叶はぬものぞ。故に何程国家に勲労有る共、其職に任(た)へぬ人を官職を以て賞する善からぬことの第一也。官は其人を選びて之を授け、功有る者には俸禄を以て賞し、之を愛し置くものぞと申さるる。
【訳】
政府の中心となり、国の政(まつりごと)をするということは、天道を踏み行うということだ。だから、少しでも私心をさしはさんではならない。徹底的に心を公平にして正しい道を踏み、広く賢明な人を選び、その職務をちゃんとはたしていける人をあげて政治を執り行わせる。これが天の意である。だから、賢明で適任だと認める人がいたのなら、すぐにその人に自分の職を譲るべきなのである。国に対してどれほどの手柄があった人でも、その職をうまく務めることができない人に官職を与えて賞するのは一番よくないことだ。官職というものは、その人を選び、それに適任の人に授けるもの。功績のあった人にはお金をあげて大切にすればよいのだ。
ここでは、政治家のことを例にしていますが、中小企業の経営者であれ、どんな小さな組織であれ、トップに立つ者はこういう心構えでなければならないのだと、私は読んだ瞬間に思いました。
つまり、トップに立つ者は天道を踏み行うものであって、少しでも自分を大切にする思いをさしはさんではならない、と西郷は述べているのです。この言葉に出会って、私は身震いしました。
当時の私は、まさに100%、会社経営に没頭していました。「個人の時間など一切ない」とさえ思っていたほどです。
企業でもNPOでもどんな団体でも、組織は本来、意思も意識も持っていない無生物であるはずです。しかし、組織のトップに立つ人間が、その組織に意識、いわば生命を吹き込むことによって、組織は生物のように活動をし始めるのです。
経営者たる者、四六時中会社のことを考えていかなければ、会社が機能しなくなるとすれば、個人というものは一切ありえなくなってしまいます。
しかし、それは実際には、どんなに厳しいことかと私は思い悩み、自問自答を繰り返していました。個人にかえるときがなければ、人間は生活をしていくことはできません。しかし、なるべく私人としての自分が、個人にかえる時間を少なくし、社長という公人としての意識を働かせる時間を多くとるようにする。つまり、自分自身のことは犠牲にしてでも、会社のことに集中する。それがトップの義務なのだと、深く悩んだ末に思い始めた、ちょうどその頃に、先ほどの西郷南洲の一節に出会ったわけです。
私は、「これなのだ」と思いました。自己犠牲を厭わず、常に組織に思いをはせることができるような人でなければ、トップになってはならないのだということを、西郷南洲は教えてくれているように思いました。(要約)
2007年発刊の『人生の王道 西郷南洲の教えに学ぶ』(稲盛和夫著 日経BP社)第一章 無私 「人の上に立つリーダーは私利私欲を捨てて正道を歩め」の項の締めとして、名誉会長は次のように述べられています。
無私の姿勢を貫き通すことは、一見非情だと思われるかもしれませんが、多くの人の上に立ち、集団を統率していくためには、何としても身につけなくてはならない、リーダーの条件であろうと考え、それを自分に課してきたのです。(要約)
「無私の姿勢を貫き通す」
トップ、リーダーの立場にある者が必ず身につけなければならない基本姿勢ではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
