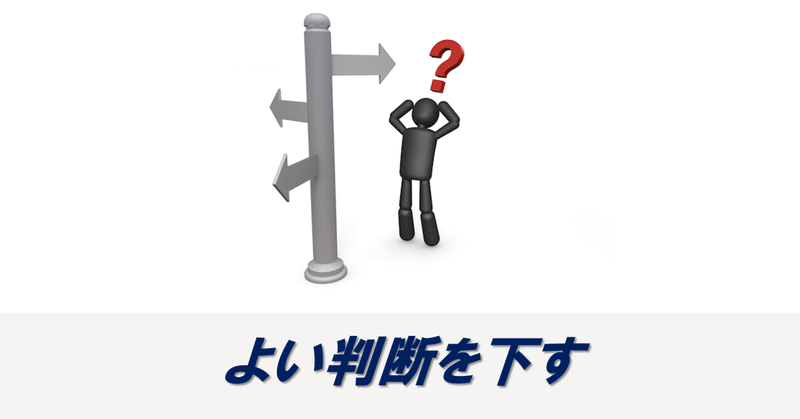
『稲盛和夫一日一言』 10月3日
こんにちは!『稲盛和夫一日一言』 10月3日(火)は、「よい判断を下す」です。
ポイント:日頃からいい加減な判断をしていては、ここぞというときによい判断は下せない。どんな些細な問題であっても集中し、真剣に考える習慣を身につけなければならない。
2015年発刊の『稲盛和夫経営講演選集 第2巻 私心なき経営哲学』(稲盛和夫著 ダイヤモンド社)の中で、「リーダーシップと判断基準」と題して、稲盛名誉会長は次のように述べられています。
リーダーとして勇気を持って、自分の組織に影響力を及ぼした人であれば、その人の判断が現在の組織をつくっている、といえるでしょう。また、個人の人生の場合も、その人の現在をつくっているといってもいいかと思います。
さすれば、我々が判断をする場合には、判断の基準というものがたいへん大事だということは皆さんにもご理解いただけるかと思います。
一番悪いのは、自分の利害得失が判断基準となっている場合です。例えば、自分の面子、地位、恰好などを基準として判断することです。
このような判断のおおもとをたどっていくと、人間の本能にたどりつきます。本能とは、その起源からして主観的で利己的なものです。
次にあるのが、理性、理性心が判断基準となっている場合です。理性は推理推論するためのものですから、主観的で利己的な本能に比べれば、客観的なものです。しかし、この理性は、ありふれたことに対する判断なら別ですが、人がやったことのない、前例のないことを判断しようとするときには一定の限界があるものです。
実は理性を超えた先に、魂のレベルでの判断というものがあります。私は、魂の本源なるものをベースとして判断をしていけば、間違いがないと思っています。
何事も決断する場合には、「動機善なりや、私心なかりしか」と自問し、それをかたくなに守り続けることが必要です。
組織のリーダーが持つべきは、素晴らしい心根と哲学だろうと思います。それがリーダーの価値を決めていくのではないでしょうか。
確かに、強引に引っ張っていくような強いリーダーのもとでは、立派な業績が上がります。しかし、それはある瞬間には成功しても、決して長続きはしません。一見大成功を収めたように見えても、すぐ没落するという例はいくらでもあります。そのようなリーダーは真のリーダーとはいえません。
リーダーシップを発揮したけれども、その発揮する方向が間違っているというケースは数多くあります。だからこそ、そのようなリーダーが素晴らしい哲学を持ち、魂のレベルで判断をしていけば、ダイナミックなリーダーシップを発揮し、素晴らしい成功を収めると同時に、それを持続することができるのです。(要約)
ここでは、よい判断を下すには、何事も「動機善なりや、私心なかりしか」と自問し、それをかたくなに守って魂のレベルで判断することが必要である、と述べられています。
では、常にそうしたよい判断を下して間違いを犯さないためにはどんな心構え、トレーニングが必要なのか。それは、頭の良し悪しには関係なく、どんなに些細なことでも真剣に考える習慣を身につけることです。
最初のうちは頭の回転も遅く、あれこれと悩みながら考えていても、それを十年、二十年と繰り返しているうちに、素晴らしい冴えを発揮できるようになっていきます。そうなるために、名誉会長は自分から能動的に意識を集中させる「有意注意」で判断力を磨け、と説かれています。
たとえ細かいことであっても、集中して深く考え、魂のレベルで判断を下す、という習慣を身につけることができれば、判断力は必ず研ぎ澄まされていき、「よい判断」をし続けることも可能になるはずです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
