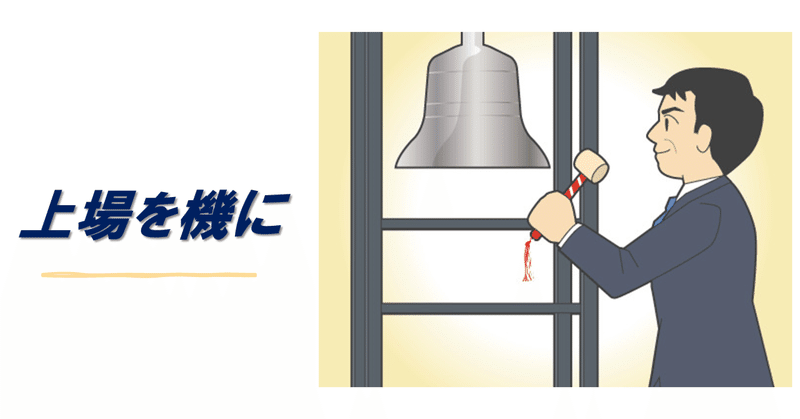
『稲盛和夫一日一言』 9月7日
こんにちは!『稲盛和夫一日一言』 9月7日(木)は、「上場 ①」です。
ポイント:上場したからには、社員やその家族のことばかりではなく、一般の投資家の方々の幸せまでも考えて、これまで以上にひたむきに働く。経営者の責任はより大きく、重くなる。
2002年発刊の『ガキの自叙伝』(稲盛和夫著 日本経済新聞社)の中で、京セラが初上場した1971年当時を振り返って、稲盛名誉会長は次のように述べられています。
会社が成長してくると、株式上場の誘いがくるようになる。私は創業当初から全員参加の大家族主義を目指してきた。そのポリシーで社員持ち株を推奨し、株主の80%は社員だった。ただ、資金需要は年々膨らんでいたし、雇用確保も難しくなっていた。
創業から13年目の1971年10月、大阪証券取引所第二部と地元の京都証券取引所に上場することにした。上場するには、三つの方法がある。
一番目は、旧来の株主が保有する株を市場に売り出す方法で、会社を創業するのに苦労のあったオーナーら古い株主に莫大なプレミアムが入る。二番目は、会社が新株を発行して市場に公開する方法で、上場時の株式代金は会社に入る。三番目は、両者の折衷案。
証券会社はだいたい一番目を進めるが、私は二番目を選択した。創業者利益を得る方法ではなく、会社の自己資本の充実を選んだのである。
会社を豊かにしておかなければ、不確実な社会情勢のなかで企業は生き残れない。パートナーである従業員のためにも、余裕資金を蓄えておく必要がある。個人の利益より企業の利益にウエイトを置くのが、経営者として当然の責務であると考えたからだ。
上場初日の夜、滋賀工場のグラウンドで祝賀会を開いた。
私は「今までの働きづめの苦労が吹き飛ぶほどうれしい。しかし、喜んでばかりいていいのか」と切り出した。そして、「これからは社員とその家族のほかに、投資家や株主にも責任を負うことになる。その人たちは京都セラミツクが今後さらに業績を上げていくと期待して株を購入してくれた。つまり、勝ち続けなければならない宿命を持たされたわけだ。永遠に走り抜く責任と覚悟を持とうではないか」と呼びかけたのである。(要約)
今日の一言には、「私は当時三十歳代後半を迎えていましたが、上場を機にこれまで以上にひたむきに働こうと思ったものです」とあります。
京セラの経営理念は、「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」
名誉会長は、この経営理念について、次のように述べられています。
この会社は稲盛和夫が大株主となって成功したいためのものではない。この会社で働く全従業員が物心両面において幸福になるためのものだ、としたのです。しかしそれだけでは、社員が幸福になりさえすればいいのかともとられかねないので、人類社会の進歩発展にも貢献するということも謳うことにしました。
それから60年以上が過ぎましたが、この経営理念をベースに経営を進めてきたことが、現在の京セラの発展をもたらしたのだと私は考えています。(要約)
長年、会社員として過ごした私には、残念ながら自社を株式上場した経験はありませんが、例えば、昇進してより大きな組織のリーダーを任されたとき、また子どもが生まれてより強く家族というものを意識するようになったときなど、「これを機に、今まで以上に一生懸命働いて、メンバーや家族をもっともっと幸せにしていかなければ」と決意を新たにした経験はあります。責任の重さはさまざまでしょうが、皆さんも、そうした経験は少なからずお持ちでしょう。
自分のためだけではない、より多くの人のために頑張ろうとすること。そうした気持ちは、びっくりするほどのパワーを我が身にもたらしてくれるものなのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
