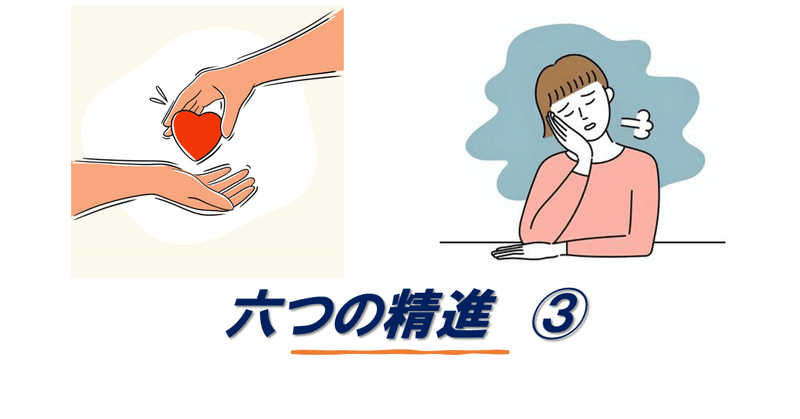
『稲盛和夫一日一言』 3月3日
こんにちは!『稲盛和夫一日一言』 3月3日(日)は、「六つの精進 ③」です。
ポイント:心を磨く指針として大切なものが「六つの精進」
精進ー5.善行、利他行を積む
精進ー6.感性的な悩みをしない
2010年発刊の『六つの精進』(稲盛和夫著 サンマーク出版)の中で、「六つの精進」の各項目について、稲盛名誉会長は次のように解説されています。
精進ー5 「善行、利他行を積む」
中国の古典に「積善(せきぜん)の家に余慶(よけい)あり」という言葉があります。善行、利他行を積んだ家にはよい報いがあるという意味です。善行を積んだその本人だけでなく、家全体、一族にまでよいことが起こるということを、中国の先賢たちは言ってきたわけです。
著書「立命の書『陰騭録(いんしつろく)』を読む』(致知出版社)の中で、安岡正篤(まさひろ)さんは、「この世の中には因果応報の法則があり、よい行いを重ねていけば、その人の人生にはよい報いがある」と述べられています。
そのように、利他行、つまり親切な思いやりの心、慈悲の心で人にやさしく接することは、たいへん大切なことです。なぜなら、それは必ずあなたに素晴らしい幸運をもたらしてくれるからです。
よいことを実行すれば、運命をよい方向へ変えることができるし、仕事もよい方向へと変化させていくことができる。私はそのことを信じて、経営の局面でも善行、利他行を実践するように努力してきました。
バカ正直に善行を積むこと、つまり世のため人のために一生懸命利他行に努めること。それが人生、また経営をさらによい方向へと変えてい唯一の方法だと思います。
精進ー6 「感性的な悩みはしない」
私自身、若いころにいろいろな悩みを持っていたため、「感性的な悩みをしない」といった考え方をすることが大切だと感じています。
人生では、心配事や失敗など、心を煩わせるようなことがしょっちゅう起こります。しかし、一度こぼれた水が元へと戻ることがないように、起こしてしまった失敗をいくまでも悔やみ、思い悩んでいても意味がありません。
クヨクヨと思い続けることは、心の病を引き起こし、ひいては肉体の病につながり、人生を不幸なものにしてしまいます。すでに起こってしまったことはいたずらに悩まず、改めて新しい思いを胸に抱き、新しい行動に移っていくことが大切です。
済んだことに対して深い反省はしても、感情や感性のレベルで心労を重ねてはなりません。理性で物事を考え、新たな思いと新たな行動にただちに移るべきです。そうすることが、人生を素晴らしいものにしていくと、私は信じています。
仕事に失敗して、我々はよく心配をします。しかし、いくら心配をしても、失敗した仕事が元に戻ることはありません。悔やみ、思い悩んでも無意味だということはよくわかっていても、なお「あれがうまくいっていれば・・・」などと、思い悩んでしまうものです。
「感性的な悩みはしない」とは、こうした意味のない心労を重ねることをやめるということです。起きてしまったことはしようがありません。キッパリとあきらめ、新しい仕事に打ち込んでいくことが肝要です。(要約)
今日の一言には、「⑤善行、利他行を積む:『積善の家に余慶あり』。善を行い、他を利する、思いやりある言動を心がける。そのような善行を積んだ人にはよい報いがある。
⑥感性的な悩みはしない:いつまでも不平を言ったり、しかたのない心配にとらわれたり、くよくよと悩んでいてはいけない。そのためにも、後悔をしないくらい、全身全霊を傾けて取り組むことが大切である」とあります。
「覆水(ふくすい)盆(ぼん)に返らず」
一度こぼしてしまった水は、元へとは戻りません。「なんであんなことをしたんだろう」「あんなことをしなければよかった」と厳しく反省をすることは大事なことですが、十分に反省したのであれば、あとはケロッと忘れていつまでもくよくよと悩む必要は一切ありません。
人生では、誰もが失敗もするし、間違いも起こします。そうした失敗、間違いを繰り返しながら成長していくわけです。
バカ正直に生きていこうとする中で、たとえうまくいかないことが起こったとしても、まずは素直に反省し、十分に反省したなら、すぐに未来に目を転じ、新しい行動へと移っていく。そうした心構えで毎日を生きていくことが大事なのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
