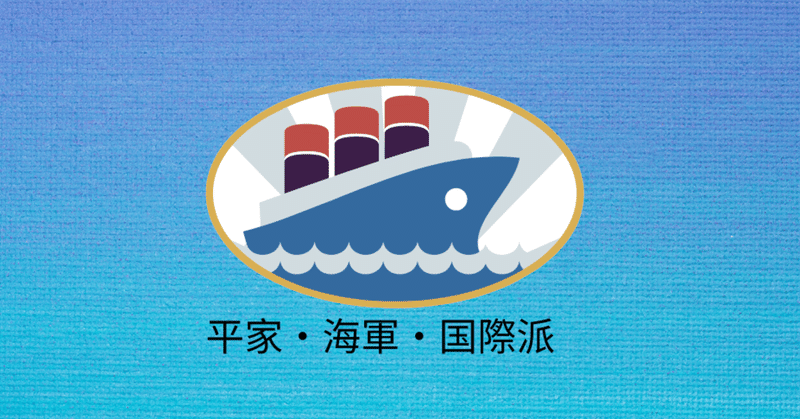
平家・海軍・国際派
今日はダジャレぬきで、企業組織論というか、ちょいと真面目な話。
もう昨年2019年のこととなってしまったが、日本出張の時に、ある80歳代の元上場企業の役員の方の話を聞く機会があった。
老いてなおかくしゃくとしていて、ぼけなどひとかけらも感じさせず、話すことは理路整然としていて、昔の話も感傷に陥ることなく、押し付けがましい意見は言わず、もう脱帽。ああいう人の昔話はたくさん聞いておきたい。面白いし、ためになる。
ある古い体質の明治創業の大企業で「国際畑」で海外赴任が長かった方で、昭和30年代になんと建国前のシンガポールを訪れている。1965年の建国前のシンガポールはどんな感じだったんだろう。華僑のビジネスパートナーに彼らのいろんな食事の場につきあわされて、彼なりにアジア・ビジネスのネットワーキングの現場の雰囲気を体で学んだという。
「こっちは中国語なんて一言もわからないのにいろんな人との飯につきあわされて、笑ってひたすら食べて飲んでだったよ」とかおっしゃるが、食事のあとで彼らが得た情報をいろいろと聞いていたという。すごいな。外国人のなかにひとり溶け込むようにはいっていって根気良くいろいろな情報を汲み出していく、というのをこちらもずっと憧れ、目指してきているので。
そんなよもやま話の中に、「平家・海軍・国際派」という、なんか一昔前の企業小説にでてきそうな、昭和おじさんビジネスマン・カルチャーなフレーズをお聞きした。それらは、「主流派になれない者の代名詞だった」という。
平家は源平合戦で負けたくらいは僕でも知っていたし、たしか、太平洋戦争も海軍が国際情勢の動向を把握していたが生かされず主流派の陸軍が暴走してしまったということだったかな。それで、戦後は、企業の「国際派」が「国内主流派?」に頭があがらない、ということなのか。
まあ、簡単に海外に行ける今、企業も国際展開していて駐在員もかなりの数がいるなか、もはや、国際派や国内派の区別の意味がなくなってきているんじゃないだろうか。たしかにアメリカで仕事をしているときは、アメリカ人の間では、彼は金融畑だとか食品系だとか、営業畑か製造畑かはあったが、国際とかドメとかの区別はなかったような。世界中とびまわっている人というのはいたが。
その方は現役の頃、部門別縦割りの人事(ある部署から海外赴任になるとまたそこの部署に戻っていく)を変えて「国際部」というのを作ってそこから海外へ赴任したり国際ビジネスを日本から管理するような人事の仕組みをつくったそうだが、その方が会社を去った後に、その会社の人事は再び、もとの縦割りに戻ってしまったという。この話は、むしろ、昔は「国際展開」の特殊ノウハウが必要だったので、それを国際部として蓄積していこうとした試みということか。
おそらく、時代の変遷としては、戦後まもない時代には、特殊な海外勤務を経験してきた人材も通常の縦割り組織にもどってその一員として働かせ、その後、この方が試みたような海外経験をノウハウとしていかそうという時代があり、もはや現在は、海外勤務があっても当たり前という時代か。というか、既に終身雇用も変異しつつあるので、そうした国内外のローテーション的な発想がだんだんなくなりつつあるのか。必要なポストには内外から人をとってと言う流れも出てきているか。
それとも、主流か傍流かということだと、いまだ新卒入社でずっといる人が中途入社派に対して主流で、新たな傍流の典型として「中途入社派」を加えるべきなのか。
はたまた、もはや英語だとか海外だとかということではなくて、デジタルIT化に対応できている派とそれができていない派の、主流争いに注目したほうがいいのか。いい名前が思いつかないが、「はんこ派」と「非はんこ派」みたいな。
まあ、そんな主流・傍流に想像をめぐらせるよりも、平時に活躍の主流派に対して、いまみたいな乱世の世にこそ、傍流の中から会社の危機を救うような人材登用の動きに注目すべきか。主流になれない傍流だからこそ、大胆な改革ができると期待したいが。トランプ現象もそんな反主流への期待だったのかな。ちょっと違うか。
新たな傍流三兄弟として、「中途入社・非はんこ・トランプ」を提唱しようかな。なんだか意味不明の三兄弟だな、だめだな。まあ、傍流は主流になれなくてもここぞという時の大事な役割はあるはずと思うんですが。
そもそもそういう三兄弟とかいう発想が、昭和の香りで、アナクロか。
(注:アナクロ=アナクロニズム;時代錯誤。アナユキ=アナと雪の女王、と混同しないように(しないよ))
結局、最後は不発弾なダジャレで失礼。Please let it go.
(タイトル絵はCanvaで作成)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
