
俯瞰道化図
ヨシローは、自分の心の弱さが気に食わなかった。家族や友達と一緒にいると、相手の考えが押し寄せてきて自分などどこかへ行ってしまう。まるで相手と自分の境目などないようになってしまうのだ。だから、ただ傍にいるだけで、ヨシローはなんでもわかってくれる。と思われてしまう。教室にいたらいたで、そこいらにいるみんなの考えがヨシローに押し寄せてくる。気がつくとみんながひとつになったような人格をヨシローは持つようになり、誰もがヨシローのそばに行くと隅から隅まできっちりと共感してもらえることに安堵し、自信を取り戻すのだ。
お母さんも周りの女の子たちも、ヨシローは優しいね、と言ってくれるのだが、自分としてはそれは優しさなのか?と疑問に思ってしまう。だいたい、おれ自身はどこにあるのだ。おれは周りに人がいなければおれになれないのか。ひとつだけ、じぶんでもよくわからないことがある。時折、頭が真っ白になるのだ。それは、気がつくと行動を起こしてしまっているときに起こる。でもそれは、100パーセント上手くいってしまう。
冬休みに入る前の日に、先生が教室で冬休み中の注意について話していた。中学生だけでゲーセンに行ってはダメとか、そんなようなことだ。ヨシローは前の日の大掃除で使った大きなたわしが教室の隅に落ちているのに気がついた。一番後ろ、角の席のヨシローに、そのたわしを手にとるのはたやすいことだった。しばらく先生の説明が続いていたが、とつぜんヨシローの頭に真っ白がやってきた。その時、まるでカーリングでもするかのように、席と席の間の隙間から、ヨシローはなめらかな動きでそのたわしを先生のいる教卓へスライディングさせた。大きなたわしは、すばらしい速さとコースで先生の足元に滑り込み、ピタリと静止した。
先生は、ヨシローが突然椅子の横に飛び出し、滑らかな動きで唐突にたわしを投げつけてきたその一部始終を克明に見ていたが、あまりのまぬけな攻撃力に言葉を失った。生徒たちは大きなたわしのストライクな動きに「またヨシローがやってくれた」といつもながらの行動ではあるのだか、そのあまりの不思議なタイミングに笑ってしまう。実際、先生もヨシローの唐突な攻撃を楽しみにしているようなところがあった。
ヨシローは、みんなが嫌だなぁ、と思いながらも、どうしてもそこでなにかをしなければならない、つまり『ほとんど中身がなくなっているのに、抜け殻のような状態でも残っている縛り』の最後のとりもちが、はなれそうでいてはなれないぎりぎりのタイミングを嗅ぎ分ける嗅覚を持っていて、それをどうしても断ち切りたくなってしまう。
『みんながおれに「それ」をさせているのじゃないか?と思っていたけれど、どうしてみんなが思う「それ」をおれ以外のだれもやらないんだろう?いつも一番怒られながらやめることができないおれってなんなんだ?』
仕掛けてしまっている瞬間の真っ白に、なにものでもない真っ白がある気がしてくる。やっぱりおれはピン芸人になるしかない。とヨシローは思うのだった。
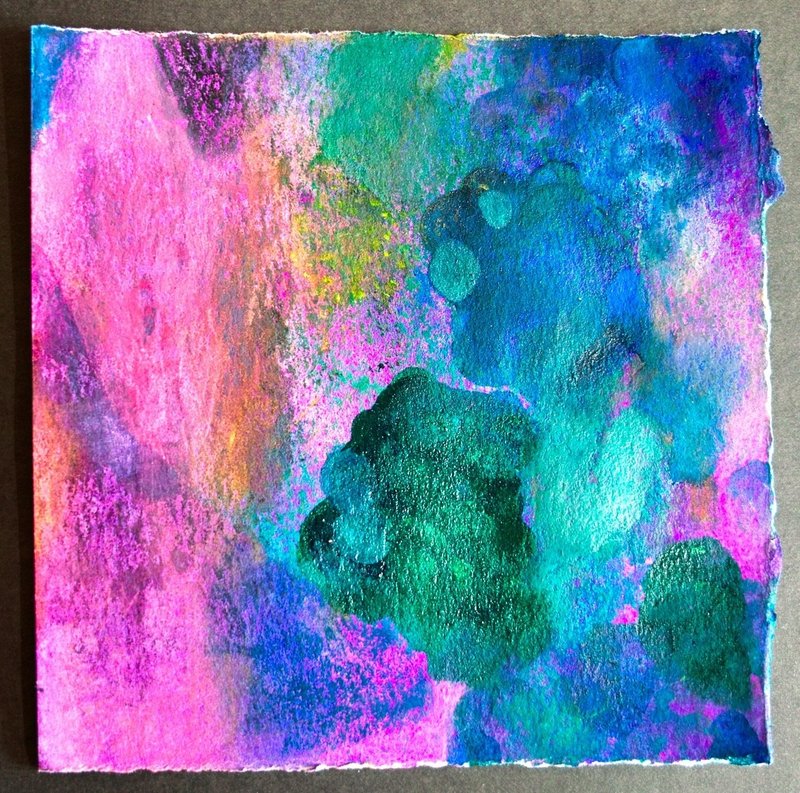
画・文 Hosoki Rumiko
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
