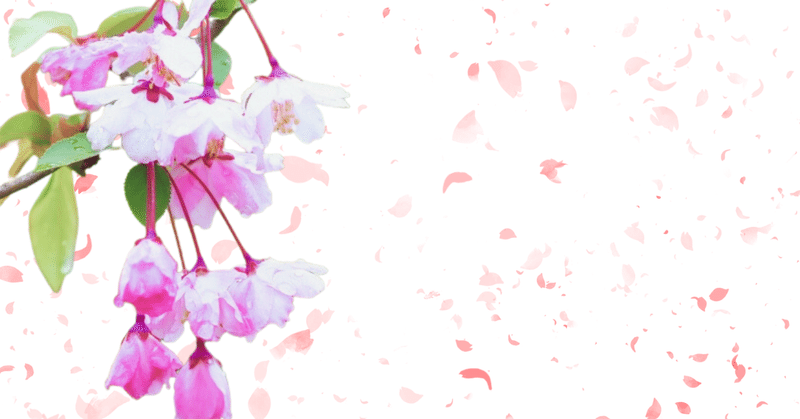
海棠の花散る下で、君と
武帝の命を受け、行方不明となっていた張騫を探す旅に出た二人の少年。しかし、その旅は、太古の呪いに仙人達の思惑が絡んだもので――
古代中国、草原を舞台に繰り広げる物語。
第一章 仙夢
それは、帝の夢から始まった。
そして二人は、彼を求め、旅だった。
「――待ってください!置いていかないでください!!」
後ろから響く情けない声に、駿は大きく溜め息をついた。そして、馬の足を止めて後ろを振り返った。
「このままだと、日が暮れるぞ!次の駅亭までどれくらいあると思ってるんだ?野宿するか!?」
「……いやです。でも……」
目に涙を浮かべながら、有為は必死にこっちまで馬を走らせた。彼は顔面蒼白で、中途半端に腰を浮かべた、妙な姿勢をしていた。その姿に、駿はピンときた。
「何だ?用足しか?大でも、小でもさっさとしてくれよ」
「……違います。場所は近いのですが」
「は?」
「痛いんです」
有為は自分の臀部を示しながら、涙を流した。
「もう、これ以上、馬に乗れません」
「ったく、何で、この俺がこんなことを!」
駿は、有為の、皮が剥けて赤く腫れ上がった尻と太腿に膏薬を塗りながらぼやいた。
「すいません。なにぶん、馬に乗り慣れていないもので……」
人目のつかぬ木陰を選んだとはいえ、そこそこ往来のある街道沿い。白昼堂々、彼は下半身を露出する羽目になって、恥ずかしさで死にそうな思いだった。しかし、鞍と擦れて腫れ上がった、尻と腿の傷みには変えられなかった。
「ほれ、塗り終わったぞ!ったく、女みたいなケツしやがって」
そう言うなり駿は有為の尻をパンと叩いた。彼の掌のあとが、有為の肌に赤く残った。 有為はひい、と悲鳴を上げ、飛び上がるように起きあがった。そして慌てて下半身をしまい込んだ。
その情けない姿に、駿はもう一度溜め息をついた。
長安を出てからというもの、有為は何かにつけて馬から転げ落ちていた。それが落ち着いたと思ったら、今度はこれだ。
でも、仕方あるまい。有為はもともと、長安のしがない薬売りの息子だ。騎士の自分と違い、馬に乗り慣れていないのにも無理はない。
鞍に負けた皮だって、乗ってるうちに強くなっていくはずだ。
だが……
こんな調子では、いつまで経っても草原に行けない。彼を見つけ出すことは出来ない。
有為を置いていく方が得策……。しかし、この探索の旅に選ばれたのは、他でもない、この有為だった。自分はただ、それに付いてきただけ。
漢と北を接する遊牧騎馬民族国家、匈奴は、また建国も漢と時を同じくしていた。
漢の高祖は、匈奴に破れ、それ以来、漢は匈奴に屈辱を味合わされ続けた
今から十年ほど前、即位したばかりの若き皇帝、徹――武帝は、漢帝国の宿敵、匈奴を破り、長年の雪辱を晴らそうと燃えていた。
そこで彼は、月氏に目を付けた。
匈奴と同じ遊牧国家、月氏はもともとは敦煌周辺にいた。しかし、匈奴に破れ、遙か西へ、逃れるように移動していった。
それに追い打ちをかけるように、匈奴の老上単于(単于は匈奴の最高権力者)は殺した月氏の王の頭蓋骨で酒杯を作り、それで酒を飲んだという。
このことは月氏の怒りに油を注いだ。だが、どんなに単于を怨んでも、戦力が足らない。共に匈奴を討ってくれる国もなかった。
為す術もないまま日々怨みだけが募っているという。
匈奴からの投降者からこの話を知った武帝は、早速、使節を月氏に派遣することを決定した。彼らと同盟し、匈奴を西と東で挟み撃ちにしようと考えたのだ。
気鋭の若者を募り、百余人の使節団が長安を出発した。
しかし、使節が月氏に向かうためには、どうしても匈奴の領土を通らねばならない。
当然のことながら、使節団は匈奴に捕まり、西へ行くことは叶わなかった。長安では彼らの生死が不明なまま、歳月だけが流れた。
ある日、武帝は夢を見た。
夢など、もうしばらく見ていなかった。
今から十余年前、僅か十七で即位した武帝は、しばらくは母や祖母、そして皇后の姻戚に縛られ、傀儡に甘んじていた。
しかし、ここ数年のうちに、祖母も母も亡くなり、皇后の陳氏も策略により廃することが出来た。彼の邪魔をするものは、全て消え去ってくれた。
また、数ヶ月前、寵妃衛氏との間に、初めての男児が生まれた。これで後継の心配もなくなり、愛する女も皇后に出来る目途もついた。
全てが彼の思い通りに動いていた。その多忙で充実した日々の中、夢など見る暇も失せていった。
そんな中の、久方ぶりの夢。
そして初めての夢。
夢が、夢だと解る、不思議な夢。
彼は立っていた。
一人ではない。
目の前には、彼が心から慕う方士、李少君がいた。
少君は、五年前、考廉という推挙制度で選抜され、武帝の前に現れた。
彼は竈の神の力を説き、蓬莱に住む仙人、安期生について語ると共に、不思議な力を武帝に示し、帝を深く魅了した。
武帝が神仙を深く求めるようになったのも、偏に彼と出会ってからであった。
少君は武帝に見えてから、間もなく世を去った。しかし武帝は彼を死んだのだと思わず、神仙界に旅立ったのだと信じていた。
目の前に立つ少君を見て、武帝は自分の考えが正しかったのだと確信した。
「先生……」
武帝は、思わず彼の側に駆け寄ろうとした。
しかし、李少君は手を静かに前に伸ばし、彼を制した。
そして、彼に周りを見るようにと、手振りで促した。
ここは草原であった。
側には大きな湖があり、羊たちが暢気に草を噛んでいた。
風が、吹き抜けた。雲が、流れていった。
どこか懐かしい、見知らぬ場所。
そうだ、ここに自分は、数多くの兵士を、送り込んでいる。
ついこの間まで、この地での戦況が、毎日のように上奏されていた。
だが、親征など、一度もしたことのない彼にとっては、見知らぬ土地でもあった
彼は、言葉では言い表せない、奇妙で不思議な気持ちになっていた。
少君は武帝に告げた。たった一言。
「張騫は、ここに」
(張騫――!?)
そこで、夢は覚めた。
張騫とは、あの、月氏に使わした使節団を率いていた者に他ならなかった。
武帝は、すぐに太卜(占者)を召すと、その夢の吉凶を判断させた。と同時に自らの取り巻きにその是非を問うた。
武帝のお気に入り、中朗の東方朔は易に長けていた。そして彼は武帝にその夢は正夢であると断言した。
さらに、朔は、その張騫は匈奴に囚われたままであるが、彼をそこから救い出せば、漢帝国の仇敵、匈奴を討ち破ることが出来るとも語った。
その言葉に武帝は大変喜んだ。
折りしも、匈奴との大規模な戦闘が終結したばかりであった。
寵妃衛氏の弟、車騎将軍・衛青は、匈奴の領土の奥深くまで侵攻し、単于庭の側にある彼らの聖地、蘢城を焼いた。
この戦いで、衛青は敵数百人を殺傷し、数多くの捕虜を得るという、輝かしい戦功を挙げた。
しかし、そのほかの将軍の成果は惨憺たるものだった。ある者は捕らわれ、ある者は部下数千騎を失った。
終わってみれば、勝ち戦からほど遠い結果となってしまった。
青のような将軍が、せめてあと一人いれば……。武帝は心の底からそう感じていた。
使節団の団長・張騫は、当時、禁中の門戸を守護する朗の職に就いていた、気鋭の若者であった。もし、彼が生きていれば、匈奴の内情にも通じた、頼もしい大将になるはずだ。
東方朔は、さらに帝に告げた。
「これは、方士李少君の導きになるもの。探索に出る者は、禁裏に出入りする方士たちの内から選ぶ方が良いという結果が出ました」
李少君の死後、怪しげな方士たちが、入れ替わり立ち替わり禁裏に出入りするようになった。皆、少君が会ったという仙人、安期生について上奏するためだ。
「さてさて、その者は……」
筮竹を見ながら、朔は言った。
「鞠陵于天の息子、有為。少君が選んだのは、彼です」
「ここでもう少し休んでいくか」
そういうと、駿は大の字になって、草の上に寝転がった。
暦の上では春とはいえ、風はまだ切るように冷たい。それでも暖かい日差しに当たってると、眠気が彼を覆った。
「でも…良いんですか?次の駅亭まで、あと、どれくらいあるのですか?」
「半分来たかどうかってとこだな。ここで休んだら、暗くなるまでには着けないな」
「では、今日は、野宿ですか……?」
有為は、不安そうに言った。それを見て、駿は苦笑いを浮かべた。
「どのみち、長城を越えれば、あとは野宿するしかないんだぞ。今から慣れておけよ」
「解ってますが、でも……」
漢の通行証を持つ彼らは、街道沿いの宿場――駅亭を自由に使うことが出来たし、必要な物資もそこから得ることが出来た。
長安を出てまだ二、三日しか経たず、旅慣れない有為にとって、屋根のないところで寝るということは、かなりの抵抗があった。
「行けます。もう、大丈夫ですから、行きましょう」
「何言ってるんだ!?」
勢いをつけて、駿は起きあがった。
「あんなに真っ赤に腫れ上がったケツで馬に乗れるのか?」
「乗れます!」
駿に負けない勢いで有為も答えた。
「これだけ休めば、もう大丈夫です。行きましょう!」
言うなり有為は馬に飛び乗った。そして勢いをつけすぎて、そのまま反対側に落ちていった。
「おい!大丈夫か?」
駿は慌てて彼を助け起こした。
「大丈夫です!」
意地になってる有為は、背筋をピンと伸ばして立ち上がった。
「ケツは痛くないのかよ?先は長いんだ、ここでつまらない無理をしたって、仕方ないんだぞ」
駿は、警告の意味も込めて彼の尻に張り手を入れた。有為は、きっと駿を睨み付けたが、さっきのような悲鳴を上げることはなかった。
「……本当に、痛くないのか?」
「あなたみたいに力の強いのにひっぱたかれたら、そりゃ痛いですよ。でも、もう、馬に乗れないほど、痛くありません」
あんなに腫れ上がっていたのが、そんなに簡単に治るものなのだろうか……?
信じられない思いでいた駿は、ふと自分の掌を見た。すると、自分の手とは思えないほど、つやつやで滑らかな掌になっていた。
「……おい」
駿は、さっきの膏薬を借りると、反対の手に塗ってみた。塗った途端、薬はすうっと肌に染みこんでいった。と、同時に、荒れた掌の細かい傷は消え、あっという間にすべすべになった。
「すっげえ……。これ、何だよ?」
あまりの効き目に、駿は感嘆の声を上げた。
「精精の膏です」
「あ?」
「そう言う名前で売ってるんです。精精とは、山海経に出てくる化け物の名です。実際にはいやしませんよ、そんなもの。肌の馴染みが良いのを見ると、馬の膏を使っているようですが、あとはどのような薬を調合しているのか、残念ながら、解りません」
漆塗りの、小さな箱に入った膏薬を薬籠に仕舞ながら、有為は答えた。
「何だよ、薬屋の息子。てめえのとこの薬だろ?何で解んないんだよ」
「大抵の薬は、うちで調合してますが、これは違うんです。
一、二ヶ月に一度、不思議に良く効く薬を売りに来る老人がおりまして、これも、その老人から買った薬です。
そして、父は老人が持ってきた薬に、妙な名前を付けて、法外な値段で売るんです。それだけならまだしも、その薬を持って、禁裏にまで赴くから、私がこんな目に遭ってしまうんです」
唇を尖らせながらぼやく有為を見て、駿も思わず苦笑した。
有為の父は、鞠陵于天などという、けったいな名で禁裏に出入りをしているが、言うことはでたらめで全くつじつまが合わず、他の怪しげな方士たちにすら馬鹿にされていた。しかし、彼の持参する薬は、神仙のものかと思えるほど、効き目が灼かであったので、かろうじて出入りを許されていた。
李少君と出会ってから、武帝は深く神仙を求るようになり、怪しげな方士たちがひっきりなしに禁裏に出入りするようになった。当然、側近たちはそのことを快く思っていなかった
東方朔が、鞠陵于天の息子、有為を探索の旅に選んだのは、そう言ったインチキ方士たちへの牽制であったと、誰しもがそう思った。
事実、有為と共に匈奴の地に赴こうとする方士は誰もいなかった。
彼らは、いるかいないか解らない安期生や、あるかどうか解らない蓬莱の探索には進んで行くが――しかも、かなりの金子を帝よりせしめて――、現実に生きているはずの張騫や、実際に目の前にある匈奴の領地には行けないのだ。
しかし、武帝は本気で捜索隊を匈奴に送りだそうとしていた。
だが、軍の方も乗り気ではなく、
「匈奴との大規模な戦が終わったばかりであるし、方士李少君の導きもあることだから」と、捜索は方士たちで行うように上奏してきた。
軍からも方士からも見捨てられ、有為は、たった一人で、見知らぬ北の大地に送り込まれそうになった。
そこに名乗りを上げたのが、車騎将軍衛青麾下の騎士、駿であった。
彼は衛青と共に蘢城に攻め入り、帰還したばかりであったが、再び匈奴の土地に舞い戻ることを志願した。
ふいに、風が有為の首に巻いた巾を巻き上げ、彼の顔を覆った。取ろうともがく有為を見て、駿は思わず笑った。
それから、恥ずかしさのあまり顔を真っ赤にしている有為の側に行くと、巾が風に飛ばされないよう、上手く首に巻き付けてやった。そこで目に入る自分の手の色と、有為の顔の白さがあまりにも違うので、またおかしくなって笑ってしまった。
軍に属する駿は、年中外にいるせいで、すっかり日に焼けて見事な褐色の肌をしていた。髪の毛まで日に焼け、赤茶けてぱさぱさになってしまっていたが、彼は全く気にしていなかった。
身長は、他の兵士たちと見劣りしないどころか、高い方であったが、衛青軍の中で一番年少であったせいか、体つきはどうも華奢であった。
他の兵士たちのように、筋骨隆々になりたくて、密かに鍛錬しているのだが、今のところ成果は現れていない。
「――さっきから、何を笑ってるんですか!?」
笑いの止まらなくなっている駿に向かって、有為はぼやくように言った。
「悪い悪い……あんまり色が違うんで」
「は?」
「碁石みたいだよな、俺たち」
「何が言いたいんですか?」
訳の解らないことを言っていると、呆れたように有為は首を振った。
長安生まれの長安育ちで、一日のほとんどを薬屋の店先と倉庫で過ごす有為は、ほとんど日の当たらない生活をしているせいか、女性もうらやむほどの色白の肌を持っていた。
中肉中背で、目がクリッとして幼い顔立ちの有為と、細身で長身、目鼻立ちのきりっとした駿は、全く正反対のタイプだった。
「でも、本当に、独生どのが一緒で良かった……。そうじゃなければ、今頃、私は路頭に迷ってました」
「大げさだな。それに、俺がこの旅を志願したのは、お前の為じゃない。親分の為だ」
「親分?……ああ、そうでした、衛将軍のことでしたね」
有為は駿に尋ねた。
「でも、どうして、将軍のことを親分などと呼ぶのです?前から、不思議に思ってましたが」
「親分は、俺の親みたいなもんなんだ。でも、親じゃないから、親分」
駿は、有為を馬に乗せながら答えた。
「衛の姓を名乗るずっと前から、俺は親分と一緒だった。俺は二親が何処のどんな奴だかは知らない。親分に育てて貰ったんだ」

衛青の父、鄭季は、もともと河東郡平陽の小役人だった。
平陽は、武帝の姉・平陽公主の所領であり、そこの下級官吏は交替で、長安にある平陽侯邸に務める習わしになっていた。
鄭季も、その役を務めるべく、長安の平陽侯邸に赴いた。そのとき、彼は衛媼と呼ばれる女性と会った。
彼女は平陽公主の夫、平陽侯曹寿に仕える妓女であった。
妓女の役割は、侯邸の宴席で歌舞を興じて貴人の相手をし、気に入られれば夜伽も務めた。彼女たちは、一挙一動が男の心に響くように、訓練された女たちでもあった
衛媼に一目惚れした季は、彼女が自分の身の回りの世話をして貰うよう、平陽侯に頼み込んだ。
地方の下級官僚は、それなりの財産がないとなることが出来なかった。鄭季も当然、平陽ではそこそこの名家で、それなりの金があった。
かなりの金子をはたき、彼は衛媼を側に置くことに成功した。
やがて、彼女は彼の子をつぎつぎと、三人も生んだ。その末っ子が衛青である。彼の上に、後に武帝の寵妃となる姉の子夫、そして兄の長君がいた。
任期も切れ、故郷平陽に戻らねばならなくなったとき、季は、彼女との子供を一人、郷里に連れて帰ることにした。
「女は、ここに置いていって。男はどっちでも良いわ。両方連れていっても良いわよ」
子供を連れて帰りたい旨を衛媼に告げると、彼女は即座にそう言った。
娘は、自分と同じ妓女に育てなくてはならない。それは、自分が決めたことではなく、妓女の娘として生まれた者の、宿命である。
娘を上手く仕込めば、貴人の歓待だけでなく、贈り物として出世や保身の道具にすることが出来た。つまり、妓女は、貴族にとっては貴重な財産だったのである。
一流の妓女にするにはそれなりの時間がかかる。だから、妓女の娘たちは幼い頃から歌舞などの修練を積まされた。
仮りに歌舞が物にならなくて、妓女として出来損ないに育ってしまっても、その場合は侍女として使うことができた。
必要な礼儀作法などは既に身に付いているし、仕事は歌舞から身の回りの雑務に変わるだけで、夜伽を務めさせられたり、物のようにやりとりされるのは同じだった。
つまり、娘には損はないのである。
一方、妓女の息子の方は、はっきり言って必要がなかった。家の雑務をこなさせてもらえれば良い方で、大抵は奴僕として売られた。
だから、地方の名家である父に引き取ってもらえる方が、息子も幸せになれる。衛媼はそう考えたのである。
長男の長君は、あまり自分に懐いていなかったので、季は末っ子の青を郷里の平陽に連れていくことに決めた。
妓女の子供たちは、当時としては珍しく、通常、母方の姓を名乗っていた。当然、衛媼の子供たちも、皆、母と同じ衛姓を名乗っていた。
だが、青は父に引き取られるに当たって父方の鄭を名乗ることになり、父と共に遠い河東郡平陽に移った。
平陽で青を待っていたのは、過酷な生活であった。
鄭季の正妻と、その子供たちは、当然、妾の子など認めるはずもなかった。
青は、食事もろくに与えられず、奴僕同然の暮らしを強いられることになった。
しかし、彼は、それに負けるような少年ではなかった。
平陽侯邸にいたときでも、蝶よ花よと育てられる姉たちと違い、自分は兄と共に、虐げられた生活を送っていた。
それでも、姉たちは何かにつけて気に掛けてくれ、兄は必ず彼を守ってくれた。ここには、その兄姉たちがいない。
腹違いの兄姉は、彼を家族とは認めていなかったし、彼もまた認めていなかった。
押しつけられた羊の番をしながら、いつも、彼は平陽侯邸での日々に思いを巡らせていた。
「いいか、俺たちには頼るべき親も、兄弟もいないと思え。頼れるのは自分自身。自分の力で、生き抜くんだ!」
兄の長君は、拳を上に突き出しながら、よく青にそう言った。青は、意味もわからないまま「おう」と相槌を打ちながら、拳を突き出した。
「よし、では、まず喰いもんだ」
そう言って、長君は同じ侯邸にいる少年たちを引き連れて、平陽侯の桑畑に侵入しては、土留め色の桑の実を摘んで口の中に入れた。
甘酸っぱい実をたらふく頬張り、管理人に怒鳴られる前に桑畑から退却する。
食事も満足に与えられない彼らにとって、これは実益を兼ねた遊びであった。
そして、遊び仲間の少年たちは、気がつくと一人消え、二人消え、徐々に少なくなっていった。
みんな、売られていったのだ。
長君は、母に似て見目が良かったので、侯邸に残されることになっていた。だが、父親似の青は、他の少年と同じように、売られていく可能性が高かった。
年長の長君は、それに薄々気付いていた。
だからこそ、自分なりに考えた生き抜く術(すべ)を、青に伝えようと必至になっていた。
そのことが、長安から遠く離れた青の中に、ゆっくりと、しかし確実に蘇ってきた。
隙を見て、彼は鄭季の家を飛び出した。そして往く当てもないまま、放浪生活を送るようになった。
体も大きく頑強で、芯の強い性格の上、義侠心に溢れていた青は、行く方々で様々な人間に目を掛けられた。そして彼らから武芸や渡世の方法を教わり、いつの間にか、河東では知る人のいない游侠の士となっていた。
駿が青に出会ったのは、その頃であった。
ある日、青は道ばたで死にかけていた幼児を見つけた。
彼は、その子の手当をして、親を捜したが、土地の長老から既に亡くなっていたことを聞かされた。
彼は、自分の後をよちよち歩きながら必至に追ってくる幼児の姿に心を打たれ、自分で面倒を見ることにした。
その子が駿だったのである。
駿は青に拾われる前、自分が何処で、どうしていたのか、全く覚えていない。青自身も、駿をどの辺で拾ったのか、すっかり忘れてしまったため、駿の故郷も、先祖も、全く解らなかった。
駿の正式な名は鄭駿、字を独生。
姓の鄭は、もともとは鄭青だった彼にちなんだものだし、名も、字も、騎士になるときに青につけて貰った名前だ。
「俺を拾ったころ、親分は今の俺とそんなに年が変わらない、――もっと若かったかもしれない――なのに、名の通った人物として、何処に行っても尊敬されてたんだ、すごいだろう?」
馬の足を進めながら、嬉しそうに駿は言った。
「今は、皇子の姻戚として、それなりの地位になってるけど、あの頃の親分は、何もない中で、巷間で確固たる存在になってたんだ。それも二十歳(はたち)になる前に!ほんと、すっごいよな」
衛青のことを話す駿の顔は、とても嬉しそうで、きらきらと輝いていた。
「でも、何で、そのような人が長安に来て、姓を変える必要があったのですか?」
「何だ、お前知らないのかよ?」
「知りません」
有為は首を振った。駿は、そんなことも知らないのかと、呆れた。だが、すぐに考え直した。
二人は出会ってまだ間もなかったし、こうやって話すこともほとんどなかったことに気が付いたのだ。
道中は道中で、有為が馬に慣れないため、先に進むだけで精一杯だったし、駅亭に着けば着くで、有為は緊張と疲れからその場に倒れるように眠り込む毎日だったからだ。
(話が出来るくらい、余裕が出てきたってことか)
この先、長安を離れれば離れるほど、旅は厳しさを増すだろう。それを考えると、徐々に旅慣れてきた有為のことを、喜んだ方が良いのだろう。
「今から十年以上前のことだよ」
気を取り直した駿は、青が改姓した理由を話し始めた。
河東周辺で旅暮らしを続ける青と駿の元に、ある時長安から使いが来た。
それは、大至急、長安の平陽侯邸に来るようにとのことであった。
おぼろげながら、青の頭の中に、平陽侯邸で過ごした幼き日の記憶が残っていた。
彼は、長いこと会っていない母や、兄姉たちの事も気になったので、その申し出を受け、平陽侯邸に赴いた。
そこで彼は、家族と久方ぶりの再会を果たし、姉の子夫に重要な使命が課せられたことを知った。
「姉上の大事というより、それは、国家の大事ですね」
平陽公主から話を聞いた青は、驚いてそう言った。
「そうじゃ。それ故、お前にも身を慎んで欲しいのだ。お前の咎が、お前に姉に及んでも困るのでな」
公主の話に、青は苦笑いを浮かべた。
河東では自分の悪名を知らぬ者はいなかったが、まさか、長安にまで響いていたとは思いも寄らなかったからだ。
彼は、姉の身を案じ、平陽侯夫妻の申し出に応じて、そのまま侯家に留まることにした。そして、姓も父方の鄭から母方の衛に改め、新たな人生を歩むことにした。
この時、駿も彼と共に侯家に置いてもらえることになり、幼いながらも彼と一緒に侯家の用を務めるようになった。
衛青が侯家に戻った理由、それは武帝に大きく関係していた。
その当時、即位したばかりの武帝は、鬱屈した毎日を送っていた。
彼は、彼の父・景帝の長子ではなく、もともと皇太子でもなかった。
そんな彼が、景帝の後継者となり、帝位を継ぐ事が出来たのは、彼が、景帝の姉の娘、陳嬌と縁組みしたからである。
彼は、景帝の姉、長公主の後ろ盾によって皇太子となり、帝位を継ぐことが出来たのだ。
つまり、彼が帝位に就いたのは、女の力によってであり、当然、後宮の女性たちの権勢は目を見張る物があった。
彼の母、王皇太后は、もともと長公主の口利きで後宮に入った女性であるし、まだ健在だった祖母、竇大皇太后も長公主は実の娘であり、陳皇后は可愛い外孫であもあった。
全てが長公主と陳皇后の意向で動いていたと言ってもいい。
政治においても、大きな変化を好まない竇大皇太后が何かと口を挟み、武帝が行おうとした改革をことごとく潰してしまった。
何一つ、彼の意志が通ることなどなかったのである。
陳皇后を始めとする、後宮の女性に指一本触れないことが、彼の精一杯の抵抗であった。
彼は、幼馴染みの韓嫣を男妾とし、昼も夜も彼と一緒に過ごしていた。
しかし、男相手では世継ぎを望めない。
男色に走った弟を案じた彼の姉、平陽公主は、あることを思いついた。
要するに、女性の良さを、彼に知って貰えばいいのである。
その女性は、地位も、実家の権力もなく、彼の意のままになる者が良い。
公主は、年や、容姿が彼の好みに合い、卑賤の身分である青の姉、子夫に白羽の矢を立てた。
公主は、子夫の母、衛媼の助けも借りて、彼女を武帝のためだけの妓女に仕上げた。
何年もかけ、丹念に仕込まれた彼女は、些細な仕草一つとっても、武帝の心に響くような女性になった。
苦労して彼女を”完成”させた頃、行方不明になっていた彼女の弟の消息が侯家に伝わってきた。
その弟――青は河東では名の知らぬ者がいないヤクザ者だという。
大切なときに、何か問題を起こされたら堪ったものではないと、公主は慌てて青を長安に呼び寄せた。
そしてこのおかげで、武帝は青とも、運命の出会いをすることになるのである。
建元二年(前一三九)年の春、三月。
武帝は覇上での禊ぎの帰り、姉の平陽侯夫妻の家に寄った。
侯邸では歓迎の宴が開かれ、そこで、公主はさりげなく子夫を武帝に引き合わせた。
彼女は、多くの妓女に混じって歌っていた。それも中心ではなく、端の方で。
姉は知っていたのだ。
弟は中心で華やかに活躍するものよりも、端でさりげなく光るものを気にかける性格なのだと。
そして、そこに子夫を置いた。
彼女は、武帝のためだけに作られた妓女。
ちょっとした表情でも、微かに動く指先でも、全てが武帝の好みに響くようになっていた。
気がつけば、武帝は彼女から目が離せなくなっていた。
全て公主が仕組んだこととは知らずに、武帝は子夫の虜になっていた。
宴もたけなわになったとき、武帝は更衣のために席を立った。貴人は用足しのたびに着替える習わしがあるのだ。
武帝は、更衣の係に子夫を指名した。
それが、何を意味しているのか、公主にはすぐ解った。そして、心の中で、高笑いを上げた。全て、自分の思い通りになったわけだから。
軒中に立った帝と子夫は、そこで肌を重ねた。
初めて触れる女性の肌に、彼は夢中になった。
事を終え、宮殿に帰るとき、彼は子夫も共に連れていった。
それから武帝は変わった。
それは、衛子夫という存在が、彼の支えになったのと同時に、彼女の先にあるものが、彼の希望になったのだ。
希望の一つは、彼女を連れて帰ってから一年後、彼女が待望の子供を身籠もったこと。彼は、父になる喜びを知った。
もう一つは――そう、彼女の弟、衛青と出会ったことである。
子夫が身籠もった建元三年(前一三八)の春頃から、彼は微行(おしのび)と称して、夜間出歩くようになった。
行き先は義兄、平陽侯邸。
最初は、子夫を引き合わせてくれた姉への礼に向かっただけだった。しかし、彼はそこで、子夫の弟、衛青に出会った。
その出会いが、彼の希望になった。
彼は、自分の力になる。帝はそう直感した。
そして、彼と親しく話すうちに、その直感は実感に変わった。
衛青は、十になるかならないかの頃から家を飛び出し、巷間で揉まれて生きてきた。その中で培った、広い見識と、知恵と、力が彼にはあった。
彼は、屁理屈に近いような、教養や学問しか詰まっていない、宮廷の官僚たちとは正反対の人間だった。
武帝は、衛青とその兄、衛長君に侍中の位を与え、宮廷で自らの側に侍るように命じた。
祖母の竇大皇太后も、母の王皇太后も、寵妃の一族を側に置くことぐらいだったら、簡単に許してくれた。
祖母も母も老いて、先が見えている。この先、そう長くはない。
一番疎ましい、自分の皇后は、自分の姉、平陽公主が追いつめていくことだろう。
姉が弟のことをよく解っていたのと同じように、彼もまた、姉のことをよく解っていた。何より、自分たちの母親は、長公主と組んで皇太子とその母を追い落とした、王皇太后その人だ。
彼女は、自分の母と同じようなことを、きっとする。
そうなれば、全て自分の意のままになる時代が来るのだ。
衛青たちを側に置いたのは、それに向けての準備の、第一歩であった。
衛青を側に置くようになっても、彼は平陽侯邸に行くという口実の微行を、引き続き繰り返した。
しかし、実際、侯邸に赴くのは稀で、長安郊外、かつて秦の阿房宮があった辺りで狩りを繰り返した。
武帝のこの狩りは、匈奴討伐の準備の第一歩でもあった。
狩りをすることで、部下の動きを見極め、役に立つ者とそうでない者を見極めていたのだ。
武帝は、定員のない朗に、これはと思う人物を次々に任じると、必ず夜狩りに連れ出した。そこでさらに篩に掛け、有能な人物を残していった。
そうやって、選ばれた中に、張騫がいた。
「本当は、親分も月氏に行きたかったんだ。旅暮らしが長かったしな……宮仕えよりよっぽど性に合ってる。でも、子夫姉さんの出産も近かったし、長兄さんの具合も悪かったから、自分が家族を支えなきゃならないって、諦めたんだよ」
駿は青の、そう言う人情の厚いところが大好きだった。そして、その選択をしたために、武帝と共に十年近くも雌伏しなければならなかった、彼の辛さも、側にいてよく解っていた。
だからこそ、駿はこの旅に出たのだ。
「張の兄貴と、親分は昔から仲が良くて、良く、一緒に朝まで飲んでたよ。特に、使節団出発の前日なんて、すごかったんだぜ」
酒を飲む身振りをしながら、駿は笑った。
まだ、幼い子供だったけれど、眠い目を擦って、駿は二人が熱く語り合うのを懸命に聞いていた。
衛青も張騫も、匈奴の傍若無人ぶりに強い憤りを感じ、彼らの略奪に苦しむ国境沿いの人々を、何とかして救いたいと思っていた。
そして月氏に使いする騫に、青は自分の希望も託した。そして、無事、使いから帰ってきた暁には、共に、匈奴を討とうと、誓い合った。
「蘢城まで攻め入ったとき、親分は、十年前に消えた使節団の人間も捜した。捜しているうちに、蘢城まで行ってしまったってほうが、正解かな。でも、見つからなかった」
衛青は、単軍で敵陣に深く攻め入った危険に気付き、充分な探索もしないままに撤退を決めた。
駿は、自分は張騫の顔を覚えているから、単騎残って、彼を捜すと主張した。だが、青は許さなかった。
「我が軍の者で、一人でも匈奴に残すわけにはいかない。全員無事帰還してこその勝ち戦だ!今動かねば、簡単に返り討ちに遭うぞ。敵が体勢を立て直す前に、胡地を後にするのだ」
そう叫んだとおり、青の軍は一番の戦功を上げたが、失った将兵も一番少なかった。
一気呵成に敵地に攻め入り、その勢いのまま帰還した彼の軍勢は、伝説となった。しかし、その伝説と引き替えに、彼は親友の消息を求める機会を失った。
「……蘢城まで行って見つからなかったのに、私が見つけることが、出来るのですか?何故、私が選ばれたのでしょう?」
有為は自信なさげに呟いた。それを聞いて、駿は、申し訳なさそうに頭を掻きながら言った。
「まあな、言い出しっぺは、あの東方先生だからなあ」
「何です?」
「東方先生の体の中には、血と一緒に嘘が流れてるからな。この俺も何度、欺されたことか……」
「嘘……!」
有為は、言葉に詰まった。目には、涙が滲んでいた。
「まあ、まあ」
駿は、馬の足を緩めて有為の隣につけると、彼の背を慰めるように叩いた。
「いいか、良く聞けよ。東方先生のすごいところは、口から出任せを重ねているうちに、それが巡り巡って本当になっちまうとこなんだ。陛下もそこをお気に召してる。俺も、それに賭けている。
お前が探索に指名されたのはいつもの出任せとしたって、張の兄貴は生きている、そう信じることだって出来る。どんなに僅かだっていい。俺は、生きてるって方に、賭けてるんだ」
「独生どの……」
有為は、顔を上げて涙を拭った。その様子を見て、駿は笑った。
「俺のことばっかり、話してるじゃねえか。お前のことは何かないのか?」
「……ありません」
有為は、大きく息をついた。
「しがない、薬屋の息子ですから。薬の調合一つとっても、まだまだ勉強不足で。でも、いつかは、この膏薬のような優れた効き目を持った薬を造り出すのが、夢でした。なのに、何でまた、このような目に……」
有為の瞳には、また、涙が浮かんでいた。
「ったく、お前は」
駿はもう一度、彼の背を叩いた。
「見知らぬ土地に行けば、見知らぬ薬に出会うってもんよ。旅は、いいぞ」
青空を見上げて、駿は笑った。
この空の続くどこかに、きっと、彼はいる。
第二章 白鷹
白い鷹。青い空に舞う。そして、その先に……。
これは、夢。それとも――
「おい!大丈夫かよ!?」
ぱしぱしと頬を叩かれる感触で、有為は目を覚ました。体中が、じっとりと汗に濡れているのに気がついた。
「……何か?」
今さっきまで見ていた夢がまだ抜けきらぬまま、ぼんやりとした頭で有為は尋ねた。
「何かって、もの凄い魘され方だったぞ」
「あ……ああ、そうですか……」
有為は頭を抱えながら、首を数回振った。
「夢、です。多分。夢、でしょう」
夢にしては、妙に生々しいものであったが、夢以外、説明が付かない。
「なら、いいけどさ。どっか調子悪いんだったら、隠さず言えよ。しばらくはまだ、沙漠越えが続くんだ。体がしんどいようだったら、休み休み行くから」
そう言いながら、駿は昨夜の焚き火を引っかき回して、風を入れた。火が蘇り、再び赤々と燃え上がった。
春とはいえ、沙漠の朝はかなり冷え込む。有為は、毛氈にくるまったまま、もっと暖まろうと、火の方に体を動かした。
(やっぱり、しんどいのかなあ……)
有為の様子を見ながら、駿は思った。
国境を越え、一面に、ごろごろとした石の転がる礫沙漠に足を踏み入れてから数日が経つ。人の往来も稀で、会うとしたら間違いなく敵――匈奴だ。
有為にとって、今までに経験したことのない緊張感が続いているに違いない。焦りもあるが、やはり、もう少しゆっくり行った方がいいのかもしれない。
「休み休みはいやです。早く、ここから抜け出したい」
炎を見ながら有為は呟いた。
「俺だってそうだ。だが、体が言うことを聞かないんなら仕方がない。この旅の目的は、張の兄貴を捜すことだ。何時までに、ここに、っていう期日が定められたわけでもない。焦って、無理をして、体が動かなくなっちまう方が困る」
鍋に、水と、適当なものをぶち込んで煮込みながら、駿は彼に諭した。
「でも、独生どのは、夏までには何とかしたいと、言ってたじゃないですか?」
「まあな」
鍋をかき混ぜながら、駿は答えた。
「春から夏にかけて、牧民はてめえの仕事が忙しくて、よそ者にもこだわらない。戦は大抵、秋から冬。この時期、ヘタに草原をうろうろしてると、捕まって何されるか解らねえ」
春は、家畜の出産の時期。牧民である匈奴たちは、家畜の世話に追われ、一年のうち一番忙しい季節だ。
夏は、彼らにとっての収穫――毛狩りと搾乳の時期。刈った毛や、搾った乳から、女たちは様々なものを作り出す季節。
男たちは、家畜の番以外は大した仕事はないが、この時期に英気を養い、訓練を積み、秋からの戦に備える。
「……独生どのは、匈奴のこと、よくご存じなのですか?」
「そんな知らねえよ。昔、親分と一緒に、胡人(匈奴)のおっちゃんから、少し話を聞いただけだ」
「胡人?」
「何でも、内紛で、親兄弟みんな殺されたってんで、漢に逃れてきたんだってさ。結構いるぜ、そうやって漢に降った連中。そのおっちゃん、道案内で張の兄貴たちと一緒に出発したけど、今頃どうしてるんだか。生きてりゃ、いいけど」
この十年の間に様々なことがあった。
衛青の兄、長君は、妹が寵妃になって間もなく、病を得て亡くなり、青が正式に衛家の家長の立場に就いた。
韓嫣は皇弟・江都王非と諍いを起こし、そのため彼を恨んだ王皇太后によって罪を与えられ、死んだ。
皇帝に並ぶほどの権勢を誇った彼の、呆気ない最後だった。
最愛の人を失った武帝を慰めたのは、他でもない衛子夫だった。結果、彼女は、武帝の寵愛を一身に受けるようになった。
男妾がいなくなっても、寵愛を受けることのなかった陳皇后は嫉妬に狂った。そこへ平陽公主がさらに彼女を精神的に追いつめた――母が、昔したのと同じように。
切羽詰まった皇后は、とうとう禁忌の呪術――媚道に手を出してしまった。そして一昨年、彼女はその罪で皇后を廃され、長門宮に蟄居を命じられた。
それ以来、皇后位は空位だった。
武帝は寵妃衛夫人を皇后にしたかったのだが、何分、卑賤の出。そう簡単に事は運ばなかった。
彼女は三人続けて女児を産んだ後、今年の初め、やっと待望の男児を産んだ。その功によって、ついにこの春、彼女は、皇后位に就くことになった。
竇大皇太后も既に亡く、今、武帝を煩わす存在といえば、ただ一つ、国境を騒がす騎馬民族国家・匈奴のみとなった。
昨年の一戦は、武帝にとって正しく満を持したものであった。が、勝てなかった。有能な将が少ないからだ。
衛青一人では匈奴には勝てない。
共に従軍した駿にも、それが痛いくらいに解った。だからこそ、戦が起こるであろう秋までには、張騫を見つけ出したかったのだ。今度こそ、勝つために。
有為を置いていけば、もっと早く草原に着く。ふと、駿の頭にそう言う考えが過ぎった。
しかし、すぐに心の中で首を振った。
そんなこと、青だったら絶対にしない。青は、弱い者は絶対に見捨てたりはしない。そして、強い者には少しも怯まずに立ち向かう人だ。
青がしないことは、絶対にしない。青がすることは、自分もする。
それは、初めて彼の元から離れ、長い旅に出るときに決めたことだった。判断に迷ったとき、彼ならどうするか、そう考えれば自ずと道が見えると、駿は信じていた。
「ほれ、喰え」
駿は、適当に作った粥を鍋から椀に入れると、有為に手渡した。有為はやっと毛氈から出ると、それを両手で受け取った。
「……独生どの、味がしません」
一口啜って有為が呟いた。
「塩、入れろ!塩!それくらい、自分でやれ」
味を付け忘れた自分が悪いのだが、何もしない有為にも腹が立って、駿はつい怒鳴ってしまった。有為は慌てて塩を捜すと、椀の中にぱらぱらと振りかけた。
駿も、自分の作った粥を口に入れてみた。本当に味がなかったので、思わず吹き出してしまった。
沙漠を越えるため、ひたすら北に進路を取っていた二人の目に、一つの穹廬が飛び込んできた。
遊牧民の移動式の住居である穹廬は、下に台車が着いており、その上に、柳材でできた家が据えられていた。馬や駱駝にこれを牽かせて、草地から草地に移動するのである。
「独生どの……どうしましょう?」
行く手に見える匈奴の住まいに動揺した有為は、震える声で訊いた。
「大丈夫だよ」
苦笑いを浮かべながら、駿は有為を宥めた。
「堂々としてろ。連中は、敵には容赦ないが、旅人には寛大なんだ。こっちから仕掛けない限り、あっちもなんにもしないよ」
駿の言うとおり、穹廬の前で、一人の女性が大きく手を振って、二人を呼び寄せていた。
「どうしましょう?」
女の誘いに、有為は戸惑いを隠せなかった。
「行くんだよ。ここで素通りしてみろ、怪しまれて、背後から襲われるぞ」
駿は馬に鞭を当てると、穹廬に向かって駆けだした。有為も慌ててその後に続いた。
女は、彼らがこちらに向かってくるのを見ると、駆け寄って二人を迎えた。
「やはり、漢の方ですね!」
彼女は、二人を見るなりそう叫んだ。駿と有為は、驚いて互いの顔を見合わせた。彼女の発した言葉は、匈奴のそれではなく、漢の言葉だったからだ。
二人が絶句したままでいるのを見て、彼女は寂しそうに笑った。
「このような、夷狄の格好をしていれば、致し方ありませんね。わたくしは、もとは山東の瑯邪(ろうや)の者でした。名を、沈玲(しんれい)と申します」
そう言う彼女の言葉には、確かに山東の方の訛りが入っていた。まだ、二十代そこそこなのだが、肌は荒れ、髪には白いものが目立っていた。
服は、いわゆる胡服。羊毛で作られた、スリットの入った長い上位に、ズボンとブーツ。腰には飾り気のないベルトが締められていた。
彼女は、自分の身の上を二人に語り出した。
今から七年前のこと。同郷の者が雁門で戍卒を務めていたが、連れ合いが急死し、不便を強いられるようになった。
戍卒というのは、長城などに沿って設けられた烽台を守る見張り兵のことだ。
徭役で全国各地から徴兵され、任地――国境沿いの烽台に赴いた。基本は一年年季であるが、他の者の分まで数年に渡って勤め上げる者も少なからずいた。
そういう者たちの面倒は、彼を送り出した郷里や一族で見るのが当然の務めであった。沈玲の同郷の者も、やはりそうだった。
連れ合いを失った彼の世話をするために、亡き妻の親戚で、年頃もちょうど良かった沈玲が選ばれ、後添えとして彼の元に赴くことになった。
そして、兄に連れられ、瑯邪から雁門に向かう途中のことだった。
彼女たちは匈奴の襲撃に会い、兄は殺され、持っていた物は全て奪われた。それどころか、彼女自身も陵辱され、そのうちの一人の妻にされた。
「あなた方は、流民ですか?」
彼女は二人に尋ねた。駿は首を振って答えた。
「人を捜して、この地まで来た者です。漢を逃れてきた者ではありません」
それを聞くと、彼女の顔色がぱあっと明るくなった。
「では、いずれ漢地にお戻りになるのですね!?」
「ああ」
「では、頼みたいことがあるのです。わたくしが嫁ぐはずだった相手は、もう年季を終え、郷里に帰ったでしょうから、致し方ありません。けれど、老いた父母に、わたくしはこうして生きながらえていると、お伝え願いませんでしょうか?
もう、二度と、お会いすることは叶いませんが、一日たりとも、忘れたこと話ありませんと。遠く離れたこの地から、長寿をお祈りしておりますと」
「そんなこと言わずに、共に帰りましょう。探し人を見つけたら、また、ここに寄ります。その時に、共に漢の地に戻りましょう」
駿は、彼女の目を見ながら、強く言った。しかし、彼女は、首を静かに横に振った。
「その言葉、大変有り難く思います。でも――」
そこへ、幼い声が響いた。小さな子供が、両手を大きく広げて彼女に飛びついてきた。
彼女は優しく微笑むと、幼子をすっと、抱き上げた。
「我が身は匈奴に穢され、匈奴の子を生みました。こうなった以上、もう、郷里に戻ることは出来ません。この地で、一生を終えるしか、ないのです」
幼子の頬に、自分のをすり寄せながら、彼女は言った。閉じている瞳から、きらりと光るものが覗いた。
そこに、若い男性が近づいてきた。幼子の跡を追ってきたのだろう。
有為の顔が、緊張で引きつった。それに気付いた駿は、さりげなく彼の背を叩いた。
男は、大声を上げて子供を抱き上げると、二人を歓迎した。そして、家の中へ上がるよう、身振りで示した。
有為は慌てて駿の顔を見た。
「中へ入るんだよ」
「え?でも……匈奴の?」
「ここで断ったら、殺されると思え」
「そうです」
沈玲も有為にさりげなく耳打ちした。
「夫は、あなた方を漢から逃れてきた流民と思っています。旅人に親切にするのは、匈奴のしきたり。従ってください。そうでなければ、本当に殺されるかもしれません。彼は、そう言う人間です」
その言葉に有為は慌てて中に入った。
「……やりきれないぜ、全く」
空行く雲を見ながら、駿は呟いた。
「女一人を、助け出すことすら出来ないなんて」
さっきまでいた穹廬を横目で眺めながら、駿は大きく溜め息をついた。
「食事をごちそうになった上、食料も分けて貰ったではないですか?あまり、彼らを悪く言うのは……」
「その食料だって、ほとんど漢の農民から奪った物だ」
「え?」
「そう言ってたよ、あの男。足りなくなったら、また盗ってくるから遠慮するなって」
駿はほんの少しであるが、匈奴の言葉を理解することが出来た。
餞別に食料を渡されたとき、駿の顔色がさあっと変わった理由が、やっと有為には解った。
「この辺は、あまりいい草地がないが、漢との国境は近い。必要な物があったら奪った方が手っ取り早いのさ。あいつらはそう言う連中だ。
馬邑の失敗があった後、俺は親分たちと一緒に、長城付近をいろいろ調べたんだ。この辺りじゃ、あいつらの略奪は当たり前のようにある。みんな、あいつらに泣かされてるんだ」
馬邑の失敗とは今から六年前、元光二年(前一三三)にあったことだ。
武帝は馬邑の商人聶壱を使って、匈奴を馬邑まで誘き出し、彼らを囲い込んで一網打尽にしようと試みた。しかし、馬邑に着く前に匈奴兵たちは異変に気付き、すぐに撤退してしまった。
この奇策は、結局なんの成果も得られぬままに終わった。それどころか、漢のだまし討ちに怒った匈奴たちによる国境付近の略奪が、返って激しくなってしまったという、皮肉な結果に終わった。
当時まだ、軍の実権を握っていなかった衛青は、自ら名乗りを上げて、長城周辺の調査に赴いた。まだ幼く、年齢的に騎士の資格を持ち得なかった駿だったが、無理矢理軍に入り、青の右腕として彼に従ってあちこちを見て歩いた。
数年がかりで、匈奴の侵攻ルートや彼らの行動をつぶさに調べ上げ、それを元にしてこちらからはどう攻めればいいのかを丹念に吟味した。その結果を持って、武帝は今度は正攻法で、対匈奴との戦いの火蓋を切った。それが去年の戦いなのだ。
「あいつら匈奴を、絶対に許すわけにはいかない」
「――でも」
それまで下をうつむいて黙っていた有為が、口を挟んだ。
「あの、沈玲と言う方、それなりに大事にされていたようではありませんか?決して不幸な身の上ではないのかも……」
「有為!何を言うんだ!」
有為の言葉に、駿は激怒した。
「あの人は、物と同じように、力で奪われたんだ。故郷と両親を想いながらも、二度と帰ることが出来ないんだぞ。これが不幸じゃなきゃ、何なんだよ!?」
「それは、その……」
駿の権幕に押されながらも、有為は言葉を続けた。
「私の、三番目の母に似ておりましたので……」
「三番目って、お前、そんなに母親がいるのか?」
「ええ、とりあえずは。
私の生母は私の誕生と引き替えに亡くなりまして、私は父の後添えに育てられました。その育ての母も、先年、病を得て亡くなり、今は私と年のそう変わらない方が、母になってます」
「――お前んちも、いろいろあるんだな」
「そこそこです。
その母の実家は、元の名家、と言うやつで、今は落ちぶれて見る影もありません。父は、そこの娘を金で買ったのです。互いに望み望まれて縁組みしたわけではありません。
でも昨年生まれた弟を、腕に抱く母の顔は、先程のあの方が、お子に見せた顔と似ていたもので――きっと、子供といれば心が和むのではないでしょうか?」
「たとえ夫は憎くても、自分の子供は愛しいってことか」
「たぶん。男の私には解りませんが」
「家族のいねえ俺には、もっと解んねえよ」
と、その時、二人の頭上をぴろろろ……と高い笛の音のような鳴き声が響いた。
見上げると、嘴から足先まで、全てが純白の、不思議な鷹が上空で弧を描きながら飛んでいた。
「あんなに真っ白なの、初めて見る。何かの前兆なんだろうか?」
駿の呟きに、有為はハッとした。
「行きましょう!」
言うや否や、有為は馬に鞭を当てると、その鷹の後を追いだした。
「有為!?」
駿は、慌てて彼を追った。
「今朝方の夢に見たのです。あの白い鷹を。あれに付いていけば、何かがあるはずです」
「夢を信じるのか!?」
「この旅だって、はじめは帝の夢でしょう?だったら、自分の夢に従ったって、いいじゃないですか」
珍しく積極的に動いた有為に、駿はとりあえずは従うことにした。凶と出るか、吉と出るか……。
二人は鷹を追って、岩山に辿り着いた。先が崖になっていたため、二人は馬の足を止めた。
気がつくと、鷹の姿は消えていた。空に浮かぶ白いものは、雲しかなかった。
二人は周囲を見渡すと、北東の方角で砂煙が上がっているのが見えた。
「あれは……」
駿は目を凝らして、それが何であるのか見極めようと必死になった。
「――匈奴兵だ!」
彼の叫びに、有為はびくっと肩を上げた。
「そんなに数はないが、――奇妙だぞ」
数騎の兵士たちで、たった一人の女性を追っているのだ。女性も、その服装から見ると、兵士たちと同じ匈奴であることは間違いないのだが……。
「有為、ここで待ってろ。ちょっと行ってくる」
「独生どの!?」
有為は慌てて彼を引き留めようとした。
「理由は解らないが、女一人に、大の男が数人掛かりとは卑怯この上ない。あの女を助けてくる」
「罪人かもしれませよ?」
「大逆非道の罪を負っているのは、あいつら匈奴兵だって同じよ。いいから、待ってろ」
そう言い捨てると、駿は馬を駆って一気に岩山を降りていった。取り残される不安から、有為も思わず彼の後を追った。
岩山を降りるのに手間取った有為が、やっとの事で追いついたときにはもう、駿は匈奴兵を二、三騎ほど馬上から引きずり下ろしていた。
(早い……)
彼の動きの速さに、有為は思わず息をのんだ。
「有為!」
有為が来たことに気付いた駿は、彼に向かって叫んだ。
「中途半端な距離を取るな!こいつらの矢は毒矢だ。射られたら命はない。近づいてこいつらの中にはいるか、矢も届かない遠くに逃げるかしかない」
そう言いながら、駿はさらに一騎を馬から蹴落とした。
「毒矢ですか!?」
毒と聞き、有為は一瞬震え上がった。
「こいつらは俺が何とかする、この女を連れて、さっきのとこまで逃げろ!」
駿は、自分の陰に隠れるようにいた女性に、身振りで有為の方に行くように促した。
ところが、有為が、懐を探りながら二人の方に走って近づいてきた。
「有為!?」
「ちょっと、目を瞑ってください!」
そう言うなり、有為は懐から出した物を、思い切り地面に向かって投げつけた。
ぱん、と大きく弾ける音が響いた。
そして音と共に、周囲に煙が立ちこめた。
「何だ!?」
突然の煙に皆が混乱していると、有為は駿と女性の手を引いた。
「煙だけで、人畜無害です。この隙に逃げましょう!」
三人は、匈奴兵が慌てふためいている間に、さっきの岩山まで戻ってきた。そして、ちょうど良い岩陰を見つけると、三人は馬を下りた。
「さっきのは、何だ?」
息を切らしながら、駿は有為に尋ねた。
「煙玉です」
有為は、懐から二粒の丸薬を出すと、彼に示した。
「以前、お話ししたことがあったでしょう?不思議な薬を売りに来る老人に貰ったのです。これを思い切り地面に叩きつけると、一時の間、煙が出てくるのです」
「面白いもんだな。あるのは、これだけか?」
「ええ、五つ貰って、一つは貰ってすぐ、試しに使ってみました。一つは、何で出来ているのかと、中を割って調べるのに使ってしまいました――結局、何故煙が出るのかは解りませんでしたが。さっき逃げるのに一つ使ったので、残りはこの二つだけです」
「そうか。またこれの世話になるかもしれないから、大事にしようぜ」
有為はその言葉に頷くと、丸薬を大事そうに懐にしまった。
「それにしても、独生どのは、お強いのですね。驚きました」
「……お前、今頃何言ってるんだよ。俺を誰だと思ってるんだ?」
駿はちょっと照れくさそうに、顔を顰めた。それから、女性の方に向き直って言った。
「なるべく馬を狙って、あいつらの足を止めるようにしていおたけど、直に追いついてくるだろう。すぐにここから立ち去れ。後は何とかする……って、言っても、俺たちの言ってることは解るわけないか」
駿は頭を掻きながらちょっと考えると、身振りと共に匈奴の言葉で、「行け」と繰り返し言った。
「馬鹿にするな。お前たちの話していることは、ちゃんと解っている」
急にその女性は口を開き、漢の言葉で言った。そして切れ長の大きな目で、二人を睨み付けた。一瞬金色に見紛うほどの明るい茶色で、中心が緑がかった不思議な瞳に、駿は一瞬どきっとした。
彼女は、見たところ、二十歳前、有為や駿とそう、年が変わらない感じがした。
光に当たると、栗色に輝く髪を器用に編み込み、両脇が布で覆われ、先がやや尖り気味の帽子の中にしまい込んでいた。逃げているうちに帽子がずれ、髪も乱れてしまったので、彼女は帽子を脱ぐと、編み込んだ髪を解いた。
その指先は、雪のように白かった。服が黒かったので、余計にその白さが際だって見えた。
黒地に赤い刺繍の入った服は、男性に比べると裾が長めに出来ていたが、馬に乗りやすいように、両脇に深いスリットも入っていた。また、男性と違い、腰をベルトで止めてはおらず、裾はふわりと広がっていた。
見慣れぬ匈奴女性のその姿に、駿は一瞬息を飲んで見入ってしまった。それから慌てて我に返った。
「漢の言葉が解るのか?」
気を取り直して、駿は女性に訊いた。
「解るも何も、私の夫は漢人だ」
その言葉に、駿と有為は思わず顔を見合わせた。
「では、尋ねてもいいか?俺の名は鄭駿、字は独生。こいつは麹(きく)有為、字を伯慈という。俺たちは、十年前、月氏に使いする途中で匈奴に捕まった使節団の行方を追っているんだ」
「使節団の行方を……?」
「その使節団を率いていた人を捜してる。名は、張騫…」
そこで、急に彼女は大きな笑い声を上げた。
彼女は懐から、錦の巾着袋を取り出すと、大事そうに両手で包んだ。そして、それに向かって小声で呟いた。
「お前が、導いてくれたんだね、ありがとう。あの人に、近づいたようだ」
それから、顔を上げると彼女は言った。
「その男こそ、我が夫だ」
その言葉を聞いて、今度は有為が叫び声を上げた。
「ほら、ほら、独生どの!夢のお告げが当たったではないですか」
「うるせえ!有為!ちょっと黙ってろ」
駿は、騒ぐ有為の頭を小突いて、彼の口を黙らせた。
「じゃあ、話は早い。教えてくれ、張の兄貴は今、どこにいるのか?いや、その前に、無事でいるのか?」
「解らぬ」
彼女はふん、と鼻で笑いながら答えた。
「――え?」
彼女は、唖然としている駿を横目に、側にあった岩に腰をかけた。
「話は長いぞ。だが、これも我が子の導き。私の身の上を聞くがいい」
そう言って、彼女は自らのことを語り始めた。
「我が名はツルゲネ。これでも、単于家の血筋、攣鞮(単于の一族)の者だ。漢人捕虜を監視するため、単于は私を騫と娶せた。今から九年前のことだ」
「九年前?子供で嫁に行ったのか?」
駿は、自分よりやや年下に思えるツルゲネに向かって、かなり不躾なことを聞いた。
「ああそうだ。子供の方が、相手も安心するからな。幼い少女が色仕掛けをするなんて、夢にも思うまい。だが、やることはやったぞ。そこまで持っていくまで、三年もかかったがな」
彼女の言葉は、きっと騫と長くいたせいであろう、妙に男っぽい話しぶりだった。色白で、大きな瞳が印象的な娘の口から漏れるには、少し違和感があった。
「騫がやっと私を妻として扱うようになって間もなく、私は身籠もった。単于の命を、やっと全うできたわけだ」
単于は、張騫の人柄を気に入り、匈奴の陣営に加えたかった。子供さえ出来てしまえば、匈奴領内に止まざるをえない。それは漢人捕虜を幕内に加えるいつもの手でもあった。
「兄貴に子供が……!男か、女か?」
「男だった。だが、それは騫も知らない」
「どういう事だ?」
「お前たち漢人のせいだ」
ツルゲネは、大きな瞳でギロリと駿を睨み付けた。
「六年前の、馬邑のこと、知っているか?」
「漢軍がお前たち匈奴のことをだまし討ちにしようとしたことか?」
彼女は頷くと言葉を続けた。
「あの一件で、単于は騫に疑いを持った。相変わらず、彼は単于に従おうとはしなかったし、むしろ内通するおそれがあったからな。だから単于は、騫を単于庭から西の領地に移した。
その時の私は、まだ十二で、初めてのお産にはまだ少し若すぎたから、長旅は駄目だと、そのまま単于庭に残された。以来、彼とは会っていない」
「そうか……。じゃあ、子供は?もう、五つか、六つになってるんだろ?どうしてる?」
彼女は、先程の袋を、ぎゅっと握りしめた。
「お前たち漢人は、本当に私の邪魔ばかりする」
「え?」
「この秋、お前たちは、我れらの聖地、蘢城を穢した。それを清めるために、我が子の血が使われた」
彼女は、袋から深紅の玉を捕りだした。鈍く光るそれは、血が固まって出来たように思えた。
「これを前にして、我が子の心臓が裂かれ、その血がこれに注がれた。我が子は、天地鬼神への、捧げ物となったのだ」
頬に、涙が一筋の流れを作ったが、彼女は気に止める風もなく言葉を続けた。
「二人で、父を待つはずであった。なのにこの子は父を知らぬままに、死者の国へ旅立ってしまった。その無念を騫に伝えるために、私は、この玉を蘢城から盗み出し、西へと向かっていたのだ」
「すまない」
いたたまれなくなった駿は、土下座をして額を地面に繰り返し打ち付けた。
「馬邑の件はともかく、蘢城の戦いは俺もかんでいる。謝っても、兄貴の子は生き返りはしないけれど、だが……」
「その通りだ」
ツルゲネは彼の頭を、足で踏みつけた。
「あの子は、帰ってこない」
「そんなこと、しないで下さい!」
二人の間に有為が慌てて割って入った。
「無意味です!今は、そんなことしている場合ですか!?」
我に返った駿は、有為に助け起こされながら、彼女に訊いた。
「あの追っ手は……」
「この玉が蘢城から失せたことに気付いた胡巫たちが遣わしたものであろう。ちょうど追いつかれたところで、お前たちに助けられた。これもきっと、この子の導きであろう」
彼女は、赤い玉をぎゅっと握りしめた。
「――それは、危険なものだ。気をつけろ」
不意に、頭上から声が響いた。三人はほぼ同時に、声のする方を見上げた。
岩山の上の方で、蒼天の雲のように白い、深衣と呼ばれる、前あわせで裾の長い服を着た青年が、座ってこちらの方を見ていた。年の頃は二十四、五。髪は結わずに垂らしていたが、色の黒々とした見事なものであった。
くっきりとした眉が印象的な、彫りの深い顔立ちをした男は、三人を見てニヤリと笑った。
有為は、その男に見覚えがあった。だが、誰だかまでは解らなかった。
「誰だ、お前は!?」
駿は慌てた。岩山の男の気配に、全く気付かなかったからだ。追っ手を播いている以上、人の気配には充分注意しているはずだったのに。
「今は、そんなこと、どうでも良い。ほれ、見ろ。追っ手が来ているぞ」
その言葉に、駿は慌てて岩をよじ登ると、男の横に立った。
確かに、追っ手がこちらに向かってきていた。さっきの戦いで多少減ったとはいえ、それでも十騎は下らない。
連中は、一心不乱にこちらに向かって馬を走らせてきていた。
「奴らには、ここに隠れていることが手に取るように解るのだよ。その玉を持っている限りな」
白い服を着た男は言った。
第三章 相柳の血
「有為!俺があの連中を食い止めているから、その間に、二人でさっきの沈玲の家まで戻れ。半日経っても俺が来ないようようだったら、そのまま二人で、張の兄貴の所まで行け!」
駿はそう言い放つと、馬で飛び出していった。
「独生どの!?」
有為が止める間もなく、駿の姿は土埃の中に消えていった。
行くに行けず、おろおろしている有為の目の前に、白い服の男が岩から飛び降りてきた。
「私も行ってくる。心配するな。ここで待ってろ」
そう言いながら、彼は駿の後を徒歩で追っていった。
「あなたは――?」
有為は、男の背中に向かって問いかけた。男はくるっと振り返ると、ニヤリと笑った。
「何を今更訊く?旧知の仲であろうに」
毒矢を警戒した駿は、大きく回り込んで、相手の背後に回った。相手がこちらに気付いたときには、もう既に矢を射るには近すぎる場所に来ていた。
駿は、俊敏の俊から来ている。
幼い頃から、すばしっこかった彼は、衛青から”俊々”と呼ばれていた。騎士になるに当たって、馬との相性がいいようにと、人偏を馬偏に替えて駿にしたのだ。
その名に恥じず、彼は匈奴のお株を奪う素早さで、相手を翻弄し、次々と倒していった。
敵にいちいち止めを刺す暇などない。
駿は、とにかく追捕されないために、相手の足――馬を狙った。敵の攻撃をかわしながら、隙をついて相手を馬から落とすか、馬を転ばすように心がけた。
しかし、どうしても多勢に無勢。こちら側の攻撃はどうしても雑になる。
落馬しても大して負傷していない兵士が、駿目掛けて毒矢を放った。
矢は、ヒュンと音を立て、駿めがけて一直線に飛んでいった。
「物騒な」
と、さっきの白服の男が不意に現れると、迷わず矢面に立った。
すると、矢は彼の目の前で、ぴたりと止まった。そして虚空に浮いたまま、ピクリとも動かなかった。
男は、ゆっくりと腕を上げると、矢の方に指を向けた。同時に、矢は、くるっと反転した。
次に彼は、指を上空に向かってあげた。それに合わせ、矢はぐんと上に向かって飛びたち、そのまま虚空に消えた
「このような、物々しいこと、止めましょうか」
男がそう言うと、匈奴兵たちが手にしていた武器が、突然、宙を舞った。そして、男の方に向かって、一斉に集まった。
彼は、腕を大きく広げて、飛んでくる武器を迎えた。そして、体をゆっくりと回転し始めた。と同時に、武器もそれに合わせて彼の周りを回り始めた。
彼は、最初はゆっくりと、そしてだんだんと早く回っていった。それに合わせ、どの武器もどんどんと回転を速くした。回る中でだんだんと武器は砕け、細かくなっていった。
粉々になった武器は、やがて、光る花びらのようになった。
彼は回るのを止めた。
花びらだけが、キラキラと輝きながら彼の周りを回り続けた。
そしてその花びらは、ゆっくりと、風に飛ばされ、天に昇っていった。
「生臭い血より、芳しい花の方が良かろう」
男はそう言って笑った。
駿も、匈奴兵たちも、その光景を、呆然と見つめるしかなかった。
「ほれ、青年。行くぞ」
男は駿に近づくと、彼の馬の尻を、手で思い切り叩いた。馬は一声嘶くと、そのまま駆けだした。
何が起こったのか、まだ理解できていない駿の横を、男は徒歩で付いていった。
全速力で走る馬に遅れずに歩く彼の姿に、駿は頭が混乱した。
夢を見ているのか、それとも自分の頭がおかしくなったのか……?
「――待てい!」
背後から匈奴の言葉で、そう響いた。意味は駿にも理解できた。
駿は、馬を止め、後ろを振り返った。
そこには、顔に奇妙な文様の、文身を施した男たちが三人、馬に乗ってこちらを見ていた。
いきなり脇の二人が、銅鼓を打ち鳴らし始めた。あまりの音に、駿は思わず耳を塞ぎ、馬も苦しそうに首を振った。
中心にいた一人が、小箱を取り出すと、両手に捧げ持った。それから、勢いよくその蓋を開いた。
中から、白い煙がもわっと吹き出した。そして、その煙の中から――毒々しい縞模様を持った大蛇が、姿を現した。
大蛇は、赤く長い舌をちろちろと出し、こちらを威嚇した。毒気のある息が、二人の方に流れてきた。
「おや、おや、こう来たか」
白服の男は、暢気に言った。
「あんた、何か策があるのか?」
彼の落ち着きぶりを見て、駿は訊いてみた。
「策ねえ……強いて言えば、逃げるが勝ち」
「え?」
男は、指をぱちん、と鳴らした。
急に、身を切るような寒風が、駿を襲った。
目の前には、雪をかぶった尾根が並んでいた。自分たちは、土埃の舞う礫沙漠にいたはずなのに、目の前を舞っているのは、白い粉雪であった。
続いて男は、手をぱんと叩いた。
と、今度は目の前に有為とツルゲネが現れた。二人とも、何が起こったのか解らず、呆然と立ちつくしていた。
「ここは……?」
彼らの問いかけに、男は何かに気付いたような顔をした。
「ああ、すまなかった。急にこの寒さでは耐えられまい」
そう言うと、男は三人の馬に、懐から取り出した丸薬を次々に飲ませた。
薬を飲んだ馬たちの体から、突然、もわっと湯気が上がった。触ってみると、燃えるように熱くなっていた。寒さで凍えていた三人は、思わず馬に寄り添って暖を取った。
「どこなんだよ!?ここは」
もう一度、駿は男に問いかけた。
「どこって、見れば解るだろう?どう見てもここは雪山だ」
「だから、」
駿は寒さで回らなくなっている口を、懸命に動かして大声を出した。
「俺たちは、沙漠にいたはずだ。なんで、雪山なんだ」
「雪山に来たからさ」
訳の解らない問答に、駿は自分の頭がおかしくなったのではないかと疑った。さっきの男の仕草といい、この雪山といい、頭がおかしいか、夢を見ているのか、どちらかでないと説明が付かない。
「あなた様は、何者なんですか?」
頭が混乱している駿に変わって、有為が問いかけた。
「おや、冷たい言い方だな。薬屋の若主人」
「え?」
街中にいる人なら、大抵、彼を「跡取り」と呼んでいて、「若主人」と呼ぶ人は、限られていた。有為は、その限られた心当たりを、懸命に思い出そうとした。
「ああ、これでは解らんか」
男は、有為の様子を見て、にやっと笑った。と、次の瞬間、男の顔がしわくちゃの老人に変わった。
「あ!」
有為はその顔を見て大声を上げた。そして、駿に駆け寄ると、彼の肩を揺すりながら興奮した口調で叫んだ。
「この人です!うちに不思議な薬を売りに来ていたのは!!」
駿は、目の前の青年が老人に変わったのを見て、確実に自分は気が狂ったのだと思った。
有為は、そんな駿に構うことなく、今度は老人の方に近づくと、跪いて深々と礼をとって挨拶をした。
「お久しぶりでございました。先程はお世話になりながら、大変な失礼をいたしました」
そう言う有為に、男は頭を上げるように促した。有為は、言葉を続けた。
「あなた様がお持ちになる薬は、この世のものとは思われませんでしたが、やはりそうだったのですね。神仙の薬を分けていただいていたなんて……こんな有り難いことはございません。もしよろしければ、お名前を名乗ってはいただけないでしょうか?」
「おや、教えてなかったか?――我が名は安期生。よく、安期先生と呼ばれているな」
「え!?」
その名を聞き、駿と有為はほぼ同時に声を上げた。
安期生と言えば、武帝が長年探し求めていた仙人の名だ。しかし、どんなに探し求めても、彼の消息も、彼のいるという蓬莱も、杳として解らなかった。
だから、駿は武帝を取り巻く怪しげな人物たちがでっち上げた、架空の人物だとばかり思っていた。
本当に、いたのか――?しかも、蓬莱にいるはずの彼が、こんな所に?
「ねえ、ちょっと」
駿は、馬に寄り添って寒さに耐えてるツルゲネに声をかけた。
「悪いけど、俺の頬を思いっきりひっぱたいてくれないか?」
「何?」
「いいから……」
そう言って、駿は頬を彼女の方に突きだした。彼女は遠慮なく張り手をお見舞いした。
冷えて、悴んだ肌に激痛が走った。二人は同時に悲鳴を上げた。
「恨むぞ。何を考えてるんだ」
ジンジンに痺れた指先をさすりながら、ツルゲネは呻いた。
「……悪いって言ったじゃないか」
頬をさすりながら駿は彼女に謝った。
「親分の教えなんだよ。悪鬼に惑わされたときは、自分の体を傷つけ、痛い思いをすれば目が覚めるってさ」
「悪鬼?」
「しっかし、こんだけ痛いんじゃあ、これは惑わされたんじゃない。彼は本物の仙人らしい」
その言葉を、ツルゲネはふんと鼻で笑った。
「安期先生!本物だって、信じていいのか?」
駿は、老人に声をかけた。
「そうだな。偽物がかなり出回っているらしいが、それではないのは確かだ」
「……また妙なことを言う」
「仙となると、全てが枯れ果て、実体が無くなるのだよ。だから、変幻自在である反面、掴み所もなくなるわけだ」
「あんたの話も、掴み所がねえよ」
駿は、彼と話してると、本当に気が狂ってくるのではないかと感じた。一方の有為は目をキラキラさせながら、彼のことを見ていた。
「老人になったり、青年になったりしたのは、そう言うわけですか」
「そうだ。もっと若くできるぞ」
そう言うと、安期生の姿がまた変わった。今度は見たところ十五、六、有為とそう変わらない年格好になった。
「はあ……お見事です」
有為は感嘆の声を上げた。
「私の店にお出ましになるときは老人で、先程は若者の姿でございましたが、何か訳などございますのでしょうか?」
「姿を決めるのは私ではない。私を見る者たちだ。お前の店に薬を持ち込むと、私のことを経験を積んだ薬士と見るであろう?だから、年寄りになるわけだ。匈奴の連中は、強きを重んじ、年寄りを軽んじる。よって、経験のない少年でもなく、弱った年寄りでもない若者の姿になるわけだ」
「では、私たちの前ではどんな姿に?」
面白そうに有為が尋ねた。
「どうするかな……おお、そうだ」
安期生はツルゲネの方に向き、声をかけた。
「おねえさん、どの姿がいいか?」
訊かれた彼女は、明らかに不快な表情を浮かべた。
「そんなこと、私に訊くな」
「じゃあ、そこの青年は?」
「俺にも訊くな!もう、この寒さを何とかしろ!」
寒さに耐えかねてる二人に気付いた有為は、慌てて安期生に言った。
「では、中間を取ってはどうでしょう?」
「そうだな」
言うなり、彼は先程の青年の姿になった。
それから、彼は腕を大きく振り上げた。と同時に、大きな火柱が上がった。
「お前たち、雪山の支度はないようだな。とりあえず、これで少しは暖まるだろう」
「雪山の支度って、俺たちは今まで沙漠にいたんだ。確かに北に向かってはいたが、いきなりこんな所に放り投げ出されて、どうしろって言うんだよ」
火に当たりながら、駿はぶつくさと呟いた。
それを聞いた安期生は、にやっと笑うと、足元の雪を掬った。雪は、彼が手に取った途端、白貂の毛皮に替わった。
彼はそれを駿とツルゲネに投げ渡した。
「火で、溶けないのか?」
それを受け取ったツルゲネは、彼に訊いた。すると彼はまたにやっとした。二人の困惑する顔が、よほど面白いらしい。
「実体はない。私と同じようにな。溶けると思えば溶けるかもしれん。だが、これで暖まると思えば、暖かくなる。お好きなように」
駿とツルゲネは顔を見合わせると、とりあえずそれを羽織ってみた。雪ではなく、確かにそれは毛皮であり、暖かかった。
有為だけは毛皮を羽織っていなかったが、仙人に出会えた興奮で、寒さをすっかり忘れ去っていた。彼は、頬を紅潮させながら尋ねた。
「先生、どうしてお姿を表されたのですか?」
「それは、そこの娘の持つ、赤い玉のせいさ」
安期生はツルゲネの方を指し示した。彼女は反射的に、ぎゅっと身を固くした。
「その玉は玗琪の玉という、ちょっと厄介な代物なのだ」
その由来は、太古、禹の時代に遡る。

太古、王朝が生まれる遙か昔、華夏の地は禅譲――徳のある者が徳のある者へと位を受け継ぐ方式で、五帝たちが代々治めていた。
当時、夏華の地には悪龍が蔓延り、帝たちはそれら悪龍たちと闘いを繰り広げていた。
五帝の最後の一人、帝舜から位を譲り受けた禹――夏王朝の始祖は、また、龍との闘いも引き継いだ。そして彼は相柳を討った。
相柳は九つの首を持つ人面龍神で、身は青く光る鱗で覆われていた。
九つの首は、九つの山を喰らい、相柳が通った後は、土が抉れ、沢や谷となった。
長い長い闘いの後、禹は、相柳を殺した。
地に流れ出た相柳の血は、異臭を放ち、植物は全て枯れ果てた。禹は、相柳の死骸を深い谷に埋めたが、土が何度も壊れ、その都度、死骸は地表に現れた。
そこで彼は、五帝に祈り、北の果てに壇を造った。そしてそこに、相柳の死骸を封じ込めた。
方形をした壇を守護するのは虎のような縞模様を持つ大蛇だった。その大蛇がいるため、誰も壇に近づくことができなかった。
長い時を経て、壇の中央には、生命樹が生えた。それは大きく枝葉を広げ、相柳が再び地上に出てくることを阻んでいた。
さらに長い年月が経ち、相柳の血を吸った樹は、やがて赤い玉の実をつけた。それは、相柳の血が固まった物でもあった。
「何時の頃からか、その樹は玗琪の樹と呼ばれるようになり、その実は玗琪の玉と呼ばれるようになった。
その玉は、もとは悪龍の血。それ故に恐ろしいまでの呪力を持つ。持つ者を、滅ぼしかねないほどの、恐ろしい力をな」
「この玉は、匈奴の聖地、蘢城にあったそうです」
「そこなのだ」
有為の言葉に、安期生は手を打って答えた。
「本来は、五帝の壇にあって、相柳を封印する物。しかし、それはある者によって持ち去られ、蘢城に置かれた」
「ある者……?」
駿も、有為と共に息を飲んでその話を聞いた。
「それは、匈奴建国の祖、冒頓単于だ」
雨が降っていた。
どす黒い空に、時折、轟音と共に光りが走っていった。稲妻だ。
滝のような雨に打たれながら、彼はひたすら馬を進めていた。この雨が、体中についた血を、洗い流してくれる。
今、彼を突き動かしているのは、恨みだった。
彼がこうして、生き延びられたのも、その恨みのおかげだった。
彼は、父親に殺されかけたのだ。
単純に、目の前に刃を突きつけられ、死を宣告された方が、どれほど楽であったか。
回りくどい方法で、自分を遠ざけ、挙げ句の果て、父自らは手を汚さずに、彼を葬り去ろうとしたのだ。
誇り高い彼にとって、それは耐え難い屈辱であった。
彼――冒頓は匈奴族の首長、頭曼の息子であり、彼の跡を継ぐべく、部族から指名された者でもあった。
しかし、ある事をきっかけに、彼の境遇が変わった。
それは、頭曼の一番若い妻が男児を産んだことから始まった。
妻は、自分の子を、跡継ぎにするよう、頭曼に迫った。彼も、若い妻の言うことを聞き、生まれたばかりの幼子を後継にすることに決めた。
次期首長の座を奪われた冒頓は、間もなく月氏へ人質として送られた。
そして彼が月氏に着くと同時に、頭曼は月氏を討った。
当時の月氏は、匈奴よりも強大で、彼らの攻撃をいとも簡単に防いだが、事情を飲み込めない月氏の王は、怒りの矛先を冒頓に向けた。
「和睦を申し入れるために、太子であるお前をこちらに寄越したのではないか?それとも、和睦は表向きで、内と外から我々を討とうと企んだのか?この儂を、殺そうと企んでいたのか?」
冒頓は何も答えなかった。彼もまた怒りに打ち震えていた。
沈黙は肯定ととらえられ、彼は従者と共に処刑されることになった。
後ろ手に縛られ、処刑場へ連れて行かれようとしてもなお、彼は一言も発せず、申し開きも一切しなかった。
申し開きの代わりに、彼がしたこと、それは――
自分を取り押さえていた月氏兵の喉を噛み切ることであった。
その場は騒然となり、月氏王の顔色は変わった。駆けつけた兵士たちは、冒頓の動きを止めようと次々に襲いかかった。
彼らともみ合っているうちに、はずみで冒頓の縛めが解けた。すかさず彼は剣を奪い取ると、目の前の一人を斬り殺した。
奪った剣を振り回しながら退路を切り開くと、冒頓は駃騠(汗血馬)を奪い去り、ただ一騎で月氏から逃走した。
行き先など、考えていなかった。ただ、このまま死ぬわけにはいかない。その思いだけが、彼を突き動かしていた。
(あの女……!)
彼の脳裏には、父の、自分より若い妻の顔が焼き付いていた。
自分の求婚を断り、父に嫁いだ女。そのことについては、彼は深く考えなかった。匈奴の風習により、自分の生母以外の父の妻は、父の死後、息子が妻にすることになっていたからである。
時間はかかるが、やがて自分の物になる。その程度しか考えていなかった。
しかし、女は冒頓を恨んでいた。以前、彼に恋人を殺されたからである。彼女は、冒頓の父、頭曼に嫁ぎ、恋人を殺した仇を討とうとした。
そのことをすぐに気付いていれば、彼はこんな目に遭わずにすんだはずである。
また、若い妻の言いなりになった父にも、冒頓は深い怒りを感じていた。その怒りは恨みとなって、彼を前に進める力になっていた。
生臭い血の臭いが、体中に染みついていた。
月氏を抜け出すときに殺した敵の血と、自分の血の臭い。傷は浅くはなかった。だが、痛みは感じなかった。
そのうち、雲が湧き、雷鳴が轟くと、激しい雨が彼の体を打ち付けた。
体に付いた血は、この雨で洗い流された。しかし、染みついた血の臭いは、消えることがなかった。一生。
雨の中、彼は導かれるように、ある場所にたどり着いた。
それは、方形をした盛り土で、中心には大きな樹が枝葉を広げていた。
その樹には、血のような色をした赤い玉が、九つ、雨に濡れて光っていた。
(力が欲しいか?)
冒頓の頭の中に、声が響いた。その声は、大樹から聞こえてきたような気がした。
(その恨みを晴らす力、欲しくないか)
彼は、馬を下りると、その声がする方に、足を踏み出した。
縞模様のある大蛇が、シューッと言う声と共に、牙を剥きだしたが、彼は動じなかった。それどころか、彼が睨み付けると、蛇は視線を逸らし、そのまま姿を隠してしまった。
(さあ、この実を取るがいい。好きなのを一つ、取るがいい)
声は言った。
冒頓は導かれるままに、その実を一つ、もぎ取った。
雷鳴が再び轟いた。それは赤く光り、いくつもの柱を伴った、巨大な稲妻であった。
落雷のショックで、冒頓ははじき飛ばされ、そのまま気を失った。
気がつくと、方形の壇も、赤い実をつけた大樹も、跡形もなくなっていた。
目の前に広がる草原に、彼は見覚えがあった。
彼は、いつの間にか自分の領地に帰ってきていたのである。手には、あの赤い実が確かに握られていた。それは堅く、宝石のように滑らかで輝きを放っていた。
手にしたその実から、不思議な力が伝わってくるのを、彼は感じた。
それは殺したい衝動。憎い者の血を、この目で見たい衝動であった。
彼は、自分の集落に戻ると、己の家族を全て殺害した。
憎い父も、あの女ももちろんのこと、幼い弟妹も、自分の妻も、我が子も、全てを血祭りに上げた。
彼の内に湧く力は、それだけでは満足しなかった。彼は、首長に就任すると、兵を率いて周辺部族を討ち、次々と支配下に治めていった。
そして気付くと、冒頓は強大な帝国を築き上げていた。
彼は、遊牧民匈奴部族の一首長ではなく、騎馬民族国家匈奴の王――単于となったのである。
彼は、かつて自分を辱めた月氏も討ち、その雪辱を晴らした。そして同じ頃興った、劉邦の漢とも戦い、彼を平城(山西省大同の東)で破った。
この戦いで匈奴は漢から多大な歳弊を得ることができた。それから七十年が経ち、武帝が即位した今でも、匈奴の優位は揺るいでいない。
誰も、冒頓の敵にはなり得なかった。彼の胸元には、いつもあの赤い玉――玗琪の玉が揺れていた。
それは、多くの血が流れるほどに、美しく輝いた。
やがて冒頓の寿命が尽きると、その子が跡を継ぎ、老上単于となた。その玉も受け継がれたが、これを直接持つことは出来なかった。
多くの血を吸い、呪力を増したその玉は、持つ者すら滅ぼしかねる物だったからである。
玗琪の玉の赤は、血の色。
持ったら最後、抑えきれない衝動に駆られ、側にいた者を見境なく血祭りに上げ、最後に自分自身も血の海に沈まなければ収まらなかった。
老上以来、玗琪の玉は、祭壇に安置されることになった。匈奴の祭壇は、”蘢(ろう)”と呼ばれ、土台の上に石や枝を積み重ねて造られていた。
祈るたびに、石や枝が追加され、年月と共に成長する祈りの場でもあった。
単于庭の側に造られたそれは、匈奴領内で最も大きく、最も荘厳に造られたために、蘢城と呼ばれた。
中心には、玗琪の玉が輝き、周囲には漢から歳弊として送られた絹布が飾られ、風になびいていた。
毎年正月には、匈奴の首長と隷属部族の王たちが集まり、その玉を祀った。
「――戦いにおいて、匈奴が向かうところ敵なしであったのも、全てはその玉の呪力の賜物であった。ただ、元は五帝の壇にあった物。もとあった所に戻すべきだという考えが、神仙界では主流であった。だが、匈奴の神と共に祀られている以上、手を出すわけにもいかなかった」
安期生は、三人の顔を、交互に見つめた。
「今、ここで、こうして見えているのは、全て、天の導きだ」
その言葉に、三人全員、息を飲んだ
「張騫の胡妻は、冒頓と同じように、その玉を持てる者だ。だからこそ、こうしてここまで来られた。そうでなければ、とっくに死んでいる」
「それは、どういう事だ?」
大方の予想はついたが、駿は聞かずにはいられなかった。それを察したのか、安期生も静かに頷いた。
「この女を、突き動かしているのは、”恨み”だ。そうであろう?」
ツルゲネの顔色がさあっと変わった。そして持っていた剣を抜き、三人に向けた。
「だったら、どうする?」
「どうもしない」
眉一つ動かさずに、安期生は答えた。
「だから、その物騒な物をしまいなさい。利害は一致してるんだ。もし、そなたが恨みをなくせば、玉の呪力は解き放たれ、ここにいる全員に危険が及ぶ。その呪力は、私でもそう、立ち向かえる物ではないのだよ」
「つまり、何が言いたいのだ?」
剣を向けたまま、彼女は尋ねた。
「行き先は同じ。ただ、お前がその恨みを果たすのが先か、呪力に飲み込まれるのが先か、問題はそこだけだ。そこで有為、お前を選んだのだ」
「――どういう事です?」
今度は有為の顔色が変わった。自分は、いい加減に選ばれたはずなのだ。
「お前さんには、仙骨があるのさ。だからこそ、私も以前から目をかけ、度々姿を現していたのだ」
「そんな……」
思いも寄らない言葉に、有為は何度も首を振った。
「信じられぬか?だが、お前さんはさっきから、そんな薄手でよく平気でいるではないか?連れの二人は寒さで震えているというのに……」
安期生に言われ、有為は慌てて自分の身を確かめた。言われてみれば、急に寒さが身にしみてきた。
「……忘れていました。先生にお会いできた興奮で、寒さのことなど、すっかり忘れておりました」
「そこだよ」
安期生は嬉しそうに言った。
「お前さんには仙骨がある証拠だ。心が、体に勝つのだよ。これで”枯れ”さえすれば、お前は”仙”になれるというものだ」
「私は、仙人になろうなどと、思ってみたこともございません。ただ、先生のお持ちになる薬の調合を学びたいとは思っておりました。もし、許されるのであれば、お教えいただけないでしょうか?」
安期生は、静かに頷いた。
「その欲のなさ、まさに仙の資質だな。だが、その前に、お前にはやってもらえなければならぬ事がある。そのためにわざわざこの旅に呼び出したのだ」
「呼び出した?」
「ああ、東方朔に一肌脱いでもらってな」
「東方先生!?あの人は、いい加減なことしか言わない人じゃ……」
何度も彼にからかわれている駿は、思わず声を上げた。
「凄い言われようだな……まあ、仕方ないか」
安期生は苦笑しながら答えた。
「彼は歳星(木星)の化身なのだ。人を惑わすように動くが、実際は天の理にかなっている。それが歳星の動き。掴み所がないのは仕方があるまい」
「掴み所がないのは、安期先生の方じゃないか」
駿はぼそっと呟いた。
第四章 氷河
「この氷河の先に、目指す男がいる」
眼下に広がる谷を指さして、安期生は言った。
「氷河?一面に氷が張っているようにしか見えないけれど……」
駿は、谷を覗き込みながら言った。
「そう、氷だ。この氷は、ゆっくりと麓に向かって移動しているのだ。それ故に、氷の河、氷河というのだ」
谷から冷たい風が吹き上がり、駿は思わず身を竦めた。安期生は構わず言葉を続けた。
「この氷は、やがて溶けて水に変わる。その水の流れは、礫沙を横切り、草原に出、沼沢となる。その地に張騫はいる」
身を切る寒風にさらされながら、駿は氷河の先を見つめていた。遠くには、礫沙漠が霞んで見えた。さらにその向こう、そこに、彼がいる。
「ここから、そこまではどれくらいかかるんです?」
駿の問いかけに、安期生は頷きながら答えた。
「馬にやった仙丹の効き目は五日。雪山に慣れぬとはいえそれぐらいあれば充分下山できる。後は、川の流れに沿って、まっすぐ行けば一月もかからぬ」
それから、安期生は駿の肩を軽く叩いて言った。
「問題は、別にある。お前、女を知ってるな?」
「は?何を言うんですか!?」
駿は顔がかあっと赤くなるのを感じた。確かに、長安を出て以来、女性の柔肌には触れてはいない。
「まだ、妻は娶っていないようだな。と言うことは、秦氏の女(遊女)専門か」
(解ってるなら、訊くな)
心の中にもやっとしたものが湧き上がるのを押さえながら、駿は安期生を睨み付けた。
「年相応で結構なことだ。男女の交わりは陰陽和合、この世を形作るためには必要不可欠な行いだ。ただ、時と場合を弁えなければならぬ」
「また変なことを……。確かに、やりてえ時はあるけど、むやみやたらに手を出すことはしません!そんなの、鬼畜のやることだ」
「私は騫の胡妻とのことを、心配しているのだ」
「先生は、俺が、兄貴の嫁さんと間違いを犯すとでも思ってるんですか?」
「お前さん自身には、問題はない。大丈夫だ。だが、胡妻は違う。気をつけろ」
「解ってます。俺は親分にも、兄貴にも顔向けできないようなことはしません、絶体に」
「その心意気なら、特に秘訣を授けなくても、大丈夫なようだな」
安期生の言葉に頷きながら、駿は、ツルゲネの方を見た。
彼女は、有為と共に火を囲んで食事を取っていた。たしかに彼女が気になってはいた。だが、それは好意と言うより、懸念だった。
「お前たちが、この雪山を降ってるあいだ、私は有為を借りる。二人きりだ。がんばれよ」
「借りる?」
「詳しいことは、彼から聞いてくれ。まずは、彼に話をする」
そう言うと、安期生は有為を呼んだ。そして駿には変わって食事を取るように指示した。
安期生に呼ばれ、有為はちょこちょことこちらに走ってきた。
「先生、お呼びですか?」
頬を紅潮させながら有為は言った。とにかく、憧れの彼と話ができるのが嬉しくて仕方ないのだ。
「これから数日、お前は駿と離れ、私と行動を共にして貰う」
その言葉に、有為は驚きの声を上げた。
「私が……そんな」
「いや、そのためにお前を呼んだのだから――お前は、私に仙丹の作り方を教わりたいと言ったな」
「はい……身の程知らずとは思いますが」
その言葉に、安期生は首を振った。
「いや、資質はある。だが、そのためには、まず、やって貰い事がある。それを成し遂げれば、お前に仙丹の作り方を教えよう」
「本当ですか!?」
「ああ、だが、私の言うことを聞けるか?」
「はい!聞きます」
有為は、心臓の鼓動の高鳴りを感じていた。そんな彼を見ながら、安期生はニヤリと笑った。
「では、お前に、追っ手の胡巫との戦いを命じる」
「は?」
一瞬、聞き間違いではないかと有為は思った。駿ならともかく、自分は戦士ではない。徭役で徴収されたって、そのまま騎士に登用されるような優秀な玉ではない。せいぜい戍卒が関の山だ。
戦うなんて、そんなこと、自分にはできるはずがない。
「そんな顔をするな」
彼の心の内を察した安期生は、彼の肩を軽く叩いた。
「今は私の術で、彼らとは遠く離れた場所にいるが、玗琪の玉がある限り、連中にはこちらの居場所が手に取るように解る。彼ら匈奴の速さは、お前だって話には聞いているだろう?追いつかれるのも時間の問題だ。
兵士たちであれば、駿が相手になる。だが、胡巫は精霊を使役する事ができる。これでは、駿は手の出しようがない」
「先程のように、先生が手を貸してくださるのではないのですか?」
駿の問いに、安期生は首を振った。
「私は、この世の者ではない。仙となった身で、彼らの相手をすることはできぬのだ。仙界には、仙界の掟がある。だから、お前を呼んだのだ。お前はまだ仙ではない。だが、自身の持つ仙の資質で、彼らに対抗できる者なのだ」
「……そんなたいそうなこと、私にはできません」
「情けないことを言うな。そのために、これから数日間、修練するのだよ」
冷え切った体に、温かい食事は有り難かった。駿は、口に運ぶたび、体の中がホッとしたものに包まれるのを感じた。
どこで、どう調達したのかは知られないが、安期生が用意した食事は、どれも初めて食べるものばかりであったが、皆、口に合い、腹も満足するものであった。
ツルゲネは、もう食べ終わって、身なりを整えていた。こういうところは、やはり年相応の娘らしい。
「小姐さん」
声をかけられて、彼女は顔を上げてこちらの方を見た。
「――何か、用か?」
駿も、彼女の顔をじっと見つた。彼女の瞳の中に、焚き火の炎が映って、揺らめいていた。
「お前、兄貴に会ったら、どうするつもりだ」
「どうするって?」
「とぼけるなよ。――お前、兄貴を殺す気なんじゃないか?」
二人のあいだの空気が、一瞬凍り付いたように感じた。
「お前の持つ、玗琪の玉は、深い恨みがないと持つことができないという。会うだけで済むほどの恨みじゃない。殺さないと収まらない、そうじゃないか?」
ツルゲネの顔に、嘲笑が浮かんだ。
「解ってるようだな。……私は、お前たち漢人が憎い。私がこのような目にあったのも、全てお前たち漢人のせい。漢人の夫にならなければ、私はこんな目に遭わずにすんだ」
彼女は、玉の入った袋をぐと握りしめながら言った。
「私の本心を知った以上、どうする?殺すか?どうせ生きていても仕方ないのだ、どうぞ、殺すがいい」
「……馬鹿なこと言うな」
駿は首を振った。
「俺は女子供には、手を出さない。お前は殺さない」
ツルゲネは、駿から目を逸らさず、じっと彼のことを見つめていた。その、刺すような視線に耐えきれず、駿は思わず下を向いた。それでも言わなければならない。彼は、言葉を続けた。
「お前は、兄貴に会って、子供の無念を伝えるんだろう?兄貴だって、きっと、知りたいはずだ。今だって、きっとまだ見ぬ子の成長を、その死を知らぬまま、楽しみにしてるはずだ。兄貴は、そう言う人だから。だから、一緒に行こう。兄貴を捜しに」
「だが、会ったら私は騫を殺すぞ」
「それはさせない。絶体に。俺は命に替えても、兄貴を守る」
駿は顔を上げて、彼女の顔を見た。彼女の瞳は、涙で潤んでいた。彼女はふいっと横を向くと、そのまま立ち上がって向こうへ行ってしまった。
入れ違いに、有為が戻ってきた。
「どうしたのです?」
ぶすっとした駿の顔を見て、有為が訊いた。
「どうもしねえよ。あの女としばらく二人きりだと思うと、頭が痛いだけだ」
「先生からお聞きになってるのですか?」
「少しだけな」
安期生は有為に語った。
もし、あの玗琪の玉が胡巫の手に渡ってしまったら、それは匈奴の神の許に戻ってしまう。そうなったら、安期生たち仙界のものには手出しができなくなる。
地上には地上の秩序があるように、神仙界には神仙界の掟があるのだ。
直接、戦うわけにもいかない彼らにとって、全てを有為に託すしかない。
「胡妻が恨みから解き放たれたら、あの玉の呪力もまた解き放たれる。その時は、私たち仙界の者が何とかしよう。有為、お前は胡巫から、何としてもあの玉を守り抜け。そのための秘術を、これから授ける」
「間に合うのですか?秘術を身につける前に、彼らが追いついてしまったら」
「その心配はいらない。間に合うように、ちゃんと考えている。最も、お前の努力も大きく関わっているが」
有為は心中複雑なものがあった。安期生の薬の調合法を知ることは、かねてからの願いであった。だが、それを教えて貰うための条件が、あまりにも重すぎた。
「私に、できるのですか」
「できるから、選んだのだ。そんなに私が信じられぬのか?」
「いえ、そういうわけでは……」
任せるしかない、託すしかない。自分が任されるように、託されるようになるためには。
「お前、本当に大丈夫なのか?」
沈んだ表情の有為を見て、心配そうに駿が言った。
「何を言うんですか!」
有為は苦笑しながら、精一杯の虚勢を張った。
「そちらこそ、ご婦人と二人きりなんです。間違いなど起こさぬように、お気をつけ下さいね」
「お前まで、俺を盛りのついた馬みたいに言うな!」
駿は、有為の頭を軽く小突いた。小突かれたら、不思議と気分が楽になるのを、有為は感じた。
二人は連れだって、ツルゲネの所へ歩いて行った。出発の時、別離の時が近づいていたのだ。
「小姐(ねえ)さん」
谷底の氷河を眺めていた彼女は、声を掛けられると、振り返ってこちらを睨み付けた。
「何か用か?」
「ああ、もうそろそろ出発だ。支度をしてくれ」
「そうか」
そういうと、彼女はすたすたと馬の方に向かって歩き出した。
「それから――」
去ろうとする彼女を、二人は慌てて止めた。
「有為は、しばらく安期先生の所にいることになる。だから、この雪山を下りるのは、俺とお前の二人きりだ」
彼女は足を止めて、二人の顔を交互に見た。
「有為とは、もうこれで別れか?」
「いや、下山した頃に、また合流する」
「そうか、それまでは、駿と二人きりか。我が夫を私から、命がけで守る、駿と」
嘲笑と共にそう言うと、彼女は自分の馬の方に歩いていった。
「――むかつく女だ!」
彼女の背中に向かって、駿は毒づいた。
「おい、人のこと、駿って呼び捨てだぜ。自分のこと、何様だと思ってるんだ」
駿は有為に詰め寄ると、そう訴えた。
漢人は風習で、成人は名前を二つ持っている。一つは諱(いみな)といい、これは両親や君主、上司、師匠など、目上の人間にしか呼ぶことが許されない名だ。それ以外の者は、通常、字という、もう一つの名で呼ばなければならない。
「あんな女に、なんで諱で呼ばれなきゃならないんだよ。あいつ年下だぞ、本当にむかつく」
「年下かどうか、解らないじゃないですか。だって、独生どのはご自分の正確な年齢、ご存じないんでしょ?」
「軍籍では、俺、二十二だ」
「そのことは、軍に入るために、サバ読んだって、自分で言ったではないですか!私と同い年の可能性だってあるんでしょう?そうしたら、彼女の方が上。おまけにあなたが「兄貴」と慕う方の細君ではないですか?別にどう呼ばれようが、従うべきです」
駿の正確な年齢が解らないのは、拾ったとき、彼が幾つぐらいだったか、衛青がよく覚えていないからだ。大体、青自身だって、平陽侯邸で兄姉と再会するまで、自分の年齢をちゃんと知らなかったぐらいだ。
だから、彼の年齢は十五から十八の間らしいのだが、正確な生年が解らないことを逆手にとって、軍籍上では二十二になっている。
漢の法政では、十五歳以上が壮年で、一人前に扱われる。
駿のような庶民が正式に軍に入るには、徴収されてから一年以上が必要で、なおかつ上官の選抜、推薦が必要になる。
少なくとも十六歳以上でないと騎士になれないわけである。
彼は、六年前、青が国境の調査に赴くときの手勢に加えて貰うため、四つ以上サバを読んで、無理矢理軍籍に入り、衛青麾下の騎士になったのである。
「ったく、解ったよ!」
やり場のない怒りを、足元の岩にぶつけながら、駿は怒鳴った。
「どうしてそんなに、怒ってるのです?本当に、これから二人きりで大丈夫ですか?」
「大丈夫も何も……」
駿は、息を切らしながら言った。
「だから、今のうちに、怒るだけ怒ってくのさ。有為!付き合え!」
「は?」
胸ぐらを捕まれた有為は、思わずのけ反った。そこへ、天の助けとばかりに安期生の手が入った。
安期生は駿の口に、ぽん、と丸薬を投げ込んだ。
強烈な香味が口の中に広がり、彼は思いきり咽せ込んだ。
「先生……なんなんです、これ?」
有為は、咽せ込んで踞っている駿の背を叩きながら、安期生に尋ねた。
「ああ、気を整える薬だ」
「え?」
「そんなに怒っても、仕方ないだろう?駿」
駿は息を落ち着けると、顔を上げて、安期生を見た。
「彼女は、胡人。胡には、胡の考え方、風習がある。細かいことにいちいち怒り、気を乱すようでは、この先保たぬぞ」
駿も、その通りだと思った。薬のおかげか、確かに気も落ち着いてきたようだった。
「先生、ありがとうございます」
彼は立ち上がってそういうと、安期生に礼を言った。
「何々、――では有為、行くぞ。駿、彼の荷物と馬は頼んだ」
「持っていかないのか?」
駿の問いかけに、有為は頷いて答えた。
「これから私たちが赴くところには、必要ないそうです」
二人は駿に別れを告げると、そのまま虚空に姿を消した。
安期生が現れて以来、常識では考えられぬ光景が何度も現れたが、何度見ても、駿はそれに慣れなかった。
彼は首を動かしたり、目を擦ったりしながら、大きく息をついた。
安期生の言うことは、尤もだと思う。だが、それだけでは、どうにも気が晴れなかった。
彼女は、張騫を殺すという。恨みのために。
それは絶体に許し難いことだ。
だが、事あるごとに、あの玗琪の玉の入った錦の袋を、ぎゅっと、胸に抱く彼女を見ると、また、別の想いに駆られるのだった。
彼女が、そこまで深い恨みを抱くに至った過程を、自分は知らない。
知っている部分は、自分たち漢人が深く関わっている。それどころか、彼女の子が生け贄にされる原因を造ったのは、他でもない、自分たちの軍だった。
自分は、どうしたらいいのだろう?
それは答えのでない難問だと、彼は思った。
そんな問題に遭遇したとき、衛青はどうするだろう?そう考えても答えは出なかった。
青は、そんな問題に出会ったとしても、おくびにも出さずに平然としていた。そしていつの間にか、解決していた。
(……しか、ないか)
駿も、彼に倣って、平然としているしかないと、決めた。
雪山の下山は、思った以上に難航した。駿も、ツルゲネも、雪山の経験がなかったため、何かと手間取ってしまったからだ。
(本当に、五日で降りられるのか?)
遅々として進まない歩みに、駿は焦りを感じ始めていた。
雪山向きの装備もない中、こうして進めるのも、安期生の術が効いているからだ。ただ、それは五日間しか保たない。
一日、一日と、過ぎていけばいくほど、駿の焦りも募っていった。
ツルゲネとの会話も、ほとんど無かった。二人は必要最低限しか言葉を交わさなかった。
ほとんど会話がないのは、有為と長安を出た頃と似ていたが、有為と違って、彼女との間には、得も言われぬ緊張感が漂っていた。
「――道を、誤ったようだな」
行く先は断崖。道らしい道は、二人の足元で途絶えていた。
「いや」
ツルゲネは先を示しながら行った。
「この部分を越えれば、歩きやすい部分が見える。足場になりそうな部分もあるから、このまま進もう」
「馬はどうする?」
「私の馬は、呼べばちゃんと来る。それに馬だけの方が、この崖を上手く越えられる」
(さすが、匈奴の娘だ)
駿は、彼女の度胸の良さに感心した。もっとも、だからこそ、彼女は一人で張騫の元に進もうとしたのだ。
駿が先に行き、足場を確かめてから、彼女を呼んだ。彼女は、駿が歩いた部分に従って、注意深く進んだ。
今日は、少し気温が高かった。
昼近くになって、どんどん気温が上がってくると、氷が溶け出し、ぬかるんで滑りやすくなってきた。
「小姐(ねえ)さん、気をつけて……」
駿は、足元が落ち着ける場所を見つけると、そこからツルゲネに手を伸ばした。進むのに苦労していた彼女は、迷わず彼に手を伸ばした。
彼女を引き上げると、そこで二人とも、ほぼ同時に大きく息をついた。
「ここで少し休むか?」
「その必要はない。もし、疲れたのなら勝手に休め。私は先に行く」
彼女は、駿の手をふりほどくと、勝手に先に進み始めた。
「勝手に行くな!危ないぞ」
そう叫んだが、間に合わなかった。彼女は足を踏み外すと、そのままふわりと宙を飛んだ。
「おい……!」
駿も、彼女に向かって飛び出した。
何とか彼女の袖を掴むと、そのまま力任せに自分の方に引き寄せた。しかし、それで駿も大きくバランスを崩した。
彼は、とにかく彼女に怪我をさせまいと、彼女の体をぎゅっと抱きしめた。そしてそのまま体を丸めて崖を滑り落ちた。
何度も崖に体を打ち付け、大きく跳ね飛ばされながらも、何とか死なずに済んだらしい。
体が確かに地面にあるのを確かめると、駿は大きく息をついた。
「大丈夫か?怪我はないか?」
駿は、自分の胸に顔を埋めているツルゲネに、声を掛けた。
ツルゲネは顔を上げ、ぼうっとした顔で彼の顔を見つめた。
「怖い思い、させちまって悪かったな。怪我はしていないか?」
「……そういう、お前こそ、大丈夫か?」
か細い声で呟くように彼女は訊いた。
駿は、したたか打った場所を確かめると、笑った。思ったより怪我をしていないのでホッとしたのだった。
きっと、安期生の術のおかげだろう。そうでないと、説明がつかないくらい、軽傷だった。
「大丈夫だよ」
「お前が大丈夫なら、私は大丈夫だ」
そういうと、彼女は立ち上がった。
「……お前が守ってたんだから」
彼女は匈奴の言葉でぽそっと呟いた。駿は、気付かなかったようだ。
彼も立ち上がると、自分たちの場所を確かめた。
「結構落ちたな。谷底の氷河の方が近いや」
「では、昇るより、下りて先に進もう」
「そうだな」
二人は、今度は崖を慎重に下り始めた。
「今度は落ちるなよ」
さりげなく彼女をかばいながら、駿は言った。ツルゲネは何も答えなかったが、今度は素直に彼に従っていた。よっぽどさっきのことが懲りたのだろう。
氷の河は、思っていたよりも静かであった。流れているというが、そんな風には微塵も感じられなかった。崖の細道を進むよりも、ずっと歩きやすかった。
それが、油断を生んだ。
今日は、この季節にしては、やけに気温が高かったのだ。
駿の足元が、急に、音を立ててひび割れた。
「駿!?」
「近づくな!」
駿自身、足が竦んでいた。ヘタに動けば、足元の氷が崩れる。
「巻き込まれる前に、お前はここから離れるんだ。馬と、安全な場所へ逃げろ」
大声を出すことすら恐ろしかった。ゆっくりと、とにかくこれ以上亀裂を広げないよう、静かにここから逃れなくては……彼の額の汗を拭うと、気を落ち着かせようと必死になった。
「馬を呼んでくる。それで、お前をこっちまで引っ張る」
ツルゲネはそういうと、急いで川岸に向かおうとした。
「おい、慌てるな!」
駿の警告は遅かった。その時、慌てたあまり、ツルゲネは足を取られて転んでしまったのだ。同時に、駿の足元の亀裂が、彼女の方まで広がってしまった。
「――!」
駿は、這いずりながらも彼女の方へ向かった。子供ばかりでなく、彼女まで死なせてしまったとあれば、張騫にも衛青にも会わせる顔がない。
「今、そっちに行くから、待ってろ!」
駿は右手を伸ばしながら、彼女に声を掛けた。彼女の顔からは血の気が失せ、唇まで青くなっていた。
氷河は、動いている。
それが、表面に発生したひび割れに微妙な影響を与えた。
あと少しで、彼女に手が届くと思った、その時――
氷が音を立てて弾け、目の前に飛び散った。
(これまでか――!?)
駿は思わず目を閉じ、死を覚悟した。
あの世からのお迎えだろうか、不思議な音が、耳に入ってきた。
それは、だんだんと近づいているように感じた。
不審に思った駿は、ゆっくりと瞳を開けた。
と、奇妙なものが、谷を飛び越えてこちらに近づいてくるのが目に入った。
それは、ケーンケーンと甲高い声で数回嘶くと、一目散にこちらに向かってきた。
ぱっと見ると、犬か狐に似ていた。しかし、光を反射し虹色に輝く毛並みは、犬でも狐でもなかった。
尾は、くるっとした巻尾だったが、十本は付いていた。そして、その一つ一つ、尾が丸まった部分に、それぞれ目が付いていた。
顔には、鼻と耳しか無く、その耳もよく見たら網のように透いて見えた。
その獣が、二人の頭上を大きく飛び越えたから解ったのだが、口は、その腹の部分に付いていた。割れ目のような、ぱっくりとした口で、舌はあったが、歯は見えなかった。
その口の両端から、先がギザギザになった、不思議な触手が二本、伸びていた。
その触手で、駿とツルゲネを捕まえると、そのまま二人をひょいと背に乗せた。
背中だけでも、二畳はありそうな巨大な獣であった。
獣は、またケーンと嘶いた。驚いたことに、その声は巻尾の方から聞こえてきた。
それから大きく飛び上がると、谷の上の方へと昇っていった。
そして、安全な場所に二人を下ろすと、獣は姿を消した。少しした後、崖の途中に残していた馬たちを連れて、また現れた。
獣は馬たちを二人の前に下ろし、ケーンと嘶くと、反対側の谷の方へ姿を消した。今の声は、別れの挨拶だったらしい。
二人は、何が起こったのか理解できず、言葉も交わせぬまま、呆然と座り込んでいた。
しばらくして、我に返った駿は、氷河で濡れてしまった服を乾かそうと、僅かばかりの火を熾した。
「燃やすものが、そんなに無いから、火勢は弱いが、とにかく暖まろう」
彼女の方を見て、駿は驚いて息を飲んだ。
彼女は、着ていた服をするすると脱ぎ始めていたのだ。白く、滑らかな肌が覗いた瞬間、駿はこれ以上は見てはいけないと目を背けた。
「濡れたもんは、脱いで乾かしたほうがいいもんな――俺さえ見なきゃ、いいんだから、ちょっとその辺ぶらついてくるよ。服が乾いたら、呼んでくれ」
そう言い捨て、彼は山の上の方へ昇っていった。
上に付くと、駿は何度も深呼吸をした。心臓がどうにかなったのかと思うくらい、早く激しく打っていた。
「胡人は胡人。胡の考え方、風習があるんだ。何かあったら、俺は兄貴と親分に死んで詫びを入れなきゃならない」
その言葉を、彼は何度も呪文のように呟いた。
結局、その日はそれ以上進むことができなかった。
獣が二人を助け出した場所で、そのまま彼らは睡眠を取った。
旅に出て以来、いつも気を張っていたせいか、そんなに深く寝付くことは稀だったのだが、珍しくこの夜は深い眠りについた。
気がつくと、その眠りが何かに邪魔をされていた。
少し冷たい指先が、彼の体をまさぐっていた。しばらくは、その心地よさに、彼はなされるがままになっていた。
その指先が股間に触れた途端、駿は我に返った。
「――お前、何をやってるんだ!?」
駿は飛び起きると、慌てて彼女から離れた。
ツルゲネは四つん這いになりながら、彼を見上げた。はだけた襟元から、月明かりに照らされた彼女の白い乳房の一部が、ちらりと垣間見えた。
「昼間の礼だ」
「――は?」
彼女の返事に、彼は一瞬耳を疑った。
「昼間、命を助けてくれた礼だ。抱きたいんだろう?」
「どういう意味だよ?」
「意味も何も、男とは、そういうものであろう」
その言葉に、駿は怒りを感じた。ついさっきまで、湧き上がる情欲を押さえるのに必死だったが、今の一言でその情欲もどこかへ吹き飛んでしまった。
「俺は、お前を抱きたいから命を助けたと思っているのか?」
「違うのか」
「馬鹿にするな!」
駿は思わず立ち上がって怒鳴った。
「お前ら匈奴のような、鬼畜と一緒にするな!俺は、張の兄貴のために助けたんだ。お前を無事に兄貴に会わせるために、やってるだけだ」
ツルゲネは、駿の顔をじっと見つめた。それから目を伏せると、乱れた服を整え、そのまま背を向けて横になってしまった。
駿はへなへなと座り込むと、天を仰いで大きく溜め息をついた。この夜は、その後一睡もしないまま、夜明けを迎えた。
次の朝、目の前に昨日の獣が現れた。獣は自分の尾を一本引き抜くと、そのまま姿を消した。
目の付いた尾は、彼らを見てぺこりとお辞儀をすると、四肢を生やして彼らを先導するように歩き始めた。
その後に従っていったおかげで、その後彼らは、難なく雪山を進むことができるようになった。
第五章 烏孫王孫、岑陬(しんそう)
今日が期日の五日目であった。
最初はどうなるかと思ったが、目のある巻尾のおかげで、最後は順調に進むことができた。
今朝からは、時々大きな轟音が耳に入ってきた。それは、この雪山の旅の終わりを意味していた。
その音に導かれるようにして、二人は氷河の終着に辿り着いた。
巨大な氷河は、そこで崩壊し、融解する。
大きな音を轟かせながら、崩れ落ちた氷は、細かく砕け、やがて水となり流れていく。この、水の流れの先に、目指す人が、いる。
「気をつけてくださいよ。大きく崩れたら、流れに巻き込まれますよ」
頭上から聞き覚えのある声が響いた。見上げると、頭上の岩に有為が座っていた。
「有為!」
「ご無沙汰しておりました」
そう言うと、有為は手を横に伸ばした。するとそこに、あの奇妙な獣の顔がすっぽりと収まった。
獣の首に捉まって有為は二人の許に下りていった。
駿たちの側にいた、目のある巻尾は、嬉しそうに体を揺すると、その獣の所に走っていった。そして、ぽん、と飛び跳ねると、獣の尻尾たちの中に身を埋めた。
尾が擦れるたびに、ケーン、ケーンという音が響いた。
「ケンケン、ご苦労様。先生によろしくお伝え下さい」
獣は、嬉しそうに尾を振るわせた。尾と尾が擦れてケーンと音が響いた。そして、空高く舞い上がっていった。
「あれは……?」
獣が去っていく姿を見ながら、駿は有為に尋ねた。
「蓬莱の獣です。ケンケンというそうですよ」
「けんけん?」
「そう鳴くでしょ?名前で鳴くのだと、安期先生はおっしゃってましたよ」
「本当か~?」
胡散臭そうに、駿は呻いた。
「でも、確かにそう言っておりましたよ」
「……あの先生も、東方先生と同類だ」
駿の頭の中に、いつも嘘なんだか、本当なんだか、訳の解らないことしか話さない東方朔の姿が過ぎった。歳星の化身である彼と、仙人。根っこは同じらしい。
「で、どんな字を書くんだ?」
「あ、そう言えば、そこまで聞いてはいませんでいした」
「じゃ、俺が決めてやる。張の兄貴の名前の”騫”を取って、騫騫」
それを聞いて、後ろのツルゲネが思わず吹き出して笑った。嘲笑以外に、彼女が笑ったのを見たことにない二人にとって、それはひどく意外な光景だった。
「――心配だったのですが、案外上手くいっていたのですね。安心しました」
「何を言う」
駿は、有為の一言に顔を顰めた。
「俺は自分の操を守るので大変だったんだ」
「は?」
「お前の顔を見て、こんなに安心するなんて、思っても見なかったよ」
そう言って、彼は有為の頭を小突いた。
「じゃあ、行きましょうか?」
照れくさそうに笑いながら、有為は自分の馬の方に歩いていった。
「五日も乗らなかったんだ、馬の乗り方、忘れてないだろうな」
後ろの方で、駿がからかうように声を掛けた。
「何を言っているんですか!?長安を出て、もう、二ヶ月、その間ずっと乗ってるんです!体がちゃんと覚えてます!!」
と言いながら、有為は馬の背を通り越して、反対側に落ちた。
それを見てひどく驚いたのは、ツルゲネだった。なにしろ匈奴は、歩く前に馬に乗れるようになることを誇りにする民族だ。馬に乗れない人間など、考えられなかったのだ。
「あいつ、何者だ?」
彼女は小声で呟くように駿に訊いた。駿は、答えに困って、ただ頭を掻くしかなかった。
「この先に、虎吼岩があります。虎が咆吼するような姿をしているので、その名が付いたのだそうです。そこで、重要な出会いが私たちを待っているそうです」
一番後ろで、えっちらおっちらとかろうじて馬を走らせながら、有為が言った。
ツルゲネは、何度も後ろを振り返り、彼を見ては首を振った。彼女にとって、こんなにも乗馬が下手な人間は、ある意味、驚異であったのだ。
「重要な、出会い?何だ?」
「解りません。それ以上詳しくは言ってくれませんでした。あ、あと……」
「何だ?」
「今は雪解けの時期で、急に水量が増えることがあるので、河床を走るのは危険だから止めるようにとも言われてました」
三人は、雪山を下りて以来、ずっと川沿いに馬を走らせていた。駿は、走りやすいからとついさっき河床の方に下りたばかりであった。
「てめえ、何でもっと早く言わねんだよ!!」
「忘れてたんです!」
「威張るな!」
駿は慌てて上の方に駆け上がった。
氷河を起点とするこの河は、その季節によって姿を変える。
冬には、その流れがほとんど無くなり、時には涸れることもあるこの河も、夏には大河に姿を変える。
春から夏にかけて、大量の氷が溶け、大いなる流れとなって、この礫沙を横切っていく。その流れは、夏の到来も意味していた。
しかし、春先の今は、まだ流れも少なく穏やかで、河床の一部分を占めるほどしかない。だが、川岸となる断崖までの距離や、抉れた大地の規模を見ると、この河がもっとも水量の多い状態がいかほどであるかは、容易に推測できた。
「――あれかな?」
流れが多いときは、きっと中洲となるのだろう。谷の中に、ぽつんとそびえ立つ岩山があった。よくよく注意してみると、それは確かに何かの獣が吠えているように、見えなくはなかった。
「でしょうかね?」
駿の問いかけに対し、頼りない返事が、有為から返ってきた。有為自身、話を聞いてはいるが、それがどんなものであるのか、皆目見当が付かなかったからだ。
先頭を走っていた駿は、スピードを落としながら、周囲を見渡した。安期生の言うことは、嘘はないが、想像通りではないからだ。駿は、神経を研ぎ澄まして警戒した。
案の定、の、ことが起きた。
ひゅん、という音と共に、矢が、駿の馬の、鼻先をかすめた。
注意をしていた駿は、落ち着いて矢を交わすと、すぐに二人を、安全そうな岩陰に避難させた。
その僅かな隙に、矢は二本、三本と彼らの足元に突き刺さった。
(かなりの使い手だ……)
矢の軌道を見て、駿は瞬時にそう判断した。様子を窺おうと、岩陰から顔を出すと、そこに向かって正確に矢が飛んできた。
「重要なって、敵に会うことか?」
「そんな……」
襲撃に浮き足立っている有為に、これ以上訊いても無駄だと、駿は首を振った。
「有為、お前、時々、ここから顔を出して、矢の的になれ」
「え!?」
驚いて、目も口も丸くなった有為に、駿は容赦なく言った。
「数を数えてれば大丈夫だ。三つ。三数えたら顔を引っ込めろ。そうすれば串刺しにはならない。ただし、顔を出す間隔は数えるな。一定の間隔だと気付かれたら、顔を出した途端に射抜かれるかもしれない」
「そんな、無理です!出来ません!!」
「そうして貰わなきゃ困る。お前が敵を引きつけている間に、俺は後ろを回って、相手をやっつける。解ったな?」
「――私が、引きつけようか?」
地団駄を踏んでいる有為を見かねて、ツルゲネが口を開いた。それを聞いて、駿は即座に首を振った。
「駄目だ。あんたに何かあったら、兄貴に面目が立たない」
「じゃあ、私に何かあってもいいんですか!?」
涙声で有為が訴えた。駿は、にっこりと笑って彼の肩を叩いた。
「大丈夫。お前には安期先生が付いている。首がもげたって、きっと、先生ならくっつけてくれるさ」
「そんな!」
有為の訴えに一切耳を貸さないまま、駿は敵に気づかれないよう、死角を選んで崖を登っていった。
「有為、交替で顔を出そう」
そう言って、ツルゲネは有為を岩陰から突き飛ばすと、三数えて、再び影に引きずり込んだ。彼の服の裾を、矢がかすめた。
悲鳴を上げた彼に構うことなく、彼女は落ち着いて岩陰から顔を出した。矢は、彼女の鼻先をかすめた。
「ほら、お前の番だ」
腰を抜かしている有為に向かって、彼女は落ち着いていった。
「時間かかってもいいが、かかりすぎたら、また、突き飛ばすぞ、思いっきり」
有為は、涙でぐしょぐしょになった顔を、必死に横に振った。
「――奴らの動きは、止まったようですよ」
射手は言った。
「どうするか?」
射手の後ろの男が尋ねた。
「向こうも、そう、数は多くないようですし、あまり矢も無駄にしたくはないですな」
「では、まずは捕らえてみるか。それで生かすか殺すか考えよう。私が下りていくから、援護しろ」
「解りました」
その話を、駿は岩陰から聞き耳を立てて窺っていた。匈奴の言葉なので、半分以上は聞き取れなかったが、おおよその見当は付いた。
駿は男が、岩山を下りていくのを確かめると、有為たちの様子を窺っている射手の後ろに、静かに近づいた。そして、彼に気付かれないうちに背後から襲いかかった。
後ろからいきなり襲われ、射手はほとんど抵抗できないまま、駿に押し倒された。そして、駿は射手の喉元に剣を構えた。
構えて、その顔を確かめた瞬間、彼は驚きの声を上げた。
「堂邑のおっちゃん!?」
そう言われて、射手も驚いた。その名で呼ばれることなど、この十年、無かったからだ。
「……お前は?」
「俺だよ、俺。忘れたのか?――」
男は、彼の顔をまじまじと見つめながら、ハッと気付いた。
「衛侍中のとこの、チビか?」
「チビはないだろう?もう、十年も経ってる」
駿は、男の手を引いて起きあがらせた。彼は、駿の顔をまじまじと眺め、納得したように頷いた。
「確かに面影がある。確かに、侍中の所の、俊々だ」
「五つ六つの子供じゃないんだから、俊々はないだろう?今、俺は鄭駿、独生と名乗ってるんだぜ。親分は今や将軍さまだ。俺はその将軍さま麾下の騎士をやってるよ」
「そうか……立派になったんだな」
男の目には、涙が滲んでいた。
「――カン!どうした!?」
異変に気付いた男の連れが、慌てて山頂まで引き返してきた。男は剣を引き抜き、駿もまた、剣を構えなおした。
「岑陬!追っ手ではありません!漢人……味方になりうる人物です」
”堂邑のおっちゃん”と呼ばれた男は、慌てて止めた。
「漢人?」
男は、剣を下ろすと、駿を品定めするように、上から下まで舐めるように見た。
彼は、匈奴とは若干違う格好をしていた。胡服と呼ばれる、乗馬に適したスリットの入った長い上衣や沓は同じような感じあったが、服に施された文様、ボタンやバックルの飾りが、明らかに匈奴とは違っていた。
また、風貌も明らかに匈奴とは違っていた。
匈奴人は体つきががっしりと大きいものが多いが、顔立ちは漢人とそう差異はない。
冒頓が強大な帝国を樹立して以来、様々な民族を飲み込んだ匈奴は、混血もまた多かった。ツルゲネもその瞳の色が示すように、西方の民族の血が混じっていた。
しかし、純粋な匈奴人は、黒髪に黒い瞳を持ち、あまり彫りは深くなく、すっきりとした顔立ちをしていた。
しかし、この男は、瞳の色は青味がかった灰色をしており、その髪は茶褐色、彫りの深い顔立ちは、明らかに、西方の民族の風貌であった。
「岑陬、彼は、武帝の寵妃の姻戚につながる者。敵にする手はありません。利用すべきです」
”岑陬”と呼ばれた男は、納得したように頷いた。
「彼は、何者だ?」
駿は”堂邑のおっちゃん”に尋ねた。
「この方は、烏孫の王孫。岑陬だ」
「前に話したことがあっただろう?投降者で、匈奴のことを俺と親分に教えて貰った人がいたって。彼がそうだ。堂邑のおっちゃん」
駿は、二人を有為とツルゲネの許に連れていくと、彼らを嬉しそうに紹介した。
”堂邑のおっちゃん”と呼ばれた彼は、駿の言葉に苦笑いを浮かべた。
本名はカン。漢地では甘父もしくは、堂邑家に使えていたことから、堂邑父と呼ばれていた。”父”は、「おじさん」という感じで添えられていた言葉だ。
かれを”おっちゃん”と親しげに呼ぶのは、この駿や衛青のように、数少ない人物であった。
「生きていてくれて、本当に良かったよ」
「俊々――いや、独生どのは、どうしてこんな所に」
「ああ、陛下の命で、張の兄貴を捜しに来たんだ」
「何ですと?」
「詳しく話せば長くなる。簡単に言えば、この有為が探索の旅に指名され、俺が、一緒に付いてきたってことさ。張の兄貴を捜すために」
「陛下は、まだ、張団長のことを……?」
「もちろん、必要としている。っていうより、親分の方が必要としているかもしれない。この間の秋、俺たちは匈奴と戦ったが、やはり、将が足りない。張の兄貴のような人物は、そうそう得られるもんじゃない。だから、俺は親分に代わって、ここまで探しに来たんだ」
「何と――!」
堂邑父は、跪くといきなり涙を流し出した。
「おっちゃん?」
「独生どの、今、ここで私をお斬り下さい」
「どういう事だ?」
「月氏への使節団が、匈奴に捕らわれたのも、ひとえに私の責任なのです。今、全てをお話ししましょう。そして死を以て、その償いを……」
堂邑父は匈奴の単于と内通していた。
堂邑父は、月氏までの道案内として、使節団に加わった人物だ。それはもともと彼が匈奴人で、草原の地理に詳しかったからに他ならない。
しかし、堂邑父は期待には添わなかった。
彼は、匈奴の内訌に巻き込まれて漢に投降した人物だったが、漢での境遇にも満足できなかった。
彼は、漢で奴婢同然の扱いを受け、堂邑という豪族の下働きに甘んじていた。不自由な身になるために、漢に降ったわけではないのに、現実はそうではなかった。
堂邑と付き合いのあった衛青は、彼とも親しく付き合うようになった。そして彼を使節団の道案内に推薦した。しかし、結局、彼はその期待を裏切った。
昔のように、自由に暮らせる身分と引き替えに、彼は使節団を単于に売ったのだ。
行こうと思えば、裏道など、いくらでもあるし、匈奴はその民族柄として、買収にも簡単に応じる者が多かった。本当だったら、使節団は簡単に匈奴の領地を抜け出せるはずだったのだ。
なのに、彼らは甘粛であっさりと捕まった。すべては、堂邑父の内通の仕業であった。
一行の所持していた贓物は、全て没収され、使節団は単于庭に連行された。
そこで彼らは、匈奴に投降するよう申し渡された。匈奴の強さの一つに、他民族を進んで登用するという面があった。特に文明の進んだ漢族を彼らは歓迎したのだ。
だが、張騫はそれに従わなかった。
怒った単于は、張騫を始めとする使節団員を、遙か北の北海(バイカル湖)に送った。
北の果てにある、北海の冬の厳しさは想像を超える。初めての冬で、団員の半分は死んだ。
生き残った者の多くは、その冬に恐れをなし、単于に忠誠を誓って南に移っていった。
しかし張騫は従わず、ろくな装備も与えられないまま、もう一冬をその地で過ごした。
単于は、彼の意志の強さに感服し、張騫を単于庭に呼び戻した。そして、彼に妻を与え、時間を掛けて自陣に取り込もうと画策したのである。
しかし、張騫は最後まで単于に従おうとはしなかった。
やがて、馬邑の事件が起き、漢との内通を恐れた単于は、彼を、遠く離れた西方、居延沢へ移したのだ。
「私は、この岑陬を、居延の張団長の下に送る途中だったのだ」
「どうして?」
堂邑父は岑陬の顔を見た。岑陬は、漢語はほとんど解さないので、堂邑父に続けて説明するように命じた。
「烏孫は、漢との同盟を望んでいるのだ」
烏孫とは、匈奴の西、イリ川周辺を支配地域とする騎馬民族国家である。一応、匈奴に服属はしているが、関係は良好ではなく、年に三度招集される首長会議にもほとんど顔を出すことはなかった。
もともと烏孫は、月氏と共に敦厚周辺に居住しており、国自体も弱小であった。
烏孫は、月氏に討たれ、部民は一旦、匈奴に逃れた。匈奴の庇護下、体勢を立て直した烏孫は昆莫を王とし、積年の恨みを果たすべく月氏を討った。
その時、月氏は既に匈奴に破られた後で、河西からイリ川方面へ逃れていた。
さらに月氏は烏孫にも破られ、彼らはイリ川から、ガンダーラ北部、トカラまで逃れていった。
月氏を破った烏孫は、そのままその地に止まり、そこを本拠とし、国も強大になっていった。
「その、昆莫王の孫が、この方です。名をグンシュビと申し、岑陬の位を賜っております」
「岑陬?」
「漢で言うと、王か、侯か…皇族が賜る位と同じような物ですね」
そう聞いて、駿は納得したように頷いた。
「我ら烏孫は、強国になった今こそ、父祖の地に帰ることを望んでいる。だが、今、その地は匈奴の領土。帰るためにはまず匈奴を討たなくてはならない。聞くところに依ると、漢は共に匈奴を討つ相手を捜しているという。その相手に、我ら烏孫が名乗りを上げようということだ」
グンシュビは駿に向かってそう言った。駿の語学力では半分理解するのがやっとであったが、横で堂邑父が通訳をしてくれた。
「それで、兄貴を匈奴から救い出し、漢との取り次ぎを頼もうとしたのか」
堂邑父に言葉を訳して貰い、グンシュビは頷いた。
「でも、どうして堂邑のおっちゃんが、この岑陬殿下と行動を共にする事になったんだ?」
「それはな――」
烏孫は、匈奴討伐の準備が整うまで、表向きは関係修復を装うことにした。
グンシュビは烏孫の王太孫で、昆莫の跡を継いで烏孫王になる予定の人物だ。
彼は年老いた王に代わって、一月の首長会に出席した。そして、単于家攣鞮(らんてい)氏から妻を娶ることにもなっており、今回の来朝でその話をまとめもした。
「一月!?今は四月になろうって所じゃないか?いくら何でも時間がかかりすぎるだろう?」
「確かに、五月にはもう、次の会が開かれるというのに」
呆れた様子の駿に、グンシュビも苦笑しながら答えた。
匈奴の首長会議は、一月、五月、九月の年三回、開かれていた。今時分であれば、五月の首長会のために、故国を出発したっておかしくない頃だ。それがまだ帰還の途にも付いていないとは。
「供の者はすでに帰国している。私は単騎残って、密かに匈奴領内を探っていたのだ。カンとはそうしているうちに出会った」
「密偵がやるようなことを、どうしてわざわざ王太孫が?」
「父の兄弟は十人以上いる。その中で、私は父の死後、無理矢理、王太孫になった。自分の地位を、確固たる物にするには、それなりのことをしなくてはならない。失敗して死んでも、代わりはいくらでもいるから、気に病むこともない」
グンシュビは事も無げに言った。
「匈奴はもう大したことはない。討つなら今だ」
「何故、そう思う?」
「聖地の力も失せた。一月の会で、彼らは何をしたと思う?幼子の心臓を、公衆の面前で――」
駿は、グンシュビに飛びかかって、彼の言葉を遮った。堂邑父に通訳して貰わなくても、彼の言おうとしていることは、簡単に解った。
「てめえ……」
駿は、彼を押し倒しながら呟いた。
「それ以上、言ってみろ。今度は俺がきさまの心臓を切り裂いてやる」
グンシュビは何が起こったか解らず、呆然と駿の顔を見つめた。
「――やっぱり俊々だな。その身の軽さは変わっていない」
堂邑父は駿をグンシュビから引き離しながら、言った。
「岑陬。そこの女性は張団長の妻で、あの幼子の母親です。出来れば、これ以上、何も言わないでいただけませんか?」
それから、堂邑父は駿の顔を見て言った。
「心臓を切り裂いてもらうのは、私ですよ。岑陬ではありません」
「おっちゃん……」
「全てをお話して、心残りはありません。あなた方が岑陬を団長の下にお連れしてください。それが、漢のためです」
堂邑父は、自分のしたことを深く悔いていた。
もともと、匈奴にいられなくなって漢に降った人間だ。しかし、その漢にも満足できずに、ふたたび匈奴に戻った。
匈奴は目先の利益に敏感な民族である。それゆえ、堂邑父のしたことは、別段特別なことではなかった。二重の裏切り者である彼を、責め立てる者など、匈奴にはいなかった。
彼を咎め立てたのは、他でもない、彼自身の良心だった。彼が、漢地で衛青たちと過ごした日々の中で培われた心だった。
どんな辛酸を舐めようとも、単于に従うことのない張騫のことを、風の便りに聞く度に、彼の心が痛んだ。
そして、去年の秋、衛青率いる漢軍が、匈奴領内深くまで攻め入ったときだ。
衛青の軍は、女子供、年寄りなど、弱者には決して手を出さなかった。それは、匈奴軍では考えられないことであった。
堂邑父は、衛青の義侠心に溢れた人柄を思い出した。彼から受けた、恩義の数々が思い出された。
匈奴から逃れ、漢に降った頃は、彼の人生の中で一番大変だった時でもあった。その時に、親身になって、彼に救いの手をさしのべてくれたのは、まさしく衛青だった。
使節団の案内役として自分を信頼してくれた張騫とともに、衛青を裏切った自分を、自分で許すことが出来なかった。
張騫を救い出したら、自分は死んで二人に贖おうと考えていた。今ここで、衛青麾下の駿と出会ったのも、何かの運命だったのであろう。
今、ここで自分は死ぬべきなのだと、堂邑父は感じていた。
「駿、どうする?殺らないのか?」
二人の後ろから、ツルゲネが声を掛けた。彼女の手には、短剣が握られていた。
「お前がしないのなら、私がする」
彼女は、掌で刃をぴたぴた叩いた。
「私の不幸の根源は、この男から始まってるらしいからな」
「だめだ」
駿は、強い調子で彼女を諫めた。
「おっちゃんは、張団長の配下。俺は衛将軍の下にいる。おっちゃんに手を出したら、俺は軍律に違反することになる。だから、俺はおっちゃんに手を出すことは出来ない」
「つまらないことに縛られてるな」
駿の言葉を、ツルゲネは鼻で笑った。
「それだけじゃない。これから先のことを考えれば、ここで、おっちゃんを失うことは得策じゃない。おっちゃんは弓の名手。匈奴に捕らわれている兄貴を救うには、おっちゃんの弓の腕が必要だ」
ツルゲネは、冷たい視線を駿に投げかけると、くるっと短剣を一回転させて、鞘にしまい込んだ。
「独生どの……私を許してくれるのですか?」
堂邑父は駿に訊いた。
「許すも何も、俺はそんな立場にはない。ただ、おっちゃんたちの助けが必要なだけだ。俺たち三人の中で、まともに戦えるのは俺だけ。この有為は戦士じゃない、別口なんだ。戦えるおっちゃんと岑陬がいてくれると、俺も心強い」
「そうですか」
「岑陬、最後の決定はお前だろう?どうする、手を組むか?」
駿の言葉に、グンシュビも頷いた。
「私が欲しいのは、漢の後ろ盾。お前が漢の姻戚に連なる者であるなら、敵に回したら話にならない。漢に取りなしてくれる者であれば、是非とも協力しよう」
(張の兄貴が第一じゃなく、漢と繋がりたいだけか……)
駿は、打算的なグンシュビの物言いに呆れもしたが、利に敏い騎馬民(かれら)のこと、いちいち気にしても仕方のないことだ。
(胡は胡か……)
雪山で安期生が言ったことが、ふと、頭の中に蘇った。
「しかし、この広い草原で、このような出会いがあるとは……天の導きなのでしょうか」
感慨深げに堂邑父が呟いた。
「違いますよ、これは安期先生の導きです」
駿の後ろから、有為が答えた。
「安期先生が、全て私たちが出会うように、導いているのです。胡妻どのと会ったのも、岑陬どのと会ったのも、全ては」
その時、甲高い笛の音のような音が天空に響いた。見上げると、いつぞやの白鷹が、大空を横切っていった。
有為は、それを見て微笑むと、静かに頷いた。
第六章 居延沢
「有為!小姐さん!」
駿は二人に向かって必死に叫んだ。
しかし、警告したって、二人出来ることなどない。
駿は、かろうじて二人の前に飛び出すと、自ら敵の放った矢の的となった。
話は、小一時間ほど遡る。
数日前、礫沙漠を抜け、一行は居延沢に無事辿り着いた。
ここは、休屠王の領地で、目指す張騫はこの王の管理下だった。
この広大な湖のどこかに、張騫がいるはずだ。
下手に動いて、休屠王に勘づかれることを恐れた彼らは、匈奴人の堂邑父に、張騫の居場所を捜すことを任せた。
氷河の果てが湖とが合流するこの場所で、駿たち四人は堂邑父の帰りを待つことにした。
待つのは十日。
十日経って堂邑父が戻ってこなかったら、彼のことは諦め、四人で居延沢を回る。とにかく、生き残った者が張騫を救出する。
そう言うことになった。
彼らは堂邑父を見送ると、この湖の畔で、しばしの骨休めをして英気を養うことにした。
しかしここは敵地。
そこで誰かが必ず、見晴らしの良い岩山の上で見張りに立つことにもなった。
駿とグンシュビが、狩りをして戻るときのことだ。彼らの許に、ツルゲネが血相を変えて馬を走らせてきた。
「どうした?」
彼女の様子に、二人は何事かが起こったと悟った。二人は彼女の案内で、急いで見張り場に向かった。
有為のいる見張り場に着くと、ツルゲネは地平線の方を指し示していった。
「見たところ全部で二十騎。しかし、休屠王の配下ではない。あの文様は、丘林――カンの部族の者だ」
匈奴は服などの文様で、自らの出自を表す。
グンシュビのような異民族は明らかに違うから、駿でもその違いが解るが、同じ匈奴族になると、その微妙な差異に気付くことは難しい。
しかし、匈奴族にとっては当たり前のように出来る見分けだった。
それよりも、駿の目にはまだぼんやりと、影のようにしか見えない騎兵たちを、ツルゲネやグンシュビはその服の文様までしっかりと見て取っていた。
この驚異の視力は、草原で生まれ育った者ゆえに持つものであった。
(こんな連中が相手だから、漢軍もなかなか勝てないわけだ)
「グンシュビ、お前、カンの部族と何かあったのか?」
ツルゲネの問いかけに、グンシュビは困ったように首を竦めた。
そして、身を屈めてツルゲネの耳元で、小声で話しかけた。すると、見る間に彼女の顔色が変わった。
彼女は首を振ると、駿と有為に向かって叫んだ。
「あの連中は、グンシュビを狙っている。私たちには関係ない」
「関係ないって、どういう事だ?」
駿の問いに、彼女は嫌そうに顔を顰めた。
「とにかく!こんな男、構うことはない」
「何があったんだか、ちゃんと説明しろよ!」
しつこく問いただす駿を、ツルゲネはキッと睨み付けた。
「口にするのも忌々しい。カンが戻ってきたら、何があったんだか訊くんだな」
「何だよ、その言い方は!」
駿はグンシュビに直接訊こうとしたが、彼も困ったように両手を挙げた。
烏孫は、長らく匈奴の庇護下にあったため、言語は匈奴とそう差異はない。
駿は、幼い頃、堂邑父から手ほどきを受け、衛青と共に国境を探っていた頃にも、必要があって匈奴の言葉を習い覚えた。だが、所詮、片手間に習ったもので、込み入った話を理解するほどの能力はなかった。
漢と結びつきたいグンシュビも、ここ数日、長安生まれで言葉が綺麗な有為から、漢語を習ってはいたが、意思疎通をするまでには至っていなかった。
「とにかく、この男の首を差し出せば、私たちには害は及ばない。さっさとあいつらにこいつを引き渡して、騫を探しに行こう」
ツルゲネは、馬を引いて来ると、そう言った。
「そんなこと、出来るわけないだろう!」
駿は思わず怒鳴った。
「利益ばかり考える匈奴と違って、俺たち漢人は、仁義・忠孝を重んじるんだ。ここで、彼を見捨てるわけにはいかない」
駿の言葉を、ツルゲネは冷ややかな笑みを浮かべながら聞いた。
「騫と同じことを言うな、お前」
「――俺と岑陬で、連中を何とかするから、お前は有為を連れてここから逃げろ」
駿は、気を取り直して、ツルゲネに言った。
「有為を?」
「あいつだけじゃ、馬に乗るのもやっとだ。お前の馬に乗せても良い、とにかく安全なところまで逃げてくれ。頼むぞ」
「……変な話じゃないですか!」
横から有為が口を挟んだ。
「男である私を、女である胡妻どのに頼むだなんて、面目が立ちません」
「面目より実を取れ」
駿は有為をツルゲネの方に押し出した。彼女は、嘲笑を浮かべながら、馬に乗った。
「有為!後ろに乗れ!」
「それは……嫌です」
「有為!」
この期に及んで駄々をこねる彼の頭を、思わず駿は小突いた。
「どうでも良い、行くぞ!」
ツルゲネの言葉に、有為は慌てて自分の馬に跨った。そして、二人は急いで岩山を下りていった。
「駿」
グンシュビの声に、駿は彼の方に向き直った。グンシュビは追っ手の方を指し示していった。
「一、十」
一人で十人やろうとう意味で、グンシュビが言った。その言葉に、駿も頷いた。
この程度の言葉で、充分通じる。
騎馬民は狩りを通して軍事訓練をするという。二人も、この数日の狩りを通して、戦いの際の、独特の呼吸が合ってきていた。
二人は馬に乗り、敵に向かって飛び出していった。
グンシュビは、敵の前に駆け出すと、馬上から弓を構えた。
彼に気付いた敵兵が、弓を構えるより早く、彼は次々と矢を放った。
それは、とても移動しながらとは思えないほど、正確に相手に突き刺さった。
堂邑父には劣るが、グンシュビもまた、かなりの腕前であったのだ。
敵兵がグンシュビに気を取られている隙に、駿は彼らの背後に回った。
弓の腕は劣るが、自らの身のこなしを生かした速攻は、駿の方が上である。それを見越して、グンシュビは自分の馬を駿に貸していた。後に武帝より西極馬と名付けられるほど、烏孫の馬は足も速く、大変な良馬であった。
駿は、相手が体制を整える間を与えることなく、次々に斬りつけていった。
半数にまで減った敵は、勝ち目なしと判断し、急に四方に散った。
そうなると多勢の有利。二騎では全てを追いようがない。
駿はグンシュビの側に馬を寄せると、彼に声を掛けた。
「どうする?」
「敵が散るなら、こちらは固まった方が良い」
グンシュビの言葉に、駿はハッとした。あの二人は狙いやすい。見つかったら、格好の餌食になるのではないか?
「岑陬」
「ああ、急ごう」
ツルゲネたちは、沙漠の方に進路を取っていた。
湖の方に行けば、休屠王の手の者に会う可能性がある。最悪、丘林の兵との挟み撃ちだ。
今まで通ってきた沙漠の方には、ほとんど人影がなかった上、季節で大きく水量の変わる河のおかげで、地形は浸食により複雑な形をなしていた。
身を隠せそうな場所は、いくらでもあった。
ツルゲネは緩やかな崖を一気に駆け下りると、ちょうど良さそうな場所を探して周囲を見渡した。
身を隠す場所を探すことばかり考えていたせいで、有為のことなど全く気に止めていなかった。
「うわあ!」
彼の悲鳴を聞いて初めて、自分が彼を忘れていたことに気付いた。
「有為?」
ツルゲネは声の方を振り向くと、崖を転げ落ちる彼の姿が目に入った。
彼女にとって、簡単に駆け下りることの出来る崖でも、有為には無理があった。
有為は、かなり躊躇ったが、置いていかれる不安に負け、目を瞑って崖を下りようとした。
が、案の定、彼はすぐに馬から振り落とされ、崖をころころと転がり落ちた。
馬の方は、邪魔な有為をさっさと振り落とすと、悠々と崖を駆け下りた。ツルゲネは、そのままどこかへ行ってしまいそうな勢いの馬を、手を伸ばして捕まえた。
それから、崖下に転がっている有為の許に急いで向かった。駿に頼まれている以上、彼を放っておく訳にはいかない。
「大丈夫か?」
「……」
ツルゲネは馬を下りると、痛みに呻いている有為の様子を見た。
その時、崖下の彼らに気付いた者たちがいた。
駿たちに攻められ、四方に散った丘林の残党だ。
三騎の丘林兵は、二人がグンシュビと共にいた者であることを皆、しっかりと見て覚えていた。そして、彼らを捕らえて人質としようと目論んだ。彼らは弓矢を取り出すと、二人に照準を合わせた。
さらに遠くの方で、その様子に気付いた者たちがいた。駿とグンシュビだ。
「先に行く!」
駿は、馬に思いっきり鞭を当てながら叫んだ。
「援護する!」
自分が貸した駿馬に着いていくのは難しいことを知っていたグンシュビは、弓を構えながら叫んだ。そして、丘林兵に向かって矢を射った。
自分たちの射程より遙か遠くにいるグンシュビから矢が届き、丘林兵は色めき立った。そして、つがえていた矢をグンシュビに向かって放ったが、遠すぎて彼の方まで届かなかった。
「このままでは不利だ。下の奴らを早く捕らえよう」
二人がグンシュビからの矢を防いでいる間に、残り一人がツルゲネたちに向かって、矢を放った。
「有為!小姐さん!」
駿は、大声を出しながら崖を駆け下りたが、既に矢が放たれてしまった。
彼は、馬から飛び降りると、矢と、二人の間を遮るように立った。
鈍い衝撃を肩に感じ、駿は呻き声を上げた。
続いて、二本、三本と彼の背に矢が命中した。
「……逃げろ」
やはり、毒矢だったようだ。気が遠くなるのを必至に堪えながら、駿は二人に向かって声を出した。
「駿!」
ツルゲネは彼に駆け寄ると、倒れそうになる彼に向かって手を差し伸べた。
「構うな!逃げろ」
駿は、ふらつきながらも剣を抜き、次々放たれる矢を、何とか払いのけた。
その様子を見ていた有為は、慌てて起きあがった。擦り傷と打ち身だけの自分は、彼に比べれば無傷に等しい。
有為は、懐から呪符を取り出すと、それに向かって口訣を唱えだした。そして、ふっとそれに息を吹きかけた。
呪符は、ふわりと宙に浮くと、丘林兵に向かって飛び出していった。それは飛びながら、徐々に形を変えていった。
丸く、大きく膨らむと、今度は横に平べったくなり、いびつな菱形に変形した。そして、それは緋色の鱏となった。
形は鱏であるが、虚空に浮かんでいる時点ですでに鱏なのかどうか、怪しいものであっだ。おまけに、その鱏には、孔雀のような尾がふさふさと生えており、鰭をよく見ると、うっすらと羽毛のような物が生えていた。
その鰭をはたはたと上下させながら、緋色の鱏は丘林兵の前に浮かんでいた。
ただ、浮かぶだけで、何もしなかった。
それがことさら、不気味さを際だたせた。笑っているような口元も、気持ち悪さを煽った。

見たこともない生物の出現に、丘林兵たちは凍り付いたように動けなくなってしまった。
「あれえ?」
その光景を見て、有為は声を上げた。
思った通りに、鱏が動いてくれないからだ。どんな仕草をしても、さまざまな口訣を唱えてみても、鱏は微動だにしなかった。
「――未熟者」
有為の背後から、聞き覚えのある声がした。その声の主は、何やら固いもので有為の頭をコン、と叩いた。
「先生?」
叩かれた頭を抱えながら、有為は振り向いて声の主を確かめた。
片手に巻物を手にした安期生が、やれやれと言った表情で立っていた。
「五雷法は、まだ無理か……」
巻物で掌をとんとんと叩きながら、安期生は呟いた。それから、巻物を脇に抱えると、両手をパンと叩いた。
怪物の出現に恐れ戦いていた丘林兵が、ふっと姿を消した。
背後から忍び寄って、彼らを一網打尽にと考えていたグンシュビは、敵が煙のようにかき消えるのを目の当たりにして、ひどく慌てた。
きょろきょろと辺りを見回す彼の目の前に、緋色の鱏がぬっと顔を出した。
初めて見る不気味な生物が鼻先に現れ、グンシュビは大きな悲鳴を上げた。
安期生は、緋色の鱏に向かって掌を伸ばすと、その掌をくるっと返した。途端に鱏もふっと掻き消えた。
目の前の怪異に、理解の範囲を超えたグンシュビは、腰を抜かしてへなへなと座り込んだ。
「グンシュビ!」
下からツルゲネが呼んだ。
「下りてこい!もう、大丈夫だ」
「あの五日間は、何であったか」
土下座する有為の周りを周りながら、巻物で手をとんとん叩きながら安期生は言った。そして、その巻物を有為の手に渡した。
「修行が足らぬ。この書を十万回読め」
「十万回?」
「この帛書(絹に書かれた書物)、一辺読んだら糸を一本抜け。十万読む頃には、抜く糸も無くなる」
「はい」
「夜は夜で、一晩中調息を行え。さもなくば、胡巫には勝てぬぞ」
「……はい」
有為は、蓬莱で安期生に言われたことを思い出した。
「今、もっとも天運の強いのは漢の皇帝。歳星の化身が側に侍っているにも理由がある。対して匈奴の運は尽き始めている。このまま、玗琪の玉が彼らの手にあるのは、あまり良いことではない」
「どうなるのです?」
有為の問いかけに、安期生は頷きながら答えた。
「あの玉は血を求める。春秋戦国、いや、それ以上の戦乱の世が訪れる。そうなれば北狄の地ばかりでなく、華夏の地も戦乱に巻き込まれるのは必至。いかに帝の天運が強くともな。だからこそ、あの玉は五帝の壇に戻さねばならない。決して、あの玉を胡巫の手に渡すではないぞ」
「この辺に散っていた連中は、皆故郷の部落に送り返した。無駄な殺生をするのではないぞ。では、私は蓬莱に帰る」
姿を消そうとした安期生を、ツルゲネが慌てて止めた。
「先生!駿はどうする?このままでは駄目だぞ」
駿は、ツルゲネの腕の中で気を失っていた。背には、矢が三本刺さったままであった。
「ああ、それか」
安期生は駿をちらりと横目で見た。
「幸い、致死性の毒ではない。その程度の怪我なら、お前たちで何とか出来るであろう?お前たちで何とか出来るのであれば、私がわざわざ手を貸すこともない」
そう言いながら、安期生の姿はゆっくりと薄くなると、そのまま消えさった。
「……逃げたな」
ツルゲネは悔しそうに舌打ちをした。そこへ、グンシュビがやっと上から下りてきた。
「あれは、何だ?漢人にはあんな不思議な力があるのか?」
「まさか」
グンシュビの問いに、ツルゲネは首を振った。
「あんな奇っ怪な奴、関わり合わないに越したことはない」
駿の毒は、相手を捕らえることを目的にした物で、体を痺れさせ力を奪う効力があった。グンシュビは、ツルゲネに駿を抱え起こさせると、特殊な小刀を使って一気に矢を抜いた。
これは西方から伝わった矢抜き用の刀で、これを使うと、余計な筋や血管を傷つけず、相手もさほど痛みを感じないで綺麗に矢を引き抜くことが出来た。
今回の来訪で、グンシュビはこの刀と同じ物を単于に献上した。単于はこれをいたく気に入り、必然的に彼ら烏孫からの使者の待遇も良くなった。
グンシュビは、駿の背に耳を当て、肺の損傷がないことを確かめると、服を脱がせ、傷の止血を始めた。
「この薬を塗りましょう」
有為は、抜いた矢から塗ってあった毒を特定すると、自分の薬籠の中から黄色い膏薬を取り出した。
「毒消しか?」
「いえ、この毒はすぐに散って、効き目もなくなる物ですから、わざわざ解毒の必要もないでしょう。心配なのは、矢傷から邪気が入ってしまうことです。これを塗れば、邪気も防げますし、血もすぐ止まります」
「それだったら、傷口を焼けば済むことだろう?」
ツルゲネは不思議そうに言った。グンシュビもそのつもりで、火を熾して剣先を熱し始めていた。
灼けた剣先で傷口を焼くという治療法は、彼ら騎馬民族の間では、ごく普通の治療法だった。
「焼けば確かに血は止まるでしょうが、新たな傷口を作り、そこからまた邪気が入ることだってあるではないですか。それに、怪我人だって苦痛でしょう?まあ、見ていて下さい」
そう言って有為は膏薬を手に取ると、駿の傷口に丁寧に塗り込んだ。
すると見る間に血が止まり、傷口もうっすらと塞がり始めた。
「凄いな……」
絶大な効力を目の当たりにして、ツルゲネもグンシュビも、感嘆の声を上げた。
「蓬莱の薬ですよ。安期先生に頂いた物です」
グンシュビは有為にぬっと手を突き出すと、何やら呟いた。有為が訳も解らずにいると、ツルゲネが彼の言葉を訳した。
「その薬、土産にくれだってさ」
有為は、納得したように頷いた。
「張団長を捜し出すまでは、また、いつこの薬が必要になるか解りませんから、今は駄目です。無事に救い出せた暁には、欲しい分だけ差し上げます」
有為の言葉を、ツルゲネが訳してグンシュビに伝えると、彼は嬉しそうに有為の肩を叩いた。それから、両手の親指と人差し指でそれぞれ輪を作ると、それをつなぎ合わせる仕草をした。約束を意味する烏孫のジェスチャーだ。
彼らには固有の文字はない。一部の知識階級は、漢など、文明の発達した大国の文字を理解したが、大半は条――結縄を使って情報を伝達したり、備忘録に用いていた。このジェスチャーは、その結縄が由来になっていた。
その時、ツルゲネの腕の中で、駿が呻き声を上げた。意識が戻ってきたらしい。
「毒が抜けてきたようですね」
有為は駿の顔を覗き込んで、安心したように言った。
「大丈夫なのか?」
腕の中で、小刻みに震える駿の体を、しっかりと抱き留めながらツルゲネは訊いた。
「大丈夫です。毒が抜けるまで、しばらくはこんな感じでしょう」
「――大丈夫だよ」
ツルゲネの腕の中から、微かな駿の呟きが聞こえた。
「駿!?」
駿は、彼女の腕の中から抜け出すと、しんどそうに座り込んだ。
「こんなの、前にもやったことある。大丈夫さ。ちょっと休めば」
「そうですね、休んでください」
有為は、毛氈を引っ張り出すと、駿にそれを掛けてやった。
ツルゲネはその様子を見て、不意に横を向いた。それから何度か目を擦った。
「……ったく、あんな下らないことで、お前が命を落としかけるなんて」
彼女は、ちょっと鼻が詰まったような――涙声で呟いた。
「下らないこと?」
駿は疑問に思って、グンシュビの方を見た。彼と目があった途端、グンシュビは慌てて視線を逸らし、所在なさ気に腕を振った。
「どういう事だ?」
駿は顔を上げて、ツルゲネの顔を見た。
「私が言うのか?」
「そうじゃなきゃ、俺は一晩かかって、岑陬から話を聞くぞ。休ませたいなら、話せ!」
妙な脅しを掛けられ、ツルゲネは仕方なく真相を話し出した。
彼、烏孫王孫・グンシュビは単于家攣鞮氏と婚姻を結ぶことになった。
生来我が儘な人間で、好みもうるさく、妻となるべき人間にも、彼はあれやこれやと注文をつけた。そしてやっと選び出されたのが、丘林氏族を統べる左大将の娘だった。
匈奴の統治機構は、大別して二種類に分けられる。
烏孫のように、もともとは別の民族で匈奴の支配を受けるようになった場合、自らの王を頂き、ある程度の自治が認められている。丁霊(トルコ)や休屠などもこれに当たる。
それ以外は、単于家攣鞮氏の者が支配した。丘林はそれに当たる。
単于を筆頭に、”四角”と呼ばれる左右の賢王、谷蠡王が続き、その下に大将、大都尉などの二十四長と呼ばれる長たちが、部民の支配に当たっていた。左は東、右は西を支配地域に持っている。
丘林は、匈奴族の中でも地位が高い方にあったので、統べる長も、四角に続く地位にある大将だった。
大将の娘は、丘林族の長の息子との婚姻が内定していたのだが、グンシュビのごり押しで破談となった。
グンシュビは、烏孫の良馬を結納として丘林に持っていき、同時に長の家にも詫びを入れに行った。
「礼儀を弁えてる。何の問題がある?」
「ここまではな。この先は、最低だ」
ツルゲネは、嫌そうに続きを話し出した。
丘林の長の家に赴くと、何故かグンシュビは病気となり、その場で寝込んでしまった。
彼の世話をしたのは、長の妻や娘だった。
「何だって?」
駿は、自分の耳を疑った。
「本人がそう言っている。丘林は美人揃いだったってね」
彼は、病気治療と称して、長の妻と娘、それぞれと関係を持ってしまった。
それどころか、見舞いに訪れた、他家の女たちとも、次々と寝たのだ。
烏孫でそこそこ遊んでいた彼のテクニックは、丘林の男どもとは比較にならなかったらしく、評判を聞いた女たちが、我先に彼の許を訪れ、彼との情事を楽しんだ。
「どっちもどっちってことかよ」
駿は、軽い目眩を感じた。
「それを知って怒った男どもに、追われていたってことか……」
「そうだ」
グンシュビたちと出会ったとき、矢で襲われたことを駿は思い出した。
彼らは追っ手を警戒していたのだ。
「間男が!」
駿は思わずグンシュビに掴みかかろうとしたが、ツルゲネと有為に慌てて止められた。
「傷口が開きますよ!」
「怒るのもばかばかしいぞ、こんな話」
「だが、俺はこの男の下半身の不始末で、こんな怪我を負う羽目になったんだぞ」
「悪かった!申し訳ない」
グンシュビは、両手を組んで、烏孫流の詫びを入れた。
「丘林に留まったのは、カンの話を聞きたかったからなんだ。そこへちょっと誘惑が入って……」
実際、丘林の長の家で用人となっていた堂邑父から、漢についての詳しい話を聞くために彼は病気と称して留まったのだ。
だが、西方の彼の容姿は、丘林の女たちにとってエキゾチックで、とても魅力的であった。彫りの深い顔に、ふっくらとした唇。薄い目の色と明るい髪が、とてもセクシーだと、たちまち大評判になってしまったのだ。
グンシュビは、軽い気持ちで”来るもの拒まず”をしていたら、気付けば丘林の女たちのほとんどと関係を持ってしまった。
事が明るみに出ると、当然、丘林の男たちは怒髪天を衝く勢いで、グンシュビを襲った。
彼は、烏孫と張騫を引き合わせたいと考えていた堂邑父によって、間一髪のところを救われ、そのままここまで逃げて来たのだった。
「いいか、良く聞けよ。漢は礼節も重んじるが、それ以上に貞操も重んじるんだ。お前みたいな淫らな奴は、そっぽを向かれるんだよ。もし、漢と組みたかったら、もう、こんなことするんじゃないぞ!」
急に騒いだせいで、駿は頭から血の気が引くのを感じた。真っ青になった彼を、有為とツルゲネが慌てて支えた。
「解ってる。もうしない」
グンシュビは、指で輪を作りながら、駿に詫びた。
彼の声を聞きながら、駿は、頭の中が真っ白になっていくのを感じた。
気がつけば、何か、柔らかい物が、自分の頬の触れている感じがした。
(これは……)
覚えのある感触に、ハッとした駿は、慌てて身を起こそうとした。
と、頬に当たっていたそれが、今度は自分の口を塞いだ。
「止めろ!」
渾身の力を込めて、駿は、彼女を突き飛ばした。
ツルゲネは、身を起こしながら、悲しそうな瞳で彼を見つめた。
月明かりに照らされた彼女の顔は、本当に寂しそうに見えた。
気を失っている間に、いつの間にか夜になっていたようだ。
「……昼間の礼だ」
「そう言うことは、必要ない。兄貴に顔向けできなくなる!」
「また……また、騫か。私の気持ちは、どうなる?」
「気持ちって……」
ふらふらする頭を必至に振りながら駿は答えた。
「誰かに抱かれなきゃ気が済まないって言うなら、岑陬に相手をして貰えばいいだろう?あいつが馬を貸してくれたから、俺は、お前たちが襲われる前に着くことが出来たんだから。功労は、あいつも俺も一緒だ」
「――そうする」
ツルゲネは服を調えると、上で見張りをしているグンシュビの方へ丘を登っていった。
駿は、大きく息をつくと、その場に座り込んだ。
「――すごいですね」
横から、有為が彼に声を掛けた。
「何だ、お前起きていたのか」
「寝てる暇、無いんです。調息をしていなきゃいけないので。それに、調息(これ)をしていると、眠くならないんです」
「ふうん」
座ったまま手を組み、静かに深呼吸を繰り替えす有為を不思議そうに駿は眺めた。
「そう言えば、お前、変わったな。最近、あんまり飯も食わないし」
「そうですね。食べなくてもいいように、変わってきてるんですよ。体が」
「何で?」
「仙術を使うためです。仙術を極めるうちに、体の中から、枯れてくるんです。そして、眠ることも、食べることも、愛することも、人として必要な欲求が全て、枯れて無くなるんだそうです」
「やだな、そういうの」
「そうですか?」
「人の作った物にケチつけながら、人の倍喰うお前の方が、いいよ」
「え?私、そんなに意地汚かったですか?」
「ぬかせ」
駿は有為のおでこを指で小突いた。有為は、調息を邪魔されて、不愉快そうに鼻を歪めた。
しばらく互いの間に沈黙が続いた。
駿は、ぼんやりと天空の星を眺めていた。
「――彼女のこと、考えてるのですか?」
邪魔されていやなくせに、先に口を開いたのは有為の方だった。
「違うよ」
そう言いながら、駿は立ち上がった。
「ちょっと早いけど、見張り代わってくる。やることやってたら、見張りどころじゃないだろ」
「無理しないでください」
「寝過ぎてるぐらいだ。大丈夫。これ以上寝てたら、逆に調子悪くなる」
第七章 約束
「あれ、一人か?」
見張り場に使っている岩の上に、グンシュビが一人座っているのを見て、駿は意外そうな声を上げた。
グンシュビも、駿の言葉に、不思議そうな顔をした。
「あの女と、やってたんじゃ……」
「やる?」
意味の説明に詰まった駿は、腰を振るジェスチャーで示した。
グンシュビはそれを見て、手を打って笑った。そして、違う違うと身振りで答えた。
「してない、してない。彼女は、あっちだ」
グンシュビが示した方を見ると、背中を丸めて踞っている彼女の姿が目に入った。
「ずっと、あそこにいる」
起きてるんだか、眠ってるんだか、遠目からは解らなかった。
「それに、もう、過ち、しない」
胸に手を当てながら、グンシュビは続けた。
「彼女は、漢人の妻。たとえ、腰を振る女でも、もう、手を出さない」
「腰を振る女?」
妙な言葉に、駿は首をかしげた。
「ん……漢には、ない?」
「ああ」
「彼女は、再婚できない。だから、腰を振る」
「え?」
戦いや狩りと違って、グンシュビの話を理解するにはかなり時間がかかった。
しかしやっとのことでその意味を知った駿は、愕然とした。
彼女の夫は、単于に罰せられて、遠い西に追いやられた。
幼子を抱え、女手一人で生きて行くには、匈奴の社会は厳しすぎた。
通常、母子家庭というのは匈奴社会ではあり得ない。
男女の協力があって、生計が成り立つ社会であるため、夫が亡くなった場合、残された妻は近親者に嫁ぎ直す。これを嫂婚制度と呼ぶ。
そうやって、生計を維持するわけであるが、ツルゲネにはそれが出来なかった。
なぜなら、彼女の夫は生きているからである。
最初のうちは、彼女の両親が面倒を見てくれていたが、その両親も相次いで亡くなってしまった。何かの拍子に、そう話していたことを、駿は覚えていた。
生きていく上で、男手はどうしても必要である。
そのため、必要になったらその都度、彼女は男に身を任せるしかなかった。
弱者の救いの手を差し伸べるような、生やさしい社会ではなかった。常に臨戦態勢を取る匈奴は、たとえ、親戚といえども打算的な関係で成り立っていた。
この五年間、ツルゲネは自分と息子を守るため、数多くの男と寝るしかなかったのである。
不特定多数の男と、自分の利害のために寝る女。
腰を振る女とは、そう言う女性を指していた。
そして、そう言う女は、烏孫でも、匈奴でも、決して珍しいことではなかった。
「岑陬、早いけど代わるよ。下で寝ててくれ」
「いいのか?」
「寝過ぎて、むしろ調子悪いくらいだよ」
二人は手をパシンと合わせると、その場を交替した。
去っていく彼の後ろ姿を見ながら、駿は大きく溜め息をついた。
彼の話は重すぎた。
自分の意志とは関係なく、不特定多数の男と寝なくてはならない。
彼は、そう言う境遇の女性を少なからず見てきた。
何しろ、親分・衛青の母親がそうである。そして彼女の周りには、そう言った女性が数多く集まっていた。
辛い、なんて一言では言い表せない。
彼女たちの涙が、駿の頭に蘇ってきた。
彼女たちは、人前では泣けない。誰も知らぬところで泣くのだ。そして、泣いても何も変わらない。過酷な運命は。
同時に、有為の言葉も思い出した。
沙漠で出会った沈玲や、自分の義母について言った言葉。
どんなに夫が憎くても、子供は愛しいのだと。
ツルゲネも、きっとそうだったのだろう。
若いどころか、幼くして母になった彼女が、生きていく上で、自分の子供の存在はどんなに大事だったことだろう。
子供の成長だけが、彼女の支えだったはずだ。
子供のために、歯を食いしばり、意に沿わぬ男にも身を任せていたはずだ。
そのかけがえのない、大切な存在を、殺したのは――
駿は、懸命に記憶を辿った。
蘢城に火を放ったのは誰だったのだろう?
自分と青が言い争っているうちに火の手は上がった。そして、その火が燃えさかる中で、自軍は撤退していった。
それしか思い出せなかった。
彼女の子を、殺したのは、やはり自分だ。
つまらない言い争いをせず、素直に命令に従って、撤退していれば、蘢城に火をつけることもなく、そこを清めるために彼女の子供が生け贄にならずに済んだはずだ。
その晩、彼は何度も溜め息をついた。
溜め息をついているうちに、夜が明けた。
「小姐さん」
駿は、一晩中同じ場所で踞っている彼女に声を掛けた。
「前にも言ったけどさ、もう、そんな体を張らなくてもいいんだよ。俺が必ず、あんたを兄貴のところへ連れていくから」
「だが、駿、お前は騫を守るんだろう?」
「ああ、それは、間違いだった」
駿の言葉に、ツルゲネは顔を上げて彼を見た。泣きはらしたような、はれぼったい顔をしていた。
「兄貴ほどの腕を、俺が守るなんてお門違いだよ。もし、兄貴が本気になったら、あんたなんて歯も立たない。だが、もし兄貴があんたに殺されるんだったら、それは兄貴の意志だ。俺がどうこうしても仕方ない」
駿は、ツルゲネの方に手を伸ばし、彼女を立たせた。
「行こう。そろそろ朝飯だ」
「駿」
「守るよ。おれがあんたを、ちゃんと。だから、もう、あんな事はしないでくれ」
「駿、お前、私の気持ちを、知ってるのか?」
駿は、彼女に背を向けると、何も答えなかった。何も、答えられなかった。
「お前は、結局私を見ていない。私を通して、騫しか見ていない。そうだろう?」
「先に、行く」
駿は、答えぬままに足早に去っていった。
食事が終わると、駿は自分が少し熱っぽいことに気がついた。
「傷のせいかな」
「夕べ、起きてるからですよ」
額に手を当てて、彼の熱を確かめながら有為が文句を言った。
「毒がまだ残ってるようですね。今日は、念のため、一日寝てるんですよ。動き出さないよう、縛り付けましょうか?」
「縛らなくても寝てるよ。矢傷を甘く見たら、命取りなことぐらい、俺もよく知ってるよ」
そう言うと、言葉通り駿はごろりとその場に横になった。
「ああ、そんな適当に。ちゃんと寝床用意しましたから、こっちで寝てください!」
有為は文句を言いながら、彼をこしらえた寝床まで引きずった。
「お前、どっかのおばちゃんみたいだな。いちいちうるせえよ」
「変なこと言ってると、傷口に塩塗りますよ!」
苦笑しつつ、有為の言うことを聞いて寝床に横になると、熱のせいだろう、すぐに駿は眠りについた。
どれくらい眠っていたのだろう。
照りつける太陽に暑さを感じ、駿は目を覚ました。
ふと、目を開けると、そこにツルゲネの顔があった。
あまりの近さに、駿はぎょっとしたが、彼女はよく眠っているようだった。
動いた拍子に、濡れた布が顔から落ちてきた。体温で暖められて、それは生暖かくなっていた。
熱を冷ますために、彼女が置いてくれたのだ。
それを何度か交換しているうちに、彼女はうたた寝をしてしまったらしい。
駿は、濡れた布切れを握りしめながら、彼女の顔を見た。
閉じた瞳に、長い睫毛がやけに栄えて見えた。そう言えば、初めてあったとき、彼女の瞳がとても印象的だった。
突然、駿の心臓が妙に高鳴った。
(やっべえ……)
熱で体が火照っているせいもあるだろう。抗えないほどの強い欲望が、駿の体を突き抜け、すぐ側で眠っている彼女の体を引き寄せたい衝動に駆られた。
(こいつは、兄貴の嫁さんだぞ)
何度も言い寄られていたが、その時よりも、今の方が彼にとって危機的状況であった。
爆発寸前なものを抱えながら、駿は右へ左へ寝返りを打った。
(そこを我慢するのが、好漢ってものだぞ)
駿は衛青の言葉を思い出した。
匈奴に攻め入るのを前に言われた言葉だった。
血を見て、男たちは興奮する。その興奮のまま女を襲いたくなるのが少なくない。それを、青は諫めたのだ。
「我慢って、どうやって?」
年季の浅い駿は、青に尋ねた。
「そこら辺の男のケツでも見てろ。陛下みたいな趣味がなきゃ、すぐ萎えるぞ」
「なんだよそれはぁ!」
その時は、冗談半分に笑って聞いていたが、今は天のお告げだ。
(ケツ……有為!)
この旅の始めの頃、馬になれない有為は大腿部と臀部を鞍で擦りむいてしまった。そこに薬を塗ってやったのが駿だ。
(ケツの穴の皺、一本一本まで思い出してやる)
半ば自棄になって、駿はあの時のことを鮮明に思い出そうとした。
(そうだ、うっかり玉にも触っちまったっけ)
気色悪い感触まで思い出しているうちに、爆発寸前な物はすっかり落ち着いていった。
「――独生どの」
と、いきなり目の前にその有為が現れた。駿は思わず悲鳴を上げて起きあがった。
「どうしたんです?念のため、傷にもう一度薬を塗りたいんですが……」
「いや、その……」
決まり悪そうに、駿は座り直した。
「お前も、たまには役に立つんだな。ありがとう」
「は?何ですか?」
膏薬を手にした有為は、変な顔で駿を見た。
「いいから、さっさと薬を塗ってくれ」
そう言って、駿はぱっと服を脱いで、彼に背中を見せた。有為は、変な顔のまま矢傷に薬を塗り始めた。
安期先生の薬が効いたのか、毒が抜けきったのか、次の日には駿はすっかり元通りに回復した。
駿は、ツルゲネと有為、三人で林に入り、食べられそうなものを物色していた。
長く旅を続けているため、彼らの手持ちの食糧は、既に尽きていた。狩りをしたり、木の実を取ったりして、その日その時の食料を得ていたのだ。
「どういうのが食べられるんです?」
都会育ちの有為は不安そうに尋ねた。
「虫と鳥が食ってれば、人間も食えるよ」
赤く熟した木の実を見ながら駿は答えた。
「解りました。もっとあっちに行って捜してみます」
心許なげに腕を前に組みながら、小走りに有為は奥に向かって走っていった。
「大丈夫か?」
彼の後ろ姿を見ながら、心配そうな口調でツルゲネは言った。
「ああ、なんかあったら、すぐに尻尾を巻いて戻ってくるって」
駿は、木の実をいくつか摘むと、彼女に渡した。
「これ、何ていう実だ?」
「さあ……ここは私の住んでいる場所とは違うから、初めて見る」
駿は、その木の実を摘み取ると、ぽいと口に入れてみた。甘酸っぱい汁が、口の中一杯に広がった。
「桑の実に似た味だな」
「桑……?」
「こんな丸い実じゃなく、つぶつぶしたかんじだけどな。葉っぱは蚕の餌だ」
「蚕って、何だ?」
「蚕も知らないのかよ。あんたの大事な玉が入っている袋は錦だろ?その布の元になる糸を作るのが蚕だよ」
「……そうなんだ」
懐から袋を取り出すと、彼女はそれを不思議そうに眺めた。
「ガキの頃、よく食べたな。親分と親分の甥っ子と、よく桑林に潜り込んじゃ取って食べてた」
ふと、駿は彼女の顔を見た。ちょっと、寂しそうな顔をしていた。
「色気ないか、こんな話」
駿は、そう言って彼女に笑いかけた。
「そうだ、今、海棠の花の頃だ」
「海棠?」
「薄紅の、綺麗な花が咲くんだ。うち――っていっても、親分の家なんだけど、陛下から貰ったいい樹があってさ、この季節になると、すっごく綺麗なんだ」
駿は、取った木の実を彼女に渡しながら言った。
「見に来いよ。今からじゃ、今年の花は間に合わないけど、来年、花が咲いたら」
「え?」
「張の兄貴に会ったら、それで終わりじゃないだろ?お前も漢に来るんだろう?だから、見に来い。待ってるから」
「……駿」
「約束だよ」
駿は、熟した実をあらかた採り尽くすと、それを全て彼女に渡した。
「静かだと、妙に心配になるな。ちょっと有為を見てくる」
そう言って、彼は林の奥の方に足を進めた。
有為はすぐに見つかった。彼は、座り込んで何かをじっと見つめていた。
「何してるんだ?」
「このキノコ、虫が付いてるんです。食べられるんでしょうかね?」
有為は、木の根本に群生している、茶色いキノコを指さしながら言った。食欲が落ちてきたとはいえ、まだ食べ物に対する興味は失ってはいなかった。
「止めとけ。キノコは解らんぞ。当たって死ぬことだってあるんだから」
「私、好きなんです、キノコ」
「じゃ、死ぬか?」
「嫌です」
そこへ、馬の足音が響いてきた。グンシュビだ。
「駿!有為!」
グンシュビは二人を見つけて叫んだ。
「カンが戻ってきた。居場所が解ったそうだ」
「兄貴の!?」
駿と有為は、グンシュビの言葉を聞いて、急いで宿営地に戻った。そこには、探索を終えた堂邑父が待っていた。
「団長は、休屠王の幕営にいます。枷を着けられ羊の番をさせられていました」
「会ったのか?」
「誰にも気付かれぬよう、遠目で確認しただけです。痛ましいその姿に、すぐにでもお救いしたかったのですが」
堂邑父は目に滲んだ涙を拭った。
「いいさ。兄貴は俺たちが、必ず救い出す」
駿は、堂邑父の肩を叩いて彼をねぎらった。
「問題は、どうやって救い出すかだな」
「問題はないさ」
グンシュビは言った。
「真正面から行けばいい」
「何か策があるのか?」
「ああ」
彼は、ニヤリと笑った。
明日の朝一番に発つことを決めた彼らは、宿営地を片付けに入った。
移動に次ぐ移動を繰り返してきた駿にとって、大怪我もしたが、良い骨休めにもなった。
荷物をまとめていると、彼の傍らにツルゲネが立った。
駿は、彼女の顔を見て尋ねた。
「もうすぐ兄貴に会える。覚悟はできてるか?」
しかし、彼女は何も答えなかった。
駿は、一つ息を大きく吸った。
「とにかく、兄貴に会ったら、ちゃんと話すんだよ。あんたの子が、どんな子だったか。あんたがどんなに大変だったか。全部」
「私は……」
「そうしたら、全て終わったら、来いよ。俺んとこへ。花を見にな。来年の話だけどさ」
「私の気持ちを、お前は知ってるのか!?」
「知らねえよ」
駿は、苦笑いを浮かべながら言った。
「だから、そこで待つんだ。お前のこと。これで、死んで欲しくない」
「――知っていたのか?」
「大体はな、想像つくさ」
「……確かに、最初は騫と差し違えて、私も死ぬつもりだった。あの子の元に行くために。だけど…」
ツルゲネは、じっと駿の顔を見た。駿は、その視線に痛いものを感じ、彼女から背を向けた。
彼の行動に、ツルゲネはむっとした。そして叫んだ。
「駿!私はお前と一緒にいたい」
駿は、どう答えていいのか、解らなかった。どんな顔を彼女にしていいのか、解らなかった。
彼は、背を向けたまま、彼女に手を振ると、その場を走り去った。
その晩、駿は眠れなかった。
見張り場で星を見上げながら、彼はぼんやりと考え込んだ。胸にツルゲネの言葉が重くのし掛かっていた。
自分は、彼女にどうすれば良いんだろう。
彼女の、かけがえのない宝――一人息子を死に追いやった自分が出来ることは、何なのだろう。
何を、してあげたいのだろう。
(生きて、欲しい)
ふと彼はそう思った。
今は亡き子供に代わる希望を、彼女に持って欲しい。
それを、自分が与えられるのだろうか?
休屠王の幕営までは三日の行程だ。彼らは、相手に気付かれないよう、慎重に進んだ。
「休屠王の幕営の死角に入る、良い場所がありました。回り込むため、二日ほど遠回りすることになりますが」
「多少回っても、その方が良いと思う」
「ああ」
堂邑父の言葉に、駿とグンシュビは頷いた。
三人は、張騫を救う手はずについて、何度も議論を交わし、出来る限り万全を期そうとしていた。
有為は、馬に乗っている間さえ、書物から目を離さなかった。帛書はかなりほつれ、うっかりすると風に飛ばされ散り散りになりそうだったが、それでも十万回にはほど遠かった。
ツルゲネは、書に気を取られて、ともすれば馬から落ちそうになる有為を気遣ってはいたが、一人、考え込むことが多かった。
彼女の中で、何かが変わっていた。
駿は、川の水で顔を洗うと、ほうっと息をついた。出来るなら服も全部脱いで、水の中に入りたい気分であったが、側にツルゲネがいたから遠慮した。
手足を洗っていると、横にいた有為は用を足すからと、どこかへ行ってしまった。
堂邑父とグンシュビは、向こうの方で何か細工をしていたので、気がつけば川辺にはツルゲネと二人だけになっていた。
(まいったな……)
駿は、このところ、彼女と二人きりになるのを避けていた。
気まずい空気が、二人の間に流れていた。
「駿……」
ツルゲネは彼の横に座ると言った。
「お前は、私のことを、どう思っているのだ?」
駿は、何て言っていいのか、解らなかった。
「結局、お前は私ではなく、私を通して、騫のことしか見ていない」
「花を見に来いって言ったのは、張の兄貴ではなく、お前にだよ。お前に来て欲しい」
「じゃあ、私は、お前の何だ?」
「――小姐さんは、兄貴の嫁。……それ以上は言わない」
その言葉を聞き、彼女は黙って立ち上がり、その場を走り去っていった。
残された駿は、うつむきながら、指を噛んだ。水面が日の光を反射して、キラキラと光っていた。
堂邑父が言っていた場所は、休屠王の幕営の北側にあった。小高い岩山が幾重に続いており、登るのは大変だが、身を隠せそうな場所はいくらでもあった。
「あれが、休屠王の穹廬か」
休屠は居延周辺で最も強勢を誇る部族だ。その王の穹廬もそれに相応しく、豪奢で巨大な物であった。
騎馬民の穹廬は、普通は台車が着いた小さな物だ。
だが、休屠王の穹廬は台車が無く、直に地面に据えられていた。台車に乗るほど、小さくなかったのだ。
柳材で骨組みを作り、羊皮で覆ったそれは、巨大ではあるが組み立ても分解も容易くできるようになっており、移動を主とする彼らの生活にあった住居でもあった。
休屠王の穹廬は、金糸、銀糸の刺繍が施され、色とりどりの旗で飾られていた。それらが光を反射し、遠目からでもその艶やかさが伝わってきた。
王の穹廬の周りには、よく見る小さな穹廬が取り囲んでおり、大地に不思議な図形を描いていた。
「じゃあ、先に行く」
グンシュビは、そう言うと、単騎、休屠王の幕営に向かって発った。
「迎えは、打ち合わせ通りに頼む」
彼の言葉に、駿と堂邑父は頷いた。二人に見送られ、グンシュビは一気に岩山を下っていった。
「どのくらいで、俺たちは行くか?」
「岑陬の姿が、幕営に見えてからでいいでしょう。焦って相手に見つかっては元も子もありませんから」
そう言いながら、堂邑父は、弓の手入れを入念に始めた。
駿は、意を決してツルゲネの方に向かっていった。
「いよいよだ」
「ああ」
そう言いながら、ツルゲネは冷たい視線を駿に投げかけた。駿は、一瞬、心臓が凍り付くかと思った。
「あのさ……」
駿は、頭を書きながら、懸命に言葉を探した。
「小姐さんの話に、ちゃんと答えられなくて悪いとは思うけどさ」
ツルゲネは、表情を変えることなく、彼の顔をじっと見つめていた。
「だけど……だけどさ、ああ、もう、じれってえ!」
駿は、見つめられることに耐えきれなくなり、彼女に背を向けた。
「離縁して嫁ぎ直すことは、漢だって、珍しい事じゃない。それに、張の兄貴も、話の解る人だ。だから、そのつまり」
駿は、肩越しにちらりと彼女を見た。彼女は、瞬き一つもせず、じっと自分を見つめていた。
「つまり、そう言うことだよ!」
そう言い捨て、駿は自分の馬の方に走っていった。
ツルゲネは、ただ黙って彼が走り去っていくのを見つめていた。
不思議に、何も感じなかった。ただ、いつもの想いが、胸を満たしていた。
彼女の心は、恨みに満ちていた。
自分の子供を殺された恨み、もう、それだけではなかった。
好きな人と、一緒にいることも許されない現実。
子供を失ったのも、望む人と一緒になれないのも、自分が幸せになれないのは、全ては張騫のせい。
玉を奪って、単于庭を逃げ出したとき、彼女は夫・張騫を殺すことしか考えていなかった。
彼を殺して、自分も死ぬ。
死者の静かな国で、親子三人で暮らすのだと。
今は違う。
自分の不幸の源を、全て殺し尽くしたい。
夫・張騫。全ての原因を作った堂邑父。
これだけでは、足りない。
夫を拘留していた休屠王も、今、共に旅をしている有為と岑陬も、出来ることなら、皆一人残らず死ねばいいのだ。
そして、愛しい彼。
この世界で、決して一緒になれぬのなら、暗い地の底で、永遠に一緒にいよう。
彼女は、剣の柄をぐっと握りしめた。
自分の力ではどこまで出来るか解らない。だが、いつものように、自分の体を武器に、上手い具合に内紛を起こすことは出来るかも知れない。
皆殺しだって、不可能ではないのだ。
そのために、今はただ、彼らが張騫を救い出そうとしていることに、大人しく協力すればいい。難しいことではない。
冷たいほほえみが、彼女の顔に浮かんでいた。
その、彼女の深い恨みを吸って、玗琪の玉はぎらぎらと輝いていた。
第八章 再会
「烏孫の王孫が、何用で来たのだ?」
休屠王はグンシュビに会うと、開口一番にそう言った。彼のはだけた上衣の間から、金色に輝く絹の下着が覗いていた。
これは、金の糸を吐く大変珍しい蚕から作られたものであった。当然、大変な珍品だ。彼は、これをさりげなく見せびらかして、自分を誇示していた。
規模で言うと、休屠より烏孫の方が遙かに強大であったが、休屠王はそんなことなど全く意に介さず、尊大な態度で彼に謁見した。
王は、自分の穹廬の中に彼を通さず、部落の広場で彼と会った。
その広場の中心に一人、周りを休屠の兵に囲まれても、グンシュビは少しも怯むことなく、威風堂々と立っていた。
彼は、月氏と拙攻する西の一大勢力、烏孫の王太孫であるという強い誇りがあった。
風に揺れる、少し癖のある後れ毛を指で整え、両手を組んで胡流の挨拶を交わすと、彼は切り出した。
「一月の会が終わった後、わたくしは図らずも病を得、許婚者である丘林の許で養生しておりました。その時、丘林の者からここで、風変わりな漢奴がいるという話を聞き、祖父王への土産話に、是非、その漢奴を見てみたいと思ったのでございます」
「確かに、ここには単于から預かった漢奴がおる」
休屠王は、グンシュビの持ってきた結縄を手にしながら、頷いた。そして、漢奴を連れてくるように部下に命じた。
グンシュビは、深々と王に礼を取りながら、内心してやったりとほくそ笑んだ。
間もなく、手と足に枷をつけられた男が、兵士につつかれながらよろよろと歩いてきた。 髪も髭も伸び放題で、手入れもされておらず、ボロ同然の服を纏っていた。あちこちに傷跡があり、垢にまみれたその姿を見て、堂邑父が涙したのも解る気がした。
(彼が張騫なのだろうか?)
堂邑父や駿と違い、張騫と面識のないグンシュビは正直戸惑っていた。それほどまでに、男はみすぼらしい姿をしていたのだ。
「彼の名は、何と申すのです?」
グンシュビは休屠王に尋ねた。
「烏孫王孫、何故、訊く?」
「何故とは……勿論、祖父王への土産話のためです」
「祖父王か」
休屠王は、結縄を指で弄びながらニヤリと笑った。
「そもそも、お前は本当に烏孫の王孫なのか?」
「何ですと?」
王は、結縄をグンシュビの方に向かって突き出した。
「偽物の結縄を持ってくるような者が、本当に王孫なのかと聞いているのだよ」
「偽物!?何を根拠にそんなことを!」
「馬鹿にするな!!」
王は結縄をグンシュビの足元に投げつけた。
「烏孫は、ここ数年、ほとんど単于庭に現れぬから知らぬが、丘林はよく知っておる!ここに結ばれている二つの結び目のうち、丘林の結び目は明らかに偽物だ!」
グンシュビは、チッと舌打ちをした。
堂邑父と念入りに、丘林の結び目を再現したつもりであったが、あっさりと見破られてしまった。
この結縄は、いわゆる挨拶状、紹介状のような物で、それぞれの部族特有の結び目を結ぶことによって、持ち主の身分を保障する物だった。
その結び方は門外不出で、族長など、限られた家系にしか伝えられない。
それ故、堂邑父と見よう見まねで丘林の結び目を偽造したのだが、やはり見破られてしまった。
「烏孫の物が偽物かどうか、解りもしないで、よくもそんな言いがかりを」
グンシュビは開き直って、休屠王を睨み付けた。
「言いがかりではない。事実であろう。漢奴に会わせてやったのも、冥府への土産話にと言う、恩情よ」
「私は、亡き烏孫王太子の長子であり、現王太孫である。事実かどうか確かめたくば、我が首を取り、烏孫の大禄に差し出せばよい。多大な褒美がもらえるぞ」
大禄は、烏孫王昆莫の次子で、グンシュビの叔父である。
先の太子、つまりグンシュビの父の死後、本来なら彼が次の太子になるはずであった。しかし、遺言を盾に、無理矢理グンシュビが太子位に就いたのである。
烏孫内の勢力は、大禄が上。隙あらば太子位を窺っているのも彼であった。
匈奴の単于家と通婚したり、漢と関わりを持とうとするグンシュビの動きは、全てこの叔父に対抗するためであった。
「では、その首、頂こうか」
広場の周囲を取り囲んでいた兵士たちは、一斉に矢をつがえ、グンシュビに照準を合わせた。
グンシュビは臆することなく、堂々と胸を張って立っていた。そして、自分を囲んだ兵士たちを、ギロッと一瞥した。
その様を見て、王はフン、と鼻で笑った。そして右手を挙げ、矢を放つ合図をした、その時――
あちこちから大きな悲鳴が上がった。
見ると、兵士たちが次々ともんどり打って倒れていった。
ひゅん、ひゅん、と風を切る音が響き、北の方角から矢が止むことなく飛んできた。
矢は、正確に兵士を射抜き、一本も無駄になっていない。
兵士たちは慌てて、照準をグンシュビから襲撃者に変更した。しかし、遅すぎた。動揺している彼らが体勢を立て直す暇も与えず、矢は次々と飛来した。
その軌道の正確さに、グンシュビは改めて舌を巻いた。
兵士たちの中心にいる自分には、擦るどころか全く飛んでこない。全て、敵の兵士に命中していた。
堂邑父の腕に感嘆した彼は、思わず口笛を吹いた。
「岑陬!何ぼけっとしてるんだよ!!」
怒鳴り声と共に、敵の輪の中に駿が飛び込んできた。彼は、そのまま馬で広場を突っ切ると、先程の薄汚れた漢奴の方に向かって行った。
「兄貴!」
そう叫ぶと、彼はその男に向かって腕を伸ばした。
男は、駿の顔を見てハッとした。
駿は頷くと、そのまま男を抱え上げ、馬に乗せた。
それを見たグンシュビは慌てて自分の馬を呼ぶと、それに続いた。
男の足枷は、革紐で繋がれていた。
駿は走りながらそれを短剣で断つと、男を鞍に座らせ、自分は尻の方に移動した。
「手は後回しにするよ。馬に乗るにはそれで充分だろ?」
「ああ――俊々」
その言葉に、駿は照れ笑いを浮かべた。
同時に、右側から有為とツルゲネが馬で近づいてきた。
「駿!」
「頼む!」
その言葉を受け、ツルゲネは脇にいる有為の馬にひらりと飛び移った。解っていたことだったが、思わず有為の口から「ひい」と言う悲鳴が漏れた。
ツルゲネは、有為の手から手綱を奪うと、駿を見た。
駿は、空になったツルゲネの馬の方にさっと飛び乗った。
男二人乗ったのでは、馬の負担は大きい。
それだったら、男女の相乗りのほうがまだまし。それから、馬になれない有為よりも、胡人のツルゲネの方が遙かに早く走れる。
何度も話し合った結果、この組み合わせで行くのが、一番だということになったのだ。
馬を移動したのとほぼ同時に、グンシュビが追いついてきた。射るのを止めた堂邑父も、北の方からこちらに向かってきていた。
「頼んだ」
「任せろ」
グンシュビは止まることなく三人の横を駆け抜け、手を伸ばして漢奴の馬の手綱を取った。それを引いたまま、堂邑父の方へ向かっていった。
駿、それからツルゲネと有為の乗った二騎は、一旦馬の足を止めた。そして、じっと敵が追いつくのを待った。
「まだですか?」
おどおどした口調で有為が尋ねた。
「もう少し、引きつけてからだ。ここで完全に捲かなくては」
駿の言葉に、有為は掌の物をぎゅっと握った。
追っ手の姿が、だんだんと、はっきり見えてきた。
「そろそろだ。数を数えよう。十数えたら、あいつらに向かって投げつけてやれ」
有為は、駿と共に、ゆっくりと数を数えた。
「今だ!」
駿の叫び声と共に、有為は掌の物を思いっきり地面に叩きつけた。
ボン、と言う大きな爆発音と共に、辺り一面に煙が立ちこめた。
煙玉だ。
「おい……大丈夫か?」
煙に咽せながら、駿は二人に声を掛けた。
「何とか」
「早く行きましょう」
咳き込みながら有為が言うと、ツルゲネは手綱を引いた。
「これはこんなに煙が出るものだったか?」
ものすごい煙量に、思わず駿は尋ねた。
「二つ一辺に破裂させたので、煙の量も二倍になったのでしょう」
「二倍どころか、十倍だぞ」
煙に紛れながら、二騎は大きく方向を転換し、グンシュビたちの後を追った。煙の中からは追っ手の咳き込む声や、怒号があちこちから響いていた。
待ち合わせの場所は、潜んでいた場所とは正反対の南側にあり、湖を望む高台にあった。「団長は、すぐに”俊々”だと気付かれたのですね」
そこで、手と足の枷をはずしながら、堂邑父は張騫に言った。
「ああ。見違えるように成長していたが、一目で解った。ここから助け出してくれるのはあいつだと、何となく思っていたからだろうな」
縛めの解けた腕をさすりながら、騫は笑った。
「しかし、堂邑父、年を取ったな」
グンシュビと共に足かせを取り外しにかかっていた堂邑父の顔を見て、ふと、騫は言った。彼の顔には、深い皺が幾つも刻まれていた。
「お互い様でしょう?」
髪に白いものが目立ち始めた騫をからかうように彼は答えた。
「そうだな。十年だ。その間に、あいつは立派な若武者になったわけだ」
馬に乗り、疾風のように駆け抜ける駿の姿を思い出しながら、騫は呟いた。
間もなく、駿たちも高台に到着した。上の方にいる三人に合流するため、坂道を上りながら、ふと、休屠王の幕営の方を見た。
白い煙が、朦々と天高く上っていた。
「まだ煙が残ってる。火が上がったみたいだぞ」
「人畜無害という話でしたから、火の手が上がるはずはないのですが」
ふと、有為は思い出したように言った。
「そう言えば、安期先生は、煙玉は必ず一個ずつ使うようにとおっしゃってました。多分、このように煙が出すぎるからなのでしょうね。もしも、頂いた五つを一度に使ってしまったなら、国中が煙で埋まってしまったかも知れませんね。それはそれで、見てみたいものですが」
「……お前、今、とんでもないこと言ったぞ」
「え?」
駿は、何だかんだ言って有為も安期生と同類なんだと首を振った。
と同時に、もし、あの時、この煙玉があったならば、運命は変わっていただろうにと思った。
蘢はいわゆる石塚だが、色とりどりの綾錦で飾られていた。火は、その飾り布に放たれた。
雨の少ない地域故に、布は良く乾いており、あっという間に火は燃え広まった。石と石の間に挟まれた小枝も、広がる火の手に一役買った。そして、消火に慌てる匈奴たちを尻目に、衛青軍は撤退した。
去り際、駿は火柱に包まれた蘢を見上げた。
それは恐ろしく、美しい光景だった。
赤々と燃え広がる炎の中、何かがキラキラと光っていた。それは、玗琪の玉だったのだろうか……?
蘢城に火が放たれなければ、張騫とツルゲネの子は死なずに済んだ。
もし、そのことが事前に知っていたならば……。
駿は、大きく溜め息をついた。
自分は神仙ではない。未来のことなど、解りもしない。
でも神仙は――安期生や東方朔を見た限りではあるが、案外、何もしない。だから、神仙でなくて、良かったのだ。
この先に出来ること、彼女に、この先、自分がしてあげられること、それは何であるか、彼には解っていた。そして、それをするための決心も付いた。
駿は、ふと、彼女の顔を見た。
彼女は一点を見つめ、顔は緊張でこわばっていた。視線の先には、グンシュビと堂邑父に足枷を外して貰っている張騫がいた。
駿は、先に馬を下りると、手を差し伸べて彼女を下ろした。
彼女は驚いたように駿を見た。
「頑張れよ」
照れ笑いを浮かべながら、駿は彼女の肩を軽く抱いた。
「今までの恨み辛みを、洗いざらい、兄貴にぶちまけろ。全部、残らず。
そうしたら、新しく生まれ変われるんだ。もう、恨みなんて何もないところで、俺は、お前を待ってるから」
彼の笑顔を見て、ツルゲネは心の中で、何かが音を立てたのを感じた。
そう、確かに、騫に告げなければならない。自分たちの子供の最期を。
そうしたら、駿は自分のことを、受けいれてくれるのか?
自分は、どうすればいいのだろう。自分は、何をすれば、良いのだろう――
唇を噛み、考え込む彼女を尻目に、駿はグンシュビと堂邑父を呼びつけると、夫婦二人だけにするように頼んだ。
それから彼はもう一度、彼女の肩を軽く叩くと、そのままゆっくりと下に降りていった。
その途中で、三人は、彼に会った。
「何で、こんなところに――」
その顔を見て、駿は驚きの声を上げた。
同じ頃、有為は自分の荷の中から、慌てて帛書を引っ張り出していた。
「どうしよう」
先生に言われた十万回には、まだほど遠かった。
まだ、七万八千四百九十五回。
「どうしよう」
来てしまったのだ。胡巫が。
仙術を身につけ始めた彼には、それがはっきりと感じられていた。
どうやら胡巫は、ツルゲネの変化によって、玗琪の玉も微妙に変化していることに勘付いたようだった。それで、道を急いでここに向かってきているのだ。
「どうしよう」
有為は、半べそになりながら帛書を握りしめた。今の自分に、彼らと対抗する力が、あるのだろうか?
有為は、下腹に力を集中し、呼吸を整えた。体中に気を巡らすために、ゆっくりと手足を動かした。それはまるで、様々な動物の姿を真似ているように見えた。
時には虎、時には鶴。様々な形態を取ることによって、様々な気が彼の中に入り込み、力を与えるのだ。
気力が体中にみなぎってくると、有為の精神も落ち着いてきた。
とにかく、やるしかないのだ。安期生――師匠の命は絶対なのだから。
有為は、敵が近づいてくる方を、じっと見据えながら、調息を繰り返した。
ツルゲネは、駿が触れた肩を、反対側の手でさすりながら張騫の前に立っていた。
言いたいことがありすぎて、何から言っていいのか、解らなかった。
呆然と立ち竦む彼女に対し、騫も、どこか所在なげにしていた。我ながらみすぼらしい格好だと、照れ笑いを浮かべながら頭を掻いていた。
「――久しぶりだったな。元気にしていたか?」
騫の言葉に、ツルゲネは何も答えなかった。ただ、彼をじっと睨んでいた。
「子供は、どうした?無事に生まれたのか?」
「……死んだ」
彼女は、懐から玗琪の玉の入った錦の袋を出して、そう呟いた。
これが、一番言いたかったことなのに、それ以上言葉が出なかった。ただ、涙が後から後から流れ落ちて、袋を濡らした。
「そうか……残念だな。会いたかった」
(駿……!)
ツルゲネの胸の中に、さっき、駿がかけた言葉が蘇ってきた。
恨み辛みを全部吐きだしたその先に、彼が待ってくれているというのに、肝心の言葉が、出てこない。
ふと、肩に何かを感じた。もう一度、彼が自分の肩を叩いてくれたような気がした。
「騫」
ツルゲネは、顔を上げて張騫の顔を見た。
「私は、駿が好きだ」
意外な言葉を聞き、騫はひどく驚いた。だが、すぐにホッとしたような、優しい笑顔を浮かべた。
「そうか……良かったな。あいつは、仲卿(衛青の字)に似て、義侠心のあるいい奴だ。いい相手を見つけたな」
「……許して、くれるのか?」
「ああ。あいつなら、何の心配もない。安心してお前を任せられる。あいつならきっと、お前にこんな苦労はかけず、幸せにしてくれる」
彼の意外な言葉に、彼女はどうしていいのか解らなくなった。
こんなにあっさりと許してくれるのなら、今まで、自分が抱いていた恨みは、何だったのだろう?
自分は、何に苦しんでいたのだろう?
そう思った途端、玗琪の玉が解き放たれた。
彼女は、声にならない悲鳴を上げた。
玉の呪力に耐えかねなくなった体は、大きく海老反った。そしてそのまま虚空で止まった。彼女の顔からは血の気が失せ、目も半開きになり白目を向いていた。
胸の中心で、あの玗琪の玉がぎらぎらと赤く輝いていた。
「ツルゲネ!」
騫は、慌てて彼女を助けようと駆け寄った。しかし、何者かの手がそれを静止した。
「俗人は手を出すな!」
そう言ったのは、まさしく安期生であった。
彼は、豊かな黒髪をなびかせながら、掌で練った気を玉に向かって投げつけた。
安期生の放った気が、呪力を覆い込もうとした途端、嵐のような大風が起こった。
吹きすさぶ風をものともせず、安期生は大地をしっかりと踏みしめ、微動だにしなかった。
彼は、腕をゆっくりと動かしながら、玉の呪力を押さえ込もうとした。
と、その時、大地から無数の腕が生えた。それは争うように彼女の体に掴みかかり、地の底に引きずり込もうとした。
「地霊が動いたか!」
安期生は叫んだ。しかし、玗琪の玉の呪力を押さえるので手一杯であった。
「お任せあれ」
その声と共に何者かが、すっと彼女の下に入った。
それは、白く滑らかな玉で出来た羊であった。
「修羊公!感謝する」
修羊公は、華陰山にいる仙人で、武帝の父、景帝に招聘され参内したことがある。しかし、景帝には仙縁がないと見た彼は、化して石の羊の姿を取り、霊台の上で長いこと時を待っていた。
霊台とは、星々の運行を観察し、時の吉凶を判断するための、一種の天文台である。
景帝が薨去し、武帝が即位する頃に、霊台の石羊は姿を消した。
修羊公は漢朝と少なからぬ因縁のあるために、こうして加勢に現れたのだ。
長いこと石羊の姿を取っていたため、とっさの変化(へんげ)もやはり石羊であった。
ツルゲネの体は、石羊の背に横たわり、胸には玗琪の玉をしっかりと抱えていた。しかし、意識はなく、ぴくりとも動かなかった。
為す術(すべ)がなくなった地霊たちの手は、石羊の体を叩いたりひっかいたりした。しかし、石羊はそれを何とも感じなかったし、地霊の手も、それ以上は何も出来なかった。
難儀をしていたのは安期生だ。
玉の呪力は想像を超え、安期生の持つ力でも、容易に封じ込めるものでもなかった。
(堪えろ!)
石の体を震わせて、修羊公は安期生を励ました。
(間もなく、東西王府から来る)
「解ってる。まだまだ、私一人でも持ちこたえられますよ」
苦笑しながら安期生は言った。
「しかし、女の情念というものは、斯(か)くに恐ろしい。これほどまでに、呪力が増すとは」
「――女を悪く言う者は、どこの者じゃ?」
と、天空から、弦の音のように響き、鈴の音のように涼やかな声がさやさやと響いた。
芳しい香りと共に、柔らかな光が、二人の仙人に向かってゆっくりと降りてきた。
有為は、帛書を抱えながら、草原の真ん中にただ一人で座っていた。
今更、慌ててこれを読んだって、十万回には及ばない。彼は、蓬莱での五日間を振り返りながら、彼らを待った。
そして、地平線の彼方に彼らの姿を見つけると、何度か深呼吸をしてから、ゆっくりと腰を上げた。
彼らの動きは速かった。地平線に姿を現したかと思うと、あっという間に有為の目の前に迫ってきた。
「ここから先は、通しません。師の命によりわたくしがお相手を仕ります」
両手を広げて有為は言った。
救いだったのは、相手は三人。
顔に文身を入れた三胡巫だけだったからだ。
三胡巫たちと共に玗琪の玉を追ってきた兵士たちは、安期生に全ての武器を奪われてしまい、新たな武器を調達するために散っていた。
事態の急変を察知した三胡巫は、彼らが追いつくのを待っていられずに先に現れた。
彼らは、漢の言葉は解さないが、有為が何をしようとしているのかは容易に察しがついた。
両脇の胡巫は、薄ら笑いを浮かべて中心の胡巫――長胡巫を見た。長胡巫は、有為がただ一人で、しかもさしたる霊力もないのを見て、ばかばかしいと首を振った。
長胡巫は、馬に鞭を当て、有為の横を通り過ぎようとした。彼に、他の二人も続いた。
「行かせはしないと、言ってるのです」
彼らの行動は、容易に想像がついた。
有為は両手を伸ばしたまま、くるりと体を回転させた。彼の手の軌跡から、蛟龍が現れた。
虹色に光る鱗を輝かせながら、蛟龍はシャーっという声を上げその細い体をくねらせた。
蛇のように細く長い体に、蹼の付いた四肢を持った蛟龍は、三騎の周りをぐるぐるぐると回り始めた。
三胡巫は蛟龍を見てニヤリと笑った。
脇の一人が銅鼓を取り出すと、蛟龍に向かってそれを打ち鳴らし始めた。
その音に、蛟龍はフルフルと体を細かく震わし始めた。
それを見たもう一人も、銅鼓を取り出し打ち始めた。
途端に、蛟龍はパチンと弾けて消えた。
「こんなのに手間取るな」
「すいません」
最初に銅鼓を打った男が、一番若輩らしい。その証拠に、彼の顔の文身は額の中央に、小さな木が入れられているだけであった。
男を叱ったもう一人の胡巫の顔の木はさらに大きく枝葉が広がり、額と頬の一部にかかっていた。
これは騎馬民の浄土、生命樹を象ったものだ。
長胡巫になると、その木は顔中を覆い、所々に聖獣の姿も彫り込まれていた。
彼らの持つ霊力と、文身は比例をしていた。
蘢城の胡巫の中でも、長胡巫を筆頭に、優れた霊力を持つ彼らが玗琪の玉の奪回に来たのだ。
玗琪の玉は蘢城の神宝。何としても、取り戻さなくてはならなかった。
「あの小僧に、精霊を使うというのはどういう事なのか、ひとつ教えてやるか」
長胡巫は有為の小手先の技を嘲笑しながら、箱を取り出した。そしてその中から、聖獣を呼び出した。
それは、虎のような縞模様を持つ、巨大な大蛇だった。
古の昔から玗琪の樹を守り続けていた大蛇の姿を招聘し、長い時をかけて育て上げた、胡巫の使役する精霊の中でも、最も霊力のあるものであった。
大蛇は大きく口を開けると、一直線に有為に向かって襲いかかった。
「その手、見切ってましたよ!」
先程のは、ただの時間稼ぎ。
有為は、安期生から聞いた話通り、彼らが大蛇を呼び出したことに正直ホッとした。彼らが蛟龍を消している間に、有為が準備したものと、見事に相性がいいのだ。
「おめおめと引き下がっては、師の顔に泥を塗ることになります。そう簡単には、負けられないのです」
そう言いながら、有為は呪符に向かって最後の口訣を唱え、それを大蛇に向かって投げつけた。
呪符は、空中でくるっと回転すると、巨大な白貂の姿に変じた。
それは熊ほども大きく、紅玉のような一つ目が顔の真ん中で輝き、雪のようにキラキラした毛並みを持つ白貂だった。それは、四つある前肢で大蛇に掴みかかった。
彼の意外な技を見て、長胡巫は仰天した。どうやら、彼の背後には、自分たちよりも優れた霊力を持つ者がいるらしい――
長は、一刻も早く玉を取り戻すべく、徹底的に有為を叩きのめすことにした。
彼は、両脇の胡巫に銅鼓を打ち鳴らすように命じた。
その銅鼓の音に乗って、長は新たな精霊を召還した。
靄が立ちこめるように、それはゆっくりと姿を現した。
それは金色に輝く鷲の姿を取ると、上空から一気に白貂に向かって向かって襲いかかった。
「あっ」
有為は、慌ててもう一枚の呪符を出すと口訣を唱えて鷲に向かって投げつけた。
と、それは巨大な緋色の鱏に変じた。鱏の巨大な体は、鷲から白貂の姿を見事に隠した。鷲は、白貂を見つけようと左に右に旋回したが、上手い具合に鱏が覆い尽くし、なかなか見いだすことが出来なかった。
「あぁ、もう……」
ふいに、有為は頭を抱え、へなへなとそこに座り込んだ。
もっと、こう、鷲に攻撃を挑むとか、何かして欲しいのだが、鱏は有為の言うことなど一つも聞かなかった。ただ、適当に虚空を漂い、偶然白貂を覆い隠しているのに過ぎなかったのだ。
有為は、白貂に大蛇を仕留めるように命じると、鱏をコントロールしようと、何度も試みた。だが、全く駄目だった。
そこへ、胡巫は新たな精霊を召還した。
それは、銀の毛並みと蒼い目をした、牛ほどもある狼だった。
狼は、鋭い牙を剥き、低い唸り声を上げて有為を睨み付けた。
「……どうしよう」
元から有為の腕では、二体も三体も鬼神を使いこなすことなど無理だった。また、鬼神を呼び出す五雷法以外の仙術も習っていなかったのだ。
有為は帛書を十万回読めなかったことを、今更ながらに後悔した。
狼は有為をいたぶるように、低い姿勢でゆっくりと彼に近づいてきた。有為は、覚悟を決めて、目を閉じた。
狼が襲いかかってくるまで、想像以上の時間が経った。有為は、不思議に思って、ふと、目を開けた。
「――有為!」
目の前に、狼の牙が迫っていた。遠くで駿の声が響いた。
あっと思った有為は、再び瞳を閉じようとした。
その時――
虹色に輝く光が、狼の頭を貫いた。
同時に、融けるように狼の姿が消えていった。
「何で……」
事態が飲み込めずに、有為は腰を抜かしたまま呆然としていた。
「遅くなって、悪かったな」
その彼の元に、駿が駆け寄った。駿は、有為の頭をくしゃくしゃと掻き回すと、敵を見据えながら笑った。
「勝ち戦だ。気負うな」
そこへグンシュビと堂邑父も二人に合流した。
「貴重な矢を、無駄にしたな」
「何を言う」
グンシュビの言葉を、駿は鼻で笑った。
「あんたやおっちゃんの腕なら、一本の矢で二人一辺に射抜くことぐらい、造作もないことだろう?」
グンシュビと堂邑父の手には、虹色に輝く矢が握られていた。
二人は、苦笑いを浮かべつつ、その矢を胡巫に向かってつがえた。
終章 海棠の誓い
「さっき、安期先生に会った」
駿の言葉に、有為は驚きの色を隠せなかった。
「いらしてたのですか!?」
「直に現れるさ。お前一人じゃ心許ないからって、俺たちに、この矢を渡していった。ただ、この矢は曲者で、使えるようになるまで時間がかかる上、一人一回しか使えない。どういう訳だか解らないが」
この矢は、持ち主の気を凝縮して効果を発揮する。それ故、常人では使えるまで時間がかかるし、一度しか使えないのだ。
これが安期生や修羊公のような仙人であれば、時間もかからないし、無限に、幾度でも使えることができる。
「その貴重な矢を無駄にしてしまったのですね」
駿の言葉に、有為は申し訳なさそうに言った。
「馬鹿。お前を助ける方が先だ。それに、堂邑のおっちゃんなら、一本で二人ぐらい、楽に出来る」
そう言って、堂邑父の方をちらりと見た。
堂邑父は軽く頷くと、力一杯矢を引き絞った。
しかし、相手も何もしていないはずはなかった。
長胡巫は両手を大きく広げて円を描いた。と、その軌跡に合わせて見えない壁が現れ、彼らの姿をふっと消し去った。
「これでは、射られない」
標的を見失ったグンシュビが、弓矢を下げて困ったように呟いた。
「そうですか?」
その様を見て、堂邑父はニヤリと笑った。
「姿は消しても、音は消えてません。気配もしかり。標的を見失ったわけではないのです」
実際、精霊を操るために銅鼓は打ち鳴らされ続けていた。しかし、姿が見えなくなった今、その音は四方八方から聞こえてくるように思われた。
その音に耳を澄ましながら、堂邑父はゆっくりと矢の照準を合わせた。それから、力一杯に矢を引き絞った。
ひゅん、という風切り音と共に、矢は放たれた。
矢は、ふっと虚空で止まると共にものすごい衝撃波が起こった。
硝子が粉々に砕け散るように、見えない壁が、無機質な音を立てて崩れた。
矢は、その壁の向こう側、長胡巫の眉間に見事に突き刺さっていた。
長胡巫は、そのまま馬から崩れ落ちていった。
若輩の胡巫が、慌てて長を助け起こそうとしたとき、グンシュビの矢が彼を貫いた。
「有為!」
それを見た駿は叫んだ。
「霊力は削がれた。今こそ、あの化け物たちを消し去る好機だ」
「ど、どうやって!?」
「何で俺に訊くんだよ?お前、何を教わった?」
「一体で、二体を相手にするなんて、私には出来ません」
力が衰えたとはいえ、残った一人によって二体の精霊は相変わらず目の前にいた。
白貂と大蛇は、互いの牙と爪で激しくもみ合っていた。金色の鷲は、行く手を阻む鱏に痺れを切らし、その背を何度も嘴で突いていたが、鱏は全く動じることなく、ただ、鰭をゆっくりと上下させながら虚空を漂うだけだった。
「お前だって、二体出してるだろう?」
「あの鱏は、私の言うことなど何一つ聞いてはくれないのです」
有為の言葉に呆れながらも、駿は鬼神たちの動きをじっと見た。
「あの白貂は言うことを聞くのか?」
「ええ」
駿は虚空で戦いを続ける鬼神たちを指し示しながら、有為の耳元で何やら呟いた。
「そんなこと、出来ません!」
「いいから、俺の言ったとおり、やってみろ」
駿は、有為の肩に手を当てて言った。そして、鱏と鷲の動きをじっと見つめた。
「今だ!白貂を大きく左に動かせ」
有為は、手を大きく回し口訣を唱えた。と、白貂はものすごい速さで左に飛び、鱏の影から出た。
やっと白貂の姿を見つけた鷲は、白貂に向かって一直線に舞い降りようとした。
と、鱏の目が、光った。
鱏にしては慌てて――だがやはり緩慢とした動きで、左に移動し鷲の邪魔をしようとした。
「蛇を、上へ放り投げろ!」
白貂が大きく動いたことで、大蛇も慌てて貂に向かって襲いかかってきた。貂は大蛇の胴体をむんずと掴むとその勢いのまま上空へ放り投げた。
何かの影が飛び出たのに気付いた鷲は、反射的にそれに飛びかかった。
いきなり掴みかかられた大蛇はシャーッと牙を剥くと、それを鷲の足に向けた。
「よし、同士討ちだ。これで弱った方を先にやるんだ」
「漁夫の利…ですね」
同士討ちを始めたのを見た胡巫は、銅鼓を打ち鳴らしてそれを止めようとした。
「有為!白貂をあの胡巫に向けろ。銅鼓を邪魔するんだ」
「解りました!」
有為は、口訣を唱えて白貂を動かそうとした。が、途中で止めた。
その必要が無くなったからだ。その時、銅鼓の音は止んでいた。
胡巫の首が、落とされたからだ。
背後から忍び寄ったグンシュビが、迷わず彼の首と胴をざくっと切り離した。
駿は、あまりの残忍な光景に目をそむけた。
眉間に矢が刺さった長胡巫は、致命傷だったが、若輩の胡巫は深手ではあったが、致命的な傷ではなかった。
その胡巫には、堂邑父が止めを刺した。
それを見て駿と有為はいたたまれない気分になった。
彼らは確かに敵であるが、戦士ではない。
力さえ削げれば、殺す必要など無い。むしろ、生かしておいて、後で何かの役に立つようにさせた方がいいかもしれない。
衛青だったら、そうしただろう。
漢軍の将でも、このような仕打ちに出る者もいるが、そのような残忍な将では、兵士は付いてはいかない。
衛青軍の結束が固く、強いのは、偏に彼の度量の大きさが物を言っていた。
駿は、その衛青に戦士として徹底的に叩き込まれた男だ。グンシュビと堂邑父のやり方に、眉をひそめるのは、当然のことであった。
だが、この残忍さこそ、彼ら騎馬民族の強さでもあった。
(こういう連中を、この先相手にするのだ…)
始まったばかりの、匈奴との戦いは、簡単に済むものではないことを、駿は改めて実感した。
制御する者がいなくなった二つの精霊は、徐々に弱っているように見えた。
「良し、有為。まず蛇を狙え!」
「はい!」
白貂は、大蛇の頭にかぶりつき、そのまま飲み込んだ。そこへ、鷲が邪魔に入ろうとしたが、ことごとく鱏に阻まれた。
大蛇を飲み込み終わると、白貂は鷲に襲いかかった。そして、足を掴むと、そのまま二つに裂いた。
裂かれた鷲は、まるで雪が解けるように、すうっと空気の中に消えていった。
使命を果たした有為は、白貂にねぎらいの言葉をかけ、口訣を唱えた。
すると白貂の姿も消え、後には一枚の札が残った。
その札を拾い上げ懐にしまうと、有為は、困ったように溜め息をついた。
「どうした?」
「あの鱏は私の言うことなど、一つも聞かないのです。どうやって消したらいいのか」
「大丈夫さ、まあ、見てろよ」
「え?」
有為は、言われたとおりに鱏を見た。と、鱏は背中に付いたつぶらな瞳をきょろきょろさせ、そのままゆっくりと蒼天に融けて、消えていった。
「何で?」
勝手に消え去った鱏を見て、有為は驚きの声を上げた。
「あれも、白貂も、蓬莱の生き物だろう?」
「ええ、そうです。安期先生からお借りした物ですから」
「あの鱏は、守り神みたいなもんじゃないか?」
「守り神?」
「ずっと白貂を守るように動いていた。守る物が帰ったから、あいつも帰ったんだろう」
「偶然、守っていたのではないのですか?」
「いや、ちゃんと意志があって、動いていたぞ」
「全く気付きませんでした」
その言葉に、駿は苦笑いを浮かべて彼の髪をくしゃくしゃに掻き回した。
「お前、大丈夫かよ!?よくまあ、こんなのを安期先生は選んだもんだ」
「ほっといてください!」
駿に乱された髪をなおしながら、有為はハッとした。
「どうした」
「あれを見て下さい」
有為は、空に浮かぶ雲を指さした。
それは、赤、青、黄、白、黒の五色が光ながら入り乱ていた。こんな奇妙な雲、駿は今まで見たことはなかった。
「太極雲です。何かが、起こっているようです」
「何か?」
「行きましょう」
有為は、雲が流れていく方に向かって走り出した。駿はその後を慌てて追いかけていった。
それは、見てはならぬものだ。
彼――張騫はそう感じた。
五色の光と共に、芳しい香りが辺り一面にふんわりと広がった。
光と香りに包まれ、その方はゆっくりと天から近づいてきた。
神仙の祟りを恐れ、騫は思わず目を閉じ、耳を塞いだ。
騫のことなど、髪の毛一本ほども気に止めず、その方は数人の侍女を従え、天より舞い降りた。
「爾、勝手なことを申すでないぞ。それは、母の持つ、深い慈愛が転じたもの」
彼女は、挨拶もそこそこに、安期生の側に立った。
その方は、九霊太妙亀山金母。西華至妙の気から化生し、西方を治める故に、西王母とも呼ばれていた。
金母という名のとおり、彼女は柔らかな、白金の光に包まれていた。
柔らかな唇は、艶のある紅色で彩られ、微かな笑みが浮かんでいた。見る角度や、その時々の表情で、無垢な童女のようにも、年を経て知恵を蓄えた老女のようにも見えた。
服装や髪型からは、三十前後の夫人である様に見えたが、彼女は化生してより、未来永劫、同じ姿でいる、不変の存在であった。
「さあ、ではこの憎悪を、その慈愛に、変じましょう。東王は?」
「――ここにおりますよ。西王」
と言う言葉と共に、俊風(東の風)が吹いた。
柔らかく舞い降りた西王母とは正反対に、荒々しく、突然の風と共に東公木公は現れた。
その方は東華至真の気から化生し、東方を治める故に東王父と呼ばれていた。
白金に包まれた西王母とは対照的に、東王父は青銅色に包まれて立っていた。そして西王母と同じように、一切の年齢を超越した不変の存在であった。
東王父は日の昇るところを支配する。それは、陰が極まり陽に転ずる場所であった。
対して西王母は、日の沈むところを支配する。それは、陽が極まり陰に転ずる場所であった。
二人は、太極を統べる者。
それ故、玗琪の玉の持つ呪力を転ずる力を持っていた。
彼らは「呪」を「嘉」に、「憎」を「愛」に転ずる事が出来るのである。これらは表裏一体。根本は同じものである。
再び俊風が吹いた。転化が始まったのである。
西王母は、手を伸ばし、自分の住む亀山にある瑶池より水を呼び寄せた。
気は風によって散じ、水によって留まる。
東王父の起こした風により、玗琪の玉に集まった呪力の気は散じ、瑶地の水によって再び集められた。そして、陰陽太極の理念により、「呪」から「嘉」に変じた気は、再び玗琪の玉に注ぎ込まれた。
俊風が吹き、瑶地の水が雨のように注がれるその光景は、この世のものではなかった。神仙界でなければ見られぬ、美しい光景であった。
張騫は、目を閉じ、耳を塞ぎ、それを見なかった。
しかし、二人はそれを見てしまった。
――駿と有為、二人はちょうど転化が絶頂に達した頃、そこに辿り着いた。
二人は、その荘厳な光景を、ただ息を潜めて見守るしかなかった。
発する言葉もなく、ただ、そこで、立ち竦むことしか、出来なかった。
瑶地の水が、玗琪の玉に降り注ぐ中、玉の色は血のような深い赤から、つややかで明るい赤に、ゆっくりと色を変えていった。
そして、それが完全に変色し終わると、雨と風は止んだ。
西王母と東王父は、互いの目を合わせ、微笑んだ。
「後は、そちらの仕事だな」
「はい。解っております」
東王父の言葉に、安期生は深く頷いた。東王父はまた、全ての男仙を統べる者でもあった。
東王父と西王母は、来たときと同じように、すっと、跡形もなくその姿を消した。
安期生は、ツルゲネの胸から玗琪の玉を持ち上げ、その掌に取った。同時に、彼女を乗せていた石の羊は、すっと姿を消した。
彼女の身が地面に落ちる前に、男の両手が彼女を拾い上げた。
彼は、彼女を抱きかかえたまま、張騫の方に歩いていった。彼こそ、仙の姿に戻った修羊公、その人であった。
彼は、麻の衫に白い綿入れを羽織り、頭の両脇の髷が、ちょうど角のように見えた。細面の顔に、小さな顎髭が相まって、確かに修羊公の名のとおり、どこか羊を連想する容貌を持っていた。
「もう、嫁御は大丈夫だ」
修羊公はそう言って、彼女を騫に渡した。
騫は、目を開けると、まだ夢を見ているような気分のまま、彼女を受け取った。
「有為!こちらに来い!」
玗琪の玉を手にした安期生は、有為を呼んだ。有為は慌てて彼の側に駆け寄り、跪いて頭を垂れた。
「一応、首尾良く終わったようだな」
「いえ…わたくしの力では…。第一、先生のお申し付け通り、あの書を十万回読むことが出来ませんでした」
「おや、おかしいな?お前、数え間違いをしていないか?」
「は?」
「お前、寝ても覚めても、あの経文を繰り返していただろうに。かなりの数、抜き忘れているぞ」
そう言うと、安期生は有為の懐から帛書を取りると。そこから絹糸を抜いた。絹糸の束は、風に乗って方々に散っていった。
「足りないのは、あと一回。まあ、それくらいは大目に見よう。今、ここで読むことを許す。読み終われば、お前は正式に蓬莱の門下だ」
「ありがとうございます!」
有為は、恭しく帛書を受け取ると、それを読んだ。――読むと言っても、ほとんどの縦糸を抜き取られたそれを読むわけにはいかず、正確には暗唱したということになるのだが――
最後の一本を抜き取ると、帛書はそのままバラバラになり、風に乗っていった。そして、雪が消えるように、一本一本溶けて消えていった。
ツルゲネを張騫に託した修羊公もやって来ると、有為の顔を見て言った。
「安期先生、彼がその子か?良くこれだけ短い期間に、あれだけの技を教え込めたな」
「まだまだ、あれは猿まねに過ぎませんよ。ちゃんと仕込む(・・・)のはこれからです」
安期生は、有為の顔を見て笑った。
「では行くぞ、これを持ち、五帝の壇に届けるのは弟子のお前の仕事だ」
それから、彼は駿の方を向いた。
「私たちは、これで蓬莱に帰る」
「帰るって…有為は!?」
「私も、蓬莱に行くのです」
「何だって?」
「最初から、そう言う話だったのです」
少し寂しそうに、有為は笑った。
「父と継母に、私のことを、よろしくお伝え下さい。まあ、父は私が安期先生の元にいることを自慢するでしょうし、継母は継母で、自分の息子が正式に跡取りになるのですから、この先も安心して過ごすことが出来るでしょう。
家を出るのが親孝行なのは、私ぐらいですね」
そう言って笑う有為の頭を、駿は思わず小突いた。それから、髪の毛をぐしゃぐしゃに掻き回した。
「馬鹿言うなよ」
駿も、有為も、涙声だった。
「両親とは、永遠の別れかも知れませんが、独生どのとは違うような気がします。いつか、蓬莱にいらして下さい」
「誰が行くか」
「いや、お前は来るさ」
不意に安期生が口を挟んだ。
「俗人が見るはずのない光景をお前は見たのだから、縁があるのだよ。いつか、必ず来ることになる」
「止めてくれよ」
駿は首を振った。それから、安期生の目をしっかりと見据えながら言った。
「俺が身を置くところは、殺戮の繰り広げられる、血生臭い戦いの場だ。あんたたち仙人のいる清浄な世界じゃない。決して行く事なんてない」
その言葉を聞くと、安期生は修羊公と目線を交わして笑った。
「でも、待つのは勝手だろう?お前はお前のいるべき世界に行けばいい」
「ああ、そうするよ」
仙人たちは、大した別れもせず、そのまま、すっと姿を消した。
有為だけは、名残惜しそうに駿の顔を何度も振り返り、そして呟いた。
「きっと、また、私たちは会える、そう思います」
そして、有為も姿を消した。
別れは、案外呆気ないもの。
そう思いながらも、駿は有為の消えた後をずっと見つめていた。
長安を出て、ここまで来る間のことが脳裏に蘇ってきた。あっという間のような気もするし、とても長い旅だったような気もした。
いつも、隣にいてバカを言い合っていた相手が、いなくなってしまった。そのことを、すぐに受けいれることには、無理があった。
「彼らは、一体……?」
事態を飲み込めない騫は、茫然としながら呟いた。
「あいつらは、あんなものさ。関わらない方が、良いんだ」
そう言って駿は振り返り、騫の腕の中にいるツルゲネの様子を見た。
「眠っているだけのようだよ」
騫はそう言いながら、駿の顔を見た。
「兄貴……俺……」
騫の前に跪き、何かを言おうとした駿を、騫は慌てて制した。
「それ以上言うな、解ってる」
「え?」
「ツルゲネから、聞いた。お前から正式に申し入れなくて良いさ。そんなことされたら、俺は、自分がいかに年を取ったか思い知らされてしまう。ごめんだ、そんなこと」
そう言いながら、彼はツルゲネの体を駿に預けた。
「幸せにしてくれよ。こいつを。……願うのは、それだけだ。胡の地で共に暮らしはしたが、今は、何か、妹みたいな感じなんだ」
「兄貴、俺――」
「なんだか、別人のようですな」
堂邑父はそう言って笑った。
「俺もそんな気がする。この格好は、何しろ十年ぶりだ」
髪と髭を整え、駿の持ってきた服に袖を通した騫は照れくさそうに笑った。
「兄貴、痩せた?」
騫の服を整えながら、駿は訊いた。
「まあな。苦労したからな」
そう言って彼は笑った。
「じき、戻るさ。年を考えると、逆に太るかもな」
「じゃあ、そう言っておくよ、兄貴の家に」
この服は、出発前、張騫の家に寄って借りてきたものであった。彼の服は、十年間大事に取ってあった。
「……みんな、変わりはないか」
「十年たったけど、幸い、減ってもないよ。増えてもないけどね」
「そうか……あいつも、まだ、残ってくれてたか」
「嫂さん、子供、育てながら、待ってるよ、帰りを。あいつらもでっかくなったから、きっと、兄貴、会ったらびっくりするぞ」
「そうか。お前もでかくなったな。俺より大きいじゃないか」
「去年の秋、親分の背も超した」
背だけは大きい駿は、照れくさそうに笑った。それから、荷物の中から厳重にくるまれた物を大事そうに取り出した。
「これは、陛下から預かった物です。もし、まだ使命を果たすのであれば、これを使ってください」
騫は駿からそれを受けると、荷を解いて中身を確かめた。
それは、見事な絹織物の数々であった。
「出発したとき持っていった物は、どうせ匈奴に奪われたのでしょう?」
「ああ、有り難い。陛下は、私に何と?」
「月氏に使いするも良し、共に帰国して従軍するも良し。どちらかを望む方を選べと言うことです」
「では、最初の目的を果たしてから、戦に加わると、そう報告してくれ」
「解りました。――俺も、親分も、兄貴がそう言うと思っていた」
駿は、グンシュビが自分の真横で、反物の数々をうらやましそうに覗き込んでいるのに気付いた。
「岑陬、何だよ」
「こんな良い物を持っているなんて、何で言わなかったんだ」
「言ってどうするんだよ!」
そのやりとりを聞いて、張騫は笑いながら反物の一つをグンシュビに渡した。彼は、驚きつつもそれをしっかりと受け取った。
「漢と好を通じれば、こんな物、欲しいだけ手に入る。烏孫王孫よ、解っているか?」
「ああ……」
騫は、反物をもう一つ、彼に渡した。
「頼みたいことが二つある。これで聞いてくれるか?」
「喜んで」
グンシュビは手にした上等の反物を返す返す確かめながら、深く頷いた。
「一つは、私たちを月氏まで送り届けて欲しい。もう一つは、駿の馬を、お前の駿馬と取り替えて欲しい」
「どちらも簡単なことだな。その程度で良いのか」
月氏と烏孫の間には、大宛(フェルガナ)・康居(サマルカンド)というオアシス国家があり、烏孫とこれらの国家の関係は良好であった。これらオアシス国家を抜けて月氏まで行くことは、そんなに難しいことではなかった。
「それが大事なんだよ」
そう言って騫は笑った。
「私は無駄な時間を使いすぎた。一刻でも早く、陛下の命を成し遂げたいのだ。それに駿も、早急に復命しなくてはならない。烏孫の助力は有り難いのだ」
「こちらも、漢は魅力的な国だ。好を通じることが出来れば、それに越したことはない」
「交渉成立だな」
駿は、グンシュビの馬と自分のを交換すると、慌てたように荷造りを始めた。
「急ぐのか?」
グンシュビは駿に訊いた。
「ああ、出来れば、今日中に発つ」
「もう昼過ぎだぞ。今からでは、そう遠くまでは行けまい」
空を見上げ、太陽の位置を確かめながら、グンシュビは言った。
「そんな暢気にしてられないのさ」
三胡巫は皆、首を刎ねられ、胴体と共に野ざらしにされている。胡巫の援軍が、その死体を発見するのは時間の問題だ。
彼らが追っていたのは、張騫の妻だし、張騫も休屠王のところから逃げ出している。
三胡巫の死に、張騫と漢が絡んでいると言うことは、誰しも考えるであろう。
彼らが復讐に出る前に、漢の防備を固めなくてはならない。駿は、一刻も早くそのことを漢軍に伝えなくてはならなかった。
「ま、一人だからな、日に夜に継いでいくつもりだよ。それに、あんたの馬は速いから、今からだって、結構、先に行けるさ」
「――一人なのか?」
「一人だよ……もう、有為は仙人とどっかに行っちまったしな」
そう言いながら、駿はツルゲネの方を見た。
彼女は目は覚めたものの、まだ、ぼんやりと座り込んでいた。
「どうして、私を置いていくのだ!」
駿が単騎、出発すると聞き、当然のことながらツルゲネは怒り、彼に詰め寄った。
「ツルゲネ」
それを張騫は静かに制した。
「お前は、私たちと一緒に行った方が良い。その方が……」
「結局は、駿とのことを許してくれないのか!?」
彼女は、今度は騫の方に詰め寄った。
「違う、そうじゃない。彼には大事な使命があるのだ」
「だからって、私が一緒に行ってはいけない理由にはならない」
駿は、慌てて二人の間に立った。
「俺が、兄貴に頼んだんだ。兄貴たちと一緒に行ってくれって」
「駿!?」
「ちょっと来い!」
駿は彼女の手を引いて、皆とは少し離れた場所へ連れて行った。
「悪いと思ってる、だけど……」
「私を見捨てるんだな」
「違うって」
どうしても話が合わないことに、痺れを切らした駿は、思わず彼女を抱きしめた。
「頼むから、落ち着いて、俺の話を聞いてくれ」
駿は、体を離すと、彼女の目をじっと見つめた。光に当たると、微妙に色を変える彼女の瞳は、不思議な宝石のようだった。
「俺は、急いで漢に戻らなきゃならない。戦が始まりそうな雲行きなんだ。それを一刻も早く、伝えなければならない」
「私は有為とは違う。彼よりずっと速く走れる。足手纏いにはならない」
駿は困ったように首を振った。
「だが、敵が来たらどうする?俺一人じゃ、守りきれないかもしれない。兄貴たちと行けば、守ってくれる男が三人もいるし、烏孫の領内に入れば、そうそう襲われる心配もなくなるはずだ。それにここからだと、漢より烏孫の方が、ずっと行きやすい」
「お前は、私を守ってくれるのだろう?今まで、ずっと守ってくれた。これからだって、守ってくれるのだろう?」
「そのつもりだよ、だから」
必至に食い下がる彼女を、どう説き伏せればいいのか、駿は途方に暮れた。そして深呼吸を何度も繰り返した。
それから駿は、自分の肩に掛かっていた巾をほどくと、彼女の肩にかけた。
「これぐらいしか、やれる物なくって悪いんだけどさ……」
照れ笑いを浮かべながら、彼は言葉を続けた。
「俺、あんたが強くて、弱いのを知っている。あんたの弱いところは、必ず俺が守る。だから、あんたの強いところに、頼って良いか?」
「どういう事だ」
「必ず、兄貴を漢に連れ帰って欲しい。
岑陬はあんな性格だから、信用できないし、堂邑のおっちゃんは、一回裏切っている。俺が一番信じられるのは、ツルゲネ、あんたなんだよ」
初めて自分の名前を呼ばれた事に気付いた彼女は、少し頬を染めた。
「約束しただろう?海棠の花の下で、待ってるって。待ってるから、必ず兄貴を連れて、漢に、長安に来てくれ」
「だが、月氏は遠い。一年では帰ってこられないかも知れない」
「何年でも待つよ。絶対。二年でも、三年でも、十年だって、二十年だって、あんたが来るまで、ずっと待つよ」
「本当だな」
「本当だよ。海棠の花の下で、また会おう。そうしたら、ずっと側にいる。側にいて、ずっと守るから……」
「ずっと、一緒なんだな」
「ああ、約束する。それまで、こんなので悪いけど、俺の分身だと思って、これで我慢してくれよ」
彼女の肩にかけた巾の形を整えると、もう一度彼は、彼女をぎゅっと抱きしめた。
遠くで、二人の様子をじっと見守っていた騫は、それを見て思わずふっと笑った。
「どうしたのです」
「いや、何、娘なんだな、と」
堂邑父の問いかけに、彼は手を軽く左右に振って答えた。
「あいつに会って、十年近くになるが、年頃の娘だって実感したのは初めてだよ」
彼の言葉に、堂邑父は不思議そうな顔をした。
「こうなったら、何が何でも、あいつを漢まで連れてかないとな。命に替えても」
「団長は、死ななくて結構。まず命を差し出すのは、自分ですよ」
そう言って、堂邑父は騫の肩を叩いた。
「そうさせてくださいよ。出なければ、償いきれませんから」
今日の空は、とても高く感じた。白い雲が、ゆっくりと横切っていく。
その光景は、先程までの争乱が夢ではないかと感じさせるほど、長閑(のどか)であった。
間もなく、駿は東に向かい、ただ一人で旅立っていった。
ツルゲネは、彼から貰った巾(えりかけ)をぎゅっと握りしめ、見えなくなるまでその姿を見送っていった。
「すっかり遅くなってしまって、悪かったな」
後ろの彼女を気にし、済まなそうに騫は言った。
「仕方ない。それにもともと、花の盛りに会う約束だったんだ」
「だが、その花も盛りが過ぎて、散り始めてしまった。本当に申し訳ない」
「気にするな。どうせ、お前たちはお国が大事なんだ。騫も、駿も、勅命第一だろう?私がじたばたしたって、どうにもならん」
駿と別れ、気がつけば三年近くが経ってしまった。
匈奴を抜け、烏孫から月氏に行くまでは順調だった。ただ、訪れた国々で、それなりの期間を滞在したため、月氏を出る時点で既に一年以上が経ってしまった。
月氏は、大夏(アフガニスタン東部)を支配下に治め、南方のインド文化、西方のヘレニズム文化に触れ、遙かに離れた東部への関心は薄れていた。
それ故、張騫の当初の目的である、漢との同盟を結ぶという使命は、果たされぬままに終わった。
しかし、月氏に変わり、烏孫との同盟を取り付け、当時、華夏に知られていなかった地についての詳しい情報を持ち帰った彼は、当初よりも遙かに大きな使命を成し遂げたと言ってもいいであろう。
月氏から漢に戻るのも、途中までは順調であった。
しかし、秋口に入り、匈奴と漢との戦闘が始まるとの情報を受け、彼らは河西回廊を避け、青海(チベット方面)より漢に戻るルートを取った。
しかし、青海に駐留していた匈奴軍に見つかり、彼らは再び囚われの身となってしまった。
一年近く拘留生活を送っていたが、期せずして単于が亡くなり、匈奴軍は一時混乱に陥った。その隙をついて、彼らは烏孫に救援を頼み、グンシュビが送った間者によって、やっと脱け出すことが出来たのだ。
張騫とツルゲネ、そして堂邑父が長安に戻った時には、休屠王の幕営を抜け出してから、二年半以上の月日が流れていた。
その間に、漢軍と匈奴は、激しい戦闘を繰り返していた。
帰国した時もまた、匈奴軍との戦闘のただ中にあり、騫は休む間もなく、漢軍のために奔走することになった。
ツルゲネは、騫の家で、彼の正妻や子供たちと共に戦の終結を待つことになった。
彼女は、騫の胡妻というより、駿の許婚者として扱われ、待っている間、漢の風習や礼儀作法を正妻から教わっていた。
「あの子は、こんな事、頓着しない子だけどね、何しろ、皇太子の姻戚に繋がっちゃうんでね、あんたはしっかり覚えなさいな。こういう事は、女がしっかりしないとね」
騫の正妻は、事あるごとにそう言って彼女に発破をかけた。
十年以上も夫の帰りを待ち、女手一つで子供たちを育てただけの人である。芯の強く、気っ風の良い女丈夫で、ツルゲネはすぐに彼女とうち解けることが出来た。
幼い頃から駿のこともよく知っていたので、彼女のする昔話が、沈みがちだった彼女の気分を紛らわせた。
長安に来て半年、別れて以来、一番駿の近くにいるはずなのに、彼のことは、風の噂にすら聞くこともなかった。
騫ですら滅多に姿を見せないような状況であったので、仕方のないことだと、彼女は毎日のように言い聞かせていた。
戦が終わり、全ての雑事が片付き、やっと衛青の屋敷に行けるとなった頃にはもう、海棠の花も終わりに近い時分になっていた。
「ほら、あそこが仲卿の家だ」
そう言って騫が指さした先を、ハッとするように彼女は見た。
荘厳な門構えの向こうから、立派な海棠の花が揺れて散っていくのが見えた。
あの木の下に、駿が待っている。
本当に、そうだろうか?
彼女は急に不安に駆られた。
同時に、嫌な噂が耳に蘇った。
三胡巫が殺され、玗琪の玉が奪われた後、案の定、匈奴は漢に復讐戦を仕掛けてきた。
それは、壮絶な戦いであった。
その戦で、有能な若い将校が、数多く命を落としたという。
もし、その死者の列に、駿が加わっていたら?
半年間、彼からの音沙汰が全くない不自然さが、それで説明が付いてしまう。
彼女は、その思いを否定しようと、彼から貰った巾(えりかけ)をぎゅっと握りしめた。
そして、僅かに残った彼の汗の臭いを嗅いだ。
寂しいとき、不安なとき、いつもそうしていた。彼が、すぐ側にいてくれるように思えた。
「ツルゲネ?」
彼女の様子に気付いた騫が、声を掛けた。彼女は慌てて笑みをつくろった。
「何でもない、行こう」
風に飛ばされて、衛家の海棠の花びらが飛んできた。薄紅の綺麗な花びら。
(約束したんだから、きっと、待ってる)
駿は、約束を破るような人間じゃない。
どんなに傷ついていても、たとえ、死んで幽鬼となっていても、あの木の下で、ずっと自分を待っているはずだ。
そして、どんなに姿が醜く変わり果てていようとも、幽鬼となっていようとも、自分は変わらず彼を愛し続ける。
ずっと、側にいる。
「私たちは、離れない、もう」
そう言って、彼女は風に飛ばされた花びらを掌の乗せた。そして、そっとそれを握りしめた。
先に門を潜った張騫が、知己に出会って感嘆の声を上げているのが耳に入ってきた。彼女は何度も深呼吸を繰り返すと、微笑みながら、彼の後に続いた。
了

この記事を「良い」と思っていただけたら、スキやシェア、サポートお願いします。 皆さまから頂戴したサポートは、今後の活動の励みとさせていただきます🙇
