ヒクイドリの賞味期限
これは「十人十色Adventar」6日目の記事です。5日目の記事はこちら。
酷く疲れていた。実験棟で工事が行われていて、私が実験を開始できるのは業者が撤退した18:00からのことだった。普段は時間がかかる実験操作ではないのだが、複数の培養株で産卵が起こっていて、卵の観察に時間がかかってしまった。研究が進展するのは嬉しいことだが、なぜ今日なのか。怠けていて成果を出せずに12月を迎えてしまった罰なのか。研究対象への愛と卒業への執着で何とか実験を成し遂げた。気づけば日付が変わろうといていた。
終電にギリギリ乗り込み、帰路に就いた。ガラガラに空いている電車内ではやつれたサラリーマンが2席を占領して熟睡している。スローテンポで変拍子のいびきが車内に響く。気が向いたら睡眠外来を勧めておこう。私は音楽を聴く余裕もなく、ただただ、疲れに任せて、目を瞑っていた。眠らないように。寝過ごさないように。

『ようこそ!夢の世界へ!』
突然、目の前にスーツ姿の男が現れた。十数秒の混乱の後、すぐに夢だと理解した。この男もそんなことを言っていた。夢を見ているということは、電車内で眠ってしまったということだ。起きようと努力したが、早々に諦めた。夢とはそういうものなのだ。ならば、この夢に身を任せてみようではないか。不思議とそう思った。
「夢の世界?ずいぶん安直な名前じゃないか。」
男に問いかけてみたが、答えは無かった。ポーズが変わることはなく、仮面のように不気味な笑顔が張り付いていた。彼はただひたすらに案内役であり、その役目は既に終えているのだ。
辺りを見渡してみると、私が今立っているのは目指していた最寄り駅のロータリーであった。しかし、彩度が失われたモノクロの世界だった。スーツの男は、いつも予備校のスタッフが消しゴムと蛍光ペン付きのチラシを配っている場所で私を待っていた。先ほどまで鮮やかだった男も色を失い、街並みと同化していた。
歩いて探検してみることにした。クリスマスムードに染まりつつある慣れ親しんだ街並みだが、ヒトや動物の姿は一切ない。鬱憤が溜まっているからか、清々しく感じた。妙に圧迫感があると思ったら、透明なガラスは白と灰の市松模様となっていて、その先を見透すことができないからであった。
「透過素材の背景かよ」
呟いてみたが、誰からも反応がない。ツイッターなら67いいねくらい貰えそうだが、スマートフォンの画面も暗黒を貫いている。ふと、道の先に色づいた建物があるのに気が付いた。あれはホテルだろうか。

シナリオに従うようにそこへ向かうと、それはペットホテルであった。このあたりでペットを連れて散歩をしている人が多いのは、これがあるからだったのか。いや待て。夢の中で新たな学びを得ることなんてできるのか。そんなことを考えながら、ペットホテルの中に入ってみることにした。
『こんばんは!そちらのペットのお預かりですか?』
「ペット?私は何も飼っていませんが──」
おもむろに受付の女性の視線の先を確認した。
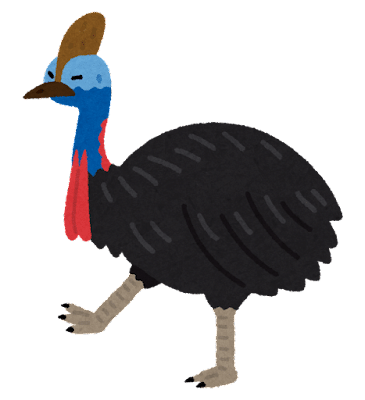
大きな黒い塊。そして鮮やかに色づいた顔。図鑑で見たことがある。ヒクイドリだ。そう理解した瞬間、恐怖で体が固まってしまった。聞いた話によると、ヒクイドリは世界で1番危険な鳥らしい。しかし、表情は穏やかで、どうやら興奮しているわけではなさそうだ。今のうちにそっと離れるのがベストだろう。1歩、また1歩と後ずさる。
ふと、自分が手に何かを持っているのに気付いた。リードだ。リードの先はヒクイドリに繋がっている。ヒクイドリはネコがつけるような鈴付きの首輪をしている。「ヒクイドリはそうやって飼わないだろ」と心の中でツッコミを入れていると、途端、私の脳内に幼少期からの記憶が流れた。
そうだ。私は幼い頃からヒクイドリと一緒に育ってきたのではないか。この子の名前はヒクイー。私は発想力に乏しい子供だった。ヒクイーとは寝るときも、食事の時も一緒だった。友人と喧嘩をして落ち込んでいたときは慰めてくれた。一人っ子の私にとって、兄弟のような存在だった。
実家の両親が旅行に出かけてしまい、私も研究が忙しくて世話ができないのでペットホテルに預けに来たのだ。しばらく会えない寂しさを紛らわすために優しくハグをして、ホテルを後にした。モノクロの街並みに歩み出るが、振り返ることはしなかった。ペットホテルも、ヒクイーも、モノクロになっている気がしたから。
この夢はいつまで続くのだろう。多少の疲労を覚えながらあてもなく彷徨っていると、突然目の前に3色の四字熟語が現れた。

「使用期限」「賞味期限」「消費期限」。なんだこれは。浮いている。現実から逸脱し過ぎている。クイズの選択肢か。こんなことがあり得ていいのか。狼狽えていると、どこからともなく声が響き渡った。
『問題!この3つの中で、守らなくてもよいものはどれでしょう!』
正解がない問題ではないか。どれも守ったほうがよいに決まっている。そもそも正解すると、はたまた不正解になると、どうなるのだ。何もわからない。ただ、回答しなければならない。そうでなくては次に進めない。私は少し迷った末に、賞味期限を選ぼうと思い至った。他の2つは命にかかわると考えたからだ。
「私の回答は、賞味期──」
『キィーーーーーーー!!!』
電車のブレーキの音だった。気づけば最寄り駅に差し掛かったところだった。運よく目的地で起きることができた。これが外国人が驚く日本人の能力というヤツであろうか。面白い夢だったなと感心しつつ、疲れの溜まった体を何とか起こし、私は家に帰った。何も食べず、そのままベッドに倒れ込み、泥のように眠った。
翌朝、シャワーを浴び、簡単な朝食を済ませ、身支度をし、いつものように大学に向かう。駅まで歩いている途中で、青い服を着た少年が、重そうなランドセルを、真っ赤な顔で運んでいるのを見かけた。

私の頃よりも学習する内容が増えたから大変な思いをしているのだろうか、教科書の電子化を進めるべきだ、などと思いながら、気の向くままに、その子のランドセルを道すがら運んであげることにした。ランドセルは本当に重く、少年の前で余裕の顔を保つのが大変だった。
『おじちゃん、ありがとう!』
まだ大学生だぞと言い返そうとしたが、腕の筋肉が悲鳴を上げていてそれどころではなかった。軽く手を振り少年と別れ、駅へと向かった。
少年は私の背後でモノクロへ変わった。
この記事については以下の記事をご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
