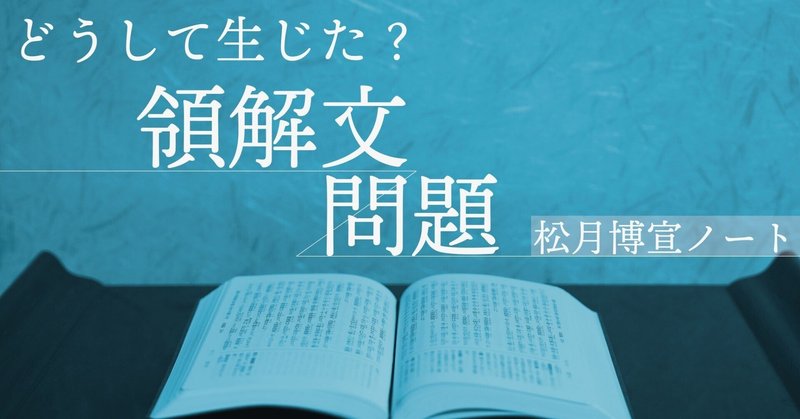
どうして生じた?領解文問題 vol.15
松月博宣ノート
例証編⑰悲痛な声
今回の領解文問題は、その制定の経緯に疑義があるという点と、その内容に多くの真宗門徒の理解が得られないという点があります。ご門徒に読んでもらうことで理解してもらおうと「解説文」を、消息同意の条件として勧学寮が出されたものを読んでも、ますます分からなくなるという奇妙なループに陥ります。
制定の経緯については、「手続きに瑕疵はない」という木で鼻を括ったような説明で終始しています。「こうこう、このように制定したのだから瑕疵はない。これについてはこのような資料や議事録があります。」の説明が未だなされていない状態だから混乱が続いていることに気づいてもらいたいものです。このまま突っ張り続けておれば宗門内は諦めるだろうと鷹を括っていては宗教団体とは言えないと思うのです。それはタチの悪い政治家と同じ事。
そもそも勧学寮の議事録の開示を求められた時、それをキチンと開示なさっておれば手続きに問題がないことの証明になる筈なのに、何故、開示を拒否されているのか?私には理解できません。開示があれば大方の宗門人は納得はしないだろうけど理解は出来ると思うのにです。しかし開示を頑なに拒否しているということは開示できない理由が他にあると考えるしか筋は通りません。これは最早あの「新しい領解文」は石上さん作である事を、総局と勧学寮が共同して覆い隠していると言わざるを得ません。
先日、「新しい領解文を考える会」福岡・北豊LINEグループ有志が主催する第1回学習会を開催しました。夕刻からの開催にも関わらず80名を超える方が、そもそも「領解文とは何か?」について研鑽をいたしました。参加者の年齢層は20代から40代が主流で若い方が今回の領解文問題は他人事ではないという問題意識をもっておられる事に宗門の未来への希望を見ました。
講義を終え質疑の時間を設けたのですが、ご参加くださった1人のお同行が
私はご縁あって浄土真宗の教えを聞くようになったのですが、最初は領解文からでした。領解文を学んでいく事で浄土真宗のご法義がやがて私の血肉になってきました。ところがこの度「新しい領解文」を暗記せよ唱和せよと言われることは、私の身体を変えろと迫られているようで辛い思いをしています。『領解文』は古語が使われ分かりにくいから、新しく変えたと聞きますが、決して分かりにくくはないと思います。学べば学ぶほどこれ程新しいものはないといます。今までの領解文のどこがおかしいのでしょう。いっときも早く元の領解文に戻してもらいたい
と訴えられました。また他の僧侶の方は
お得度で受式者に新しい「領解文」を暗唱してこいと知らせがあった。子どもが得度を希望しているが、心にもないものを暗唱し唱えろと言われるほど辛いものはないと思う。得度をいただくためには一応覚えなくてはいけないだろうが、本人の心は違うからやり切れない。この心をどう始末つけたらいいのでしょうか
この二つの訴えというか質問はこの度の領解文を問題とする本質的なものだと思います。そこにいる者、誰も的確な回答を持ち合わせておりませんでした。これらの問いに答えなければならないのは「新しい「領解文」についての消息」を書いた石上さん、あなたです。おそらく「ご門主が決められたことだから」と答えると思いますが、嘘を付いてはなりません。
『宗教的人格権』を脅かす宗務の方針だと指摘したことがありますが、これはまさにそれに当たることなのです。事は手続きとかの問題以前のこと。このような問いに真摯に答えてこそ同朋教団のあるべき姿勢であるにも関わらず、権威を傘に着て高圧的・強権的に命令すようなことではありません。1人のお同行を大切にできない宗門が社会的責任など負えるものではありません。もっと足元を見つめ、向き合い真摯に対応してもらいたい。護るものを履き違えた石上さんの姿が今の本願寺派と思うとやり切れないものがあります。
例証編⑱宗意安心はどこへ
『新しい「領解文」(浄土真宗のみ教え)についての消息」発布、その後の唱和推進に関わった全ての方の、あまりにも『領解文』を安易に考えている状況に複雑な思いでおります。それは宗意安心に対する安易さに通じるということを『領解文』を改めて学ぶ中に気付かさせてもらっています。
「現代版領解文」を制作しようと発案した時点で「領解文の持つ意味」を緻密に精査した形跡がなく、「『領解文』の理解における平易さという面が、徐々に希薄になってきたことも否め」ないから現代人に分かりやすいものを作ったらいいと言う発想。この「理解における平易さ」(消息)と言う表現もいかがなもなかとは思います。
それでも何とか「現代版領解文」を作ろうと「宗門の叡智」を結集して作成した「浄土真宗救いのよろこび」を、無量寿経に説かれる他力の救いの世界観(法蔵菩薩従果降因)を、世間知に長けるがゆえ理解出来ない1人の総長が「自見の覚悟」で作成した、ご親教「浄土真宗のみ教え」を、何の企みか何としてでも「現代版領解文」に据え変えたい意図をもって「拝読浄土真宗のみ教え」改訂委員会を設置規則も作らず開催し、最終的には掲載する内容の判断を「総局一任」とするようし向け、結果として「浄土真宗救いのよろこび」を「出処が明らかでない」と理由にもならない理由付けで削除させ、自分が書いた「私たちのちかい」などを掲載させた。その後「救いのよろこび」が掲載されている旧版全部の廃棄を命じ、ご門徒からの浄財の無駄遣いをさせています。それを命じられ廃棄処分の作業をせざるを得なかった職員は後に「あれほど虚しい仕事はなかった」と述懐していたと聞きます。
満を持してご親教で「浄土真宗のみ教え」をご門主に語らせ、これを以て「現代版領解文」はすでにご門主によって語られたと既成事実化した上で、「現代版領解文制定方法検討委員会」という訳のわからない委員会を設置し、宗門の最高位の学僧方をスケープゴートに使い、領解文の意味を熟知されているからこそ「領解文という文言は混乱を招く恐れがある」「領解文の本質から言って、新たに制定する事は不可能」などの意見を全く無視した上で「ご門主に制定いただくほかはない」と結論に向かわせたのです。これに加担したのは前総長のみならず新総長も所管総務としてその委員会をリードしていた事を忘れてはなりません。
形としてはご門主から「消息」の諮問を受けた勧学寮員方は、あれほど混乱を招くからと注意喚起した「領解文」という言葉が使われ、取ってつけたような「師徳段」が入れられただけのものであったので、「驚天動地、開いた口が塞がらない」(寮頭曰く)状態であったと聞きます。しかし寮員方はご門主を護ろうと、真宗義とは異なるものであると分かっておりながら何とか会通(相反する説示を、矛盾するものではないと明らかにすること)しようと「解説文」を書き、これを読むことで「新しい「領解文」」を誤解しないようにしてもらおうとしたにも関わらず、かえって「新しい領解文」自体に問題がある事を鮮明にしただけではなく、門主が書いたものとする事で、ご門主の名を未来にわたって傷付けることに加担した形になってしまいました。
ここで知っておきたい事は、「ご親教」にしても「ご消息」にしても、一応ご門主の手になるものと形式上なってはいますが、門主無答責の原則によってご門主の出されるものは「総局」の申達に依ることになっている事です。前総長はこの無答責を利用して、自分の考えが間違いないものと過信し、教学者に相談する事なく数々の親教と消息に関わり続けていたのです。
前総長は「龍大が嫌い」「宗学が嫌い」「ご法義地が嫌い」と身近な方に公言していたようです。それら全てに当てはまる教学者に、ご親教やご消息を自分で書いてご門主に語らせる直前に一応見せていたようです。その教学者が「これは、ちょっと不味いですよ」と言っても、前総長は「これで行くから」と、忠告を一顧だにせず突き進めていたのが真相のようです。
表面上(形式上)は綺麗に整っていると見えるようにはしてはいるが、実情は全く違うという事はよくある事。この度の「新しい「領解文」(浄土真宗のみ教え)についての消息」発布も同じことが当てはまります。このご消息を書いて門主名で発布させた石上氏の真宗理解に過誤がある事は言うに及びませんが、「新しい領解文」について宗意安心に誤解を生じさせる恐れがあるから取り下げを、と訴えている勧学・司教有志の会の声に対して、今の勧学寮は沈黙をしたままというのも理解に苦しみます。
またご門主も龍大大学院で真宗学を学んでおられるのだから、「この内容でご消息発布を」と申達された時、違和感なく読まれたという事はあり得ないと思います。それを何故追認されてしまったのか。たとえ総局のすることに門主として関わる事ができない仕組みであるとはいえ、また色々とお世話になった伯父にあたる前総長とはいえ、事は宗意安心のことですから前総長の真宗理解に対しての裁断をして欲しかったと思うのは私だけでしょうか。
また勧学寮で消息発布に必要な寮員全員の同意があったのか自体も疑われますし、もしあったとしてもその形式が妥当なものであったのかも明らかではありません。それは勧学寮から明らかにしてもらうしかないように思います。
石上前総長さまへ
「手続の正当性」がそのまま「内容の正当性」とは言えないのです。石上氏は職を辞しても尚、発布手続きの正当性をあちこちで喧伝されている。「総長退任とお礼の挨拶」という文書が東京教区内の全僧侶に送られてきたよと、東京教区の友人がFAX送信してくれました。
「世代交代と人心の一新を図る時と判断したことと、主治医から暫く安静が必要との診断を受けたこと」が辞任の理由と述べ、「8年9ヶ月の間、重積を担えたのは皆様の変わらぬお支えがあったればこそ。ここに幾重にも頭をたれ衷心より厚く御礼」、後任には池田行信氏が選任され「前総局の方針を継承し宗門の発展・法義繁盛」と決意している旨が書かれていました。
これで必要十分なご挨拶だと思いますが、石上氏の真骨頂は「追伸」の部分で発揮されていました。そこには、
「新しい領解文(浄土真宗のみ教え)についての消息」に関し、主要な事実につきご報告を申し上げるため
とし、自らがお書きになられた「総局見解」と「浅田勧学寮頭への、新しい「領解文」にかかる対応について(お願い)」、そして「第322回臨時宗会における小職の「総長挨拶」全文」を『以上関連する3点の資料を同封した。暇な折などにご高覧を賜れば有難き幸せ』と。わざわざ「新しい「領解文」に関し『主要な事実につき』関連文書を同封」と書き、事実を明らかにする為のものとして自分の書いた3点セットを同封されています。
うーん、石上氏ご本人の中では整合性が付いているのだろうが、これほど整合性のない文章はないなぁの印象。
消息に深く関与し、手続きにも数々の疑念をもたれているのは石上氏。消息に全く関与せず、また本当に手続きに全くおかしな所がないのなら、その間の事を証明する議事録なりの記録が必ず存在するはず。それを開示し、且つ勧学寮員など第三者の証言を得られてこそ「手続きの正当性」ははじめて担保されると思います。
しかし「事実について」の報告すると掲げたのが自分で書いた文書。これでは「私が言ってきたことに間違いはありません。これを信じてください。他の方々が言う事は嘘です」という事になります。果たして東京教区内の僧侶の皆さまはこれをまともに受け取っていらっしゃるのだろうか?件の住職は「暇がないから、読まない!」、、、、、。と言ってましたが。
浅田寮頭へのお願い文書は確かにあるけど、浅田寮頭の返事がどうであったのか?寮頭から「寮頭と言えども指導する立場にはない」と対処する事を拒否された事は何処にも書かれてはいません。
総局見解にしても、ご自分の見解をただ羅列したもの。辞職挨拶にしても一方的に有志の会やSNS上で新領解文批判をする方々を「宗門の秩序」を乱す行為と批判するだけのもの。
そこには何故批判されるのかの自己凝視が欠損しているように思えるのです。また「手続きへの疑問」と「内容への疑問」は別な事。それを「手続きの正当性」を言うことで「内容も間違ってはいない」と主張されているようです。しかし手続きの正当性を主張されればされるほど、内容の不当性を覆い隠している感が否めないのです。
まず「内容に問題」がある事が大前提、宗意安心に誤解を生じさせるようなものであるから、それを問題にし、このような文章は何故門主の名で発布されたのか?そこを問うているのに、問題のすり替えをなさっています。
今朝の朝日新聞全国版には大々的に「聖典現代版をめぐり『お家騒動』」と書かれています。その騒動を引き起こしたのは「これひとえに」石上さんが書き、ご門主に発布させられた「新しい領解文」にある事を、私たちと同じ阿弥陀さまのお慈悲の中にいる同行のひとりとして立ち返られお考えいただきたいものです。
例証編⑲唱和一色
今の本願寺派は「唱和一色」に染まっています。何故このような景色に変えられてしまったのかを考えてみたいと思います。それには、あらためてご親教やご消息の中身を点検する必要があります。
先のご消息に
念仏者として領解すべきことを正しく、わかりやすい言葉で表現し、またこれを拝読、唱和することでご法義の肝要が正確に伝わるような、いわゆる現代版の「領解文」というべきものが必要になってきます。そこでこのたび、「浄土真宗のみ教え」に師徳への感謝の念を加え、ここに新しい「領解文」(浄土真宗のみ教え)として示します。
とし、最後の部分に
この新しい「領解文」(浄土真宗のみ教え)を僧俗を問わず多くの方々に、さまざまな機会で拝読、唱和いただき、み教えの肝要が広く、また次の世代に確実に伝わることを切に願っております。
とあります。この中で「さまざまな機会で拝読、唱和いただき」と書き込まれている事が、宗務の基本方針の「唱和推進」の根拠となっています。前総局も現総局もこの一点を金科玉条とし、この「新しい領解文」の唱和推進をしていくことが門主の心に沿うことだと言っています。確かに唱和という行為は「一つのテキストを口にし続ける事で、それが身体化する」という善きにつけても悪しきにつけても効果があることは否定しません。
かつてのオウム真理教信者が「修行するぞ、修行するぞ、徹底的に修行するぞ」「解脱するぞ、解脱するぞ、徹底的に解脱するぞ」と麻原彰晃の掛け声に合わせて唱和し続けることがありました。あるいはマルチ商法の顧客拡大をする営業マンが目標額を大声で連呼し成績達成に向けて社員を鼓舞するなど、唱和する事で自己暗示もしくは集団催眠状態に陥いっていく姿を私たちは知っています。
それと同一視することに違和感を覚える方もあるかと思いますが、唱和という行為にはそういった面がある事は否めません。ですからあらゆる場面で利用されてきたのです。翻って今の本願寺派を見ると「唱和一色」に染まっています。一歩間違えば人を操り不幸にしてしまう恐れのある「唱和」に何故ここまで拘るのか、その根拠を先ずは「ご親教3部作」に見ていきます。
ご親教「念仏者の生き方」の中で
私たちは阿弥陀如来のご本願を聞かせていただくことで、自分本位にしか生きられない無明の存在であることに気づかされ、できる限り身を慎み、言葉を慎んで、少しずつでも煩悩を克服する生き方へとつくり変えられていくのです。それは例えば、自分自身のあり方としては、欲を少なくして足ることを知る「少欲知足」であり、他者に対しては、穏やかな顔と優しい言葉で接する「和顔愛語」という生き方です。
と、念仏申す者は「変わっていくのだ」と語り、続いて
たとえ、それらが仏さまの真似事といわれようとも、ありのままの真実に教え導かれて、そのように志して生きる人間に育てられるのです。
(中略)
仏法を依りどころとして生きていくことで、私たちは他者の喜びを自らの喜びとし、他者の苦しみを自らの苦しみとするなど、少しでも仏さまのお心にかなう生き方を目指し、精一杯努力させていただく人間になるのです。
と、阿弥陀仏の救いに預かった者は、こういう「生き方」になっていける(はず)ことを教えているのが浄土真宗だと規定したものとなっています。
つまり浄土真宗本願寺派はこれから「生き方」を前面に打ち出していきますという宣言が、このご親教「念仏者の生き方」でなされています。このご親教を基に「浄土真宗的生き方」を具体的に示したのが「私たちのちかい」です。その一節に
この「私たちのちかい」は、特に若い人の宗教離れが盛んに言われております今日、中学生や高校生、大学生をはじめとして、これまで仏教や浄土真宗のみ教えにあまり親しみのなかった方々にも、さまざまな機会で唱和していただきたいと思っております。
と、ここに示される「生き方」を「唱和」する事で、信者に「理想的な念仏者となっていこう」との思いを抱かせようと目論見、その次のご親教「浄土真宗のみ教え」の中では
聖人が御誕生され、浄土真宗のみ教えを私たちに説き示してくださったことに感謝して、この「浄土真宗のみ教え」を共に唱和し、共につとめ、み教えが広く伝わるようお念仏申す人生を歩ませていただきましょう。
と、「教え」を「唱和」させる事で信者にそれを植え付けていこうとの目論見。そして最後の部分では重ねて
なお、2018(平成30)年の秋の法要(全国門徒総追悼法要)の親教において述べました「私たちのちかい」は、中学生や高校生、大学生をはじめとして、これまで仏教や浄土真宗にあまり親しみのなかった方々にも、さまざまな機会で引き続き唱和していただき、み教えにつながっていくご縁にしていただきたいと願っております。
と、未信の者や若い世代、はたまた、今までの信者も、まともに教えを聞かず、生き方も出来ていない者であるから、これらを「唱和」させることで「教え」と「生き方」を身に付けさせようとの意思を見ることができます。
例証編⑳教学の組み替え
先に今までのご親教とご消息を読み解くと、未信の者や若い世代、はたまた、今までの信者も、まともに教えを聞かず、生き方も出来ていない者であるから、これらを「唱和」させることで「教え」と「生き方」を身に付けさせ「しっかりとした信者に育てよう」との意思を見ることができるとしました。
万歩譲って、そのような考え方もあるとは思います。それは昨今の教線の衰退を鑑みるとき、それを打破するには「伝え方」を大きく変えていく必要があると思っているからです。だからと言って「教え」の解釈を曲げてまでとは思いません。
「浄土真宗的生き方」については、前々ご門主によって『浄土真宗の生活信条』が私たちの生活上の努力目標(規範)として示されています。また「浄土真宗の教え」については、前ご門主によって2008年4月の立教開宗記念法要ご満座のご親教であらためて示されています。(以下、当時門主の光真前門さまのご親教)
宗祖親鸞聖人の御誕生800年・立教開宗750年を控えた1967(昭和42)年4月、当時の宗門を憂えられた大谷光照門主が「浄土真宗の教章」を定められ、親鸞聖人の流れをくむものとして、心に銘ずべき肝要を示されました。以来40年余り、そのご教示は、浄土真宗門徒の信仰生活の規範となってきました。一方、宗門は1946(昭和21)年に制定された「宗制」を根本にして活動してきましたが、このたび「宗制」が改正され、時代を超えた不変のことがらと時代に即応すべきことがらが整えられました。それにともなって、新しい教章を制定いたします。
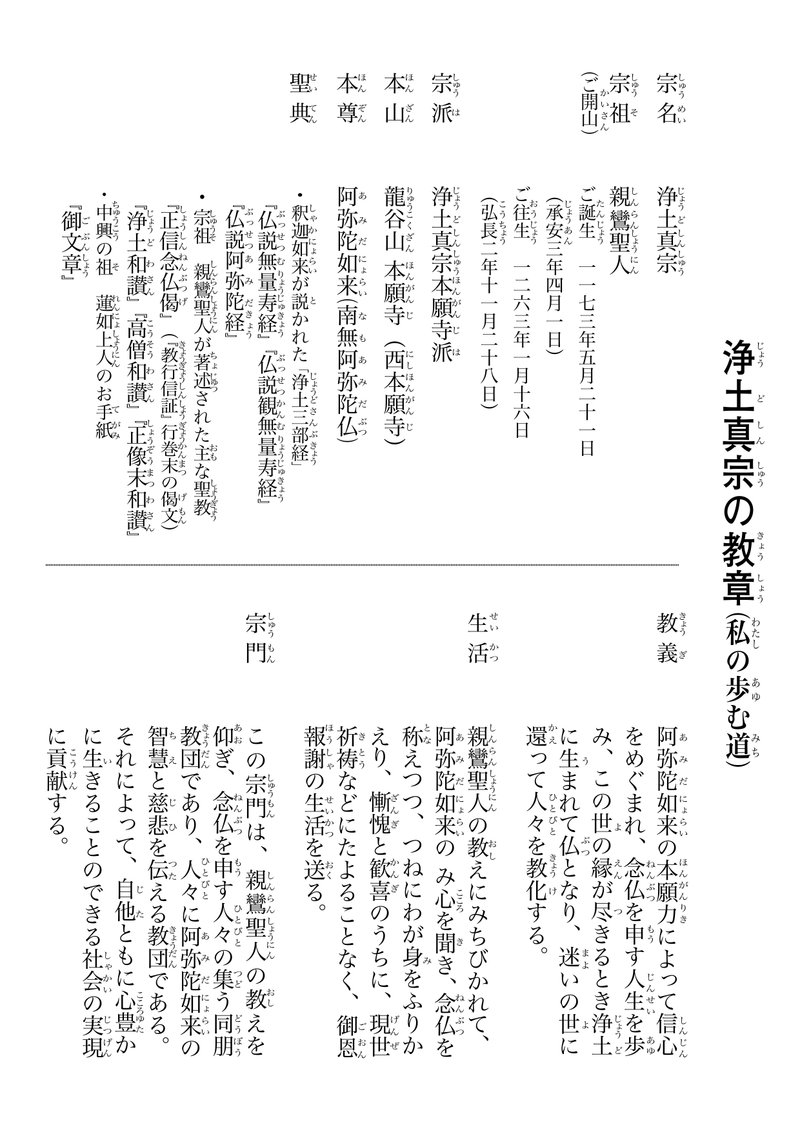
と、前々門主が1960年代の本願寺派の教線の現況と将来を憂い制定されたのが『浄土真宗の教章』であったが、「宗制」改正に伴う措置として一部変更する。しかし少し今の時代の状況と未来を勘案したもので制定し直すとされている。そこには浄土真宗の伝統を代々伝承するという門主としての姿勢が貫かれています。
こうして俯瞰してみると、50年前宗門の「教章」と「生活規範」では現代には通用しないと考えた当代の門主が「ご親教3部作」と「ご消息」によって、前々門主と前門主の制定した「教え」と「生活の在り方」を全面否定し塗り替えていったとみるのが妥当のように思えます。しかし、これは当代のご門主(当門さま)お1人でお考えになったものでは無いことは、今までの論証でお分かりになっていると思います。
伝統的な宗義により布教していては「伝わらない」。現代人は高度な知識を持ってはいるが生きる上での規範を見失った生き方しか出来ていない。それが現代という時代を生きている人々の不安であり悩みである。
それに応え得る「新しい浄土真宗」を構築しなければならない。つまりは現代人に通じる「教学の組み替え」をしていかなければ宗門の未来は無い。その先頭に立つのが総合研究所を大幅に機構改革して新たに設置した「伝わる伝道研究室」なのだと語ったのは石上前総長である事は既知のこと。
甥っ子である若い門主の側にあり、宗門の未来に対する危機感を共有したお二人が、二人三脚で、「ご親教3部作」と「ご消息」を出したものと考えると、「小職が文案に関与した事実は一切ございません」と言い続ける意味がわかるような気がします。まことに歪なご門主の守り方だとは思いますが。
例証編㉑宗会議員とのやり取り
「唱和推進」を推し進めている総局に在籍するお二人の方とお話をする機会がありました。お一人は「うちのお寺では元々『領解文』は使っていない。また「唱和」すること自体に違和感を持っているから「生活信条」なども使っていない」というお方。もうお一人は「「ちかい」や「浄土真宗のみ教え」が出たとき内容に違和感を感じ、「浄土真宗救いのよろこび」を現代版領解文とするように訴え続けてきた。」とする方。
「「新しい領解文」の内容と唱和推進することについて、どう考えているのか?」という事を、321回定期宗会で提出した「請願書」を絡めて聞いてみました。何故ならお二人とも請願を不採択としたお立場であるからです。
以下、グレー背景は総局議員さん。
あの請願は門主を批判する文面であったから不採択に回った。
唱和推進すると宗務の基本方針にあるが、唱和を推進することは門主を傷付けることになる恐れがあるから、取り敢えず唱和推進する事を慎重に取り扱って欲しい(一旦保留して欲しい)」という文面で提出されたはず。
ご消息の中に門主が唱和するよう勧められているではないか。内容に問題があるから一旦保留して欲しいというのは、あれを書かれた門主を批判することになる。
確かに消息には書き込まれている。あの請願は総局の宗務行為についてのみの請願。あの文章は門主が書かれたものではない。申達した側、つまり石上さんが書いたもの、それでなくては門主無答責が成り立たない事になる。
(申達した内容に問題がある)
石上さんが書いたという証拠は無い。あくまでも噂としてしかみていない。
噂ではなく門主ご自身が『総局の進める事項に関わることは困難です』とおっしゃっている。
あくまでも門主が出されたものだから、その線で物事を進めるのが政治。
いや違う。宗会は行政(総局)をチェックする機関であるはず。議員がこれはおかしいと思ったことを、おかしいと言えない宗会になってるから、それが機能していない。
宗本区分の宗法改正で宗会では力が無くなり『常務委員会』が最高の議決機関となっているから如何ともし難い。
それは言える。しかし宗会で歯止めを掛けることは出来る。それをしてもらいたいが故の「請願」であった。(議員の判断に期待していた)
請願書の実物を見たのは宗会終了2日前くらいで、、、(読み込めなかったの意味か?)。自分としては「ちかい」や「浄土真宗のみ教え」があった時、おかしいと批判していた。
それは知っている。しかし政治家は結果が全て。どんな事を言っていたにせよ、議員がどんな投票行動をしたか?何をしているか?私たちはこれで議員を見る。本当は思いは違うんだけど(言い訳)は通用しない。
そうですよね。
今度の総長選挙、あれで流れが変えられるチャンスだった。憂鬱な朝を迎えたと書いてあったから一言コメントしたよね。
本当に憂鬱だった。
それはよくわかる。白票は議員としては責任放棄と書き込んでいたから、白票は門主に「これでは選挙出来ません」と意思を伝える行為で立派な投票行為。それを分かってくれなかったね。
保滌さんに入れろとか色々私のところに連絡があった。だから本当に憂鬱な朝だった。
だろうね。池田君に入れるということは、石上さんを継承する事を是とする事だから。教区内の声だ。いずれにせよ、教区内には君の行動について(総局入りしたことも含め)キチンと説明をしないと、みんな納得してないよ。3人の宗会議員揃っての報告会をしかるべき機関に設定でもしてもらおうか?
出来たらお願いしたい。
他にも門主制とか総長指名制など話しました。この二つについては私と同じ考えでした。話した内容を記憶してる範囲忠実に再現したつもりですが、直接皆さんの前で話をすると言ってくださいましたので、それを期待をしています。
例証編㉒両堂の意味
6月23日の中外日報「ひと」欄に新総長池田行信氏が取り上げられていました。見出しは『両堂の意味を大切に』。その中で、社会状況の変化や宗門の多くの課題が目立ってきた中で、『つまずきの石は踏み石にもなる。ポジティブに転換していける道を探っていきたい』と。
池田氏の言う通りだと思います。踏み石に転換できるのは、宗祖の明らかにされたご法義を中心に、今までご歴代の宗主が思慮に思慮を重ねて伝統されてきた『本願寺』の意味するところを肝に据えて、この度の混乱に真摯に向き合う事だと思います。
池田氏のご自坊が所在する関東北部辺りは『浄土真宗はまだまだ浸透していない』との認識があるようで、そこに浄土真宗を伝えるには『仏教としての浄土真宗という視点に立ち、そこから浄土真宗を理解してもらう必要性』があるとの事です。これは前石上総長の思想と同じ事に注目したい。浄土真宗は大乗の至極と宗祖が言われるように究極的な『他力の救い』であります。その意味で「伝わりにくい」と考えられているのかも知れません。かつて私もそう思っていました。
そんな私は師匠から『浄土真宗(ご信心)に入る階梯は無い!お前は他力がなんも分っとらん。聞き直せ!』とこっぴどく叱られたことがあります。私が『物事には段階があるでしょう?何も知らない人には仏教の基本から徐々に解きほぐし、段階的に浄土真宗の教えにたどり着いて貰わなければ理解できないんじゃ無いですか』と問うた時です。師匠は、
あんたは偉い人じゃの。だから日曜学校では、お釈迦さまの生涯から始め、諸行無常、諸法無我、涅槃寂静を縁起や空で教え、それからご開山の生涯に続けて、その教えへとカリキュラムを組んでいるんだろう。それは『教育の論理』なんだよ。真宗は「教育では無い、お慈悲のお救い」。初心の者には先ずは『お慈悲の救い』法蔵菩薩から直接伝えるのだよ。ご本典を見てごらん初っ端からお救いに逢えたよろこびから始まっているでは無いか。我々は宗祖のその姿に学んでいくんだよ
と、知に走る私の思考をこっぴどく打ち破ってくださった思い出があります。また、
人間のはからいで教えを人に伝えようなどと言うのは思い上がりも甚だしい。お同行と共に御真影さまの前に額ずき、宗祖が仰がれた阿弥陀如来の名号の救いをお聞かせに預かっていくのが坊主の仕事だ、馬鹿になりなさい。
とも。こう言われた時まで、私も現代人は「自分の思索、自分の学び、自分の経験を中心に物事を考えたり、見たり、行動することが、知識人として当たり前。高学歴になった人びとに自分の能力を否定されていく、一見ネガティブに見える教えは受け入れ難いものがあり、馬の目を抜くような社会の中で生きている人に伝えることは甚だ困難」だと思っていました。
しかし釈尊も『阿弥陀経』流通分に
われ五濁の悪世においてこの難事を行じて、阿耨多羅三藐三菩提を得て一切世間のために、この難信の法を説く。これを甚難とす
とあるように智慧第一の舎利弗尊者に阿弥陀さまをお告げになってらっしゃる意味に立ち返る必要を思うのです。
池田新総長は同記事の中で『御影堂は祖師信仰、阿弥陀堂は人類の課題に立つ普遍宗教を意味する』と語られています。また続けて『両堂をトータルに見る教団(サンガ)論が十分ではなく、両堂の意味の理解が進んでいない。』と語っておられます。両堂を二元論で語る方に初めて出会い驚き、一読して「大谷派の宗務総長が語ったのか?」との印象を持ちました。
私は祖師を信仰するつもりでお参りしたことは一度たりともありません。宗祖がお示しになられた浄土真宗に遭わせてくださった祖師にお礼をするためでした。私が本願寺にお参りに行くのは「ご開山のお宅に伺い、お礼をするため」でした。それがご開山がお示しになられた如来の作願を改めて尋ねさせて頂く「場」としての「御影堂」。ご開山が常に礼していらっしゃる御内仏としての「阿弥陀堂」にもお参りさせてもらう。
という理解でした。これでは古いのでしょうか?江戸教学に侵された可哀想な私なのでしょうか。『人類の課題に立つ普遍宗教』などというアカデミックな思考は恥ずかしながら私にはありませんでした。宗祖の『弥陀をタノミといたしましょう。罪悪生死を繰り返し迷いを生きている者、誰一人取り残さず、輪廻の迷いを人間境涯をもって打ち止めとし、後生はお浄土の悟りに納めてくださるお救いですよ。その生命(人生)を生かされているもの同士、お互いの命を大事にしあいながら生きていこうではありませんか』のお勧めに頭が上がらない私ですから。
池田氏は続けて『両堂の意味の理解が進んでいない。そのため、宗本区分が十分生かされているとは言えず、組織体系一つとっても整理が行き届いていない』と語られています。つまり本願寺を一般寺院と同じ視点で捉えていると言うことでしょう。宗派は社会に向けて何かを発信する役割のものとの認識であると伺います。果たしてそうなのでしょうか?
例証編㉓九州組長会
昨日まで九州組長会(そちょうかい)が鹿児島別院を会場に開催されたとの事。プログラムには「新しい領解文」唱和は入っていなかったようで、このことを全体協議会での質問で長崎教区のある組長さんが「あれだけ唱和推進100%を言っている総長をはじめ本山から役員の方がおいでになっているのに何故プログラムに唱和を入れないのか。本気で100%達成を思っているのか?」(これは皮肉なのですが)との質問があったとの事。それに対して中井所務部部長が「各教区教務所長には唱和するよう通達をしている。各教区の判断で唱和するしないかは任せる。唱和せずとも罰則は無い」と回答。
この時点で宗務の基本方針の具体策「2026年度宗勢基本調査年度までに全寺院での唱和100%をめざす」が不可能となる事になります。あれだけ宗会で認められ常務委員会で議決されたものであると、その制定経緯の正当性を主張しているのに、その議決された具体策の一部を早速自ら反故にすることを容認したことは、すでに達成不可能になりますが、その責任はどうするのか?と皮肉を言ってみたいものです。いつの時点で方向転換をしたのか不明ですが、これほど問題化しても一向に取り合わなかった総局、漏れ聞くところによると「九州組長会を乗り切れば、あとはなんとかなる」と語られていたようで、その場しのぎのご都合主義も甚だしいものです。おそらく「めざす」としているのであって、必ず「する」とはしておりません。とかわすのでしょうね。
今回は「担当教区の鹿児島教区が混乱を避けるために唱和を入れなかった事を、総局が容認した。」ようですが、そもそも混乱を起こしてしまうようなものを発布したことを、ゴリ押しで正当化しようとしているところに混乱があることに総局は真摯に向き合って欲しいものです。見識が高い人物と門主から目され指名された池田氏なら必ずできると思うのですが。
しかし、これで教区での研修会等で唱和を必ずしもしなくても良いこととなり、ペナルティも課せられないことが公式見解として語られたことは一歩前進だと思います。これからは、唱和をプログラムに入れない事について本山から何か言われたら『九州組長会では入れない事を容認されていたじゃないですか』で、すべて通用します。
次に満井総合研究所所長の
ご門主さまが唱和をお勧めになっている。戦後世代は自己肯定感が高く、そのような人々に真宗の人間観を語ることは、教えが伝わりにくい要因となっている。そのお考えからご親教やご消息は語られている(要旨)
と語られた事に対して、大分のある組長さんは
戦後世代が皆そうではなく低い人もいる。そんな方は唱和するのが辛い人もいる。それなのに何故100%唱和推進なのか?総長は前総局の方針を継承すると言っているが、それでいいのか?せめて独自性を出して唱和100%は取り下げたら如何か?たとえ「新しい領解文」発布はご門主の意向とはいえ100%唱和推進は総局の宗務方針であり、それが混乱に輪をかけている。これは総局の責任である。
と。
唱和100%の危険性について深く考えることもなく宗務の基本方針具体策に入れた時点で、この宗門はいつでも世間の声に迎合できる体制に戻ってしまったと思うのです。私たちの宗門は戦時中ご門主の「消息」や「説諭」などによって、多くのご門徒を戦地に赴かせ死なせてしまった悲しい歴史があります。その反省で「宗制」を改変し、歴代門主の「消息」を準聖教扱いにしないと決めていますのに、「ご消息にご門主が唱和をおすすめになっている」という一言で、「新しい領解文」を唱和推進することの正当性を主張しているのが前総長であり現総局なのです。
この度の総局に入った方の中には『「新しい領解文」には私個人としては同意しかねる』と予てから言い続けている方も入局されています。それでも唱和推進すると公約し、公言している池田総局に在籍するということは「世俗の論理に自分の信念を売り渡した」と批判されても仕方ないことです。この思考は「本当は戦争は反対だけど、世間がその方向に向かっているから心外ではあるが仕方なく」に通じることだと思いますが、違うでしょうか?
考えたくもありませんが、もし世の中が戦争に向かう時が来た時、「社会に必要とされる僧侶・教団像」を目指した石上前総長の方針を継承している現総局ならば、早速門主に戦争加担の消息発布の申達をしてしまう危険性が潜んでいます。「社会に必要とされる」とは「社会に役に立つ」ということです。社会は宗教界に「今の社会の空気を読め」と要求するのは当然ですから、かつてがそうであったように。
「そんなことはありえない」と強弁しようとも、法義を主とせず世間知を主とする姿勢は、その恐れを十分含んでいることを知らなければなりません。宗教(法義)は世間の価値観に一定の歯止めをかける所にこそ存在価値が発揮されることですし、それが宗教の倫理観の基軸となるものと考えています。
松月 博宣
浄土真宗本願寺派僧侶
龍谷大学文学部仏教学科卒業。本願寺派布教使。
福岡県海徳寺前住職。
https://www.kaitokuji.info/
いただいた浄財は、「新しい領解文を考える会」の運営費に活用させていただきます。
