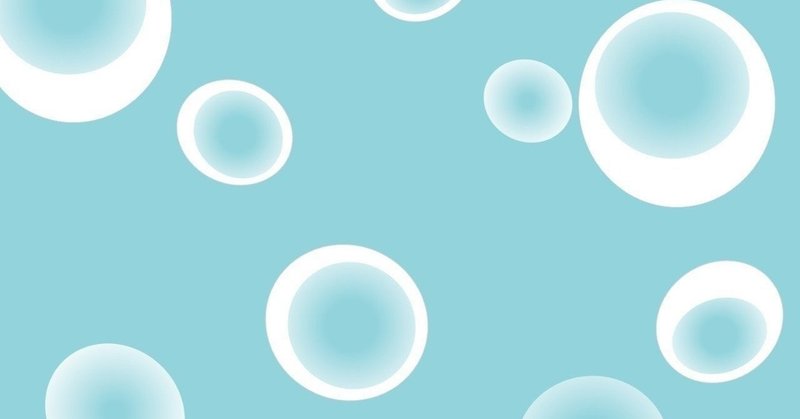
短編小説 幻谷(まぼろしだに)⑦
目を覚ますと、ブツブツと穴の開いたトラバーチン模様の天井が見えた。
それからじわじわと、自分が体を持っている生物だとわかっていくように、腕から手、太ももから足へと人間である感覚が戻っていく。ただ、頭の中には鉛が入り込んだような重い違和感を感じる。
呆然としていた意識の中に、視界の左端からひょっこりと誰かの顔が出てきた。
「圭太だいじょうぶ?あたしのことわかる?」
肩まで伸びた茶髪に切れ長の目をした女性が俺を見て泣いている。口にはマスクがしてあるが、泣きはらしたように眼が腫れていているのが分かる。俺はその時やっと、左手が握られていることを感じた。その手触りの温かさは心の奥底で蠢く不安を、優しくなでるように安心させてくれている。
俺は何を言うべきか迷った。とても親しい人のような気もするけど、子供の頃を最後に何十年かぶりに会った人のような気もする。ただ何となく無意識に口から出した言葉は自分でも意外なほど自然だった
「かあさ・・・ん?」
母と思われる女性は「そう!そうよ!!よかった、本当によかった」と言って赤く滲んだ目もとから更に涙を流し始めた。さっきよりもさらに強く手を握られ続けていくうちに、俺の母だとわかった。
更に意識が回復していくほどに、自分が今病院のベッドにいる事や、坂道から転げ落ちてくる誰かの姿が蘇ってきた。そしてだんだんと後頭部の鈍い痛みが酷くなってくる。
「あの・・・今、俺どうなってんの」
母は左手から手をはなして涙を拭うと、ゆっくりと深呼吸をしてから続けた。
「あなたはね、坂道で転げ落ちたお父さんにぶつかって、後頭部を壁に打ちつけたの。そしてら意識失っちゃって、血が出てきちゃって、もう、ほんとに・・・死ぬかと思ったんだから・・・うう。」
と、また泣き始めた母の言葉を聞いてから記憶を手繰り寄せていたが、どうにも父の顔が思い出せない。そして、自分にとって重要な何かを忘れている気がした。
その後、MRIなどの精密検査を受けて奇跡的に脳に大きな異常が無いことを知らされた。搬送先が大学病院だったので、40代ぐらいの担当医師の顔つきはドラマのような緊張感があった。インフルエンザの時の小太りのヤブ医者とは違うな、と思ったその時だった。
「あっ、そうだ。インフルエンザだ。あれ?」
頭の片隅でもやもやとした霧が少し晴れた。そうだ、俺はインフルエンザに罹ったはずだ。
「ちょっと圭太、どうしたの」
説明を聞いていた母が俺を振り向くと、担当医も俺を見た。
「いや、俺さインフルエンザにかかってたよね」
肯定的な返事が返ってくると思っていたが、母は眉根にしわを寄せて予想外の言葉を口にした。
「何言ってんの。インフルエンザに罹ったのは父さんじゃない」
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
