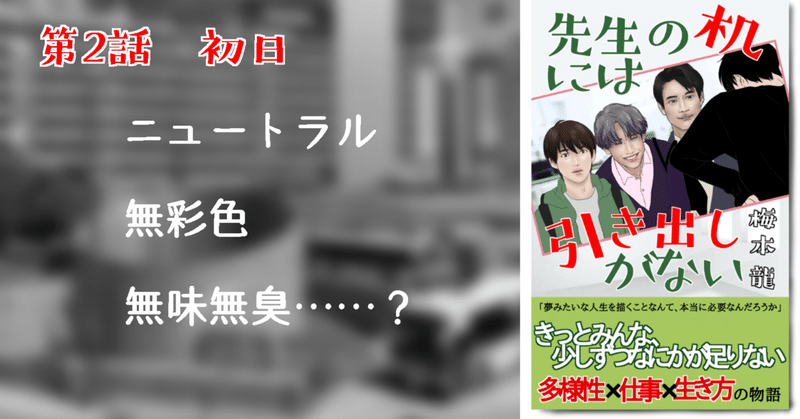
「先生の机には引き出しがない」第2話
※目安:約4300文字
第二話 初日
いよいよ今日が初勤務日。これからのことも詰めたりするし、引継ぎや説明もあるから夕方よりも昼間がいいねということになった。それで土曜日の今日、十二時半に新宿駅で余丁さんと待ち合わせだ。
朝は曇っていたのにどんどん天気が良くなって、てっぺんに昇ったばかりの太陽が二月とは思えないほどの熱を送ってくる。地上からも地下からもいろんな音や気配、景色などの情報が、次々と畳みかけるようにして僕の感覚を刺激し続けている。高い建物がそこだけ切り抜かれて大きな穴があいたみたいな、開けたバスターミナルには、絶え間なく大型バスが行き交っているし人の流れも活発だ。演説する人、募金活動をする人、待ち合わせをする人、たむろする人、忙しなく行き交う人。人の数だけ世界が存在しているみたいに雑多で騒然としていても、この狭いようで広い景色の中では秩序が保たれているかのようだ。この中で育った僕にとっては、それさえも居心地が良い。
小宇宙のようなバスターミナルを正面から一望できる場所にある花屋が、目印にもなると言って僕はそこを待合場所に提案してみた。そうしたら余丁さんがすんなりOKしてくれたので、今日僕は約束の時刻より五分前からここにいる。
「柏木くん、お待たせ。待った?」
「いえ、大丈夫、です」
ただ単に五分前行動をしているだけなので、待たされている感覚はない。けど、今日は太陽が眩しくて、日当たりの良いこの場所は冬なのに若干暑い。時間ぴったりに大きなトートバッグを担いだ余丁さんが登場する頃には、暑さで少しだけぼーっとしてしまっていた。駅ビルから外に出てきた余丁さんは一瞬だけ眩しそうな顔をしたけれど、
「じゃぁこっちね」
大して足も止めずにそう言って、さっと左手で進行方向を指しながらスタスタ進んでいく。僕はテンポの速さに驚きつつも、はぐれないようにぴょこぴょこその後ろをついていく。もしかしたら今来た道を、このまま戻って家に帰ってしまうのかな? そう思ってしまいそうな順路で僕たちは歩いていた。
大通りから枝分かれした道をいくつか選んで進んでいくと、雑踏さえも届かない静かな場所が現れる。え。このままいくと僕、家に着いちゃうんですが。変にドキドキしてきちゃったけど、自宅に向かうための最後の分岐を無視して直進したので、ちょっとホッとした。そのまま歩いていたら、小学校のすぐ近くにある小綺麗なマンションの前で誘導が止まった。
「勤務地は、ここね」
道、わかった? 早足だったかな? と振り返りながら余丁さんは言った。
「はい。近所なので大丈夫です。そこの小学校、僕の母校なので」
「えっ? マジで?」
「それと昔、クラスの子がそこの家に住んでいました」
マンションの近くにある一軒家を指さす。一軒家だけど借家らしくて、今ではずいぶん古さを滲ませるその家に、もうその家族は住んでいない。更に言うとするならば当時、これから勤務先になる目の前のマンションはなかった。今でもすぐ隣にある神社からは、常に境内の木陰から心地いい風が流れてくるようだ。それに変わりはないけれど、この辺はもともと古いアパートが密集していた。災害対策の区画整理もあって古い建物が一斉に壊され、僕が中学何年生だったか、その頃にこのマンションが建った。四階建てで土地柄の割にはゆったりとした敷地の使い方をした、単身者向けの賃貸マンション。まさかそこにバイトで通う日がくるなんて、何が起こるか分からないものだ。
「へ、へぇ~すごい偶然だね」
余丁さんは目を大きくして僕を見た後、僕に分かるように暗証番号を入力してマンションの入り口を開けると、そのまま中に入って行く。エレベーターを経由しながら三階の端っこにある部屋まで僕を連れて行ってくれると、ドアの前で大げさに振り返って僕を見た。
「いいでしょ? 角部屋!」
人懐っこい笑顔と陽気な声で楽しそうに言われたけど、僕は緊張していたので正解の反応はできなかったと思う。表札には301って書いてあるだけで、名前は書いてない。まぁ、マンションってこんなものなのかな。
ピンポーン
「……」
「先生ー、余丁です。アルバイトの子、連れてきましたよー」
「……」
カチャッ
「鍵開けて入ってくればいいのに」
さらりとした声をした男の人だった。
感情が含まれていないけど、でも冷たいわけでも不機嫌なわけでもない。温度感のない、ニュートラルでするりと流れていってしまう感じの声。この人が、小説家の淀橋矢来。
実は採用が決まってから、淀橋先生の小説を一冊読んでみた。言われてみれば、本屋にたくさん著書が並んでいる有名な小説家で、でも映画化が決まったばかりというその新作も含めて、実際に著書を読むのは初めてだった。ものすごくキラキラと彩度が高くて、文字だけのはずなのに、まるで華々しい色彩感のある壮大な映画のような、完璧に色調補正されたカメラロールのような。そして描き上げたばかりの神々しい巨大壁画を見ているようだ。それでいて妙に現実的で少し不思議な現代小説だった。僕はあまり小説を読む方じゃないけど、文章そのものというよりは、描き出される世界観がとても心地いい印象で、好きだな、絵を描く感じに近いな、と思った。著者近影みたいなものはないし、どんなにネットで調べてみても著者情報については何も引っかからない。デビュー作の発表からは七年目という事らしいので超大御所作家ではなさそうだけど、作家名だけはそれなりに有名のようだ。でも年齢まではわからないし、厳密に言うと性別だって確定していなかった。結局みどり書籍の専属小説家という事実と、作品にまつわる情報以外は何もわからなくて、今日に至る。何よりも、そんな淀橋矢来先生が、僕の自宅からこんな近くに住んでいるとは全く知らなかった。意図的かどうかは知らないけど、正体がバレないまま小説を書いているということなら、仮に道ですれ違っていたとしてもわからなくて当然なのかもしれない。と妙な納得をしていた。
そんな状態だったから、バイトとはいえ実際に会えるとなると、作品のイメージから、どんなにキラキラした人なんだろうって僕なりに思い描いて、正直なところ今日の初出勤を少し楽しみにしてきた。けど、目の前の男の人はキラキラとは程遠く、『無彩色』『ニュートラル』『無味無臭』という言葉がぴったりなくらいの人だった。無味無臭って変だけど。でも、表情も特になくて、それは冷たくも暗くも病んでもない。ただただニュートラルな印象だった。それもあってなのか、温度感のない表情と、陰も陽も映さない瞳がなんとなく無垢で幼くも見えたから、実は若い人なのかなという印象は受けた。でもやっぱり、最終的にはこれといった特徴がない人で、強いて言うとするならば、黒。服も髪も黒い。あと、ひょろりと背が高い。比較対象が僕なら、みんな大きくなっちゃうけど。そんなことを一瞬のうちに頭の中で考えていた。
「どうぞ」
先生はそう言うと部屋の中にすっと消えてしまった。小さな玄関は、真っ黒な出で立ちの先生と対照的に真っ白だ。先生の靴は出ていなくて、余丁さんの茶色い革靴と僕のスニーカーだけが並んだ。
「柏木くんね、これがタイムカードになってるから。まず指紋登録させてもらっていいかな」
下駄箱の上の、飾り棚みたいなところには、小さな機材と小振りの白いスマホだけが置かれていて、それは本社のシステムと繋がっているそうだ。余丁さんに言われたとおりに指紋登録をして、勤怠画面で出勤の打刻をした。退勤の時もこれで指紋認証をして退勤打刻をするそうで、イマドキだなぁって思った。去年末までしていた薬局のバイトは、個人商店ということもあるんだろうけど、細長い紙のカードを機械にガシャンと差し込んで打刻するタイプだったから、なおさら。
「先生ねぇ、こんなんだし一筋縄ではいかないと思うけど、みんなそう言ってるから、気にしないでね」
余丁さんはそんなことを小声にもしないで、ふつうに話しながら僕を部屋の中に案内する。そしてそんな僕たちを、感情の見えないニュートラルな表情で淀橋先生が見ている。奇妙な感じだった。冷めているわけでも怒っているわけでもない。たぶん、ポーカーフェイスとも違う。不思議な人。
部屋の中も基本的に白かった。でも冷たいわけでも無機質でもなくて象牙色に近い色彩だ。明度はぐっと高いけどやっぱりニュートラルな感じで、初めての場所なのにどことなく落ち着く。扉から入って左側に広がる十五畳ほどの広いリビングには、木製の作業机と、椅子二脚以外、何も置かれていない。二方向に開いた窓には低刺激なイメージのクリーム色、恐らく遮光でも遮熱でもないシンプルなカーテンと、白の薄いカーテンが取り付けられていて、今日の暖かい日差しが存分に部屋の中に降り注いでいた。部屋が暖かいのは、この日差しだけのお陰だとは思わないけど、そう錯覚するくらい穏やかで暖かい、そして何もない部屋だ。右側を向くと、コンパクトながらマンションだなという感じのキッチンがあり、こちらも殺風景だった。小説家のアトリエ、と言われて連想するような大きな本棚などもない。情報量が少ないから落ち着くのかもしれない、なんてふと思った。
「柏木くん、そこ座ってよ」
余丁さんは僕にそう言ってから、淀橋先生に向き直って続けた。
「この子なら、たぶん先生と上手くやってくれますから! 面接した時、直感でタイプの系統が近いなぁと思ったんで。うんうん、きっと大丈夫です! 大久保さんもね、大絶賛!」
先生は変わらずニュートラルな目とさらりとした声で
「そう」
と軽く反応するだけ。この報告をどう思っているのかは全然読めない。余丁さんも『この子なら』って、ちょっと僕を買いかぶり過ぎじゃない? 僕本当に何もできないけど。
僕は余丁さんがセッティングした椅子にセッティングされた向きのまま緊張して座り、先生はパソコンが置いてあるシンプルな机を背に、立ったまま話す余丁さんを少し見上げるように座っている。
「あ、よろしくお願いします。柏木一です」
怒っているかもしれないと思うとなんだか緊張して、どんどん声が小さくなった。なんとか先生の顔を見て挨拶する。本当に、どう思われているのかわからない。何とも言えないニュートラルな顔だ。
「……改めまして淀橋矢来です。よろしく」
先生は、感情の見えない目を一瞬だけこちらに向けて、そうさらりと言った。
第三話へ続く
続きは近日販売開始させていただくkindle電子書籍orペーパーバック版でお楽しみいただけると嬉しいです!
電子書籍につきましてはkindleunlimited対象ですのでいつでも好きな時に好きなところから¥0で読み放題となります!
勿論、紙の本をパラパラしたいという方はペーパーバック版をお手に取っていただけると幸いです。
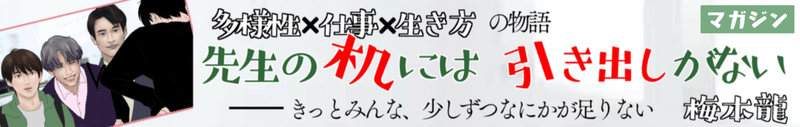


最後まで読んでいただきありがとうございます!
