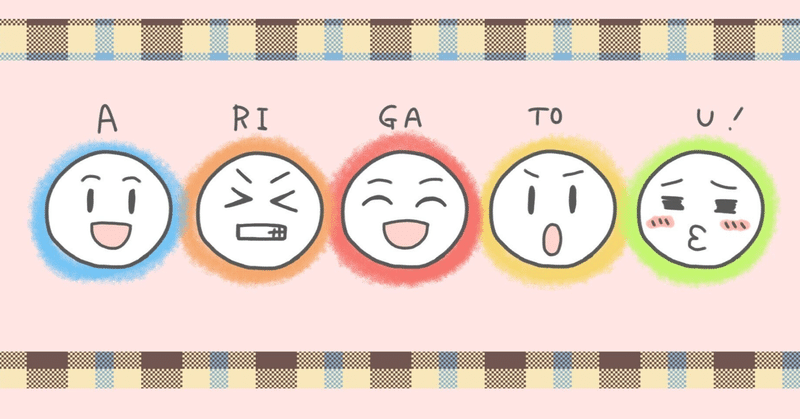
自己肯定感を高める道のり 第三部①:怒り・恐怖・不安に向き合う
私は、同僚からの指摘に対して、強い感情に苦しんだ結果、休職することを余儀なくされました。
自己肯定感を高める取り組みで、自分を苦しめた「落ち込み」の感情は薄れてきましたが、「怒り」、「恐怖」、「不安」の感情の克服は、休職前から復職を目指す今も、大きな課題です。
「怒り」、「恐怖」、「不安」の「3つの感情」は、皆さんの日常生活においても頻繁に浮かび上がる負の感情だと思います。
そこで、第三部では、この3つの感情と向き合い、克服する道のりで得た知識を、ご紹介(5回~7回を予定)していきたいと思います。
まずは、自分がどんな感情を抱いているか知ることが、感情と向き合うためには第一歩となります。
「怒り」とは
まずは、わかりやすい「怒り」についてです。
「怒り」を簡単に定義すると、「対象に対しての強い不快感などの負の感情」です。

「恐怖」と「不安」とは
次に、少し似た感情でわかりづらい「恐怖」と「不安」について表にして比較します。

それぞれを簡単に定義すると、「恐怖」は、「対象がある確実なものに対して抱く負の感情」、「不安」は、「対象がない不確実なものに対する負の感情」です。
例を上げます。
上司からのパワハラに感じる負の感情は恐怖です。
会ったことはないが異動先の上司にパワハラされるかもと感じる対する負の感情は不安です。
3つの感情の要因
3つの感情の要因(1つではなく複数存在する)となるものを説明します。
怒りの要因となるもの
他人の行動や発言(不正、侮辱、妨害)、自分自身への不公平な扱い、環境や社会の問題、ストレスなどです。
これらの要因が怒りの感情を引き起こします。
恐怖の要因となるもの
環境要因(高所、暗闇、恐ろしい物体や生物・人)、出来事(事故、災害、パワハラ)、心理的な存在(幽霊、怪物)などです。
これらの要因が恐怖の感情を引き起こします。
不安の要因となるもの
将来への不確かさ、社会的な状況(対人関係、試験)、未知の状況、身体的・心理的な健康への懸念、トラウマなどです。
これらの要因が不安の感情を引き起こします。
向き合うべき3つの感情「恐怖」、「不安」、「怒り」について、どの感情を抱いているかを知るために、それぞれの定義や要因を考えてきました。
しかし、私たちの感情は複雑で、それぞれが密接に関連しています・・・。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
私の経験があなたに役立つなら、幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
