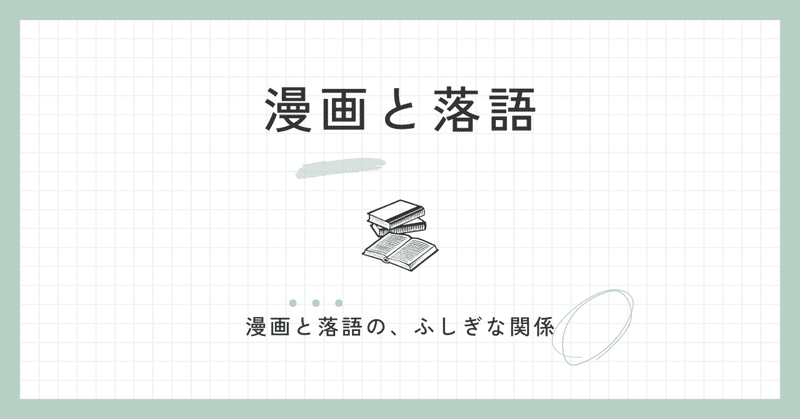
漫画と落語:田河水泡『のらくろ』 4
江戸っ子・田河水泡
田河水泡の本名は高見澤仲太郎という。
1899(明治32)年2月10日、東京府東京市本所区本所林町(現在の墨田区立川)で仲太郎は生まれた。父方の家系は曾祖父が直参旗本の本多某に仕えていたと伝えられており、仲太郎が生まれた当時、生家はメリヤスの家内工業を営んでいた。

仲太郎が満1歳になる頃、実母が肺炎で他界してしまう。すると翌年、父は再婚を機に仲太郎を姉夫婦に預けるのであった。このため仲太郎は、伯母夫婦の暮らす深川区松村町(現在の江東区福住)で育つことになる。田河水泡と江東区の縁は、このような経緯で生まれた。
伯母夫妻が親代わりとなってくれたものの、仲太郎には「(父に)捨てられた」感覚があったのかもしれない。
伯父の佐藤藤助は、もとは生薬屋の惣領だったが、早くに引退して悠々自適の生活を送っていた。盆栽を嗜んだり、南画を描いては展覧会に出品したりと、なかなかの趣味人であった様子がうかがえる。
この伯父を通じて幼少時から絵に親しんでいたことが、のちの仲太郎の人格形成に大きく影響を及ぼす。
この藤助伯父は家作を持って差配をしていたというから、いま風に言うならば大家業を営んでいたことになる。家作を持って隠居する、というのは、この時代には割とポピュラーなセカンドキャリアだったようだ。
家賃を滞納した店子が「女房が患った」と言い訳すれば、「そいつはいけねえな、これで薬でも買ってやんな」とあべこべに薬代を出してやったというから、まさに落語に出てくるご隠居のような人物であった。
なお、落語に出てくる子供(金坊)や与太郎は、自分のことを「あたい」と呼称する。この呼び方は、大正の初期までは東京の下町では男女問わずに子供の一般的な一人称であった。
大正の中期頃から廃れ始め、昭和に入る頃にはあまり使われなくなったもので、明治の末期に下町で育った田河水泡は、「私あたりが最後だっただろう」と記憶している。
俗に下町(日本橋、京橋、神田、下谷、浅草、本所、深川)生まれを江戸っ子と称すが、その際に「ちゃきちゃきの」と形容することがある。
この「ちゃきちゃき」とは、「嫡々」のなまった言葉であるとされ、嫡子の嫡子、つまり三代続けて下町生まれであることを意味する。落語には「三代続けて水道の水で産湯を使う」という江戸っ子の啖呵があるが、神田上水と玉川上水の水道の水を産湯に使える周辺地域で家系が三代(嫡々)以上続いたことが江戸っ子のアイデンティティであった。
本所生まれ深川育ちの田河水泡は、江戸の風に育まれたのである。
「少年倶楽部」(大日本雄辯会講談社)や「漫画少年」(学童社)で編集長を務めた加藤謙一の子息である加藤丈夫は、著書『「漫画少年」物語 編集者・加藤謙一伝』(都市出版)のなかで、終戦後の1948(昭和23)年頃に出会った田河水泡の印象を「和服をサッパリと着こなし、江戸っ子らしいベランメエ調で話すのには独特の風情があった」と書き残している。
写真で見る田河は繊細な文士風だが、生前の姿を知る人々の逸話を総合すると、「江戸っ子」と呼ぶにふさわしい人物像が浮かび上がってくる。
なお、妻の高見澤潤子は、田河水泡の人となりについて、次のように書いている。

しかし、T(※注:田河水泡のこと)は、本所でうまれ、深川で育った下町っ子である。下町気質とか、下町根性というものを、ずっともちつづけている。
「江戸っ子は、義理をしらなくちゃいけねえ、困ってる者をみたら、裸んなっても、助けてやらなくちゃいけねえ」
と、子供のときから、きかされて来たし、日本で一番偉い人は、幡随院の長兵衛だと思いこんできた。
大人になっても、ひとの世話をやいて、自分が損するぐらいでなきゃ、江戸っ子の面汚しだ、というような気もちは、Tの心の底にはっきりときざみつけられていた。
なお、幡随院の長兵衛とは、江戸時代に花川戸(現在の東京都台東区)で大名へ奉公人を斡旋する人入れ稼業を営んでいた侠客である。落語では「芝居の喧嘩」や「鈴ヶ森」に名前が出てくる。
下町に溢れたポンチ絵
下町で育った仲太郎は、幼少期から漫画に触れていたようだ。後年、雑誌「新女苑」(実業之日本社)昭和27年1月号で弟子の長谷川町子と対談した際には、幼少期の思い出を次のように語っている。
田河 僕の子どものころ、漫画の本といえばポンチ絵というのが大分ありましたね。東京だったからね。駄菓子屋でも売っている。本屋でも売っていた。
明治時代には、まだ「漫画」という言葉は一般的ではなく、コマ漫画などは「ポンチ」「戯画」「狂画」などと呼ばれていた。
ポンチという言葉は、もともとは1862(文久2)年に横浜でイギリス人のチャールズ・ワーグマンによって創刊された漫画雑誌「ジャパン・パンチ」に由来する。西洋風のカリカチュア(誇張的な風刺など)は「パンチ」から転じて「ポンチ」と呼ばれるようになったわけだ。
なお、幕末期には、風刺的な寓意を込めた浮世絵が多く出された。絵の余白が言葉で埋め尽くされたもので、こうした様式は江戸時代の草双紙という絵入読物にも通じる。やがて風刺浮世絵や草双紙の様式を引き継いだポンチが生み出されていく。
日清戦争(1894〜1895)以降、草双紙や浮世絵を扱っていた版元が多数参入し、題名に「ポンチ」という言葉を入れた袖珍本(小型の冊子)が大量に刊行されてブームになった。漫画研究家は、この時代の冊子を「明治ポンチ本」と呼称している。
「明治ポンチ本」には現在の4コマのようにコマ割りされたものもあり、昔話を模倣したストーリー性のある御伽噺なども存在する。
大きさは縦11.5cm、横16.5cmが主流なので、ちょうど現在の新書本を横向きにしたようなサイズ感を想定するといい。
「明治ポンチ本」の発行元や卸問屋は、東京の場合、日本橋区、浅草区、神田区、下谷区に集中していた。仲太郎の住んだ深川区とは近い。
しかし、「明治ポンチ本」は日露戦争(1904〜1905)後には下火になったといわれている。
とすると、1899(明治32)年生まれの仲太郎は、「明治ポンチ本」のブームの直撃世代からは、少しズレる。「下火になった」とはいえ、仲太郎が駄菓子屋や本屋で買えたわけだから、「明治ポンチ本」スタイルの冊子は、子供向けの娯楽として定着していたのだろう。
ともあれ、江戸時代の戯画や絵草紙から近代的な漫画へと移行する過程において、「明治ポンチ本」というものが子供文化に存在したのであり、田河水泡の作家的ルーツのひとつに「明治ポンチ本」がある可能性も頭に留めおきたい。
ちなみに「漫画」という語句は、江戸時代には山東京伝や葛飾北斎が用いていたようだ。やがて明治期に北澤楽天が「comic」の訳語として「漫画」を用いるようになり、1902(明治35)年に楽天が新聞「時事新報」誌上で毎週日曜の常設漫画欄「時事漫画」を創設すると、次第に「漫画」の語句が広まっていき、明治末期ごろには一般的になったものと考えられている。
よろしければサポートのほど、よろしくお願いします。
