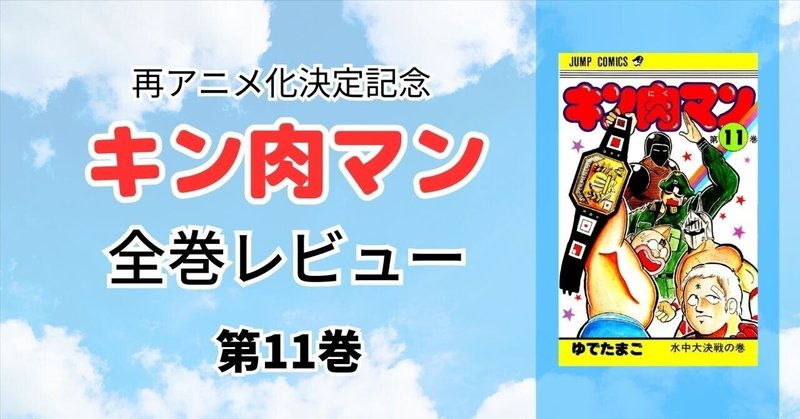
第11巻:水中大決戦の巻
第11巻データ・アナリティクス
読者に支持された“ストーリー漫画としての”『キン肉マン』

「掲載順=人気」とは一概に言えないが、人気を測るバロメータのひとつとして参照する。
1号あたりの漫画作品の掲載本数は15〜17本。
単行本11巻の発行日は1983年2月15日。
第11巻の収録話は従前より1本少ない12本。それまでは1話あたり13ページが基本だったが、このあたりから15ページが基本となり、「大激突!!の巻」にいたっては大増20ページに。徐々に『キン肉マン』がストーリー漫画として扱われるようになってきている。
おそらくこの頃は、まだ13ページの感覚のまま制作しているので、15ページになった直後の「7人の悪魔超人編」は1話あたりのヤマ場が多い。結果的にそれが奏功し、このシリーズでは読者の印象に残るシーンが多くなっている。水面から顔を出したロビンのマスクとアトランティスの「ケケケ〜〜ッ」(「水中大決戦の巻」)、救世主のレッグ・ラリアート(「怪超人!!の巻」)、ウォーズマンの1200万パワーの光の矢(「一発勝負!!の巻」)など、思い出せる場面は数え上げたらキリがない。
とりわけ印象的なのは「いきのこるのは!?の巻」の、ザ・魔雲天との戦いを終えたテリーマンがテアトル東京まで戻ってきてキン肉マンと再会するシーンだろう。「ただいまキン肉マン」「おかえりテリーマン!!」のラストシーンは作中でも屈指の人気エピソードである。この回ではじめて読者アンケート1位をとったという。
なお、テリーマンがザ・魔雲天とブレーンバスターで谷底に落下しながらも、奇跡的に生還した回は、『キン肉マン』が『ジャンプ』の人気投票で初めて1位を獲得した記念すべき回であり、ボクたちにとっても思い出深い興行なのだ。
この回は、1980年39号の「グランド・キャニオンの絶叫の巻」(第5巻収録)以来、およそ1年半ぶりに巻頭カラーを飾った。注目度の高い巻頭カラーで内容が充実していれば、当然のことながら人気はついてくる、というわけだ。
1982年18号では表紙を飾っているが、他作品との合同ではない『キン肉マン』単独での表紙となると、1980年9号「氷上のキャメルクラッチの巻」(第3巻収録)以来なので、2年以上間隔が空いたことになる。この年は、さらに26号、32号、45号と表紙に起用された(いずれも単独)。くわえて他作品との合同で表紙を飾ることもあり、人気を持ち直すどころか、完全に看板作品になっていく。
愛読者賞での『闘将!!拉麺男』
1982年9号の巻頭特集「日本一の漫画家は誰だ!!」では、第10回愛読者賞のノミネート作家が紹介されている。この年の愛読者賞に選ばれた作家は本宮ひろ志、秋本治、鳥山明、高橋陽一、高橋よしひろ、ゆでたまご、北条司、江口寿史、宮下あきら、平松伸二の10人。ゆでたまごは2年ぶりに選出され、錚々たる面々に名を連ねた。
この年の愛読者賞でゆでたまごが描いた読み切り作が『闘将!!拉麺男』である。
『キン肉マン』本編に登場するラーメンマンを主役にした作品だが、キャラクターのみ流用し、設定やストーリーは『キン肉マン』とはまったくの無関係。そのため、外伝ではなく、スピンオフという位置づけになる。この愛読者賞版の『闘将!!拉麺男』は、「少年ジャンプ」15号(3月29日発行)に掲載された。
ラーメンマンは『キン肉マン』シリーズでも指折りの人気キャラクターである。「アメリカ遠征編」後半、「車いすの少年の巻」(1980年50号掲載/第6巻収録)のトビラに掲載された超人ランキングでは、「人気超人部門」と「悪役超人部門」の両方で3位に入っており、このときはランキング発表にあわせてレフェリーとしてゲスト登場もしたほどだ。
しかし、「超人オリンピック ザ・ビッグファイト編」の準決勝ウォーズマン戦で再起不能の重傷を負い、植物超人となってしまった。決勝戦終了の「勝利をわが手に!!の巻」(第9巻収録)を最後に、第10巻での出番はない。ステカセキングが超人大全集第5巻を使用した際に擬似的に登場する(「ミラクル・ランドセルの巻」第10巻収録)ことはあるものの、ラーメンマン本人は登場していない。アイドル超人軍団が勢揃いしたのに、そこにラーメンマンの姿はなく、再登場を待望する声は大きかったことだろう。
そうしたなか、1982年8号「大激突!!の巻」で謎の超人が登場。フードを被って正体を隠しているが、ラーメンマンのような辮髪をしていて、トランクに中国服を潜ませるなどの「匂わせ」をする。事実、のちに正体がラーメンマンであると判明するが、これが実に14号ぶりの再登場であった。
謎の超人(=救世主)は、続く9号「怪超人!!の巻」では北海道のUFO発着所でブロッケンJr.を救出し、レッグ・ラリアートでミスターカーメンをK.Oする。正体を明かさないままフェイドアウトし、読者が今か今かと待ち侘びているそのタイミングで、15号に愛読者賞『闘将!!拉麺男』が掲載されるわけだ。
そして、その翌週の16号「血しばり地獄の巻」で救世主は再び姿を現し、モンゴルマンとしてキン肉マンのタッグパートナーとなってシリーズに本格参戦する。この一連の流れをまとめたのが以下の表だ。

上表を見ると、企画(愛読者賞)と作品内容(ラーメンマン登場)をリンクさせて読者の興味を引こうと試みている様子が見てとれる。雑誌という特性を活かした演出で、読者の期待感を掻き立てているのだ。
なお、救世主が活躍する9号のサブタイトルは「怪超人!!の巻」で、モンゴルマン初登場の20号(第12巻収録)のサブタイトルは「怪超人の巻」となっている。エクスクラメーションがないだけで、じ語句を用いており、モンゴルマンを正体不明で、敵か味方か判然としない「怪超人」としてプレゼンテーションしているが、読者の目にはその正体がラーメンマンであることは明らかであった。
さて、愛読者賞作品の『闘将!!拉麺男』は読者の反応がよく、同賞のアンケート人気は2位。この年の1位に選ばれたのは『100Mジャンパー』(高橋陽一)だった。本作はのちに高橋陽一短編集(読切傑作集)に収録され、同書のタイトルにも採用される。
この年、集英社は「少年ジャンプ」の兄弟誌として隔月刊誌「フレッシュジャンプ」を創刊(奇数月発行)し、『闘将!!拉麺男』は同誌で連載がスタートする(創刊号は1982年8月1日発行)。
「フレッシュジャンプ」は新人作家の発掘を目的とした雑誌で、創刊当初は掲載作品のほぼすべてが読み切りであったが、唯一、連載作品として掲載されたのが『闘将!!拉麺男』であった。
同誌は1983年より月刊化し、その後も『闘将!!拉麺男』の連載は『キン肉マン』と並行して続き、1988年にはアニメ化もされる。
第11巻収録話の連載期間の出来事
「少年ジャンプ」は1982年16号で創刊700号を迎えた。この記念すべき号の表紙を飾ったのは『Dr.スランプ』(鳥山明)と『ストップ!!ひばりくん!』(江口寿史)で、この2作品が当時の人気のツートップだったようだ。上記7号から18号までの12週間での両作品の掲載順は、以下のとおり。
・『Dr.スランプ』
「4,1,4,5,5,7,5,5,9,1,6,4」
・『ストップ!!ひばりくん!』
「2,3,1,4,4,4,4,4,4,-,5,12」
江口寿史はたびたび休載することがあり、この号では表紙は飾るが連載作品は載らない、という珍事が起きている。『Dr.スランプ』はアニメ化決定前後のような猛プッシュではなくなったが、この当時はアニメも絶賛放映中で、「東映まんがまつり」では劇場用アニメ作品も公開されており、作品人気は依然として高かった。
ただ、両作品ともギャグをベースとするコメディ作品である。連載が長期化すると、作者が休載したり、作品が疲弊したりしていく。これに対し、ギャグ漫画からストーリー漫画へと転向した『キン肉マン』は疲弊を免れ、このあと人気が加熱していく。
ちなみに、18号からは『ハイスクール!奇面組』(新沢元栄)の連載がスタートする。もともとは『3面奇面組』だったが、作中で登場人物たちが高校に進学するのを機に、タイトルが改められた。主人公の境遇によってタイトルが変わる作品は類例が少なく、古くは『のらくろ』、メジャーなところでは『島耕作』シリーズ(弘兼憲史)などが挙げられる。
『ハイスクール!奇面組』ものちにアニメ化し、「少年ジャンプ」80年代のアニメ路線を語るうえでは欠かせない作品へと成長していく。
アイドル超人と悪魔超人の団体戦
ピラミッドパワーの謎
北海道UFO発着所での「ブロッケンJr. vsミスターカーメン」戦は、「全員集合!!の巻」(第10巻収録)では「ピラミッド・パワーデスマッチ」と銘打たれている。試合形式や「ピラミッドパワー」についてとくに触れられないまま試合が進行していき、救世主がリングに乱入した際に、ミスターカーメンの口から「このピラミッドパワーの中ではリングのロープもなにもかも生あるわたしの体の一部になる!」と説明される。
現代の読者からすると「ピラミッドパワーとは何か?」との疑念が浮かぶかもしれないが、そのような説明は不要なほど、この当時、「ピラミッドパワー」の概念は世間に知れ渡っていた。
そもそも「ピラミッドパワー」とは、エジプトにある遺跡のピラミッドに宿る(とされる)神秘の力のことである。ピラミッドそのものだけでなく、同じ形状であれば模型であっても効力が発揮されるものとされ、ピラミッド内に置いた食べ物は腐らず、使用済みのカミソリの切れ味が復活したり、植物の成長を促したり、さらにはヒーリング効果も望めたりするらしい。
このような力は科学的に立証されているわけではないが、ピラミッドの神秘性が説得力を生んだのか、とりわけニューエイジ思想やスピリチュアル界隈で広く信じられていた。
日本では1973年4月にたま出版から『ソ連圏の四次元科学』(著:S.オストランダー & L.スクロウダー、監修:橋本健、翻訳:照洲みのる)、さらに1978年1月にはベストセラーズから『ピラミッドパワーを発見した』(著:マックス・トス&グレッグ・ニールセン、翻訳:岩倉明)が刊行され、折しものオカルトブームに乗り、数々のピラミッドパワーグッズが発売され、ピラミッドパワー・ブームが巻き起こる。
このブームはフィクションにも波及し、フジテレビ系列で放映されたアニメ『科学忍者隊ガッチャマンII』の第6話「衝撃のピラミッドパワー」(1978年11月5日)では、地中海の無人島でイジプート財団がピラミッドパワー・システムの実用化を目指してピラミッド都市をつくっている。この回の演出は、竜の子プロダクション時代の押井守である。
なお、ピラミッドパワーグッズはさまざまな雑誌に広告を出稿しており、1979年に学習研究社が創刊したオカルト雑誌「ムー」などでも見受けられた。
ちなみに、『キン肉マン』でピラミッドパワーが出てくるのは、このミスターカーメン戦だけではない。「キン肉星王位継承編」でキン肉マンチームと知性チームで争われた決勝の次鋒戦、「ラーメンマンvsプリズマン」戦にも登場する。
ジャングル・ビッグ・ジムでプリズマンと対戦することになったラーメンマンは、プリズマンのレインボーシャワーでカピラリア七光線を浴びて瀕死のダメージを負うが、ジャングルジムの頂上部にある回転ゴンドラをピラミッドの形に改造し、ピラミッドパワーの効果によって体内のカピラリア毒素を排除して体力を回復、形勢を逆転する。この回「再生!ラーメンマン!!の巻」は1986年38号掲載(第33巻収録)なので、およそ4年半ぶりのピラミッドパワーということになる。この際には、ジェロニモによってピラミッドパワーについての詳細な説明が行われる。
プリズマン戦の最中に、ミスターカーメン戦がプレイバックされることはないものの、「7人の悪魔超人編」でピラミッドパワーを体験した救世主(=ラーメンマン)が、その4年半後にピラミッドパワーを駆使してプリズマンを撃破する(公式記録は両者ノックアウトの引き分け)ので、このときの経験が生きた……と解釈すれば、長期連載作品ならではの醍醐味が増すといえよう。
バッファローマンと『鉄腕アトム』と超人強度
この第11巻では「ウォーズマンvsバッファローマン」戦の最中に、はじめて「超人強度」の概念が登場する(「超人強度!!の巻」)。これ以降の『キン肉マン』シリーズにおいてきわめて重要な要素であり、現行の新『キン肉マン』(リアル・ディールズvs超神)でも重要なテーマとなっているので、しっかりと確認しておきたい。
この超人強度については、作中で解説者のタザハマが「超人のもつパワーを数字であらわしたものですよ」「そしてその数字が高い超人ほど強いというわけです」と簡単な説明をする。
2015年2月5日発行に発行されたムック『BIG FIGHT 01』(スコラマガジン)では、『キン肉マン』の二代目担当編集の松井栄元がインタビューに答えており、超人強度についても言及している。松井は「超人オリンピック ザ・ビッグ・ファイト編」から「7人の悪魔超人編」の最後まで作品に関わっていたと発言しており、そこで「超人強度とかはボクが言い出した記憶があるんだよね」とも述べている。超人強度に関する、より詳細な該当箇所を以下に引用する。
松井 (略)例の超人強度にしても、もともとボクの感覚では『鉄腕アトム』だったんですよ。プルートゥっていう史上最強のロボットだと。浦沢(直樹)さんもオマージュで描いてましたけど。
——超人強度とは、強さを数値化しようという。
松井 そうそう。でも、ボクのイメージは『アトム』だから10万とか20万とかキリがいい数字なんだよね。だけど嶋田さんは97万とか88万パワーとか。
——ずいぶん刻んでるなっていう(笑)。
松井 ビックリしたよ。「あ、刻んだ」って(笑)。でも、それが結果的にいい方向にいった。
文中にある「プルートゥ」とは、手塚治虫『鉄腕アトム』の第55話「地上最大のロボット(初出時:史上最大のロボット)」(光文社「少年」1964年6月号〜1965年1月号)に出てくる巨大ロボット「プルートウ」のことだ。
講談社漫画文庫の『鉄腕アトム』は、各エピソードの冒頭に、手塚治虫による作品解説マンガが付け足されており、講談社漫画文庫版『鉄腕アトム』第7巻収録の「地上最大のロボット」冒頭には「この物語はアトムの中でもいちばん人気のあったものです」との説明が加えられている。この人気エピソードを原案として、1本の物語としたのが、浦沢直樹の『PLUTO』(2003〜2009年)である。
ここで『鉄腕アトム』の「地上最大のロボット」について少し触れておきたい。アラブのサルタン(王)ことチョチ・チョチ・アババ三世はアブーラ博士に命じて、プルートウをつくらせた。サルタンはプルートウが地上最強であることを証明するために、世界各地にいる最高のロボット7人(日本のアトム、スイスのモンブラン、スコットランドのノース2号、トルコのブランド、ドイツのゲジヒト、ギリシャのヘラクレス、オーストラリアのエプシロン)の撃破をプルートウに命じる。アトムの10万馬力に対し、プルートウはその10倍の100万馬力である。
プルートウの外見的な特徴としては、巨大な体躯で、頭部に長大な2本のツノを有している。そしてプルートウは、移動する時は両手を振り回し、ハリケーンになって空を飛ぶ。また、アトムが空を飛んで突撃してプルートウの左ツノを折るなど、バッファローマンに関してはプルートウから得たインスピレーションが大きかったものと推測される。
あるいは「7人の悪魔超人」の「7」という数字は、作者お気に入りの映画『荒野の七人』『七人の侍』あたりに由来するのだろうが、プルートウの標的が7人であったことも、もしかしたら影響しているのかもしれない。
「地上最大のロボット」では、アトムはプルートウに対抗するために、自分の体を100万馬力に改造してほしいとお茶の水博士に直訴する。しかし、お茶の水博士はこれを拒否し、アトムを諭すのだが、その際のセリフが示唆に富んでいるので引用しておく。
もしちからの強いだけがえらいのなら プロレスの選手は世界一えらいことになる……だが実際はそんなことはない
十万馬力のロボットだって その使い方によっては世界一のロボットになれるのじゃよ
※現在刊行されている「手塚治虫文庫全集」(講談社)でも7巻に収録
『キン肉マン』の超人強度に目を移すと、実は前述したタザハマの解説では説明しきれないところがある。たとえば「超人オリンピック ザ・ビッグ・ファイト編」の第三次予選「新幹線アタック」では、超人強度20万パワーのタイルマンの記録が博多(終点=最高記録)で、100万パワーのカナディアンマン(小倉)や97万パワーのラーメンマン(岡山)を上回っていることから、単純に「パワーを数字で表したもの」とは言えない。
あるいは、95万パワーのキン肉マンが1000万パワーのバッファローマンを破るなど数々のアップセットを果たしていることから、一概に「数字が高い超人ほど強い」とも言いがたい。
『キン肉マン』の超人強度は、後世の『ドラゴンボール』(鳥山明)の「戦闘力」のように「力の強さを数値化したもの」と思われがちで、ときに数値設定の齟齬についてファンの間でも取り沙汰されることがしばしばだが、その実、数値の多寡が絶対ではない『鉄腕アトム』のお茶の水博士の思想を受け継ぐ概念であるとも言える。
なお、のちに追加される設定として、キン肉マンに敗れてサタンの制裁を受けたバッファローマンが、自身に残された300万パワーを3人の超人(ウルフマン、ロビンマスク、ウォーズマン)に分け与えて生き返らせている(「ミート生還!!の巻」第13巻収録)。「黄金のマスク編」では悪魔将軍の地獄の断頭台を受けて瀕死のジェロニモに対し、ロビンマスク、キン肉マン、ブロッケンJr.、ウォーズマンが10万パワーずつ分け与えようとし(「勇者の秘密!!の巻」第15巻収録)、ブロッケンJr.が「オレたち超人は輸血と同じようにパワーを他人に与えることができる!」と説明しており——このときはジェロニモがまだ人間だから超人パワーは受け取れないのだが——、自分の意思で抜き出して譲渡も可能なものであることがわかる。
このような性質を考えると、超人強度とは、戦闘能力を示すものというよりは、おおまかに「超人の生命力を数値化したもの」と捉えておくのがよさそうだ。
団体戦の戦績と、悪魔超人のオリジナル・フォー
アイドル超人と悪魔超人の団体戦の結果は2勝3敗で、悪魔超人が勝ち越した。このうちバッファローマン、スプリングマン、アトランティスと、悪魔超人初出時から確定していたメンバー4人のうち3人が勝利しており、シナリオ的に既定路線であったことが推察される。団体戦前に敗北したブラックホールも、「血しばり地獄の巻」のトビラ絵で掲載された対戦表ではキン肉マンの「大苦戦」と表記されており、7人のなかでもこの4人は扱いが上であるということを念頭に置き、新『キン肉マン』の「完璧超人始祖編」(第38巻〜第60巻)を読むと、誰が活躍するのかが見えてくる。
セント・へレンズ大噴火とは?
上野不忍池でロビンマスクに勝利し、キン肉マンと対戦することになったアトランティスは、キン肉マン戦において「水芸セントヘレンズ大噴火」を披露する(「魔の水芸の巻」)。
ここで言う「セントヘレンズ」とは、アメリカのワシントン州にある活火山「セント・ヘレンズ山」のことで、位置は下図のとおり。

アトランティスの出身地は「さけたミート!!の巻」(第10巻収録)のトビラ(読者投稿超人の紹介ページ)では「アトランティス」と、大西洋に存在したとされる幻の大陸名が表記されている。のちにオーストラリア・グレートバリアリーフへと設定変更されるが、いずれにせよ、アトランティスとセント・ヘレンズ山は関連性が薄い。
セント・ヘレンズ山は1980年5月18日に噴火をした。噴火は9時間にわたって続き、山頂部が崩落して馬蹄型のカルデラが形成され、もともと2950mあった標高が2549mにまで減少してしまった。とくに北側斜面で起きた地滑りは有史以後最大規模とされ、セント・ヘレンズ山はアメリカにおいて「火山」の代名詞的な存在となった。
社会を揺るがす大事件や事象は作品に落とし込むのが『キン肉マン』の特性ではあるが、57名が死亡したとされる大規模な自然災害は、発生から2年後というタイミングを鑑みても、現在のポリティカリー・コレクトネスの見地では題材にするのは難しいようにも思える。
その是非を問いたいわけではなく、40年以上前に描かれた作品だから、現在とは価値観が異なっているということを付言しておきたい。それだけ世間に大きな与えたインパクトを与えた噴火であり、その衝撃度は今日では追体験する術はなく、むしろこのようにフィクションに反映されている様を見るときにこそ、当時のインパクトの大きさに気づくことができる。
フィクションは社会を映す鏡なのである。
よろしければサポートのほど、よろしくお願いします。
