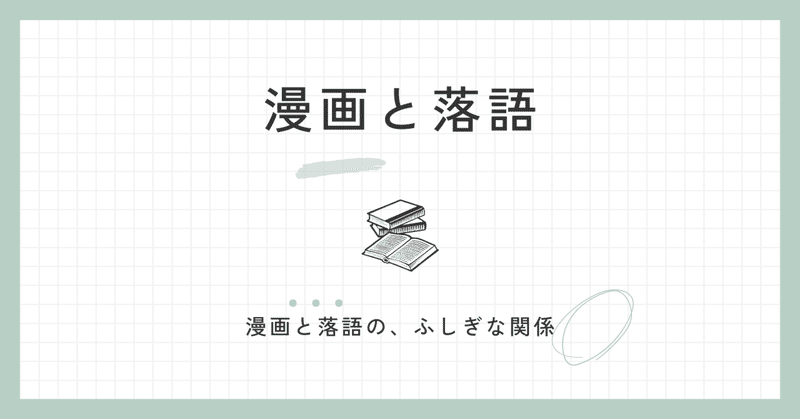
漫画と落語:田河水泡『のらくろ』 8
大正の新雑誌創刊ブーム
1925(大正14)年、日本美術学校を卒業した仲太郎は26歳になっていた。卒業後はグラフィック・デザイナーとして身を立てようと考えていたが、実績のない状態では、そうそう仕事があるわけではない。商店街の看板や街頭装飾の仕事を請け負うことはあったようだが、季節によって案件の数にバラつきがあり、定期的な収入が得られるものではなかった。
とにかく定期収入を得なければ生活が立ちゆかない。思案した挙げ句、仲太郎が目をつけたのが、雑誌での連載であった。
折しも大正後期の出版業界は、空前の雑誌創刊ブームに湧いてきた。1922(大正11)年2月には「週刊朝日」(朝日新聞社)、同年4月には「サンデー毎日」(毎日新聞社)、翌1923(大正12)年1月には「文藝春秋」(文藝春秋)と、今日まで続く雑誌が次々と産声を上げていた。
(※「週刊朝日」は2023年5月での休刊が発表されている)
この時期、とくに世間の耳目を集めたのが、1924(大正13)年11月に大日本雄辯会講談社から発行された雑誌「キング」である。同社が社運をかけて創刊した雑誌であり、その初版の印刷部数はなんと50万部であった。
大日本雄辯会講談社は書店に幟旗を提供したり、コマーシャルソングをつくったり、ちんどん屋を活用したりと、あの手この手のマーチャンダイズを行い、創刊号は増刷分を含めて合計74万部を売り上げたのである。幟旗を宣伝に用いたのは、このときが本邦初とされる。
「キング」で有名になった作家の代表格といえば吉川英治だ。吉川は雑誌「講談倶楽部」(大日本雄辯会講談社)に投稿した懸賞小説『江ノ島物語』が三等に入選(筆名は「吉川雉子郎)して以降、様々な筆名であらゆる雑誌に作品を書いてきたが、いまひとつ確たる人気を得てはいなかった。
だが、「キング」創刊号から連載を開始した『剣難女難』(大正14年1月号~大正15年9月号掲載)で人気を得る。「吉川英治」のペンネームを用いたのは、この作品からであった。その後、大阪毎日新聞での連載『鳴門秘帖』(1926年8月11日~翌年10月14日)で大ブレイクし、あっという間にスター作家の仲間入りを果たすのであった。
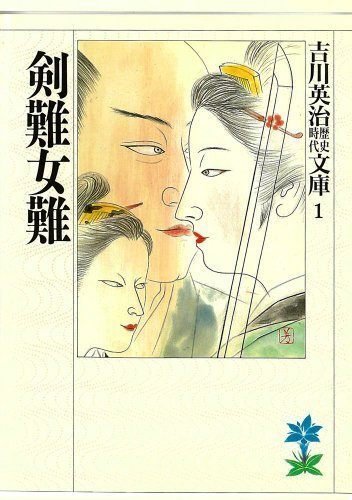
新作落語はブルーオーシャン?
流行に敏感な仲太郎は、商業雑誌のトレンドを嗅ぎ分けていた。定期刊行物に連載を持てば、定期収入が得られる。
だが、何を書けばいいのか。
二番煎じでは、自分が入り込む隙はない。雑誌を読む仲太郎は、ふと、あることに気づいた。雑誌には講談や落語といった大衆演芸の読み物が掲載されているが、既存の古典をそのまま掲載しているか、速記ものばかりで、新作は載っていない。
落語の新作なら、もしかしたら需要があるかもしれない。
下町育ちの仲太郎にとって、いわゆるベランメエ調の落語口調や、落語の世界観は慣れ親しんだものである。むしろ仲太郎自身が、落語世界の住人のような人物だ。誰も書いていない新作であれば、あるいは……。
かくして仲太郎は新作落語を執筆し、出版社に原稿を持ち込むことを決めた。持ち込み先は、大日本雄辯会講談社である。
落語作家・高澤路亭の誕生
受付に預けられた「高見澤路直」名義の原稿を目にしたのは、雑誌「面白倶楽部」の中島民千編集長であった。中島はかつて無名時代の吉川英治を見出した敏腕編集者である。原稿を一読した中島は、すぐさま仲太郎に巻紙に毛筆で書いた手紙を送り、面会の約束を取りつけた。
MAVOを主催した村山和義は、自著『演劇的自叙伝』のなかで、この当時の仲太郎の外見について以下のように記している。『のらくろ一代記』からの孫引きになる点はご了承いただきたい。
私より一つ年上だが、今のヒッピー族ソックリに、長髪を真ん中から分けて、左右に、肩の近くまでたらし、それをしょっ中、かきわけて顔を出していた。彼は五反田の駅近くの物置のような所に住んでおり、呑み助で、朝、私が例の三角のアトリエの窓をあけると、その下に積んである土管の中から、目をさまして起きて来たものだ。いつも汚いルパシカを着ていた。
中島編集長は面会に来た仲太郎を、作家の使い走りと勘違いし、「ああいうものを書く人を待望していました。来月も書いていただけるよう、お作りになる方によろしくお願いしてください」と言付けたという。だが、仲太郎は、「書いたのは私です」と言う。
それがかえって中島の興味を惹いたのかもしれない。そもそも実演者ではない者が、新作の落語を“読み物として”書くということが目新しかった。
実演を目的としない、読み物としての落語。
かつて講談は、速記本から「書き講談」となり、やがて講談を下敷きとしない時代劇小説(歴史小説)へと発展していった。そうした新しい文化の萌芽を、仲太郎の「書き落語」に感じ取ったのかもしれない。
いずれにせよ、中島はこの原稿を自分の雑誌「面白倶楽部」に掲載することに決めた。ただ、「高見澤路直」というペンネームは、あまり落語作家らしくない。そこで編集部は、「高見澤路直」の名から「高澤路亭」という落語家っぽい雰囲気の筆名を考案するのであった。
かくして1926(大正15)年、「面白倶楽部」6月号に高澤路亭の新作落語「一夜学問」が掲載され、高澤路亭は落語作家としてデビューを果たすのであった。
高澤路亭の活躍
高澤路亭がデビューした「面白倶楽部」に先立ち、大日本雄辯会講談社には「講談倶楽部」という雑誌があった。
1911(明治44)年に創刊された「講談倶楽部」は、当初は講談の速記を掲載していたが、のち「書き講談(「新講談」の名称を用いた)」へとシフトしていた。この「講談倶楽部」のヒットを背景に、1915(大正4)年、姉妹誌として創刊されたのが「面白倶楽部」である。
編集長の中島民千が高澤路亭の原稿を「面白倶楽部」に掲載し続けたのは、こうした講談の流れを踏まえて、落語もやがて速記から「書き落語」へと移行していくと見越してのものだったとも推測できる。
高澤路亭の新作落語は好評を博し、やがて「講談倶楽部」にも新作が掲載されるようになる。「講談倶楽部」には、高澤路亭以外の新作落語も掲載しており、そのなかに今村信雄がいた。
今村信雄の父・今村次郎は、落語や講談の速記者であり、落語研究会(紆余曲折を経て現在はTBS落語研究会に)の創始者のひとり。「講談倶楽部」が速記から「書き講談」に舵を切った際には、今村次郎との確執があったとも伝えられている。
今村信雄は父と同様に落語速記を手掛け、1924(大正13)年には三代目神田伯山の『清水次郎長伝』を武俠社から出版していた。現在でも口演される演目「試し酒」は、今村信雄による創作とされる。
なお、「試し酒」は明治期の外国人落語家・初代快楽亭ブラックの「英国の落し噺」(「ビールの賭け飲み」とも)を下敷きにしているともいわれており、のちに七代目三笑亭可楽の手を経て、現代まで伝えられている。やはり作品というのは、書き手と読み手だけでなく、広める者がいなければ後世にまで残ることはない。
高澤路亭が落語作家としてデビューした翌年の1927(昭和2)年、高澤路亭は「面白倶楽部」や「講談倶楽部」に加え、「キング」にも新作落語を書くようになる。この年の新年号で「キング」は120万部を発行し、日本の雑誌史上はじめて100万部を突破した。日本最高のマンモス雑誌にもフックアップされた高澤路亭は、当代一の人気落語作家といえた。
高澤路亭の代表作といえば、やはり「猫と金魚」(雑誌初出時の原題は「濡れ鼠」)だろう。商家の大旦那が、金魚鉢を猫から狙われないような場所に移すよう、番頭に命じるだけの会話だけで成立する噺だが、大旦那に対する番頭の受け答えのナンセンスさが光る。
この噺を気に入った初代柳家権太楼は、実演させて欲しいと路亭に願い出て高座にかけるようになり、のちにはレコードも発売された。
「猫と金魚」はもともと短い噺なうえに、大旦那と番頭のやり取りを増やしたり減らしたりすることで時間調節ができ、寄席で重宝された。
実演を目的とせずに創作された「書き落語」が、落語家によって実演され、さらに演者から演者へと伝えられていったのである。およそ100年経った現在でも「猫と金魚」は多くの落語家に口演されており、もはや「古典」と言っても差し支えない噺となった。

昭和51年刊行の『田河水泡新作落語集』田河水泡(講談社)
古典と新作の違い
ここで落語の「古典」と「新作」について触れておきたい。
落語の演目には「古典」と「新作」がある。だが、明確な区分基準が設けられているわけではない。大雑把なイメージとしては「古典=昔から口伝されてきた(作者不明の)噺」「新作=あらたに創作した噺」なのだが、これだけでは正確性に欠ける。
たとえば立川志の輔の「みどりの窓口」は、JRの乗車券発券所(みどりの窓口)と居酒屋を舞台に物語が展開する噺だ。創作者がはっきりしていて、現代を題材にしているから、「新作」に分類するのは容易だ。
しかし、創作者が判明していても、古典に分類される噺もある。たとえば「真景累ヶ淵」や「牡丹灯籠」「文七元結」などがそうだ。これらは明治期に三遊亭圓朝が創作した噺である。また、高澤路亭の「猫と金魚」や今村信雄の「試し酒」も、現在では古典として扱われることが多い。
つまり、創作者と創作年代は、かならずしも「新作」「古典」を区分する要因とは限らないことになる。
では、噺の内容についてはどうか。
JRの「みどりの窓口」が出てくれば現代が舞台であることがわかるし、「古典ではない(=新作)」ことは明白だ。
一方で「真景累ヶ淵」「牡丹灯籠」「文七元結」などは江戸時代が舞台であり、古典らしい雰囲気をまとう。しかしながら、先述のとおり、これらの噺が創作されたのは明治期だ。江戸時代にリアルタイムで創られた噺ではない。はじめから「昔の出来事」として作話されたわけである。
落語には、江戸時代の庶民生活をベースとする「落語的世界観」のようなものが存在する。落語の創作者たちは、その世界の舞台設定や人物設定を共有し、それを利用して二次創作的に新作を創っていったわけだ。
つまり「創作されてから年数が経過した(=古くなった)から古典、新しいから新作」ということでもない。
だから古典落語とは、和菓子における苺大福のようなものだ。苺も大福も大昔からあるから、和菓子の定番商品と思い込みがちだが、実は1980年代のブームで定番化した。あんころ餅や大福と比べれば、はるか最近に定着したものなのだが、「昔からあるもの」と思い込みやすい。消費者が「定番として受け入れた」のが苺大福である。
突き詰めれば、落語の演目がいつ「古典」になるかといえば、それは観客が「古典として受け入れた瞬間」と言うしかない。強いて言うなら、創作者以外に演者がいるかどうかの差でしかないように思われる。
落語の世界は杓子定規で測れるものではなく、その曖昧さを許容するものであり、「演者本人が作ったものは新作、他人が作ったものは古典」くらいのアバウトさでいいのかもしれない。
いずれにせよ、高澤路亭の「新作」は、読者や観客から「古典として受け入れられる」だけのポテンシャルを秘めた噺だったのである。
よろしければサポートのほど、よろしくお願いします。
