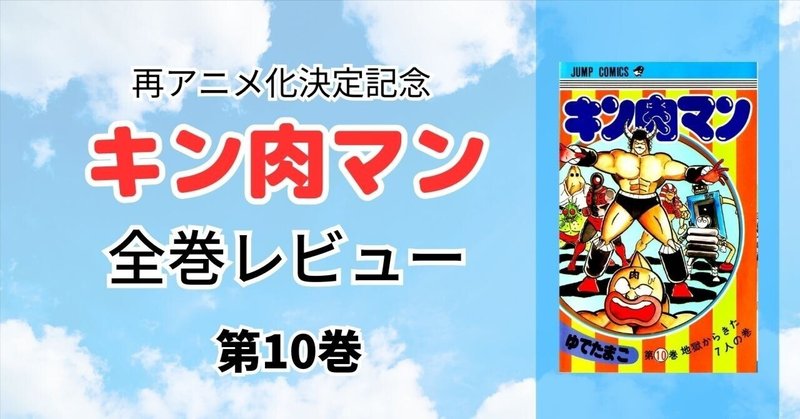
第10巻:地獄からきた7人の巻
第10巻データ・アナリティクス
「7人の悪魔超人編」の開幕

「掲載順=人気」とは一概に言えないが、人気を測るバロメータのひとつとして参照する。
1号あたりの漫画作品の掲載本数は16〜19本。
単行本10巻の発行日は1982年10月15日。
第8巻や第9巻の掲載順に比べると中位が目立つようになり、一時期の低迷を脱した感のある第10巻。「少年ジャンプ」45〜47号では新連載攻勢が続き、それが一段落した49号からの掲載順は、前巻収録分と比較すると明らかに向上している。そのことからも前シリーズの「超人オリンピック ザ・ビッグファイト編」の評判が上々だった様子がうかがえる。
第10巻冒頭の「地獄からきた7人の巻」が掲載されたのは1981年45号(10月19日発行)。ここから「7人の悪魔超人編」がスタートして『キン肉マン』人気が不動のものとなるのだが、シリーズ開幕当初の掲載順はまだブレイク前夜、といった様相。これがどのように変化していくのか見守っていくうえで、そのパースペクティブの起点として上記の掲載順を記憶しておきたい。
第10巻収録話の連載期間の出来事
1982年3・4合併号から『風魔の小次郎』(車田正美)の連載が開始する。前作『リングにかけろ』の終了から中11号での新作スタートであり、3・4合併号、5号、6号と3号連続で巻頭カラー。6号では表紙も飾っており、編集部からの熱い期待が感じられる。
なお、3・4合併号には「Dr.SlumpオリジナルCalender1982 保存版」が付録でついており、『Dr.スランプ』人気がまったく衰えていないことがわかる。
正義超人と悪魔超人の団体抗争
シリーズの概略
新シリーズが開幕すると③対象物、④友人、⑤好敵手、⑥トリックスターのセットが更新されるので、ここでは「7人の悪魔超人編」におけるロールを確認しておきたい。
①主人公は変わらずキン肉マン、③対象物はバラバラにされたミートくん、④友人はテリーマンとアイドル超人軍団(ロビンマスク、ウォーズマン、ブロッケンJr.、ウルフマン)、⑤好敵手はバッファローマンと悪魔超人軍団、⑥トリックスターは救世主(モンゴルマン)、となる。
悪魔超人の行動原理は「地獄からきた7人の巻」で語られるように、「われわれをたおさずにチャンピオンを名のることはゆるさん!!」であり、その目的は「キン肉マンに挑戦すること」。彼らは「悪魔」ではあるが、地球侵略や人類支配などは眼中になく、それゆえにプロレス・ルールを守って戦う。このあたりが『キン肉マン』という作品のユニークな点だ。そして、目的達成(=キン肉マンと戦う)のためにミートくんをバラバラにし、それを争奪の対象としている。
④友人に関しては、まずテリーマンが挙げられる。「キン肉マン参上!!の巻」でテリーマンはキン肉マンのマスクをかぶって登場し、キン肉マンのかわりにブラックホールと戦おうとするのだが、これは第6巻のレビューで述べた「友人の擬似主人公的な役割」の典型的な例である。このシリーズではロビンマスク、ウォーズマン、ブロッケンJr.、ウルフマンが同様にキン肉マンに代わって悪魔超人軍団と戦うのだが、その先鞭をつけるのがテリーマンであり、④友人のなかでも特別な存在であることが浮き彫りになっている。
アイドル超人軍団のなかでは、ブロッケンJr.だけがキン肉マンと対戦経験がないのが興味深い。作品に登場する順番としてはウルフマンより前だが、やはり主人公との対戦経験の有無が、読者の印象として「経験不足」と映るのだろう。次シリーズで味方になるジェロニモ(やはりキン肉マンとの対戦実績なし)と同様、ブロッケンJr.はアイドル超人軍団のなかではグリーンボーイとして扱われるが、キン肉マンとの対戦経験が大きな判断材料になっているように思われる。
なお、アイドル超人軍団のなかに、しれっとロビンマスクがいることが大きな驚きであった。キン肉マンへの復讐心にとらわれ、ウォーズマンのマネージャー・バラクーダとして前シリーズで暴れ回り、それでいてウォーズマンとは違い、キン肉マンと心を通わすシークエンスは描かれていない。第9巻ラスト「超人オリンピック総集編の巻」では、「第1回、第2回超人オリンピックをふりかえって……」のコーナーで、ロビンマスクは次のようにコメントしている。
チッ あのウォーズマンのうすのろ野郎 これで奴との師弟関係もご破算 この次はオレ自身がキン肉マンをたおしてやる!!
ところが本シリーズでは、とくに説明もないままにアイドル超人軍団のひとりとしてキン肉マンの味方になっているので、物語的な整合性が取れていない。のちの展開を知っていれば、「その間にいろいろあったのだろう」と行間を読むことができるが、初見時には唐突感は否めない。
この時期の『キン肉マン』は、内容的にはすでにストーリー漫画になっているが、1話あたりの基本ページ数は13ページのままなので、ロビンマスクの心理的な葛藤を丁寧に描くことに紙幅を割くよりは、ストーリーのテンポ感を重視して省略したのだろう。というより、省略せざるをえなかったものと推察される。
「ツッコむ側」から「ツッコまれる側」への変化

「地獄からきた7人の巻」では7人の悪魔超人が登場するのだが、初出時(第10巻P.19)では7人、同一エピソード内の二度目の登場時(第10巻P.20)では8人が描かれており、それぞれメンバーの顔ぶれが異なっているうえに、のちに確定する正式メンバーとも異なっている。
ここで描かれる「7人」と「8人」は、次回「さけたミート!!の巻」のトビラで紹介されている読者考案の超人なので、それを参照に各超人を確認しておきたい。
初出時の7人はバッファローマン、ブラックホール、スプリングマン、アトランティス、プリプリマン、ミスターアメリカン、アームストロングの。このうちプリプリマンのみ読者投稿ではないキャラクターで、後世に作者が名前を明かした。
二度目の8人はバッファローマン、ブラックホール、スプリングマン、アトランティス、フラッシャーバルーン、クモのコチラス、ミリオン・ヘル、ダークII世(?)。
両方に共通するのはバッファローマン、ブラックホール、スプリングマン、アトランティス。この4人は早い段階から確定していたようだが、あとのメンバーは連載中に徐々に固まっていく。最終的に全7人のメンバーが確定するのは「役者がそろった!!の巻」で、最後にミスターカーメンが登場。シリーズ第10回目にして、ようやく敵メンバー全員が判明する。
この回のラストにはアイドル超人軍団が駆けつけるので、サブタイトルの「役者がそろった!!の巻」はキン肉マンの味方が出揃ったことを意味しているような印象を抱きがちだ。だが、実際は悪魔超人サイドもこの回ではじめて全員集合しているので、両陣営の役者が初顔合わせすることを同時に意味している。
7人の悪魔超人の顔ぶれのように設定がコロコロと変わるのは、おなじみのツッコミどころとして『キン肉マン』ファンのあいだでは有名だ。連載時の勢いを重視するスタンス込みでファンは本作品を愛しており、こうした「勇み足」的な部分は新装版でも修正されていないし、望まれてもいない。
ただ、指摘しておきたいのは、それまで『キン肉マン』はギャグ漫画として、世の中で起きた出来事や事件をパロディとして作中に取り込んできた作品であり、いわば「ツッコむ側」であった。それに対し、本シリーズ以降は読者から「ツッコまれる側」となることが多くなる。それは本作がギャグ漫画からストーリー漫画に転じたからである。

時代が求めた「団体抗争」
この「7人の悪魔超人編」は正義超人vs悪魔超人の団体対抗戦となる。「アメリカ遠征編」で団体抗争は不評だったが、3団体の抗争でわかりづらかった反省点を活かし、今シリーズでは「正義vs悪魔」のシンプルな構図に落とし込んでいる。
それにしても、なぜ作者は再び団体対抗戦をやることにしたのか。
この年(1981年)、日本のプロレス界は大きな転換点を迎えていた。というのも、夏に国際プロレスが活動停止を発表し、日本マット界は全日本プロレスと新日本プロレスだけになってしまっていた。
両団体による引き抜き合戦など、きな臭い事件が続くなか、国際プロレスに所属していたレスラーはそれぞれ移籍先を模索し、ラッシャー木村、アニマル浜口、寺西勇の3人は「はぐれ国際軍団」として新日本プロレスのリングに上がることを決める。
9月23日には、新日本プロレスの田園コロシアム大会のメインイベント前に会場に割って入り、10月8日の蔵前国技館で「新日本vs国際」の対抗戦をアピールした。このときラッシャー木村が律儀に「こんばんは」と挨拶をして会場の失笑を買う珍事(「こんばんは」事件)が起こるわけだが、かくして10月8日の新日本プロレスの蔵前大会は「新日本 - 国際対抗戦 創立10周年記念興行第3弾」と銘打つことになり、「アントニオ猪木vsラッシャー木村」「藤波辰巳vs寺西勇」「剛竜馬vsアニマル浜口」のカードが組まれた。
なお、第9巻のレビューで前述した「敗者マスク剥ぎデスマッチ(タイガーマスクvsマスク・ド・ハリケーン)」が行われたのも、この大会である。
こうした流れを受けて「時代が団体抗争を求めている」と判断した……と考えるのが妥当だろう。
事実、水面下では馬場と猪木が密談しており、1982年6月16日付の東京スポーツには「夢の8.26オールスター戦、再び実現へ!」の見出しが踊った。「夢の8.26オールスター戦」とは、第2巻のレビューでも触れた「プロレス夢のオールスター」(1979年8月26日開催)のことである。
それだけにとどまらず、後世の複数人の証言によると、「日本プロレス統一コミッション」構想まで立ち上がっていたという。しかし、同紙7月9日付の紙面ではオールスター戦の開催断念が報じられ、さらに翌年には新日本プロレスでクーデター騒動があり、諸々のプランが立ち消えになってしまった。
ともあれ、こうした動きは当時は明るみになることはなかったものの、世間の風潮として「対抗戦待望論」が持ち上がっていたのは事実である。ゆでたまごの嗅覚は、こうした時代の空気感を鋭敏に察知していたのだ。
UFO発着所とは?
正義超人vs悪魔超人の団体対抗戦は、全国5カ所で同時に開催された。「ウルフマンvsスプリングマン」戦は鳥取砂丘、「ブロッケンJr. VSミスターカーメン」戦は北海道UFO発着所、「ロビンマスクvsアトランティス」戦は上野不忍池、「テリーマンvsザ・魔雲天」戦は秩父連山、「ウォーズマンvsバッファローマン」戦は田園コロシアム(東京都大田区)の5会場。
そしてシネマスコープで有名だった銀座の映画館「テアトル東京」(1981年10月31日閉館)にてクローズドサーキット(現在のパブリックビューイング)の5元中継された。作中では、かつて存在したテアトル東京の王子卯の姿が描かれており、後楽園球場、旧国立競技場、田園コロシアム、蔵前国技館、有楽町日劇などと並び、かつて存在した名所が作中で確認できる。こうした“ありし日の名所巡り”ができるところも、旧シリーズを読み返す際の楽しみのひとつである。
この5会場のなかで、かなり異色に感じるのが「ブロッケンJr. VSミスターカーメン」戦の会場となった北海道UFO発着所である。これは北海道沙流郡平取町に実在した施設だ。
厳密には、日本でも最古の部類に入るUFO研究団体「宇宙友好協会」(1957年設立)が1964年から建設を開始し、1067年に完成させた記念公園「ハヨピラ」のこと。この場所は、アイヌに様々な生活の方法を教えた文化神「オキクルミカムイ」が降臨した地とされ、オキクルミカムイを宇宙人と同一視する宇宙友好協会が、ピラミッド型の祭壇やUFO発着所を備えた公園を整備したのである。
宇宙友好協会は、のちに団体の運営に行き詰まると、この地を平取町に寄贈した。平取町は「ハヨピラ自然公園」としたものの、2003年に崩落の危機があるとして閉鎖されるのであった。
UFOとコンタクトを取るUFOコンタクティーとしては、アメリカのジョージ・ヴァン・タッセルが有名で、彼は宇宙船を呼ぶ際に「ベントラ、ベントラ、スペースピープル」との呪文を唱えた。それを日本に紹介したのが、宇宙友好協会だったとされる。
なお、『うる星やつら』(高橋留美子)の「【PART3】悲しき雨音」の回(「少年サンデー」1978年41号掲載/第1巻収録)では、宇宙に帰ったラムを懐かしむあたるの同級生たちが「ラムちゃんを地球に呼ぶ会」を結成し、学校の屋上で手をつないで輪をつくり、「そして心の中でベントラベントラスペースピープルと唱えるのだ!!」と、UFOを呼び寄せる方法を説明している。70年代のオカルトブームを通じて、気鋭のギャグ漫画のネタにされるほどに「ベントラ」の呪文は広く知られていたようだ。
それにしても、ミスターカーメンとの試合場がなぜUFO発着所になったのかは不明だが、「7人の悪魔超人編」はアトランティス、ブラックホール、ミイラ(ミスターカーメン)、ピラミッドパワー、UFO発着所と、70〜80年代に大流行したオカルトブームのエッセンスが凝縮されたシリーズであったともいえる。
よろしければサポートのほど、よろしくお願いします。
