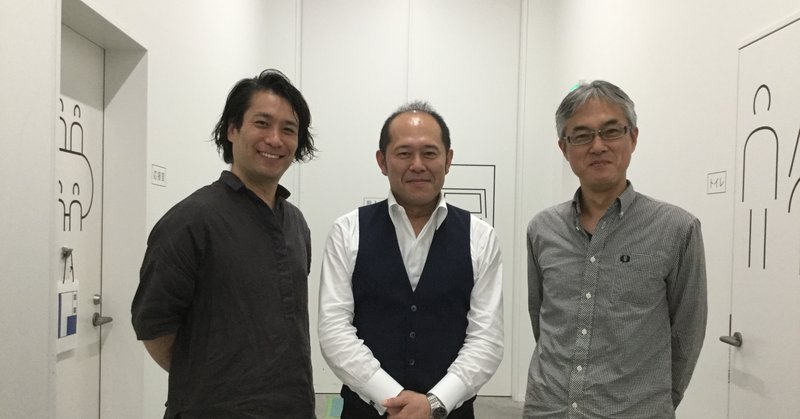
6年ぶりの再会〜敬愛する人に会いに松本へ
コミュニティデザイナーの山崎亮さんと長野・松本市長の臥雲義尚さんのトークイベントに参加してきました。これからの時代のまちづくりやライフスタイルについて、具体的なヒントが満載の楽しい2時間半でした。山崎さんとお目にかかったのは6年ぶり。久しぶりにゆっくりお話を聞かせていただき、山崎さんがお持ちの膨大な知識資産に改めてびっくりしました。とても楽しかった再会を祝してイベントのレポートを残しておくことにしました。まずは山崎さんご本人について、僕が改めて感じたことから。
「どらえもん?南方熊楠?宮本常一?」〜山崎亮さんの膨大な経験知と時空を超える博識ぶり
北海道から沖縄まで日本全国のまちづくりの現場に入り込んできた山崎さん。膨大な経験知に裏付けられた膨大な知識資産をお持ちです。お話を聞いているとドラえもんみたいです。どんな話題になっても、どんな質問をしても、「北海道のあの町では〜」とか、「商店街でワークショップをやったときは〜」とか、これまでの経験の引き出しの中から「なるほど〜」と思う事例を引っ張り出してきて話してくださいます。
さらにびっくりするのは、まちや暮らしに関する博識ぶりです。「町内会はGHQが解散を命じて〜」とか「中世のギルドは〜」とか、歴史を遡ったり、「イタリアに行ったときに〜」とか、「教科書に載っているんですけど、デンマークのオーフスでは〜」とか、話が世界に飛んだり、時空間の移動の仕方が縦横無尽。知識のスケールが大きいんです。
山崎さんは、個別のまちづくりの事例の意味を、歴史的な視座や世界的な視野からも位置付けてくださるので、経験知にずっしりとした重みと説得力を感じます。
山崎さんの頭と身体の中に積み上げられてきた、膨大な経験のアーカイブと歴史を遡り世界を見渡す膨大な知識。今の日本できっと唯一無二の存在だと改めて感じました。「在野の大学者と言われた南方熊楠さんって、山崎さんみたいな人だったのかなあ」と想像しました。
そのわりには威圧感はまったくありません。どちらかというと子どもと話しているのに近い感覚です(山崎さん、すみません、、)。もちろん山崎さんはたくさんの人びとの暮らしが幸せになるように願っています。だけど、ひょっとすると、それ以上に、素朴な好奇心で日本全国を歩いてめぐっているのではないか。こんなにも旅(=コミュニティデザインしながら)をしたり、人に会ったり話を聞いたり、論文や本を調べたり書いたり、大学院で教えたりしているのも素朴な好奇心がエネルギー源なのでは、と感じました。
そして前職で仕事をご一緒させていただいたときもそうでしたが、きょうもダボっとしたショーツにサンダル姿でした。「僕、歩くのが好きなんですよ。いやあ、なんか歩いちゃんですよね〜。タクシーはどうも、、、」と言って、待ち合わせ場所まで歩いていらっしゃいました。サンダル姿の山崎さんと松本の町を歩いた感覚を思い出し、日本全国を自分の足で歩き回った民俗学者の宮本常一さんって、こんな感じの方だったのかなぁとも感じました。
では、イベントでしてくださったお話を3つのテーマに絞ってご紹介します。
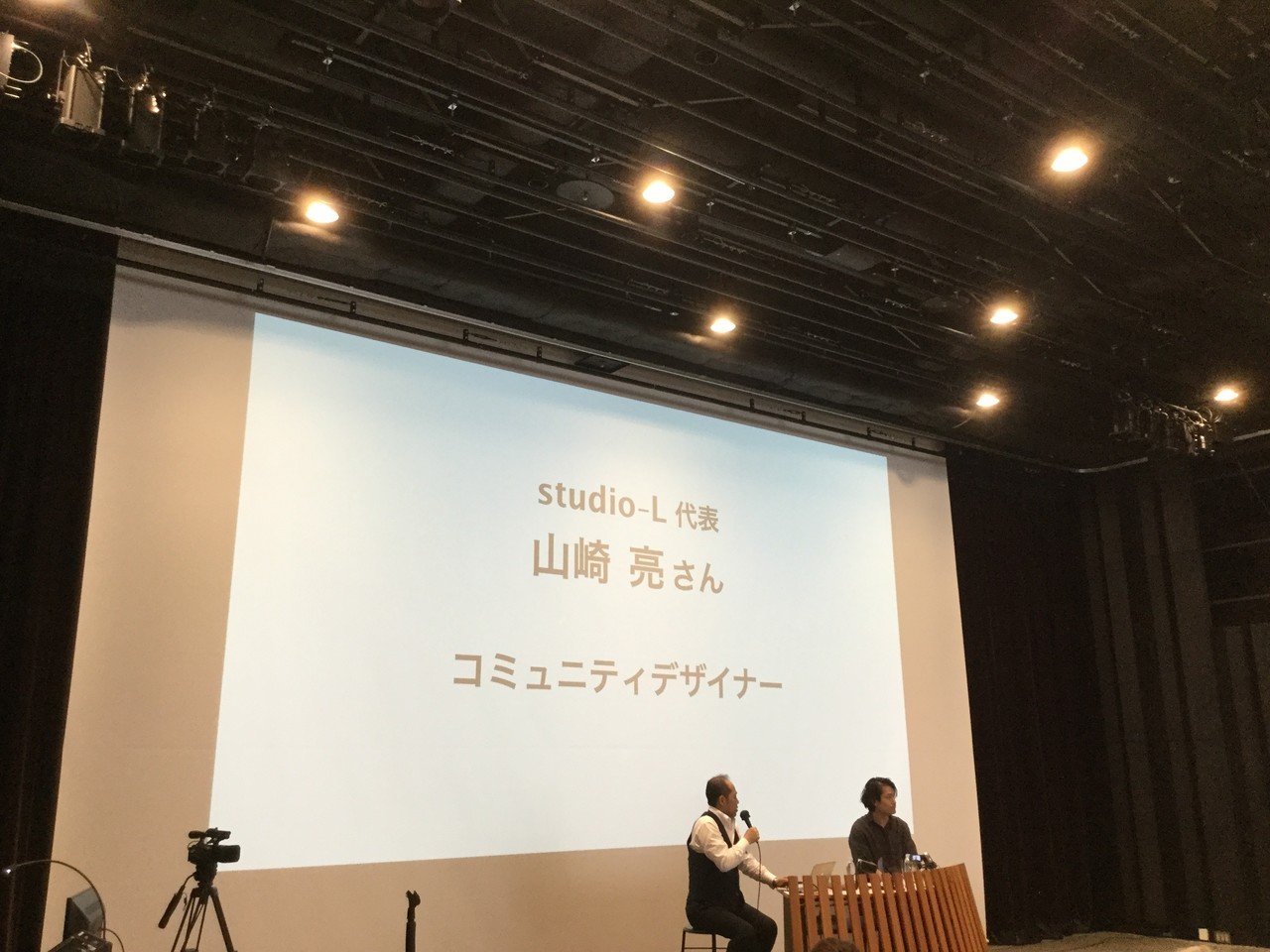
身のまわりを美しく。家の中を美しく
今ずっと家にいます。こうなって、住宅の設計のありかた、家の快適さをもう一度みんなが考えなければならないと思うようになりました。その意味では、民藝やクラフトなど、手仕事で身のまわりのものを整えていた町は強い。北欧と松本は近いという感覚があります。この職人の手仕事と身のまわりのものという歴史をたどると(19世紀後半にイギリスで起きた)アーツ・アンド・クラフツ運動に行き着きます。産業革命で機械による大量生産により、美しくないものをつくる社会、仕事が楽しくなくなる社会になったとき、アーツ・アンド・クラフツ運動は起きました。(1920年代に起きた日本の)民藝運動は直接、アーツ・アンド・クラフツ運動の影響を受けたわけではありませんが、(この2つの運動に挟まれた)時差の中に、北欧で同じような運動がありました。北欧は冬が長く夜が長い。室内を美しくしないと精神を病んでしまう人が増えます。そこでエレン・ケイやカール・ラーションといった人たちが美しい室内の絵を描き、インテリアを大事にという意識が広がりました。IKEAの創業者にも室内を美しいものにという思想がありました。アーツ・アンド・クラフツ運動、北欧(の室内の装飾)、民藝運動にみられるような、美しいものを身のまわりに置いて普段づかいしましょうという動き。かつての日本にいくつかの情報発信拠点があり、そのひとつが丸山太郎がいた松本でした。製品の品質の高さから流通に至るまで、手仕事でつくるモノの生態系を持っているのが松本だと思います。
デジタル社会教育で95歳のYouTuberを
今、オフラインのワークショップが増えていますが、オンラインのワークショップとどちらがいいということはないですね。それぞれよい点とよくない点があります。
オンラインのワークショップでは、親密な関係性をつくり、笑顔でなんでもしゃべれる空間をつくろうと、あえて「三密」を作っていました。仲間をつくれたり、アイデアを出せたり、実際に会えるメリットもあった。ただ、実空間でワークショップを開くと、参加できない人もいます。たまたま出張でいないとか、遠くにいるけれども松本を応援したいという人の意見が入らないし、反映もされなかった。せっかく仲間になりそうな人を排除してしまっていた。でもオンラインだと東京、大阪どこからでも参加できる。一方で、オンラインのデメリットもあります。どうアクセスしていいかわからない人は排除されます。今はどちらのワークショップをやったほうがいいのか、合わせ技でやったほうがいいのか、判断できるようになりました。
デジタル技術は、電気ガス水道と同じくらい大切なインフラです。水道は蛇口をひねれば、電気はコンセントに差し込めばどうなってそれをどう使いたいか、自分たちはわかっています。でも、Wi-Fiや5G、有線LANのことはまだ水道の蛇口ほどにはわからない。でも使い手側がちゃんと学べばわかります。Zoomでおじいちゃんおばあちゃんが100人くらいでお茶会やっている。そんなものをつくれたらおもしろいですよね。Zoomでも笑えば口角が上がります。毎日本気で笑っている人は健康寿命が伸びるそうです。テレビでお笑い番組を見て心の中では笑っていても、ひとりだと表情が動いていない。脳は感じていても表情筋が動いていない。オンラインだと人々と家の中にいて、つながることができる。フレイル予防にZoomを使う。Zoomを使うと何ができるか、みなさんがわかっていれば健康で豊かになるものに変わっていくかもしれません。
1930年代に、当時の中華民国で、晏陽初という人が農村で識字率を高める運動を展開しました。農家の生産性を高めるためには収穫量の計算や文字の読み書きができないと、という考えから始まったもので「平民教育運動」と呼ばれていました。重要な点は、たくさんある漢字の中でふだんよく使う1000文字使えるようにしようとしたこと。そのうえで、文字を読めるようになった人は隣村に教えてくださいとしたことです。そうすると喜んで教える。教えに行くとなるともっと勉強しないといけなくなる。さらに隣村の人はその隣村に教えに行かないといけないということにして、なかなか盛り上がったんです。それから100年近く経ち、2020年になり、今でいう識字率はZoomって何?ミューラルって何?リモでこっそり話そうというものです。パソコン画面でできることはいっぱいあります。僕らの生活で5個くらい大事なオンラインツールを教えてもらって、どこがわかりやすいか、わかりにくいかをつかんで、その人がまた紹介していく。そのうち80歳で起業する、95歳のYouTuberが松本で有名になるなんてなったらおもしろいですね。こういう社会教育は5年くらいで大きな成果をもたらすのではないかと思います。
地域の人が若者を全力で応援する
今、インターネットの活用方法にたけた人であれば、日本全国どこでも相当、情報を得られます。過疎と過密という二項対立ではない、適切な疎という意味の「適疎」という言葉を2010年くらいに本に書きました。これはあくまでも自分にとって「適切に疎」という意味です。東京にとって適切な疎は、松本かもしれないし、千葉かもしれない。福岡から見れば大分かもしれないし、あくまでも相対的な概念です。みなさんひとりひとりにとって適切な疎とはどんなものか、という考え方です。
20世紀は仕事を用意するからこの町に来てくださいと言えた時代でした。でも今は平均23.5年で50%の会社がつぶれると言われます。先を読めない時代を生きているんです。仕事を用意したからこの町に来てくださいと言っても、20代で来たら、40歳〜50歳で仕事がなくなることもある。
一方で、小さく起業したいと思っている若者はたくさんいます。その起業をサポートする市民の気持ちを醸成するのが大事です。若者は、まわりの人たちに「一年以内に倒産するぞ」と言われてあきらめます。でも地域の人たちが本気で応援するなら続きます。それが(まちの)寛容性です。たとえば若者がカフェをつくったら地域の全員が店に行き応援する。行動を変容させることが若者を変えることになる。そういう機運をつくれるかどうか。事業を起こせば応援してくれるとなれば、若者は「この町はめちゃめちゃ応援してくれる」とSNSで発信します。そうすると続いて若い人が来る。地域の人は若者が来たらめちゃくちゃ喜んだほうがいいです。この人たちに老後が支えられると理解して祝福し、お金をつかう。重要なのは地域の人の意識と具体的な態度です。自分たちが地域に払ったお金は乗数効果でずっとつながっていきますから。
以上、イベントでのお話も一部ご紹介しましたが、山崎さんの言葉に感じる重みと楽しさは書き言葉に移すと伝えきれません。お話をするときの山崎さんの笑顔や時々登場する関西弁、人の話を聞いているときの温かいうなづきなどを言語化できないからです。
山崎亮さんに関心のある方は、チャンスがあったら絶対に一度実物にお目にかかるのがおすすめです。もちろん本もおもしろいのですが、それとは違う穏やかであたたかいオーラを感じ取ることができますよ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
