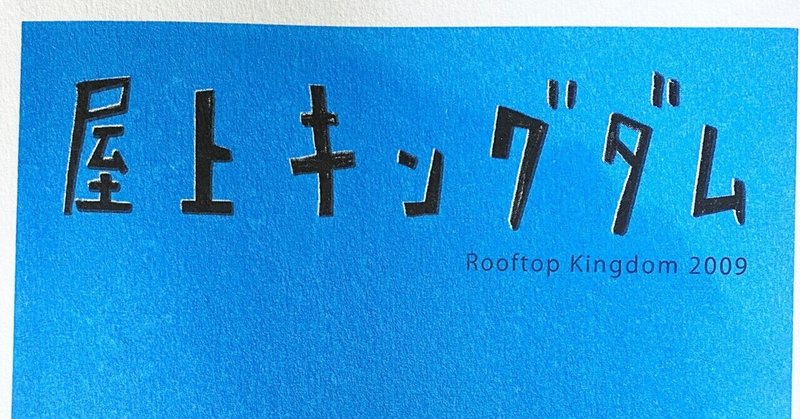
「R」
※2009年12月発行の同人誌『屋上キングダム』に掲載した小説です。(ヘッダー画像の題字は後藤グミ)
■登場人物
佐々岡貴子……猫の飼い主
山崎透…………12年前の中学生
加地眞人………獣医
◆現在(佐々岡貴子)
出窓には、猫がそこにいたくなる「なにか」が備わっているに違いない。
猫は、今日も出窓のカーテンの向こう側に座って外を眺めている。少し上を向き加減に座る後ろ姿は、物悲しそうにも、凛としているようにも見える。匂いを嗅いでいるようでもあり、瞑想しているようでもある。
「あなた、いつもいつもそうしているけど、なにが見えるの?」
私はカーテンの裾から頭を突っ込んだ。私には一瞥もくれない猫と、同じ目の高さから、同じ角度で少し上を向いてみる。この12年間で何度同じことをしたかわからない。
視線の先には、いつもの通り田舎でも都会でもない街の、くたびれたマンションが見えるだけだった。
「ヤ、ヤヤヤヤ」
そのとき猫が変な声で鳴き始めた。ささやくような、語りかけるような、あまり聞かない鳴き方だった。
「なに? その変な声。鳥かなにかいた?」
猫はその声にも反応しなかった。
どこからか吹奏楽の演奏が聞こえる。
「あら、珍しい。中学校かしら?」
私は誰に言うわけでもなく、つぶやいて出窓から離れた。
猫はまだ、変な声で鳴き続けている。
◆12年前(山崎透)
生きるとは、選ぶことだ。選ぶとは、選んだもの以外を捨てることだ。
僕は今朝、このマンションの屋上に昇ることを選んだ。それはつまり、屋上に昇ること以外の、例えば中学校の授業とか、その後の塾とか、優等生だった昨日までの自分とか、その自分に対する親の期待とか、そういうのを全部捨てたのだ。
このマンションは、僕の住む街で一番高い建物だ。1本だけスッと建っている様子が、赤くて長いブロックに似ていることから、学校では「テトリス」と呼ばれている。
いつも「あのてっぺんから街を見下ろすとどんな感じだろう」と思っていた。
でも、それを実行するのが今朝であることや学校をサボることは、家を出るまで考えもしていなかった。
いつも通り学校へ行くつもりで家を出た。学校のほうを向いて歩こうとしたとき、「ダメだ!」と思った。思ったというより、誰かに言われたような感じだった。気がつくと、学校とは反対方向に歩き出していた。生きるとは、選ぶことだ。
縁もゆかりもないマンションに入っていくことは、学校をサボるよりもずっと悪いことをしている気分だった。できるだけキョロキョロしないように、うつむきながら一直線でエレベーターに向かった。向かいながら「万引きさせられたC組の片山くんは、こんな様子で店を出たんだろうな」と、関係ないことを考えていた。
エレベーターの入口の上には1~18の数字のあとに「R」と書かれている。唯一アルファベットで表示されていることが、いかにも特別な場所という感じでかっこいい。でも行き先を指定するためのボタンは最上階の18階までしかなかった。エレベーターでは昇れないのか。ひとまず「18」のボタンを押した。
18階は、当たり前だけれど普通のマンションだった。自分が住んでいるわけでもないマンションの、最上階にいる中学生。しかも平日の午前中。誰かに会ったら、間違いなく怪しまれる。僕は屋上への階段を探した。
それは、意外と無防備に、エレベーターの脇にあった。半円を描くみたいに屋上につながっている階段を、ゆっくり踏みしめて昇った。屋外の、誰も使っていない感じの、埃っぽい階段にちょっと緊張していた。
階段の終わりには、小さなスペースと、扉があった。ここまできて……。ゆっくりと扉のノブをつかんだ。「回れ!」と強く念じて、右に回すと、回った。
扉を開けると、のっぺりとした屋上だった。
誰かの家に上がるみたいに、おずおずと屋上へ進んだ。誰もいない。当たり前なのかもしれないし、偶然なのかもしれない。
この街でいま一番高いところにいる。叫びたいような気持ちになった。晴れた朝の街を見下ろす。公園に人がいる。僕はみんなに気づいているけれど、誰も僕に気づかないことが愉快だった。
学校が見えるほうへ移動する。あそこにいるはずの僕は、ここにいる。担任の中西は、もう家に連絡しただろうか、なんて考えたけれど、どうでもいいことに思えて、考えるのをやめた。高いところと晴れた空は、いろんなことをどうでもいいことにする。
屋上は、思った以上にしっくりくる場所だった。すばらしいのは、用がない人は絶対に来ないことだ。もっとすばらしいのは、ほとんどの人は屋上に用がないことだ。
ところどころ錆びてはいるけれど、太くて頑丈そうな金網が、ここが危険で非日常的な場所であることを示していた。
のっぺりとした屋上の南側には、給水タンクがある。その脇には、給水タンクに昇るための階段があった。この屋上で唯一屋根のある場所で階段に通じる扉があった。まだ上がある。僕はその扉を開けて、階段を昇り、さらに給水タンクに昇るための鉄の梯子に手をかけた。梯子をつかんだ手がひんやりとしていた。梯子を昇りきって、給水タンクに腰をかける。
今日、ここに座ることを、選んでよかった。
給水タンクから降りて、カバンを枕にして、あお向けに寝転がってみる。誰もいないのに、気恥ずかしいのはなんでだろう。そのまま目を閉じる。
そういえば昨日の夜も、塾と宿題が終わったときには、もう午前1時だったんだ。眠いはずだよ。
気がつくと、少し太陽の角度が変わっていた。中学校の時計を見ると、11時を過ぎている。
今日は、これでいいや。屋上がどういう場所か分かったし、見下ろした街がどう見えるのかも分かった。どうせまた来ることになるし。今から学校に行けば、言い訳はどうとでもなる。選ぶことは、確かに選んだもの以外を捨てることだけれど、捨てなくて済むならそれでもいいや。僕は起き上がり、背中とお尻とつぶれたカバンを適当に払って、立ち上がる。よし、学校に行こう。
「じゃあなー」
同じクラスの浜野と別れたあと、コンビニで「サッポロポテト」と「キリンレモン」を買う。
あの日以来、塾が休みの火曜日には、欠かさず屋上に昇っている。していることと言えば、マンガを読んだり、寝転がったり、家にいるときとほとんど変わらない。ただ家の息苦しさがなくて、いい。もっと言うと親がいないから、いい。カバンにはさっき浜野からもらった『少年ジャンプ』が入っている。あとは行くだけ。
たぶん、猫? だよな。
屋上へ行こうとマンションの下の公園を歩いていると、ビャー、ビャーとしか聞こえない声で鳴いている生き物を見つけた。毛が長くて、色はグレー。子猫というには、少し大きい気もする。
ビャー、ビャーと鳴きながら近づいてきて、スニーカーの匂いを嗅いでいる。僕のことを怖がっている様子はない。どうしたらいいのか分からないまま見下ろしていると、つま先に鼻を擦りつけてきた。
両親が動物嫌いだったせいで、一度も生き物を飼ったことがない。猫をこんなに間近で見るのは、初めてかもしれない。お腹すいてるの? さっき買った「サッポロポテト」を開けて、少し考える。猫ってジャガイモなんて食べるのか? 数本を自分で噛み砕き、柔らかくしてから、スニーカーのつま先に置いてみる。猫は、フンフンと匂いを嗅いだあと、ハフッと食べた。あ、食べた。「次は?」という顔で見上げる猫を見下ろしているうちに、ふと思いついた。
「ちょっと待ってて」と、実際声に出して話しかけ、走り出す。さっきのコンビニに戻って、猫のエサの缶詰を買う。猫のエサまで売ってるんだ。コンビニって、すごい。公園に走って戻ると、猫はまだそこにいて、ゆっくり僕に近づいてくる。しゃがんで、買ってきた缶詰のフタをあけ、開けたフタで缶詰を食べやすいようにほぐす。はい、と猫の鼻先に置くと、すごい勢いで食べている。「おいしい?」と、また実際に声に出して聞いてみる。僕に見向きもしないで缶詰を食べていることが、おいしい証拠じゃないか。ゆっくりと手を伸ばして、そっと猫の背中に置いてみる。大丈夫。怒らないし、怖がらない。そのまま毛並みに沿って、背中をなでる。柔らかい。猫っ毛ってこういうことか。
一缶すっかり食べ終えた猫は、自分の口の周りを満足そうに舐めている。僕は、もう地べたにどっかりと腰をかけている。指を出すと、まず指先を嗅いでから、ザリザリと舐め始めた。猫の舌って、痛くて、全然気持ちよくないんだな。ゆっくりと両手で猫を抱えてみた。まったく嫌がる様子がない。モワモワとした長い毛の割に、意外とやせている。軽い。抱かれ慣れているのだろうか。猫は、すぐに自分で収まりのいい格好になって、ゴロゴロと喉を鳴らし始める。人懐っこいにもほどがある。
「そろそろ屋上に行くんだけど」と、懐の猫に話しかける。まったく聞こえていない様子で、気持ちよさそうに目を閉じている。寝ちゃったのか。猫を抱いたまま立ち上がる。公園の回りは、車通りの多い道で、この猫が公園から出て行かない保証はない。この猫、普段エサはどうしているのだろう。「一緒に屋上、行くか?」と聞いても、ゴロゴロというばかりだった。僕は猫を抱いて、屋上へ向かった。
名前は、もう決めている。
◆現在(加地眞人)
診察がひと段落ついて、看護士兼受付兼経理兼秘書の加奈ちゃんと、少し前に近隣のオフィス街であった飛び降り自殺のことを話しているとき、病院の扉が開く音がした。
加奈ちゃんは、怪訝そうな表情で受付のほうへ向かい、やっぱり怪訝そうな顔で戻ってきた。
「山崎さんという男性が、先生に会いたいと来られています。飼い主さんじゃないと思いますけど。私、面識のない方だったから」
山崎、誰だっけ。
「了解。待合室で待っててもらって。すぐ行くから」
山崎、山崎……。思い出せない。待合室に行くと、20代くらいの青年が座っている。
「先生、お久しぶりです」
青年は立ち上がり、礼儀正しく挨拶をしたけれど、この山崎さんはどの山崎さんだろう。よほど曖昧な顔をしていたに違いない。
「覚えていませんよね。12年前アールという猫を診てもらいました。僕は中学生で」と、ここまで聞いて「あー!」と自分でも驚くほどの声が出てしまった。加奈ちゃんが、待合室をのぞき込んだくらいだから、相当大きな声だったのだろう。
「透か!」
「はい。山崎透です。先生、変わってないですね。その節はお世話になりました。12年前のお礼をいまさら言うのもあれなんですが」
「俺はなにもしてないよ。あ、ちょっと座ってて」
立ち話であることに気づいて、彼に座るように促したあと、一度診察室に入る。
「加奈ちゃん、お茶、出してくれる?」とだけ告げて、待合室に戻る。あのときの男の子が、もうこんな立派になってんだ。俺も歳を取るわけだ。
戻ると彼が、財布を手にしている。
「あのときの代金を払いたいのですが」
「もらえるかよ。そんなの」
「でも」
「いいから、しまえって」
彼は本当に申し訳なさそうに「すみません」と言ったあと、「アールは……」と少し口ごもりながら言った。12年間、ずっと気になっていたのだろう。
「ああ、透が現われなくなって、すぐあとくらいかな。ちょうどその時期に飼っていた猫をなくした女性が、入口に貼ってた張り紙を見てな。何度か話し合って、この人なら、と里親になってもらったんだよ」
「そうですか。あのときは突然姿を消して、申し訳ありませんでした」
「いいよ。どうせのっぴきならない事情だったんだろ?」
彼の目が少し潤んだように見えたけれど、気のせいかもしれない。
「両親の事情で、急遽街を離れることになってしまって。その前にここに来て、先生とアールにはどうしても会いたかったのですが、そもそもここに来ていたことも、アールのことも親には内緒だったので、来られなかった」
「そうか。あ、アールは今でも元気だぞ。丸々として、毛もボワボワでふくろうみたいでな。貫禄あるよ。相変わらずビャーって鳴いてる」
ちょうど加奈ちゃんが、コーヒーを入れて持ってきてくれた。「ほら、佐々岡さんのところのアールくんの」と話すと、「ああ!」という顔で透を見ながら、コーヒーを渡してくれる。
「そうですか、よかった。アール、懐かしいな」と、コーヒーをすすりながら遠い目をしている透に、俺はごく素朴な疑問を投げる。
「ところで透はいま、なにやってんだ? 学生じゃないよな」
すると彼は、恥ずかしそうに、でも誇らしげに言う。
「獣医です。まだ駆け出しだけど。先生みたいになりたくて」
その言葉以上の代金はないよ、と思ったけれど、口には出さなかった。
◆12年前(加地眞人)
入口の電燈を消して、病院としての診療時間を終える。診察室で、明朝診察する猫のカルテを確認していると、病院の扉を叩く音がする。ドラマでよくある感じの乱暴な叩き方だ。酔っ払いか?
出てみると、中学生くらいだろうか。少年が今にも泣きそうな顔で、俺を見つめている。段ボール箱を抱えている。
「どうした?」
「こんな時間にすみません。猫を診てほしいんです」
少年は、必死だ。悔しそうな顔で、うつむきながら続ける。
「でも、今はお金を持っていません。今は持っていませんが、あとで必ず払いますから」
俺は代金のことには触れず、「きみの飼い猫?」とたずねる。
「家で飼っているわけじゃないけど、大切な猫なんです」
「とにかく入りなよ」
待合室の電気をつける。
猫は毛布が敷かれた段ボール箱に、うずくまっていた。
事情を聞くと、少年はできるだけ克明に状況を伝えようとする。
「アールは、1週間前に公園で拾った猫です。家では飼えないので、別の場所に連れて行ってエサをあげていました。これまでは変わった様子もなかったんだけど、きょうあげた缶詰を食べてくれなくて。ずっとうずくまったままなんです。抱き上げるとぐったりしていて。僕、どうしていいか、わからなくて。わからなくて」
話を聞きながら、猫を見る。毛ヅヤは悪くないし、衰弱しているようには見えない。耳も汚れていない。捨てられたばかりの猫か。それ以上のことは、すぐにはわからない。
「診察するよ」
診察室の扉を開けながら言うと、少年は「あ、ありがとうございます!」と頭を下げる。
診察室に入り、診察の準備をしながら聞く。
「名前は?」
「アールです」
「君は?」
「山崎透といいます」
「じゃあ透くん、アールを診察台に乗せてくれるかな」
少年はゆっくり猫を持ち上げて診察台に乗せ、心配そうに背をなでる。
診察しながら、少年にひとつひとつ気になっていることを、聞いていく。聡明な少年で、話し方も誠実だ。
「この猫、どこで飼ってた?」
少年は、一呼吸置いて「テトリスの屋上」と答える。
「テトリス、ってあのマンションの?」
「はい。僕が学校帰りに寄ったり、学校をサボったりするときに使ってたんです。両親とも動物が苦手で、家で飼うのは最初から無理だと思って」
「エサはそこで?」
「はい。給水タンクのところに、屋根も扉もあるスペースがあって、そこに寝床とトイレ、エサをあげる場所を作ってました」
「猫、何年生きるか知ってるか?」
「この前、調べました。10年から20年くらい」
「この猫はまだ1歳にもなっていない。君は家で飼えるあてがない猫を、このあと10年から20年、どうするつもりだったんだ?」
少年は、答えない。答えられない。俺は続ける。
「確かに、保護されずに公園にいたら、交通事故で死んでしまっていたかもしれない。でも、誰か家で飼える人に拾われたかもしれない。命の話に正解はない。正解はないけど、連れて帰ることを選んだのなら、それ以外を捨てる覚悟は必要なんじゃないのかな」
少年は、ハッとしたように目を見開いて、俺を見上げる。
俺が君ぐらいのとき、同じ状況に置かれても、同じようにふるまっただろうけど、と思いながら、さらに続ける。
「例えば、さっきのこの先どうするのか、という問いに『学校を辞めて働きます』という答えが返ってきたら、俺はその覚悟に反対できない。それが世間的に無謀なことであっても、だ。でもそうじゃないだろ? だったら俺は『覚悟がないまま、命を軽く扱うな』と思う」
「はい」
「例えば、通常の診察でいくと、この猫にはいまから点滴が必要だ。点滴は1回数千円かかる。詳しい病状を知るための血液検査も必要だから、さらに数千円かかる。今晩はここで様子を診たほうがいいから、宿泊してもらうことになって、さらに数千円かかる」
少年は、泣きそうな顔のまま、僕を見つめる。
「いや、お金は取らないよ。取らないけど、そういうことだよ。生き物を引き受けるってことは」
「代金は、必ず払います」
強情だ。
「じゃあ、それはわかったよ。だったら、この猫が助かったとして、そのあとどうする? 家には連れて帰れないんだろ。また屋上に戻るのか?」
答えられない少年の代わりに、俺は言う。
「俺が引き受けるよ。ただし、獣医としてではなく、友人として、だ。俺が透くんの友人として、アールに責任を持っていい里親さんを見つけてやる。ここで保護している間は、いくら会いに来てもいい。もちろんお金もいらない。どうだ?」
少年の目からは、抑え切れなかった涙が落ちる。悔し涙なのか、安堵の涙なのかはわからない。
「ありがとうございます。よろしくお願いします」
アールが来てから3週間が経つ。順調に回復してひと安心だけれど、里親候補はまだ見つかっていない。
透は、あれ以来学校が終わると毎日病院に来て、アールと遊んで帰る日々だ。その間、透とはよく話した。俺が中学3年生のときよりも、ずっと考え方が大人で、内心感心していた。
いつも決まった時間に現われる透が、今日はまだ来ていない。
宿題でも忘れて、居残りさせられているのだろうか、と思ったその日から、透が現われることはなかった。
◆12年前(佐々岡貴子)
あれ以上は、望めない最期だったことは理解できている。それでもまだ何かできたのではないか、と考えては、ふさいでしまう。
その猫は、白い発泡トレイに入った水と一緒に歩道の脇に捨てられていた。29歳、ちょうど結婚した年の冬だった。寒い日だった。
拾った当初は、目やにと鼻水がひどかった。なんとか体力が回復してくると、それにつれて、猫の表情が穏やかになっていくのがわかる。長い灰色の毛が、ふくろうを思わせた。私はその猫を「アウル(=フクロウ)」と名づけた。
アウルはそれから21年も生きて、しかも苦しまずに私のひざの上で逝ってくれた。大往生と言える。でも、それとさみしさとはまったく別のものだ。
いなくなったことを、本当に思い知るのは、なくなってしばらく経ってからだ。いるはずの場所に、いるべき存在がいない。ソファに座っても、ひざにあるべき重さがない。
別の猫を飼うことも考えたけれど、なんだかアウルに申し訳ない気がした。別の猫を飼うことが、アウルを記憶ごと捨てることのように思えてしまう。ちょっとしたことで泣けてくる。そんな日々が2ヶ月続いた。
不安定な私を見かねたのだと思う。
昨日、夫が「加地先生の病院に」と、なにげなく話し始めた。
加地動物病院は、アウルがお世話になっていた病院だ。院長の加地先生は、若くて、猫が好きで、変わり者で、よく笑う。いい加減そうだけれど、信頼できる先生だった。アウルをなくしてからは、もちろん病院には行っていない。
「加地先生の病院がどうしたの?」
「ああ、今日たまたま通りかかったら、猫の里親を探しているって貼り紙が貼ってあったよ」
「私、もう猫は」と言いかけると、夫は「まあ、先生に挨拶がてら、覗いてくれば?」と言って、のんびりと寝室に向かった。
本当に挨拶だけのつもりで、2ヶ月ぶりに加地動物病院へ向かう。散々お世話になったのだから、一度きちんとお礼をしようとは考えていた。夫の言うとおり、病院の扉には「里親募集」の貼り紙がある。「詳細は院長までお尋ねください」と書かれていて、詳しいことは書かれていない。
扉を開けると、扉の上にぶら下がっているベルが「リリン」と鳴って、来客を知らせる。
その音で診察室の扉が開いた。
「佐々岡さん!」
「先生、ご無沙汰してしまってすみません。アウルのときは、本当にお世話になりました。これ、つまらないものですが」と持ってきた菓子折りを渡す。
「そんな。あ、では、ありがたく頂戴します。いただきます」
変な遠慮をしないところがこの先生らしい。
「そうだ。ちょっと待ってていただけますか?」と、先生は、診察室の奥へ戻る。
「今、こいつの里親を探しているんですけど……」と、長い灰色の毛の子猫を抱いてきた。
「ちょっとアウルに似てませんか?」と先生は言うけれど、比べてしまうのはアウルにも、この子猫にも悪い気がして、曖昧に笑った。
「どうぞ、抱いてみてください」と先生に言われるがまま、子猫を抱く。
腕の中でゴロゴロと喉を鳴らすのを聞いて、わけのわからない涙が止まらなくなった。
先生はなにも言わずにいてくれる。
泣きはらした目で「先生、この子猫、名前はあるんですか?」と、たずねると、先生はなぜかうれしそうに答える。
「アールって言います。ローマ字の『R』。屋上の意味の『R』です。短い期間でしたが、アールは屋上に住んでいたことがあって。そういえば名前まで似てますね。アウルとアール」
「……私、少し落ち着いたらまたアールくんに会いに来てもいいでしょうか?」と言うと、先生は「もちろん」と笑う。
その後、先生と何度も話し合って、アールは私の家の敷居をまたぐことになる。
◆現在(山崎透)
病院をあとにして、街を歩く。
この空き地には、なにが建ってたんだっけ。ああ、なんか垢抜けないショッピングセンターがあった気がする。12年だもんな。街も変わるよ。それにしても先生は、全然変わっていなかった。アールも、まだ元気なんだな。よかった。
さっきから街並みは懐かしいんだけど、なんだろう、この違和感は。すべての建物や道が、記憶の中の大きさよりもこじんまりしている。僕の身体が大きくなったからだろうか。知っているけれど、知らないような変な世界に紛れ込んだみたい。
コンビニに寄って缶ビール、は我慢してペットボトルのお茶だけを買う。学生らしい店員同士が、深夜によく来る女性客の噂話をしながらレジを打つ。
アールと出会った公園を抜けて、12年ぶりにテトリスへ入っていく。
エレベーターで18階まで行き、屋上へ続く階段を昇る。
扉を開けると、そこは昔となにも変わらない屋上だった。
屋上をゆっくりと一周してから、給水タンクに座る。
あのときアールを選べなかった僕は、そのことがきっかけで獣医になろうと決めたんだ。両親には、猛反対されたけれど、もう、その程度で揺らぐような覚悟ではなかった。
この屋上から、全部始まったんだ。ペットボトルのお茶を飲み干す。
帰ろう、と思ったそのとき、どこからか吹奏楽の演奏が聞こえてきた。
(了)
そんなそんな。
