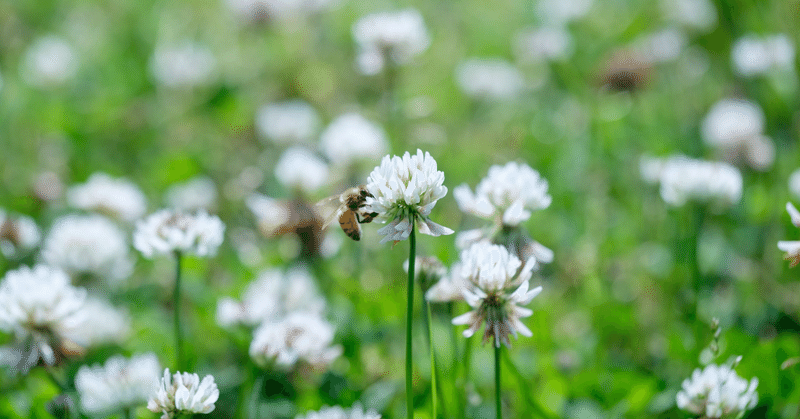
黎明の蜜蜂 (その1)
パワーポイントに向かって目を凝らし、パッドの上で無線マウスの頭をコンマ・01ミリの角度で下に押しつつ前後左右に微妙に動かしている結菜の耳にパンプスのヒールの音が響いてきた。カッカと床にあたるヒールの音に苛立ちが混じっている。
「櫻野さん」と頭上で呼ばれるまでスクリーンを凝視してマウスの操作を止めなかった。
「今朝お願いしたこと、まだやってるの」
顔を上げた結菜に二歳上の先輩、片山玲子は畳みかけてくる。
「後2ページほどで完成します」と緊張の面持ちで答える結菜の手を払うようにマウスを取り、玲子はスクリーンにカーソルを当て、せかせかとスクロール・アップとダウンを繰り返し20ページほどのスライドを見る。そして持ってきた資料を、音を立てて結菜の前に置いた。
「この資料のまとめも付け加えて頂戴。添付資料として最後に5ページくらいにまとまるようにね。2時から係りの打ち合わせがあるから。その前に目を通して修正も必要だと思うから私には遅くても一時半には渡してね。もちろんお昼ご飯はちゃんと食べてもらって大丈夫よ」
壁の時計が目に入った。午前11時半。昼ご飯抜きだ、と結菜は思った。働き方改革の流れがある中で、片山玲子はパワハラなどと言われるリスクをヘッジしているのだと結菜は思う。しかし「はい」とだけ答えた。
新しい資料にざっと目を通し、全体の分量から内容の要点をどうまとめたら5ページのスライドに収まるかを素早く構想する。緑と黄色のマーカーを手に、資料の要所要所に線を入れて行った。
隣に座って結菜の助手の立場を務める水原唯にそれを渡し、今取り掛かっているページを済ませたら、スライドをこちらに送って、添付資料に取り掛かってくれるよう頼んだ。
「緑でハイライトした部分は各ページの大項目に、その下に少しフォントを変えてインデントして黄色でハイライトしたところを書き入れてくれますか? 文の言葉の最後は整えるようにしてね」
唯は黙って受け取った資料をパラパラとめくり、結菜を見た。
「もうお昼ですけど、私ランチの約束があるんです。12時半から1時半まで外してよろしいですよね」
最後の言葉は語尾を強めて、有無を言わせぬ態勢でくる。
「では12時半までにできるところまで進めてください」
そうとしか言えない。玲子の態度も唯の態度にも正直やるせない思いがこみ上げてくるが、そんな気分に浸っている暇さえない。とにかくやり通すのだ。
唯からメールで送られてきたスライドを取り入れて、新しいスライドに取り掛かる。12時半きっかりに唯から添付資料とタイトルをつけたスライドが一枚送られてきた。唯の方を見ると既にパソコンはスリープ状態にしており、引き出しから財布などの小物を入れた小さな手提げをもってさっさと出て行った。
それにしてもあの作業内容で1時間スライド2枚足らずか、と胸の内で嘆息し時計を見ながら目を見開き作成速度を上げる。スライド全部を仕上げてから、最初から見直して気になるところに素早くチェックを入れて、もう一度各ページを開いて手直しをする。最後に再度全体を見終わったところで1時半。
「ドラフトです。ご検討お願いいたします」とメッセージをつけて片山玲子に送る。すぐに彼女の席まで来るようにという返事が来た。急いでフロアの逆側にある片山玲子のところに行く。
玲子は自分のパソコン上でスライドを繰りながら、構成がどうもね、とか、これでは論点がはっきりしないわよね、とか言いつつ、かと言ってどうしろという指示もしない。結菜は一つ一つのコメントに「はい」「はい」とうなずきつつ修正案を頭にめぐらす。
玲子は、何度もスライドを繰りなおして、結局、このスタイルは好きじゃないから色を変えて、フォントはこれじゃ駄目ね、ここは「も」じゃなく「は」でしょ、などとあまり重要とは思えない指摘をして修正を命ずる。
その指示をメモに取り、結菜は席に戻った。1時50分だ。結局玲子も時間には間に合うようにマイナーな修正にとどめたのかも、とポジティブに考えて急いで修正作業を終え、ファイルの名に完成版と括弧書きをつけ、玲子に送った。
間髪入れず、これで10部印刷して持ってきてくれという指示が来る。ファイルをコピー機に送り、右肩をホチキス止めと入力し出てきた10部をトントンと揃えているところに唯が戻ってきたので、玲子のところに持って行ってくれるよう頼む。1時半には戻ると言っていたが、あてにしていなくて良かった。
とにかく時間に間に合ってよかった。ほっとすると同時に喉の渇きを覚えた。ずっと緊張していたせいか空腹は感じない。とりあえずエレベーター・ホールの横にある自動販売機でコーヒーでも買って、たとえ5分でも一息つこう。
一台ある自動販売機の横に衝立が一つ、その先の壁と衝立の間は1メートルもないが、そこに2人掛け用サイズのベンチが置いてある。150円を入れてコーヒー、砂糖あり、クリームありを選ぶ。いつもは砂糖なしだが、とりあえずカロリーの足しにはなるかも知れない。コトンという音とともに紙コップが下りてきて、コーヒーが出来上がる。
衝立の裏に回って腰かけた。紙コップを両手で包み、一口飲む。話し声が近づき、コインを入れる音がした。同僚の田中聡美と水原唯の声だ。二人とも一般職で働いており、いつも一緒だ。結菜は立ち上がろうか迷ったが、飲み物を買うだけだろうと思ってそのままの姿勢でいた。とにかく一息つきたかったのだ。
「ね、今日も片山さんと櫻野さんのバトル見ものだったわよね」
聡美に唯が答える。
「あれはバトルとは言えないでしょう。片山さんの櫻野さんいびりと言った方が当たってるんじゃない?」
「櫻野さんが目障りってこと?」
「まあね。櫻野さんも銀行の一大イベントだからって、何も支店の営業担当が『ゆうゆう銀行再生案募集』なんかに応募することもなかったんじゃないかと思うけど。なんか突飛なアイデアだったって言うし」
「へえ、そうなんだ」
「その突飛さを役員が面白がったのかもしれないけど、ブレイン・ストーミングみたいな感じで取り上げて、それで櫻野さんを企画部に抜擢とか、私もよく分かんないわ」
唯に情報先取りされている感のある聡美も負けじと言葉を継ぐ。
「そうよね。いくら地銀だと言っても企画部はその中のエリートが集まるところだから、櫻野さんではね」
「彼女の卒業した大学って偏差値も低い地方大学なのに、一流大学を出た片山さんの出した案はボツで櫻野さんの突飛な案が何で役員賞なのって、同じ企画部の同僚として働くのはまっぴらってところなのかも」
また唯に先取りされてしまって聡美は話の矛先を少し変えた。
「私もね、片山さんが特に好きってことではないけど、何かうちの銀行も悪あがきが始まったって感じがするわ」
結菜に対するそういう空気は結菜自身も日ごろから感じている。しかし立ち聞きになっては良くないから声を掛けようか、と思ったところで二人は話しながら行ってしまった。入れ替わりのように人の気配がする。
もう席に戻ろうと立ち上がったところで、乾真一の顔が覗いた。
「あ、これは失礼!誰もいないと思って」と踵を返そうとする。
「あ、私もう行くので」
「いや、まだコーヒー残ってるじゃない。それなら僕はこちらのパイプ椅子に座るから飲んでしまって」
真一と結菜は同期だ。入行後の研修で一度だけ同じチームになったこともあって、お互い知らないわけではなかった。その後の配属先は全く違ったし、今回結菜が企画部に配属になってからも、まだ特に会話もしていなかったが同期らしく声をかけてきた。
「朝から忙しそうだったじゃない。昼飯はもうすんだの?」
「ええ、まあ。それ程お腹が空いている訳でもないし」
曖昧に答える結菜の顔を一瞬見つめて、真一はポケットからグラノラ・バーを出した。
「これ、僕が昼飯行けない時にかじるために常備しているやつ。栄養バランス満点!とか袋に書いてあるだろ?まあ、どうだか分らんけど、小腹は満たせる」
「あら、私に貰えるの?ありがと」
「今日は僕しっかり社食をお替わりまでしたからね、カロリー充填はもう済んだよ」
グラノラ・バーを受け取ってコーヒーだけ急いで飲み干し、後で頂くわと言いながら立ちあがる結菜に真一は思いついたように言った。
「あ、今日、居酒屋でちょっと集まりがあるんだ。来るのは主に行内の若手だけど、6~7人。それに高島さんが来る」
「高島さんって?」
「ああ、あの高島さん。M銀行の出世頭だった彼女、最近こっちの調査部に出向になったでしょ?」
その出来事は少なくともこちらの銀行内ではかなりの事件として噂の的になっていた。高島涼子は日本に三行しか残っていない大手都市銀行で、結菜の勤めるゆうゆう銀行の属するホールディング・カンパニーの中核でもあるM銀行にいた。しかも同年の男女合わせた中で出世頭と言われていた。しかし、40歳代初めにして関西の大店の副支店長になったところで、急に地銀でも第二地銀と言われるゆうゆう銀行の調査部に出向となったのだ。
きっと何かやらかしたんだ、と皆がひそひそ話をしたが真相は知られていない。触れると自分にも厄災が及ぶのではないかと思っているかのごとく、皆がそれについては口をつぐみ涼子を遠巻きにして眺めていた。
しかし彼女の持つ知識や物事への洞察力は抜きんでていると云うそれまでの評判は生きていて、なにか困ったことがあれば個人ベースで彼女に情報提供やアドバイスを頼みに行く者が出てきた。
高島涼子は相手がだれであっても、どんな質問にもできるだけ丁寧に答えようとする。自分の得点になる訳でもないのに、時には自分の時間を使って調べてまで情報を提供した。そういうことは結菜の耳にも入ってきている。
「この飲み会は間島先輩が始めたグループなんだ。企画部からは先輩と僕で2人。後は営業部とか他の部とかで面白そうな奴を間島先輩が一本釣りしてる。櫻野さんもどうかなって言ってたから。櫻野さんが来れるなら企画部から3人」
何の集まりなの、と結菜が聞く前に真一はもうスマホを出してラインのQRコードを差し出してきた。
「場所や時間はあとで知らせるよ」
面白そうと思ったが、急に帰宅が遅くなっても家の方は大丈夫だろうか。行けるかどうか確かめてラインするわ、と言うのがやっとで真一のQRコードを自分のスマホに読ませる。これで「友だち」登録完了。
もう本当に席に戻らなくてはならない。それじゃ、と言って結菜はそそくさとその場を離れた。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
