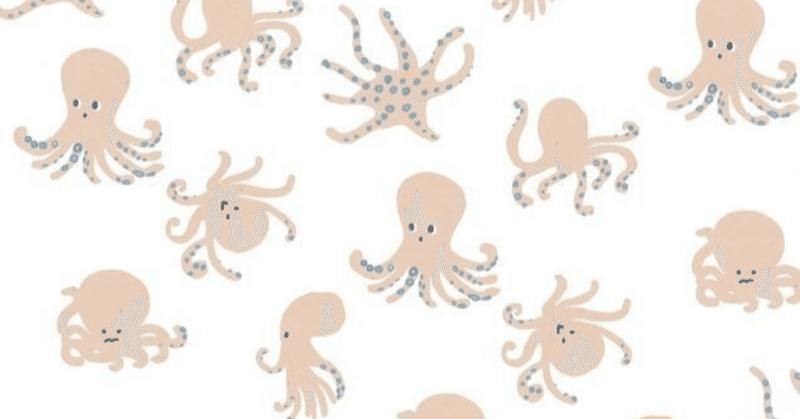
Photo by
momoro66
半夏生(タコの日)
7月2日は極雨時の夏至から十一目ごろを半夏生と呼び、この時期から夏に向けての体力・精力をつけると言う意味で、この時期の「旬」の魚である「たこ」を食べると良いと言われています。
半夏(ハンゲ)はカラスビシャクの球茎で、いろいろな漢方薬の材料に使われています。体を温めて、胃腸の働きを良くし、痰をとったり、咳を鎮めたり、胸のつかえを取る効果があり、半夏厚朴湯にも入っている生薬です。半夏は別名「ヘソクリ」という名前もあります。カラスビシャクは畑でよく見かける雑草ですが、薬用にもなるので、昔の農家の奥さんが草取りの際に集めといて薬屋さんに売って内緒で貯めていたことが由来になります。
カラスビシャクは夏の半ばに花が咲くので半夏というそうです。雑節では夏至から11日目(7月1日〜2日頃)を半夏生といいます。
我が家でも早速タコを買って酢味噌和えで頂きました🤤

タコやイカや甲殻類に多いタウリンは、遊離アミノ酸の一種で血中コレステロール値を抑え、動脈硬化や高血圧を予防すると同時に肝機能を高めたり、眼精疲労にも効きます。酢ダコで常食していると、血を補いわ気を増して丈夫な体になります。
酸っぱいものは肝を潤してくれます。肝が働き過ぎて弱ると、血液の解毒や貯蔵がうまくいかず、血液ドロドロの「瘀血」になったり、頭に血や気が上がった「上衝」の状態になります。瘀血や上衝は、目の充血や吹き出物、のぼせや頭痛、精神不安定、過敏な人は花粉症などのアレルギー症状となって現れるので、血や気の巡りを良くするタコがオススメです♪
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
