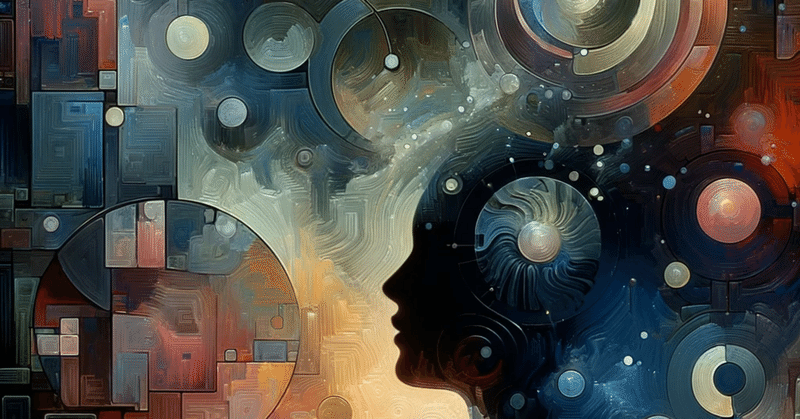
『痛みと悼み』 四十三
この苦しみを終わりにしたい。
母に先を越された今、めぐむの願いは叶えられない。
復讐。
知られないまま、完全に世の中から姿を消して、それを悟られないように一人暗い世界で暗く微笑む自分を夢見ていた。
もう叶えられない。
終わりにしたい。
のたうち回りながら白い腹を見せる何十ものヘビから、降り続く雨で薄く光る堤防に空ろな視線をやる。
誰もいない。
頭に過ぎる甘美な誘惑を感じる。
このまま川の流れに身を任せたら、あっという間に何もかも終わらせてくれる。
そのまま海に流れ着き、静かで冷たい海底にたどり着けば、出来損ないなりの、誰にも知られることのない死にたどり着けるかもしれない。
水面を見つめるめぐむが前のめりになる。
水面がどんどん近づき、目の前のうねりが茶色く濁った色に合わさって判別がつかなくなり、甘美な誘いの声と一つになる。
右手のビニール傘が水面に落ちると、スタートの轟音の中を真っ先に進むマラソンの先導車のように流れていく。感電したかのようにクルクルと水面に弾かれて踊っている。水の流れの上を喜び狂ったようにあっという間に見えなくなる。
スタートする水泳選手のように、めぐむは重力に身を任せて水の中に崩れ落ちる。

めぐむの目の端で何かが動いた。
耐えきれずにフライングするように、めぐむより先に、左手に持っていた白い布に包まれた木箱が、手元から離れる。
布に包まれた木箱は、堤防の傾斜に一度鈍い音をさせて当たったあと、小さく跳ね返って白い布が解けると、中の木箱がそのまま茶色と白のうねりの中に転がり落ちて飛び込む。白い布が別れを惜しむ桟橋の紙テープのようにめぐむの手元から水に漂う。
木箱は流れに一度沈んだあと、真っ直ぐに浮かび上がった。
強い流れの勢いで木箱の蓋が外れて水が入り、バランスを失う。
転覆する小舟のように木箱はゆっくり横になる。
水流を揺蕩うように時計回りに回転し、めぐむに開口部を見せたとき、そこから白い陶器と埋葬許可証の入った封筒が流れ出す。
白い陶器はポカンとからかうような軽い音を出し−轟音で聞こえるはずがないのに聞こえたと思ったのは、めぐむが作り出した母への葬送行進曲だったのかも知れない−蓋が開いて、そこから白い骨片がヘビと化した流れと戯れるように水面に浮かんでバラバラに散らばる。
母の声が聞こえる。
悲鳴なのか、嗤い声なのか。
生き急ごうとするめぐむを押しとどめようとする母の何かなのか。
尋ねるように身を乗り出す。
それを制するように白い骨片たちは、互いに戯れるように流れて、めぐむの視界から離れていく。
めぐむは、残された白い布の端を強く握り締める。
自分が溺れているように、見つめる。
骨片たちは、喜悦の表情を浮かべて流れていく。
骨片たちのしんがりのように最後に流れる木箱が、やがて遠くの下流に見える赤い橋を越えて見えなくなる。
暖かい雨は粒を大きくしてさらに強く降り出し、傘を落としためぐむの水色のワンピースの背中の色を濃くして濡らす。
大粒の、手を差し伸べるような雨だった。
消えていく木箱。
代わりに飛び込むように落ちていった母が、めぐむに問いかけたものに狼狽える。
傷ついた体を引きずるように家に帰り着いた。
めぐむは、叩きつけられて潰れたカエルのように、その日から部屋でひとり静かにキズを舐め続けた。
なすすべもなく絶望し、治らないことを知りながらうずくまる。
部屋に絶望が満ちたとき、静かに事切れる瞬間が来るのを待っていた。
太田さんに助けられなければ、孤独な死との誠実な戯れの始まりとなるはずだった。
自分が黒いシミとなることを、弱っていく体と尖っていく意識の中で夢見ながら。それは、黒いシミたちの最後に見る景色だったのかもしれない。
その雨の記憶から、蘇る。
甘く暗い無に向かい合った時間から、今、明るい日の差す教会の中にいる。
聡二さんに尋ねたことは、あの河の轟音とうねりの中から投げ掛けられた母の問いであり、自分自身への問いなのだろう。
母藍子が求めていたものは、めぐむができないと思おうとしていただけではないか。
死者に思いを巡らすことは、生きている者の独りよがりだと思っていた。
