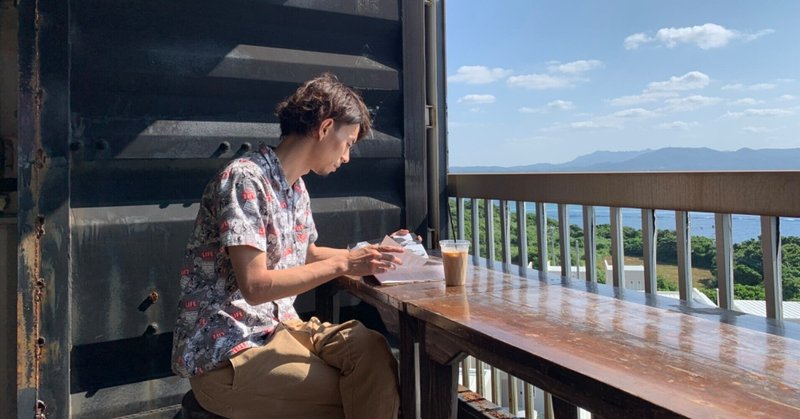
社会人からの学習習慣が年収を上げる
私が新卒で入社したメガバンクでは、新入社員には自己研鑽という名の学習が奨励されていました。
人事評価のExcelにも自己学習の成果や取得した資格を記載することが義務付けられ、新入社員としてのやる気もあり、また銀行員としての出世の道を閉ざされたくない恐怖心でおのずと全員、勉強に勤しんでいました。
まずメガバンク3行に共通することとして、1年目・ひいては入行前から勉強に勤しむことを奨励されるということです。
入行前には証券外務員の資格取得が望ましいとされ、内定者の実に9割以上の方が入行前にこの資格を取得します。
みずほ銀行と三井住友銀行においては英語学習が推奨され、具体的にTOEICで730点に満たない内定者には大量の英語力向上のための通信教育が用意されているとのこと。
就職活動時に730点以上のスコアを持っていても、内定式後に課されるTOEICで730点を超えなければ例外なく通信教育が待っているので、注意が必要です。
ちなみに730点を超えた内定者にはスカイプ英会話が待っているようです。実際筆者の内定者サイトには、義務ではないものの「ビジネスコミュニケーションルール」や「簿記3級」「FP取得」のための映像が用意されておりました。
入行後1年間は幾多の研修を通して生損保商品を売るための資格や、簿記3級・FP3級の取得が目標とされているようです。
重箱の隅を突けば別ですが、概ねこの記事に書いてあることは当たっているように思います。加えていえば、本部から課されている資格取得の目標以外に、配属支店ごとに支店長から課題が与えられるケースも多いです。
私の友人の配属支店では、毎日新聞のスクラップを1記事作って、それに対する自身の意見を書いたものを支店長に提出、というようなことをしていたと聞きます。
土日も例外なく必須だったため、当時は日曜の夜のたびに3日分作る友人が気の毒だったものです。しかし今になって振り返ってみると随分面倒見の良い支店長だなとも思うものです。
閑話休題。人事評価と出世ルートという飴とムチである意味無理やりやらされていた自己学習なのですが、今となっては良い思い出であり、学習をしていてよかったと思うものです。
本日はそうした観点から、「社会人の学習の重要性」について考察していこうと思います。
1.誰も勉強していない
冒頭に書かせていただいた銀行というのは極端な例です。社会人になっても学習を続ける人は少数派です。
総務省が実施した「平成28年社会生活基本調査」の結果によると、有業者(すなわち、社会人ですね)が「学習・自己啓発・訓練」に充てる時間はなんと、1日当たり平均6分間です。
小学校からずっと10年以上、毎日何時間も勉強していたことを考えると、働いている時間があるとはいえ、社会人の勉強時間がいかに少ないかがよくわかるものです。
統計ではここまでしか示されていませんが、平均6分という結果の原因は、恐らく大半の社会人が0分だったことによるものだろうということは容易に想像できます。
たとえば、東海道新幹線の1本あたりの遅延時間はわずか36秒。東北・上越新幹線などJR東日本が運航する新幹線では20秒程度(東海道新幹線のほうがダイヤが過密なので遅れが出やすい)、定時運行率(定時±1分)は95%にもなる。
引用元:サラリーマンのボヤキ
定時運行率が95%の新幹線で、平均遅延時間が30秒前後というデータがあります。こういったものから推測するだけでも、おそらく勉強時間0分の社会人の割合もおそらく90%とか95%あたりだろうと予想できます。
資格のための勉強などをイメージすれば、1日10分20分では足りないことが想像できるでしょう。そうした人を含めての平均6分という結果は、ほとんどの社会人が勉強をしていないことを如実に表しています。
2.年収と学習時間の相関性
学習時間は年収とも相関関係があると言えそうです。
雑誌「PRESIDENT」の記事では、下記のように掲載されています。
「仕事以外の時間に勉強している」と答えた人は、年収2000万円以上で69.2%、年収500万円台で41.2%だった。また3カ月に1回以上セミナーや勉強会に参加する人は、年収2000万円以上で過半数の53.2%だが、年収500万円では31.5%だった。収入の高い人と低い人の行動量の差が浮き彫りになった結果といえよう。
引用元:年収2000万vs500万学習法比較(下記画像もこちらから引用)


先ほどの総務省の平均6分という調査とは、恐らくアンケートの母体や方式が異なるために結果も異なっているのでしょう。
とはいえ、調査の結果として、1日に1時間以上の勉強時間を取っている人は、年収500万円台では29.9%、年収2,000万円台では48.0%となり、如実に開きがあります。
もちろんこの記事だけですべてを語ることはできませんが、年収が高い人ほど、どうやら積極的に学習を行っている傾向がありそうだということが読み取れます。
3.学習のもたらす効用
社会人としての学習がもたらす効用は、主に「意思決定」と「アイデア」の2面で発揮されるように思います。
社会人は出世すればするほど、不確実な状況に対する多くの意思決定を行うことに迫られます。さらに言えば、立場が上がれば上がるほど、その意思決定に対する結果責任も問われるようになります。
自分の勘と経験だけで、数多の意思決定を正しくこなすことは容易ではありません。競合の事例、海外での実験結果、世界情勢のニュース、新しい科学技術、異文化で当たり前の考え方、などなど、、、前提知識は多く持っておくに越したことはありません。
アイデアというのも同じです。勘違いされがちなことではありますが、素晴らしいアイデアが天から降ってくるというのは現実にはほぼ存在せず、多くの斬新なアイデアは、既存のアイデアの斬新な組み合わせであることがほとんどです。
野菜寿司(野菜×寿司)
機能性チョコレート(乳酸菌・GABA×チョコレート)
ハルランドリー(コインランドリー×美容室)
幼老複合施設(保育園×老人ホーム)
引用元:意外な組み合わせで人気になった商品・サービスまとめ
少し調べるだけでもたくさん出てきます。様々なアイデアを、どういう共通点でもって結びつけるのか。その前提には多くの学習に基づく知識が不可欠であることは言うまでもないでしょう。
冒頭にも書いたように、まずほとんどの人が学習をしていないのですから、競争相手が少ないです。また、先立つお金もそれほど多額には必要ありません。さらに、知識は一度身に着ければ一生役立つ財産になります。
学習は最高の自己投資といえるでしょう。
本日は以上です。
コメントやSNSシェア、フォロー、「スキ」機能で応援いただけますと励みになりますので、是非お願いします。
Twitterも是非フォローお願いします!→@sai_to_3
それではまた次回。
2022.1.28 さいとうさん
よろしければサポートお願いします!より良い記事を執筆するために有効活用させていただきます。
