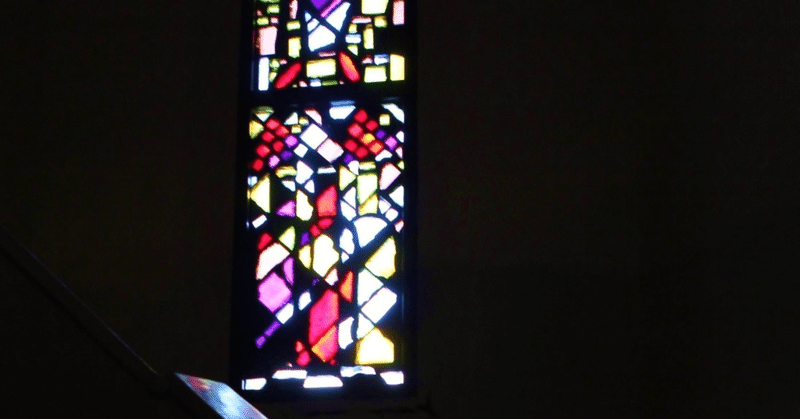
Gくんのお母さんの話 シスターになりたかった
家の窓からの景色が見渡す限り田んぼの田舎で生まれた私は、幼稚園は自分の町ではなく、ちょっと都会(あくまでも当社比、今から思うと全然都会でも無かった)の隣町のカトリック系幼稚園に送迎バスで通ってました。
幼稚園の園長先生はシスター、と呼ばれる女性でした。頭から垂らした布が一瞬長い髪に見える帽子のようなものを頭にピンで数カ所きちっと留めて、化粧気は無し。足元まであるたっぷりとした長いスカート。最初は不思議な人に見えました。シスターは園児と直接生活で関わるわけでは無いけれどいつも穏やかに微笑んでいました。シスターはせがわ〜、シスターおの〜というようにシスターの後に苗字をつけて呼んでいました。
先日、市の図書館でシスターの後ろ姿を見かけました。街中でも、シスターを見かけると必ず目でグィっと追う私。何故か無性に追いかけて話したくなります。頭では分かっています。目の前のシスターは私の知ってるシスターでは無いこと。ただ同じような格好と雰囲気だから私の知ってたシスターと直に繋がっているような錯覚がぱちっと起こります。
幼かった私はもう50過ぎで子どもの時とは全く違う街に住んでいます。あの時のシスターは存命ではないとわかってる、でもシスターを見かけた瞬間、心は大好きだった幼稚園時代に飛んでいます。シスターの定番の黒い冬の服装も好きだったけど真っ白な夏服、薄いブルーの合服、どれも綺麗だなぁと見ていたこと、溢れるように思い出します。
当時住んでた社宅は田舎だったので庭付き一戸建てでした。各家間取りは違うけれど、柘植の木の生け垣に囲まれ、なぜか屋根付きの井戸まである、木造で古い家でした。昔は幹部向けの社宅だったとのこと。全部で15軒ぐらいだったかと思います。山に沿って建てられ上の社宅と下の社宅を繋ぐ広場のある真ん中に位置する小さな坂で三輪車を押して上がっては乗ってサーっと降りるを繰り返したり、泥水のコーヒー牛乳作ったり、そばの大きな金木犀の木の下が秋になると金木犀の落ちた花でオレンジ一色の絨毯になってた記憶が香りとともにあります。
我が家から一番遠い端っこの社宅に同級生のGくん一家が住んでました。G君はおっとりしたおとなしい子で雰囲気がムーミンに似ていました。
幼稚園を卒園したあと、私は幼稚園の母体の教会の日曜礼拝に通うようになってました。大好きな幼稚園と卒園後も繋がれる感覚が嬉しかった、当時の同学年の仲良しだけど同じクラスでは無かった友達のYちゃんに毎週会えるのが嬉しかった、が理由だったのだろうと思います。
教会へはGくんのお母さんと一緒にバスで行ってました。一緒というより連れて行ってもらってたのだと思います。Gくん家はお父さんがいませんでした。Gくんが小さい時に亡くなり、代わりにGくんのお母さんがお父さんと同じ会社で働いていました。
Gくんのお母さんこと「おばちゃん」はショートカットで丸い縁のメガネの奥の目がいつも微笑んでいる小柄で穏やかな人でした。私は「おばちゃん」のことが大好きでした。おばちゃんは洗礼も受けていて熱心に祈る姿に子ども心ながら信仰が厚い人だなぁと思っていました。Gくん兄弟は教会には通っていませんでした。
ある日の教会の帰りのバスの中での会話です。「私、シスターになりたかったの。」おばちゃんが唐突に言いました。「でもね、シスターは一度結婚するとなれないの。」その時の小学1年?2年?だった私はなんと返事したか覚えていません。おばちゃんならシスターの格好がそのまま似合うと咄嗟に思ったこと、その言葉を聞いたのは、バスの後ろの座席からバスをちょうど降りるために立ち上がったタイミングだったこと…そんなことははっきり覚えています。大人から夢を聞くとも思って無かったので、聞いてしまってもしかするとちょっと困ったような顔をしていたかもしれません。
夢を聞いたけど、その夢はもう叶えられない夢だった…ただ何となくその言葉にお父さんがいらっしゃらない中、一人で明るく頑張ってるおばちゃんの苦労を当時の私なりに勝手に感じてました。この話は帰っても親にも話しませんでした。だっておばちゃんの大事な秘密だと思ったからです。
小学3年の秋に引っ越しをして社宅を出ました。相変わらず教会へ通っていたけれど引っ越し先からは大きくなったこともあり自転車で通ってました。もうGくんのお母さんとバスに乗ることはありませんでした。
小学生高学年になってから、Gくんのお父さんが実は自殺で亡くなられたことを不意に知ります。
シスターになりたかった、の一言に込められたおばちゃんの思いが私の心の中でズンと重くなりました。
それから40年、母と話していて偶然、Gくんのお父さんが亡くなったのはご自宅だったこと、第一発見者はなんと私の同級生の当時幼かったGくんだったこと、Gくんのお父さんは病気で長い間会社を休んでいて久しぶりに職場へ行ったら自分の机が無くて、その後帰宅し亡くなったことを知ってしまいます。。。
今だったら、休んでいる人の机を勝手に無くせばそれはれっきとしたパワハラです。会社を訴えることだってできます。しかしメンタルヘルスという言葉すら無かった昭和40年代の田舎でそんなことはとても出来なかったのではと思います。会社としては代わりにおばちゃんを雇って一家の住むところを社宅として確保したのがせめてもの償いだったのだと思います。これは本当のところは知らないので私が勝手な推測です。
おばちゃんは、結婚されたGくんのお兄ちゃんの住んでるところへ呼んでもらって一緒に暮らしているらしい、が母の知ってる随分前のそれも人づたえに聞いた話でした。
あの社宅で鮮明に姿と言葉を覚えているおばちゃん、生きていらっしゃったら私の両親の同年代なので高齢です。にこにこと幸せに暮らしていらっしゃると信じたいし、勝手にそうであると思っています。もしおばちゃんに会えれば、あの時、小さかった私に夢を話す気持ちになったわけをそっと聞いてみたいなぁと思ったりします。
きっとそんなことはもう覚えていらっしゃらないだろうと思いつつ…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
