
8話 東日本大震災に駆け付けたヘリパイロットの隔靴掻痒記 3.11とその前後
大規模災害が発生し罹災県に十数機の防災ヘリコプターが応援に駆け付けた。それらをどのように運用すべきかを7話で考え始めた。受け身のタクシー配車的な運用では罹災者に申し訳がたたないとも書いた。そこで任務分析と云う手法を取り入れてみた。それは応援防災ヘリコプター部隊の「地位」と「役割」を原点に成すべき「目標」を具体化するものだった。次はその具体的な目標をいかに実行するか、の考察が必要となる。
実はこのような思考過程は自衛隊時代、徹底的に鍛えられた。その思考過程は、混沌とした状況の中でことを成すための判断、つまり決心するためのものなのだ。
「状況判断は最良の戦術行動を案出するために、
①任務を基礎とし、
②任務達成に影響するあらゆる要因を理論的に考察して
③結論に到達させる。
卓越した戦術能力はこのため不可欠の要件である。この際、先入主に陥りあるいは根拠のない直感によることは厳に戒めなければならない。とされていた。」
卓越した戦術能力とあるが、戦術に奇はない、きわめて常識的なものだ。だからこの考え方は遍く世上一般に通ずるものであると考えている。だからこの部分は「卓越した常識力はこのため不可欠の要件である」と読み替えてよい。戦術行動とは世上一般では問題解決の方策とお読みいただきたい。
あのとき、あるべき状況判断を試みたい。
状況判断の第一は任務である。
それは前7話で考察した任務分析で案出したところの、
「必ず達成すべき目標」と「達成することが望ましい目標」が任務になる。
再掲する。
______________________________
必ず達成すべき目標(任務)
① 被災72時間を限度とする集中常続的な空中からの救命活動の最大化。
→在空監視からの空中吊上げ又は降着による救助。
→不明地域に人員を投入する検索とその情報による救助。
② 現地活動と連携した負傷者の医療機関への後送。
③ 孤立した地域への緊急物資空輸。
④ 防災ヘリコプターの非損耗。
達成することが望ましい目標(任務)
① 県の災害対応指針の策定に資する情報活動。
② FBフォワードベースを主要被災沿岸市町村近傍に設置し、空地通信、燃料、搭乗員の宿泊給食に必要な資機材を追送し、FBに拠る独立的任務を可能とする。
③ HBヘリベース(花巻空港)から現地活動ヘリコプターとの通信と、その帰投経路保全のため、天候偵察兼務の無線中継機を現地活動時において努めて常時在空させる。
______________________________
次に上の任務を達成するための方策を考えるのだが、その前に「状況」を理解しておく必要がある。
その状況とは、以下の3項目だ。
① 天象地象
② 被害の状況
③ 関係機関等の状況
その上で「任務」を達成するための方策をいくつか案出する。
その方策のことを「行動方針」と呼んでいた。任務達成のために正面から行くのか、左からかそれとも右からいくのか、あるいは行くのは無理だから留まるのか。行動方針が一つしかないのは怠慢でしかない。
序でに記しておけば、このような問題を考えるとき
①人事機能 ②情報機能 ③作戦運用機能 ④兵站補給機能
の4つが不可欠だ。陸上自衛隊では平時から、この4つのそれぞれの機能を専門とする幕僚(スタッフ)が指揮官を支えている。さらには陸上総隊、方面隊、師団(旅団)、連隊、大隊、中隊と規模の違いはあるがすべての指揮所にこの4つの機能が備わっている。だからその機能の幕僚ごと調整を行うから上下級部隊や隣接部隊との意思疎通が容易な構造となっている。
県の災害対策本部は恒常業務の組織をいわば解体して、上の4部門の指揮所に編成替えを行っている。恒常のきめ細かい行政のためにこそ便利な組織でも、かかる緊急事態では対応できないことが分かる。
その指揮機能だが、基本的には自衛隊の師団司令部も、県の対策本部と同一地域に並列して開設される場合が多いようだ。岩手県庁では一つの階をまるまる開けて、県の対策本部と師団司令部を置いた。そして互いに①~④の機能ごと対応したと小川和久さんの本で知った。
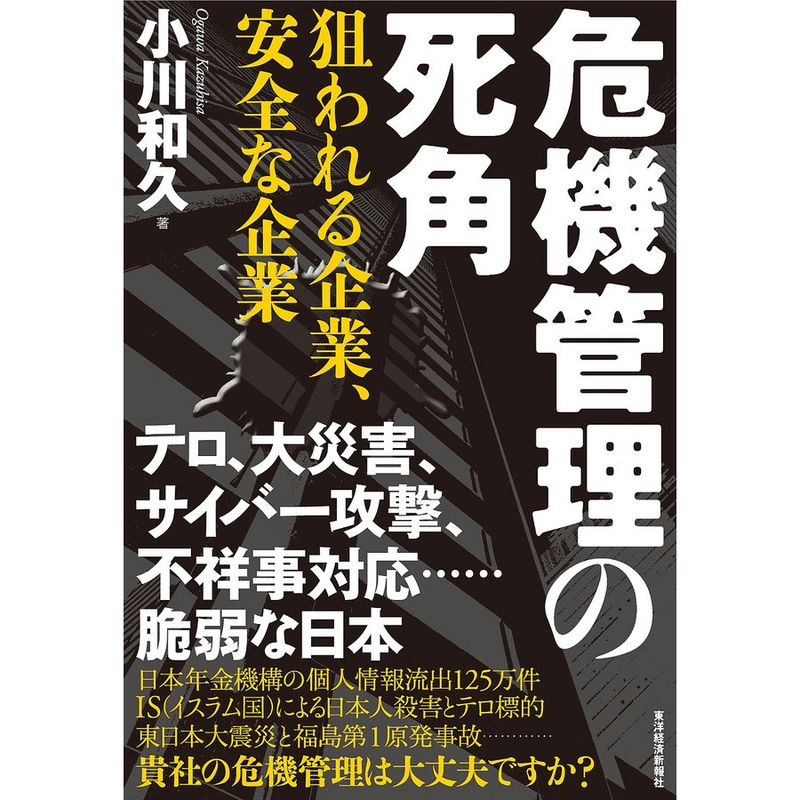
任務達成のための行動方針の話しだった。
行動方針(任務達成のための方策)が一つなどあり得ないとも書いた。ではこの状況でどのような方策が考えられるか。下に整理したい。
______________________________
災害対応立ち上げ時の状況判断の一例 前半部分
1 任務
(任務分析で考察した地位役割からの具体的目標が任務であり、ここでは記載を省略するが、これが一番大事だ。上に書きだした項目をもう一度確認していただきたい)
2 状況及び行動方針
(1)全般状況
2011年3月11日1146東北地方太平洋沖で発生した地震は、岩手県海岸部において震度6+から5+の揺れと津波による被害をもたらした。被害状況は不明である。
(2)隷下関係部隊の状況
ア 岩手県防災ヘリは当面活動可能であるが、各県からの応援航空隊の受け入れ業務の増加に伴い活動不能となる。
イ 県が使用できる応援機の推移は下表のとおりと見積もられる。

ウ 被害甚大な地域における消防等機関の活動は各地域で孤立し各個対応中であるが細部は不明。
エ 自衛隊、警察、海保、米軍その他民間ヘリコプター等の活動状況は不明である。
(3)気象の推移予報及び明度資料 略
(4)行動方針(の列挙)
O-1 使用可能防災ヘリを一元管理し飛行任務の判明にともない逐次任務を配当する。
O-2 津波被害甚大な主要市町村に防災ヘリ1機基幹をもって直接支援して現場の航空要求に対し迅速に対応するとともに、県が必要とする航空要求及び直接支援ヘリの航空活動の継続維持に関して、残余の全般支援用ヘリをもってあてる。この際被災72時間後となる、3/14日12時までの救命救助のための航空活動を全力対応できるごとく運用する。
O-3 防災ヘリを地域に区分し独立的に偵察させ要救助事案に直接対応させる。
O-4 県の災害対応方針決定に資する情報活動。
O-5 航空安全確保のための施策。
______________________________
先ずはここまで。
上の第2項の全般状況と隷下関係部隊の状況には、不明のことまで取り上げて、あえて不明と書いた。不明なことは大事な情報であり、後の決心に欠かせないものだ。だからこそ不明のまま流されてしまわないよう書いている。そしてこれは情報収入計画に取り入れるべき事柄となる。
また第(3)項の「気象の推移予報及び明度資料(太陽や月の情報)」を紐解くだけで、あるいは任務の冒頭に書かれるべき「被災72時間を限度とする集中常続的な空中からの救命活動の最大化」を自覚するだけで、08時出勤などあり得ないことがお分かりいただけるだろう。
そもそも、そんなことはこのような分析を行うまでもないことだが。
次に、第(4)項の「行動方針(の列挙)」である。この任務を達成するための具体的方策は、任務と状況をすり合わせて案出できる。ここではO-1からO-3の3つを大方針として列挙した。この「O」はオプションのOだ。
O-4とO-5は少し毛色が違い大方針ではないが、活動を支える大事な項目であり、忘れないために挙げるのだ。陸上部隊の作戦では奇襲防止の観点からこのような事項を付け加える。
さてここまで来たら次は、O-1からO-3のどれを採用するかとの段階になる。次回はその方法論を考えたい。
本編の目次ページへのリンクです!
⇩
https://note.com/saintex/n/n848c8bb9ab3c
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
