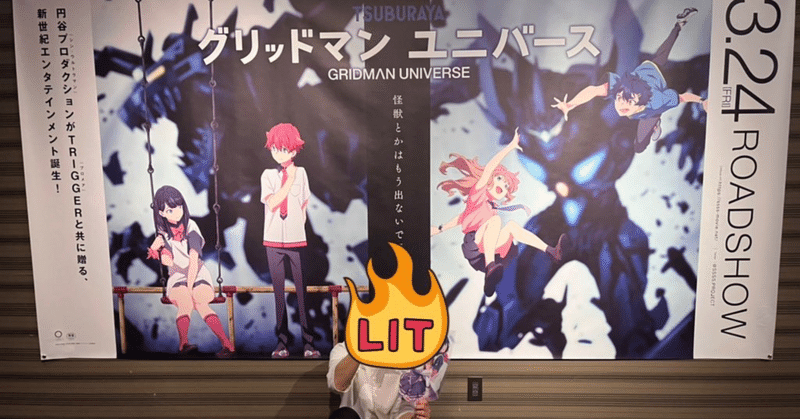
創作への爆熱ラブレター、グリッドマン ユニバース
グリッドマンユニバースが終映したらしいですね。僕が住んでいる県では2箇所でしか上映がなく、しかも5月中旬にはレイトショーだけになっていたので高校生の俺は実質的終映を迎えてはや2ヶ月経ってしまいましたが、今更グリユニの話をします。
(マッドオリジンの正体は・・・!とかは流石に知っている前提でいきます)
本当に「創作」というものと誠実に向き合った映画だった。さまざまな作品が作り手/監督たちの私物であるかのように解釈・消費されることが蔓延している現代において
「この宇宙も誰かのものではない(Universe fighterのセリフ)」つまり、「創作の世界は作り手ですら私物化してはいけない」という主張をかましたのは本当に最高でしたね。
グリユニを見た直後のことはよく覚えていませんが(何ヶ月も経ったので)、「フィクションの力を信じている人には全員見てほしい」みたいなことをぼやいていた気がします。あの映画はフィクションという営みを全肯定するエネルギーがあったと思うんですよね・・・
以下、頭の中で思っていたこと・考えていたことを書きまくっているのでうまくまとまっていないかもしれません・・・・
2次創作の世界=ユニバース という反則級の答え合わせ
ほぼ説明不要であろうことを大雑把に説明しますが、この映画の中には「グリッドマンユニバース」という概念が登場し、それは「オリジナルのグリッドマンからどんどんパラレルワールドが生えて膨張し続ける宇宙」みたいな感じで説明されていたと思います(だいぶ曖昧です)。
劇中で二次創作作品の漫画のコマが溢れ出す演出などがあったことからも察せますが、これはおそらく「グリッドマンから派生したSSSSシリーズを含むあらゆる二次創作を内包する創作の世界」だと思われます。これがヤバかった。
実を言うと、僕はグリッドマンユニバースに何も期待していませんでした。公開前は。「SSSS.DYNAZENON」が個人的に(OA当時は)不満だったからかもしれません。ダイナゼノン世界とグリッドマン世界のつながりの説明を(流石に説明されるだろうから)聞きに行くくらいのノリで見に行きました。
するとまあ発狂してしまったんですよね・・・まさか「二次創作」だったなんて思わないじゃないですか。SSSS.GRIDMANの世界も新庄アカネの創作物でしたが、「ああ、DYNAZENONね。あれは"派生作品"なんだよ」みたいな100点満点の繋げ方をしてくるとは思わなかった。というか、ここまでメタな話だとすら思わなかった。
ダイナゼノンにグリッドマンのようなメタいシリアスさがなかったのも全て頷けてしまう。だって新庄アカネが意図した世界ですらないんだもん。そういう創作の世界の構造を作品の中に、それもファンがあれこれ考えていた2つの世界の関係性の答えとして落とし込んでくるのは本当に誰もにとって予想外だったし、改めてSSSSシリーズが「フィクションの世界」の話をするのだと強調されたようで嬉しかったです。
すべてのフィクションには力がある
個人的にこの映画で嬉しかったのは内海と裕太がウルサマのDVDを見たり、お涙頂戴の演劇を見に行ったりするシーンの存在です。裕太からすればウルサマのヒーローショーの映像を見て内海が泣いていることは完全に理解不能ですが、内海からすればいかにも安っぽい量産テンプレ演劇を見て泣いている裕太の姿も理解不能なんですよね。
これは現実にもよく起こることで、「感動の形はひとりひとり違う」んですよね。でも、逆に言えば「ひとつひとつの創作物には必ず刺さる人が居て、つまり等しく力がある」ということになるんですよね。
僕はこれまでの人生でいわゆるオタク趣味を隠してきたし、友人が見ているものとかいわゆる売れている音楽とか、「一般的な趣味嗜好」みたいな。そういうものに表面上はある程度合わせていました。だから俺にはずっと「(一般には)変な音楽や作品が好きな自分」を肯定してくれるものが欲しかった。なのであの演劇パートはかなり刺さりました。
あくまで鑑賞体験としての話で、作品外の話になりますが、僕が平日の朝っぱらからグリッドマンユニバースを見に行ったとき、大人の客が結構入ってたのに衝撃を受けたのを覚えています。応援上映を特オタと見に行ったときもデカい声でグリッドマンを応援するオタクが何人も居て衝撃的でした。
こんな「デカいロボットが技名を叫びながら怪獣を倒すアニメ」を愛している人たちが俺以外にも居たんだ、というあれがあったんですね。
今思えばSSSS.GRIDMANは新庄アカネが創作の世界の中で救われる話でしたが、その「虚構は誰かにとっての救済になりえる」というテーマを一歩勧めて「すべての虚構は誰かにとっての救済になりえる」というところまで言い切ってくれた感じがあって、それはクライマックスの展開にもものすごく活きていた気がします。
2代目がダーリン・イン・ザ・フランキスみたいな巨大化の仕方をしたり、新庄アカネがプリキュアみたいな変身をしたり、アレクシスにコックピットがあったり。あれは解釈も後付もなんでもありなフィクションの世界を象徴していますよね。その力でマッドオリジンをぶん殴ったのが最高だった。
作中で行われる「創作」
グリユニの話のヤバさとして「創作」が作中で行われてしまうところがあると思います。シーンを挙げると、裕太のインスタンスアブリアクションのところとか、ビッグゴルドバーン誕生のシーンです。両方ともはっきりと「お前の頭の中にあるものを使うんだ!!!」と新庄アカネによる指導が入っていましたね。完全に創作活動です。本当にありがとうございました。
特に後者のシーンはちせの思いが「後付設定」を生み出した感じがあって初見でボロボロ泣きましたね・・・それって「創作」ぢゃん・・・って言いながら泣きました。2回目も泣きました。隣に居た特オタも泣いていました。
グリッドマンでも「一週間後には街が復興しきっている」特撮あるあるをギミックとして意図的に利用するあれがありましたが、まさか「まずい!敵を強くしすぎて主人公たちが勝てないな・・・強化アイテム出すか」みたいなあの過程を作中でやってしまうのはやばいって!!!!!!!!!
創造主不在でもフィクションの世界は生き続ける
この作品を通して強調されていたのは「創造主不在でも世界は生き続ける」ことだと思いました。具体的に言えば、新庄アカネ不在でも裕太たちは生き続けますし、ダイナゼノン世界は勝手に生えますし、よもゆめはいちゃつきますし、ゴルドバーンがちせの元を離れてもピンピンしてるわけです。
特にラストシーンの裕太が六花に告白するシーンなんか、SSSS.GRIDMAN時空が修復されたあとの話ですし、あのシーンが最後に来ていたのは観客に「新庄アカネもマッドオリジンも居なくなったあとも、フィクションの世界は生き続けるんだよ」と示す意図があったように感じます。
変な話「雨宮哲不在でもグリッドマンの世界は生き続ける」んですよね。またさらに30年後もグリッドマンのことを誰かが覚えていれば、そこからまたユニバースが生まれる。みんなの落書きからUniverse fighterが爆誕するシーンと同じです。そういう事を言いたかったんじゃないすかね・・・
フィクションの世界は誰のものでもない。だから美しい
なんか、現代って「作品の世界を正面から愛そう」という考え方が欠けていると思うんですよね。有名監督のアニメ映画が出ればそれあの登場人物はジブリの〇〇さんなんだ!とか、やれあのキャラの正体は監督の奥さんだ!とか。創作の世界と正面から向き合っていない。登場人物たちの物語としてすら読み取っていないんですよね。これは「創作物は作者の私物」っていう考え方が原因だと思う。
SWは別にジョージ・ルーカスの私物じゃない。エヴァは庵野秀明の私物じゃない。ガンダムは富野由悠季の私物じゃない。君たちはどう生きるかも別に宮崎駿の私物じゃない。でも、そういう読み方が一般的になってしまっているのが現状なんですよね。
僕もそういう読み方をしてしまうときが多いです。このグリユニ感想文もついつい雨宮哲という固有名詞を出してしまっている。でも本来はそうではないんですよね。それは創作物に対する愛が足りない。
本当に巨大ロボットと怪獣が殴り合う特撮番組を愛しているから、変身も合体パターンも思いつく限りやった。あの世界を本当に愛しているから、作り手の干渉なく「続く世界」を描いた。そこにはフィクションへの誠意があると思います。それがあるから、「創作物の力」を描けたんですよね。
要するに僕はグリッドマンユニバースは「創作に対する爆熱ラブレター」だった、と解釈しています。本当にいい映画だった。メモリアルブックは受注の情報を知らなかったので買いそびれましたが、Blu-rayが出たら一番高いやつ(特典とかアホみたいに付いてるやつ)を買おうと思っています。はやく毎日見たい。
当日追記(2023.8.01)
ブルーレイの情報出ましたね・・・・ユニバースファイター付き(22000円)いきます・・・
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

