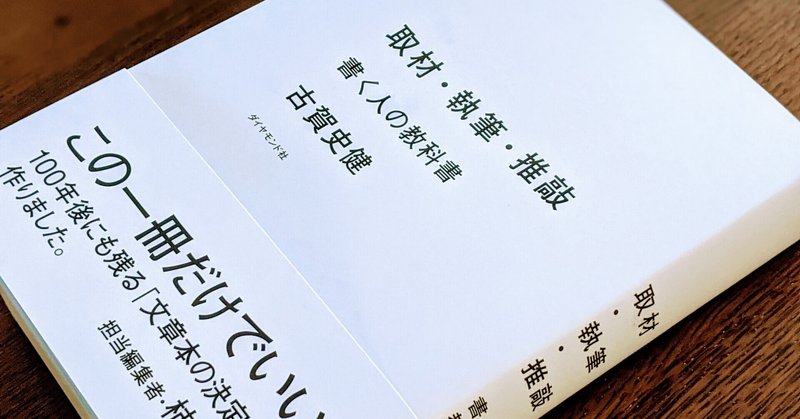
激詰めしてくれてありがとう、『取材・執筆・推敲』
古賀史健さんの新刊、『取材・執筆・推敲 書く人の教科書』を読んだ。
読み終わって最初に思ったのは、「私はライターの仕事を続けていいのだろうか」ということだった。最終章にはこうある。
ガイダンスからここまでの話を読んできて、自信を失ったライターもいるかもしれない。むずかしすぎると感じたり、考えることが多すぎると感じたり、自分には無理だと投げ出したくなったり、これまでの自分を否定されたような気持ちになったライターもいるのかもしれない。
見透かされている。そのとおりである。全編通して、古賀さんに詰問されている感じがする。ある程度、意図的に書いていると思う。「プロ失格」「怠慢」「傲慢」「失敗」「甘すぎる」「ぜったいにやってはならない」「愚策」「(そのライターは)何もわかっていない」など強めの言葉をあえて使っている。こういうことをするのはダメなライターだ、という具体例も多い。はい、私です。
本書はライターでない人が読めば、「へえ、ライターってここまで考えているんだ」「ここは自分の仕事にも参考になるな」といった発見があり、おもしろく読めるだろう。
ライターでも仕事の範囲が一致していなければ、発見と示唆に満ちた興味深い本、と捉えられるはずだ。
ライターというのは細分化されている。古賀さんのように取材をベースにして、ジャンルを問わず(なにかの専門ライターではなく)、ウェブ、雑誌だけでなく書籍まで書いている、というライターの数は多くない。この限られた人数のライターを確実にキルしてくる本である。
ページをめくるごとに、自分の仕事ぶりに対して「で、お前はどうなんだ」と、突きつけられる。書いてあることが全部、自分事なのである。なんとしんどい読書体験か。
「日常のすべてを『読む』ように生きているか」
「取材で相手の話を『聴けて』いるか」
「わかっていないまま書いていないか」
「1つの原稿に対して50冊以上の資料にあたっているか」
「取材対象者がどう語っていたか音源にあたって何度も振り返っているか」
「何をおもしろいと思ったのか掘り下げたか」
「取材対象者の話を丁寧に翻訳できているか」
「主張+理由+事実を意識して論理的な文章が書けているか」
「起転承結を意識しているか」
「そもそもここまで文章の論理構造について考えて書いているか」
「『書くこと』と『書かないこと』を適切に選別できているか」
「体験の設計として本を作っているか」
「対談原稿で両者の文体を明確に書き分けているか」
「ありきたりな比喩ではなくおもしろい比喩を考えて使っているか」
「導入で希少性の高い話をするために、本題とは違う部分まで取材をしているか」
「推敲時に一度書いた原稿を箇条書きにして論点を整理しているか」
「違和感がある場合、ゼロから書き直しているか」
そして、「書く」ことにここまで、半ば狂気を感じるほどに、真摯に向き合っているか。
すべて答えは、「いや、あの、全然できてません……」である。「編集者がついていれば、その人はプロのライター」と古賀さんは書いているが、編集者さんがついてくれていても、私はライターとは言えないのではないか。
というわけで、Twitterで古賀さんに「感想聞きたいな!」と返事をいただいても、しばらくは「恐れ多くて何も言えない」という気持ちだった。
しかし数日経って気がついた。
古賀さんは詰問してるのではない、教えてくれているのだ。ほぼ同じような仕事をしている大先輩から、仕事のダメ出しをしてもらえるなんて、そんなありがたいことはない。すべてが突き刺さるということは、すべてに改善の余地があるということ。すばらしいじゃないか。
この本には、私が仕事でぶつかる「こういうところで困ってた……!」という部分について、古賀さんなりの答え・やり方が丁寧に書かれているので、めちゃくちゃ参考になる。ある意味、贅沢な個別指導を受けているようなものだ。
こう思えたのは、時間を置くことで冷静になったからだ。読んでいるときはこの本に気圧されて、読み終わってからもその影響下からしばらく逃れられなかった。
これでもかというほど徹底的に思考し、読者に伝えようとするその熱量。古賀さんが全身全霊を捧げて書いた本。しんどかったけど読み通せてよかった。これから何度も読み返します。古賀さん、本当にお疲れさまでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
