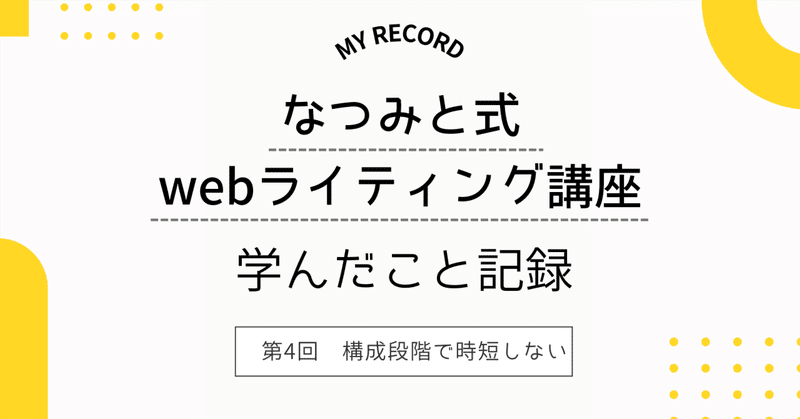
「構成」のステップを無意識にサボっていた
前回までのあらすじ
理系ライターになりたくて「難しい内容をいかに分かりやすく書くか?」ばかり練習してきました。
が、理系ライターの大先輩に弟子入りして数日で撃沈。
「理系云々以前に、ライターとしての基礎力が足りないから、顔を洗って出直してこい(意訳)」とのこと。
オンライン個別指導を始めたばかりのなつみ先生に3ヶ月でライターとしての基礎力を鍛えていただくことにしました。個別指導なので、目標設定や講座の内容もすべて私合わせ。(ありがてぇ……)
面談とこれまで書いた文章から見つかった私の問題点はこちら:
・文章の要約が出来ていない
・文章の密度が低い
・「考えきってから書く」習慣がない
第4回の講義で教えていただいた内容から、構成・構成案に関する部分だけ、まとめて公開していきます。
「構成」を作るまでのステップ
教わったこと。
KWに対して、自分=読者=検索者、と想定して質問リストを作る
検索や勉強で、質問の答えをもつ
1,2のトピックをグルーピングしていく(=意味段落ができる)
グルーピングしたトピックをh2、h3に割り振っていく
4のh2、h3に見出しらしい言葉をつけていく
自分がもともと詳しい分野でも、依頼されて初めて勉強した分野でも、同じ手順を踏まなくてはなりません。
読者と同じ目線を持っている「あまり詳しくない分野」の方が分かりやすい構成にできそうですが、そうでもないのが私の悩み。どうやらこれは解像度が低いまま突っ走ろうとするから。
その記事自体の締切や、他仕事からの焦りから、ステップ1,2の工程を無意識に手を抜いていた可能性が高いのです。少しは考えるけど「考え切る」ほどではなかった。原因はこんなところでしょう。
先に見出しを考えることによる弊害
ちょっと前のnoteで、構成がテンプレになってしまう、つまらない、というような悩みを書いた気もします。
この原因はおそらく、先に見出しを決めてから書いているため、なんですよね。
私は、先に見出しを決めてしまうと「考えきる」のをサボり、見出しにあった要素を出すことに一生懸命になってしまうんです。木を見て森を見ず、の典型例ですね。よくない。
クライアントワークでは、自分が構成を考えないこともあるし、自分で考えても上位表示最優先にすることもあるしで、仕事と練習を両立するのは難しい気もします。できる人はできるんだろうけど。私には無理なようなので。今はきちんと時間をかけて自主練して身につけていきたいですね。
今週の宿題は1本! 時間をかけて作るぞ!
考え始めるところから、見直しまできちんと時間をかけて取り組んでみます。
テーマは、そう、今この瞬間、私が最も、調べたいこと……!「応援うちわの作り方」です。
今週木曜日、雨が降ろうが槍が降ろうが、私は手作りのうちわを持って富士急に行かなくちゃいけないんだ……ッ!
こんだけ時間をかける時間をかける言うてて、前日に慌てて書いたり、誤字脱字多発だったりしたら、目も当てられないゾ!(フラグ・・・ではない)
ではまた来週・・・
勝手に宣伝コーナー。
▼私と一緒に頑張りたい方へ(勝手に宣伝)。
なお、わたしはモニター生徒です。
注意:なつみ先生の講座は完全個別指導で、カリキュラムや目標設定、課題設定も生徒に合わせて決めているそうです。ゆえにこの体験談を読んで講座に申し込んでも、講座内容や課題自体は私とは全く異なると思います。
私のこのnoteは「生徒に対する指導の細かさ」や「具体的な課題の設定」という点でのみ、参考になると思います。
▼なつみ先生の著書。お世話になった方もいるのでは……(勝手に宣伝。スゴイ人に習ってると思うと自分もスゴイって気がしちゃうよね!)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
