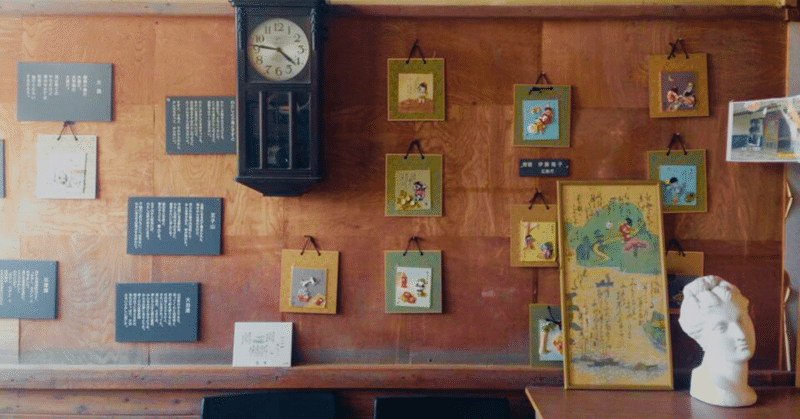
個性を生かすための「型」習得〜あるいは、学校生活を生き延びるための術〜
「最近ドラマといえば、テレ東系のばっかり見てるよ。アマプラで。」と私。
「テレ東のドラマはゴールデンタイムでも30分なんですよ。予算も少ないらしくて。」と学生。彼は将来、ドラマ制作に携わりたいと考えている。
「確かに俳優も有名な人は少ないよね。でもそういう制限が面白い番組を作っているんだと思うよ。制限があった方が、創作は独創性が発揮されるってことがある。テレ東系のドラマはすっごいこだわりが感じられる。」
「そうなんですよ。企画も製作者のこだわりを突き通した方が会議通るらしくて。それに、一人で2〜3つ企画が通って掛け持ちで制作するとかもできるらしくて。」
最近立て続けに、学校教育について評論している本を2冊読んだ。ひとつは、工藤勇一 (著), 鴻上尚史 (著)『学校ってなんだ!〜日本の教育はなぜ息苦しいのか〜』 (講談社現代新書)。もうひとつは、石原千秋(著)『生き延びるための作文教室』(河出書房新社)。
前者は劇作家の鴻上さんが、個性をひたすらに潰しにかかる<学校>に対して、もう何十年前に卒業したにも関わらず深い恨みをもって「どうしてそうなのか?」という疑問を東京 麹町中学校校長の工藤氏にぶつけていく。
(鴻上氏)僕がずっと演劇を続けてきた動機の一番奥深くには、中学校の演劇部の時に、上演したいと希望した戯曲を、演劇部顧問と学年主任と教頭から「その戯曲は中学生らしくない」と、取り囲まれて言われ続け、拒否されたことへの怒りがあります。
そしてとりわけ、鴻上氏の「怒り」は校則に対して強く向けられている。しかしそれに対して工藤氏は、校則は学校の問題のなかでは枝葉末梢であり、本質的なことではないと指摘する。
(工藤氏)日本の学校教育にどっぷり浸かれば浸かるほど、世の中で活躍する人材は生まれてこないんじゃないかとも思うんです。世の中をつくっていくのは異端児ですよ。必要とされているのは、慣例に疑問をぶつけることのできる人間です。しかし、今の教育は、ただ従順で素直な人間をつくろうとしているように思います。
どこが本質的な問題か。学校では子どもたちに自己決定権がないことだと工藤氏は述べる。鴻上氏もこれに同意する。
こうした自己決定権の尊重から、麹町中学校では校則を生徒たちが決め直しただけでなく、定期テストや宿題を撤廃させた。工藤氏曰く、宿題はやったかどうかを評価材料に使うためだけの教師側の都合で出すものであり、生徒が自由に学校外学習をすることを妨げるものだった、という。
鴻上氏はアーティストであり、感覚の人である。だからこそ、自分の体験を重んじる。ただし、それを安易に学校論・社会論に結びつける危うさがある。それに対して工藤氏が現場の経験、そして専門家としての見地から意見を述べることで、バランスの取れた内容となっている(鴻上氏が「だから日本の学校は〜」というような主語のでかい発言をし、それに対して工藤氏がイギリスの教育も同じですよ、と相対化する場面があったりする)。
自己決定権がないから、自己肯定感も低くなる。自由にできるという経験がないから、いざなんでもやって良いとなった時に、何もできなくなる。子どもたちをそうしてきたのが日本の教育。そのような主張がこの本を通じて繰り返し語られる。
こうした同書の明快な学校教育論に対し、『生き延びるための作文教室』は、中学生に向けて書かれた本でありながら、一読しただけでは内容的にとっ散らかっている印象を受ける、きわめて分かりにくい構成で書かれている学校教育論だ。出版社のオーダーと著者の書きたいことがズレたのか。あるいは著者は、「わざと」わかりにくくしたのかも、とも思った。暗号のようにすることによって、「分かる人には分かる」ようにしたのかも知れない、と。
この本の主張について、著者は「おわりに」に次のように書いている。
ずいぶんシニカルな作文教室になった。それは、ぼくが学校空間は個性を伸ばす場ではなく、個性を殺す場だと感じているからだ。
ここだけ読めば、同著の学校論は前掲著(『学校ってなんだ! 』)と同様であるようにみえる。しかしながら同著で書かれるのは前掲著のような本質的問題解決思考ではなく、やもすると小手先の解決策にも思われかねない、生徒が学校で「生き延びる」方法に焦点が当てられている。同じく「おわりに」から引用。
そういう学校空間で、個性的な人はどうやって生き延びればいいのか。個性的でない人はどうやって生き延びればいいのか。この本で書いたことはその一点である。
そこには、学校とは鴻上氏のような個性的な人にとってだけでなく、没個性的な人(作者曰く「自分のような」)にとっても息苦しい場であることが指摘されている。そして著者は、「作文の書き方」という、きわめて表面的でノウハウ的なことを切り口に、そこでのサバイバル術を語っているである。
「個性を伸ばす」という名目で作文や読書感想文の課題が出て、実際には「人格形成」と称して、道徳を教え込んでいる。それが作文力だと呼ばれるのを、健全な教育だとは思わない。自由や個性はときとして危険なものなのだから、学校空間はそれに耐える技術を早く開発すべきだ。
自由にいきたい生徒、自由が怖い生徒。その両者が学校生活を生き延びるためにどうしたらいいのか。作文を例としながら、そのための「型」を教えているのが同著なのである。
作文や読書感想文では、学校的な正しさとしての「正解」はこういう内容だ(これを同著では「ふつう」と呼んでいる)。でも、それだけ書いても点数は取れない。ここをこう工夫をしてみれば、学校的正しさから大きく外れることなく、オリジナリティを出すことができるよ、というアドバイスがこの本では書かれているのである。
高校の時、体育で柔道を習ったことがある。そのときに一番最初は「受け身」を習った。これは、ケガをしないためである。受け身が上手に取れれば、投げ技をくらっても皮膚の表面的な痛みで済み大ケガはしにくい。その次にするのは柔軟運動だ。これも、ケガをしないために行うのは理解していただけると思う。つまり徹底してまずは「ケガをしないため」の練習が行われる。
こうした技能習得の順序はもちろん、柔道が命に関わる格闘技であるからだろう。しかし没個性な生徒にとっては、学校でいじめ・差別・特別視(「浮く」)といった、命にも関わる「大ケガ」をしないことは、最低限かつ最重要課題となる。テストの点数はその次だろう。もちろん、成績もズバ抜ければ一目置かれることになるので、そういう選択肢もあるが、現実的には難しい子の方が多かろう。
「学校改革」は、中長期的にはしたら良いと思うし、すべきことではある。そのために、それを現場からどうやって進めていけるか、あるいは政治の場でどう議論してもらうのか、という戦略的な話が必要になってくる。ただそれでは、今まさに「息ができない」生徒たちは救うことができない。
いち現場の教師としてできることは何か。学校のなかで大ケガしないために「型」を教えること。限定された自由の中で「個性」を発揮するにはどうしたらよいか教えること。そうしたことは、社会や学校に変革をもたらさないし、現状追随で大火事をバケツ消化しているだけのくだらない教育なのだろうか?
上で取り上げた二つの本では、奇しくも共通して語られることがらがある。それは、「言葉を丁寧に使おう」という主張である。
(工藤氏)差別的な言葉を用いても、「いや、心の中では差別なんてしてませんよ」みたいな言い訳が通用しちゃってるわけですよね。私はやはり、言葉はとても大事なものだという教育をしたいんです。
(工藤氏)機会をつくってあげただけでは、人はやっぱり成長しないんですよ。言葉を発することの意味を教えないといけない。
問題は、『流行語』が思考に目隠しをしてしまうところにある。最近、「多様性」が大流行だ。何を論じても、何を説明しても、結論は「多様性」である。ぼくもつい使いたくなる。こういう時には注意しなければならない。「多様性という便利な言葉を使うことで、思考停止してしまっていることが多いからである。
息苦しい学校生活の中でも、自分の言葉は手放してはいけない。それは、制限のある中での独創性をつくる上で大事なこと。それだけではなく、「自分はここにいる」という自己肯定感をなくさないため、でもあるのではないか。だからテレビ東京のドラマは、諦めずに捨てずにいたその人の「大事なもの」が見え、それが強烈な個性的魅力となって惹きつけられるのではないだろうか。
論文やレポートも限定的な「型」のなかでオリジナリティを発揮させる技が求められる。もちろん紋切り型な文句もたくさんあるが、しかしクオリティの高い論文に求められるのは、言葉を丁寧に紡いでいくことである。
型に沿って書けば、実際には9割は「書きたいこと」ではなく、「書かなければいけないこと」を決まり通り書くだけになる。しかしそれも没個性者からすれば福音で、個性が無くても大丈夫だし、とりあえずルールに沿っておけば及第点なのである。残りの1割で個性を発揮することになるが、それについても、なんでも言えるわけではなくて、9割の型通りの内容から合理的に「言えること」を書けばよい。
誰もが、世の中の大きな枠組みを疑い、突破することができる人間ばかりではない。そうした一部の天才になれなくても、「型」を学び、自分の言葉を大事にすることで、ユニークなアウトプットを産むことは誰にだって可能だ。そうした学習経験も、自己肯定感を高めるのではないのだろうか。今日も私は凡人による凡人のための教育を行っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
