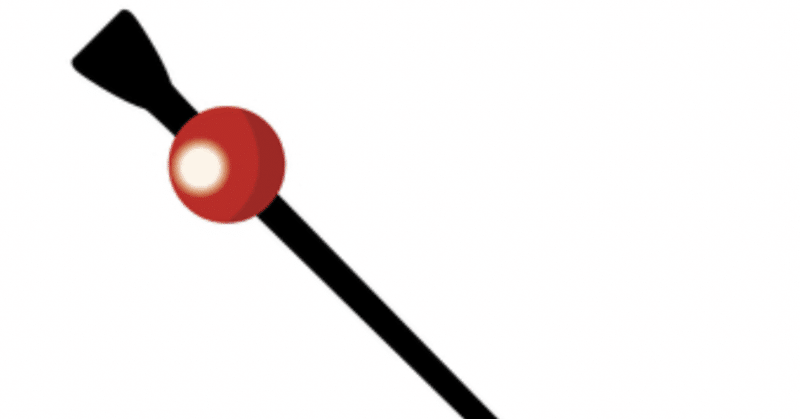
【SS】みやげもの
清掃の仕事を始めてどれくらいか。
担当場所が変わって初めてゴミを回収に訪れたそのオフィスは、夕方を過ぎたころも慌ただしく人が動いていた。
ゴミ箱をひとつひとつ回る初老の男性のことに目もくれず、パソコンに向かっている。コピーを取りに行く女性もまるで私なんて存在しないかのように通り過ぎていった。
どこもそのようなものだ。たまに廊下で挨拶をしてくれるかどうか。こうやってパソコンを使って仕事をするようなデスクワークの人たちは、身体を使う清掃業のような仕事を無意識に下に見ているのだろうと思う。
最後のゴミ箱に手をかけたとき、ありがとうございます、と声がした。顔を上げると女性が私の方を見ていた。とは言っても私と年の変わらないであろう、熟年の女性だった。
一瞬固まった。ありがとうに対する教科書的な解答はどういたしまして、だが、この場合は適切でない気がした。
いえ、のようななんともわかりにくい言葉を表情と動きで表現し、私はそそくさとその場を後にした。存在をなき者にされることに劣等感を強く覚えた割に、いざ存在を肯定されるとどうしていいのかわからないものだ。
それからというもの、そのオフィスに訪れるたび、その女性は私にお礼を言った。私は毎度なんと言っていいのかわからずに複雑な表現を顔と動きで繰り返した。
あるとき、仕事が終わる頃に違和感に気づいた。今日はありがとうがなかったのだ。そうだ、今日あの女性はいなかったんだ。それはそれで毎回浮かべる表情を変えなくて済むので軽い気持ちで仕事を遂行できたが、とはいえ物寂しさのようなものを感じていた。まあ、有給休暇ということもあるだろう。
翌日は意識をしてその女性のデスクに目を向けた。その日も彼女はいなかった。木金と休んで旅行をすることもあるだろう。ここは平日はいつも人がいるから、土日休み。ならば土日と合わせて連休を作ることもあるだろう。
彼女は休みを使ってどこでなにをしているのだろう。私と変わらない年なら家族もいるだろう。いや、もう子どもも自立したような年かもしれない。じゃあ夫婦水入らずの旅行というものか。
仕事をしている彼女しかしらなかったが、仕事を終わった後の彼女の時間というものも確実に存在していて、そこに初めて家族の影が垣間見えた。私は明らかに彼女に恋心を抱いていたわけじゃなかったが、なんとなくショックを受けた。それは、きっと彼女を自分と重ねていたからで、自分と同じように帰宅して家で一人で過ごしているのではないかといった前提をなぜか脳内で作り上げてしまったからだろう。
週明けにオフィスに向かうと、久しぶりに彼女はいた。いつもと同じようにお礼を伝えてくれたが、私はいつもよりも複雑な感情を表現してしまったかもしれない。だからそのあと彼女があっ、と声をあげたのに心当たりのようなものがあって驚いた。
私の思いとは裏腹に、彼女が差し出したのはひとつの小さなお菓子だった。どうぞ、と渡されたそれはかんざしというお菓子で、きっとオフィスの人に配った残りだったろう。
今度はわたしがありがとうを返す番だというのに、私は何を思ったか「ご旅行ですか」と聞いた。これが初めて私が発した文字だったので、こんな声だったのか、と思われたかもしれない。私の言葉には自分の複雑な心境が篭っていて、そこには幸せに過ごす彼女への当てつけも含まれていたと思う。普通の会話に化けた、攻撃的な言葉だった。
「いえ、母が倒れて地元に」彼女はそう言った。「すみません」咄嗟に謝るといえ、と彼女は笑って仕事に戻った。私はとうとうありがとうを返すことなくオフィスを後にした。
そこからはいつものありがとうございます、と複雑な表情とのラリーが続く毎日だった。毎日、オフィスでの会話を聞いていると、彼女はあまり仕事ができない人なんだということがわかった。
「ここ、間違ってますよ」「あら、すみません」
「いくつか問題が見つかりまして」「ごめんなさい」
そういった会話がよく聞こえてきた。私がパソコンをうまく使いこなすこのオフィスの人たちに劣等感を抱いていたが、彼女はそれが苦手なようだった。
彼女は子どもと一緒に旅行もしていなかったし、夫婦水入らずの旅行もしていなかった。ただ病に臥した母親のために地元に足を運んでいて、オフィスでは上手く仕事をこなせないそんな人だった。
帰宅後、彼女がどのような生活を送っているかはわからない。あのとき旅行をしていなかっただけで、家族がいるかもしれないし、子どもがいるかもしれない。だけどなんとなく、家族と過ごしていなかったことと、仕事ができないという事実が、私の心を軽くした。私はそれから一度も彼女と言葉を交わさなかった。
ある日また彼女がオフィスにいなくて、またどきりとした。一度落ち着いたはずの自分の気持ちが、また速度をつけてきた。今度こそ、彼女の幸せが見えてしまうと思った。けれどそこから彼女がオフィスに現れることはなく、彼女の存在など私の空想の上だったかのようにデスクが整えられていった。しばらくしてその虚に座った若い女の子は、他の人と同様に私を空気のように扱ったが、もはやそれが私に安堵をもたらした。
私の担当のオフィスはまた変わって、そこでもやはり誰もお礼などを言ってくれることはなかった。空いたデスクの上に、ご自由にお取りくださいというメモ付きでかんざしが置いてあるのを見つけた私は、今日は久々に母親に電話でもかけようかと思った。
もしも良いと思われましたらサポートお願いします!いただいたサポートはインプットやら活動のために使わせていただきます。
