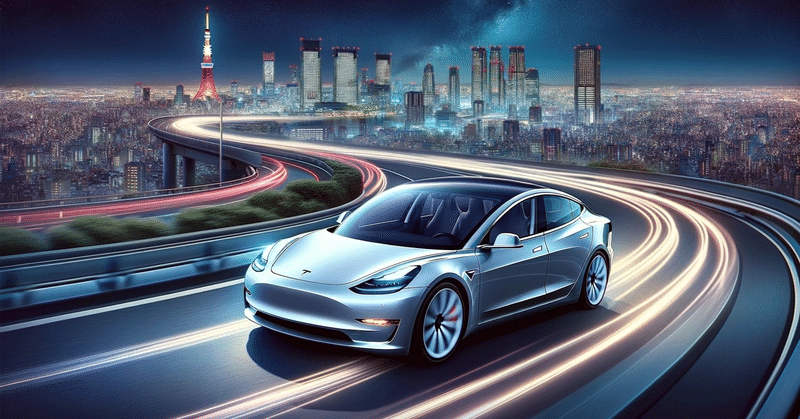
完全自動運転が実用化し、普及した社会を描写してみる 佐々木俊尚の未来地図レポート Vol.806
完全自動運転が実用化し、普及した社会を描写してみる〜〜〜「歩ける街」の楽しさから観光立国の未来は始まる(4)
3回にわたってウォーカブルシティ(歩ける街)の可能性について解説してきました。今回は、この「歩ける」という都市機能が自動運転の実用化によってどう影響を受けるのかということを論考していきます。
いまタクシーの「台数足らない」問題が大きな議論になっています。この問題は都市と地方、あるいは都市でも中心部と郊外とで温度差が大きいことに留意が必要でしょう。都心の道路を見ていれば、タクシーはたくさん走っているし、新宿や渋谷なら空車をつかまえるのも難しくありません。いっぽうで郊外に行くと、夜になればタクシーはほとんど走っていないという最適化されない状態になっているのがわかります。
地方はもっと深刻です。わたしの経験を紹介しましょう。わたしはこの10年、福井に家を借りて東京・長野とのあいだで三拠点移動生活をしています。福井では少し前まで、若狭湾沿いの美浜町というところに古民家を借りて住んでいました。中核都市の敦賀からクルマで20分ぐらい。人口9000人あまりの小さな町です。
最近は多拠点居住や移住がブームになっていますが、都会に住む人だと気づきにくい多拠点居住の問題は「現地での移動手段」です。東京や大阪から最寄り駅までは鉄道で行くにしろ、そこから先はどうするか。
美浜の家について言えば、JR小浜線美浜駅が最寄りだったのですが、歩けば20分はかかります。気候のよい時ならともかく、真夏や雪の降る時期にはこの距離はけっこうつらい。小浜線も列車の運行本数が少なく、東京からの行き来に利用するのにはかなり不自由です。駅前にはタクシーが数台いるのでこれを使って拠点にたどり着いたとしても、今度は日常生活が送れません。スーパーまで徒歩30分、ホームセンターまで徒歩20分、美味しいと評判の大衆食堂までは徒歩40分。
そこであれこれ試した結果、最終的にこういう方法を採りました。敦賀駅近くに月極め駐車場を借り、そこにマイカーの軽自動車を置いておくのです。東京から東海道新幹線と北陸本線を乗り継いで敦賀に行き、そこからこのクルマに乗れば20分ほどで拠点に到着できるというわけです。もちろん日常の買い物にも使えます。
若い都市住民には最近、運転免許証を持たない人が増えています。免許証を持っていても長年運転していないというペーパードライバーが少なくありません。東京は地下鉄や私鉄などの公共交通機関が網の目のように発達しており、高い駐車場代を払ってマイカーを維持する理由があまりないからです。
ところが地方では、よほどの中核都市の市街地でもない限り、クルマのない生活などほとんどあり得ません。公共交通機関は乏しく、路線バスはあっても1日3本しか走っていないなんていうのがザラです。新型コロナ禍はこの問題をさらに深刻にしました。タクシー運転手さんや運転代行の運転手さんが、仕事がなくなって軒並み廃業されてしまったのです。高齢の方も多かったため、コロナが昨年5月に五類移行してからももはや戻ってきていません。
近年、地方創生というスローガンのもとに自治体が「まずは遊びに来て」と移住体験施設などを作るような試みも増えています。移住人口はすぐには増やせないので、観光客よりも密接に関わってもらえる「関係人口」を増やそうという流れです。しかし交通機関の整備されている観光地以外の土地に滞在してもらおうとすると、とたんにこの「現地での移動手段」の問題が浮上してくるのです。典型的なラストワンマイル問題です。
ちなみにラストワンマイルというのはもともとは通信業界用語で、通信網を住宅などに提供する最後の接続をどうするか、という課題でした。最近は物流や交通などでもこの用語が使われるようになり、「お客さんにモノやサービスを提供するための最後の部分」を意味するようになっています。
この移動のラストワンマイルを解決する手段として、ライドシェアが注目されており、この4月からは限定的に解禁されました。正規のタクシー運転手でなくても、副業として空いている時間にドライバーの仕事ができるシェアリングサービスなので、運転手不足をある程度は担えるのではないかと期待されています。ただ、ある程度の人口のいる街では需要を満たせるかもしれませんが、過疎化していく土地ではそもそも人が少ないので、ライドシェアだけでは高齢者の買い物需要などを満たすのは難しいと考えられています。最終的な解決があるとすれば、レベル4〜5の完全な自動運転の普及しかないでしょう。
完全自動運転なら、運転免許返納を求められている後期高齢者の買い物難民問題が解決します。また自動運転車はすなわち電気自動車なので、これは現在過疎地で深刻になっているガソリンスタンドの減少にも対応できます。地方生活は多くが戸建て住宅で、電気自動車を自宅で充電するハードルも低いからです。さらに電気自動車は災害時の非常電源にもなり、電気で駆動する自動運転車は過疎地にこそ最適な移動手段になるでしょう。
さて、ここで論じていきたいのは過疎地のモビリティの話ではありません。将来に都市部で完全自動運転が実現し、無人タクシーが縦横に走り回
るようになれば、わたしたちの街はどう変わるだろうかという予測です。そしてその時に、ウォーカブルシティとしての都市はどうなるのだろうかという話です。
2024年の東京では、多くの人々が日々タクシーで移動しています。しかし先ほども書いたように都心の駅には空車が密集し、郊外にはほとんど走っていないという最適化されない状態になっています。この状態に対して、客がどこでタクシーを乗り、どこで降り、そのあいだの渋滞や道路状況はどうだったのかというようなデータをたくさん集めてAIで分析すれば、ある程度は客の乗車場所と下車場所の予測が立てられるようになるでしょう。
その予測をもとに、自動運転のタクシーを運行させれば乗車の時間待ちは減り、かなりの最適化ができるようになるはずです。これは非常に高度な都市運送システムの実現です。たとえば自宅から移動しようとしたら、スマホで呼んで数秒から数十秒で空いている無人タクシーが到着し、目的地までそのまま運んでくれるとしたらどうでしょうか。
ここから先は
¥ 300
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
