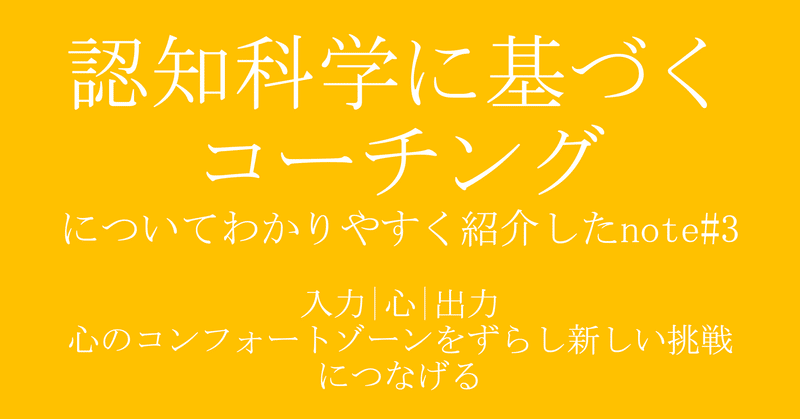
認知科学に基づくコーチング 心の作用
こんにちは!
さとしです!
今回も認知科学に基づくコーチングのアウトプットとして株式会社GOAL-Bの山宮健太郎さんの動画をまとめていこうと思います。
今回は「心の作用」についてまとめていこうと思います。
○心の作用(入力/心/出力)○

入力=世界からのインプット
例)情報/人間関係/経験/様々な出来事/環境
心=心のフィルター
例)人生において得た経験で無意識にできたフィルター
出力=心のフィルターを通して解釈した情報をアウトプット
例)検索エンジンで「〇〇」と入力して検索すると特定の情報が出てくるイメージ
経験によると〜、私は〜考えます。
この時、人は無意識に情報を入力しますが、出力する際は、心のフォルターで入力した情報を解釈するため、意識的に出力を行います。
例えば、以下のような質問を受けるとします。
例1) 日本と韓国どっちが大事なのか?(入力)
日本人=大抵が「日本」と答える(出力)
韓国人=大抵が「韓国」と答える(出力)
例2) 【日本 韓国 中国 台湾】を大事な順に並び替えてください。
(入力)例 A. 日本→韓国→台湾→中国(出力)
普段考えていなくても、無意識的に心のフィルターを通して判断することができる
選択した事実(A)自体が心のコンフォートゾーンになっています。
つまり、Aのように選択されないことは心のコンフォートゾーンから外れることになり、違和感に感じるのです。
○心のコンフォートゾーン○
前回のnoteに記述しましたが、人には自分が安心で安全でいられるコンフォートゾーンがあります。コンフォートゾーンに対して、無意識にホメオスタシス(現状維持機能)が働くことでコンフォートゾーンを維持することができます。
例1)転職し、シフト制の職からフレックスタイム制の新しい職場に行く
→普段の決められた生活リズムが変化し、新しい生活リズムになり、心がざわつく
例2)朝8時に出勤する人が朝8時に起きる
→焦る 心がざわつく なんとか遅れを取り戻そうとする
元通りの生活リズムに戻った時、心のざわつきがなくなる
大前提として、人間にはコンフォートゾーンがある
→コンフォートゾーンに対してホメオスタシスの力が無意識に働き、現状の生活を維持しようと行動する
だからこそ、新しい生活リズム、挑戦、行動の変化を求め、行動しても
ホメオスタシスのフィードバックが入る
→ホメオスタシスは良くも悪くも働く(サウナ○/新しい挑戦×)
つまり、新しい挑戦/変化をすると言うことはホメオスタシスとの戦いであるといえます。
○認知科学に基づくコーチング◯
では、どのようにしてコンフォートゾーンをずらし、新しい生活や挑戦を成功させることができるのでしょうか?
A. 認知科学に基づくコーチングをコーチが提供することによって、鮮やかにコンフォートゾーンをずらしてあげることができるのです。
具体的な理論に関しては次回のnoteで紹介させていただきます。
最後までお読みいただき、誠に感謝致します。 よろしければサポートをお願い致します!今後、プロコーチとしての活動(CTI受講料/コーチング資料購入)に活用し、みなさまにアウトプットさせていただきます!
