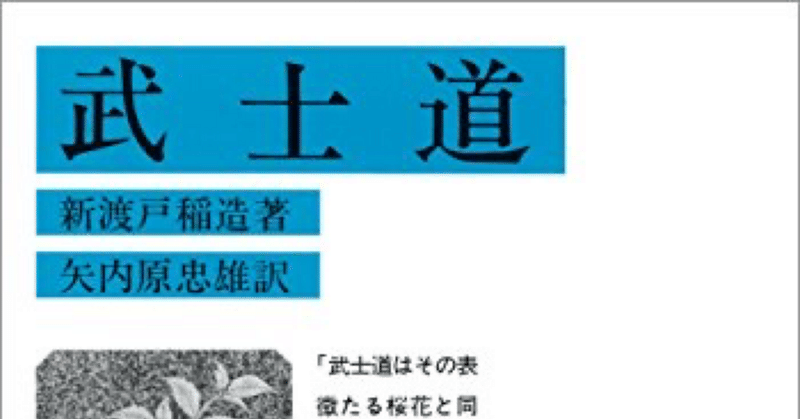
Lost Samurai─新渡戸稲造の『武士道』(5)(1993)
7 武士とキリスト教
室町時代の終焉後、17世紀ごろからさまざまな方法によって武士の存在意義は理論的に正当化され始めるが、武士道はその一つである。キリスト教も、一時期、有力な規範道徳として機能している。戦国末期から江戸時代初期にかけて、数多くのキリシタン大名が出現する。
1563年、肥前の大村純忠が最初に洗礼を受け、他には、大友宗麟、有馬晴信、高山右近、小西行長、黒田孝高、蒲生氏郷らが知られる。キリシタン大名は、ローマ字の印章や十字架あるいは聖像の旗印などを用い、領内の神社・仏閣を破却したりもしている。短期間のうちに、西日本にとどまらず、東北地方にもキリスト教徒の武士が現われている。伊達政宗は、1613年、単独で家臣の支倉常長をスペインやローマに使節として送っている。1587年、豊臣秀吉は伴天連追放令を出し、江戸幕府も1613年にキリシタン禁制を厳しくしたため、多くは改宗している。ただし、高山右近は、領地を没収され、1614年にはマニラへ追放となっても信仰を貫いている。
なお、長崎県の生月島・平戸島・五島列島・外海などの間に居住する隠れキリシタンに今日まで伝承されてきた「オラショ」、すなわちラテン語と日本語による祈祷は、世界的に見て、貴重な史料である。「オラショ」はラテン語の「祈り (orazio)」の転訛であり、特に、生月島には唱えるだけでなく、歌う「歌オラショ」がある。
反宗教改革を目的としたトレント公会議(1545~63)後の典礼刷新の中、ローカルな典礼・聖歌は200年以上続いたものを除いてすべて廃止し、カトリック教会ではローマ式典礼とグレゴリオ聖歌の採用が勧告されている。ローカルな典礼・聖歌の多くは、以降、ヨーロッパでは史料として散逸してしまい、いかなるものだったのか部分的に不明になっている。
ところが、イエズス会士による日本への布教はこの公会議と並行していたため、彼らが伝えたのはイベリア半島のローカルな典礼・聖歌であり、多くの研究者によってオラショはその失われた祈祷だと確認されている。つまり、ヨーロッパの失われた文化を知るのに、日本の伝承が助けになっている。
申し上げ
でうす・ぱいてろ
万事かないたもう
うらうら
天にまします
がらっさ
けれんど
あわれみのおん母
十のまだめんと
さんたえけれじゃのまだめんと
根本七悪
七つの善
さんたえけれじゃのさからめんと
慈悲の所作
べらべらんつらんさ
万事かないたもう
みぜれめん
御からだまき
きりやれんず
ぱちりのちり
あめまりあ
いにてすぺりんと
十五くだり
敬いて申す
十一ヶ条
ぱらいぞ
らおだて
なじょう
まにへか
べれんつす
ぐるりよざ
たっときは八日の七夜の
ぱらいぞのひらき
でうす・ぱいてろ
(『歌オラショ』)
8 士道と武士道
キリスト教をあげるまでもなく、武士が基づかなければならない道徳思想は武士道だけではない。武士道は、むしろ、非主流であり、新渡戸の『武士道』によってあたかも主流であるかのような神話が以降に形成されている。それは、江戸期、マイナーな学問にすぎなかった国学が、明治以降、国家主義ロビーによって伝統的に漢学と並ぶ地位を占めていたという不遜な歴史のパースペクティヴがつくり出されたのに似ている。かつては「兵(つはもの)の道」や「武者の習い」、「弓矢とる身の習い」という兵士として守るべき徳が説かれていたが、戦国期になると、武士は戦闘員であるだけでなく、領国や領地を治める為政者としての性格も持つようになる。
江戸時代に入ると、そうした二重性により武士道と士道が分離し、両者は対立している。前者は昔ながらの伝統を重んじる狭義の徳であり、後者はそれまでの武士の道徳を儒教によって根拠づけられたものである。江戸期の武士道論は肥前国鍋島藩士である山本常朝の談話をまとめた『葉隠』、士道論は山鹿素行の『山鹿語類』士道篇が代表している。
特に、死に関する姿勢において、両者は対極にある。『葉隠』は、「武士道といふは、死ぬ事と見付けたり」と表現されている通り、死の美学を説いている。人間の一生は短いので、つねに「死身」の奉公を心がけ、生への執着を否定すべきである。その代わり、最善の忠節は出世して家老となり、藩主の傍で奉公することである。いさぎよい死は真の奉公であり、忠義にほかならない。主従関係は情に基づいているため、殉死も衆道(男色)も肯定される。「戦後二十年の間に、日本の世相はあたかも『葉隠』が予見したかのような形に移り変わっていった。日本にもはや武士はなく、戦争もなく、経済は復興し、太平ムードはみなぎり、青年たちは退屈していた」や「われわれの生死の観点を、戦後二十年の太平のあとで、もう一度考えなおしてみる反省の機会を、『葉隠』は与えてくれるように思われるのである」(三島由紀夫『葉隠入門』)。
一方、士道は、武士道と比較にならないほど、理論的な色彩が強い。第一、山鹿素行は林羅山の門下生である。朱子学者の林羅山は徳川家康以下四代に渡って仕えた幕府のブレーンであり、大坂冬の陣のきっかけになった方広寺大仏殿鐘銘事件を引き起こし、幕府法令や外交文書の起草、典礼などにも務めた幕府の最大の御用学者の一人である。明治以前の中心的な学問は中国古典の研究であって、朱子学は学問の中の学問にほかならない。素行の士道論では、死はつねに心に置いておくべきだが、それは人間がいつ死ぬかわからないから、普段から一瞬一瞬を懸命に人倫を生きることの重要性が説かれている。
武士が為政者でいられるのはその高い道徳性にある。武士は人倫の指導者的立場にある以上、わずかなことにも礼儀を正し、他の身分の模範とならなければならない。武士の身分は道徳的優越性に基づいており、道徳的自覚のない侍はたんなる遊民にすぎない。武士が従うべきなのは道徳規範であって、主従関係において、諌言を聞き入れない主君の下にはとどまるべきではない。殉死も衆道も結果として否定される。「国鉄も一つぐらい大臣の言うことを聞いてくれたっていいじゃないか」(荒船清十郎)。
この点は、主君が諌言を聞きいれないとしても、主君の味方となるのみならず、主君の身代わりになるべきだと主張する武士道論とは決定的に異なっている。「組織の一部がやったことであり、強いて言うなら個人ぐるみです」(酒巻英雄)。武士道の思想の中心は奉公であり、士道は為政者としての正統性を語っている。
ただ、素行は儒学者であるが、最初の日本主義者の一人でもある。素行は士道を展開する際に、朱子学の抽象性を批判したため、一時期、赤穂に流されている。古学に傾倒した素行は、古代儒教の学問を通じて日本人として自覚すべきであり、日本と中国を比較した場合、むしろ、日本こそが古代儒教で理想とされる中朝であるという中朝主義を主張している。
新渡戸が士道でなく、武士道をとりあげたのは、『武士道』の中で日清戦争の勝利を武士道精神の賜物としているように、中国の影響を払拭したいからである。士道でも日本の中国に対する優越性は導き出されるとしても、あくまで中国文化の圏内にとどまっている。日本は中国からの影響関係を清算しなければならない。
また、江戸時代、庶民の道徳的基礎は吉田兼好の『徒然草』である。辻本雅史の『教育の社会文化史』によると、17世紀、商業出版が発達し、現在日本の「古典」と呼ばれる作品が出版される。『太平記』を始め、『平家物語』や『源氏物語』、『万葉集』、『古今和歌集』、『枕草子』、『方丈記』、『日本書紀』などそれまで一部の公家や僧侶しか読めなかった作品が次々と刊行されるだけでなく、その注釈本や解説書も刊行される。国学の誕生はこの出版ブームなくしてありえない。
中でも、『徒然草』は朱子学者の林羅山も『野槌』という注釈本を出していることからもわかるように、儒学や仏教、歌学、俳諧など広範囲に影響を与え、20数種の解説書が出版されている。庶民は『徒然草』を道徳の規範として読み、江戸の論語という地位を獲得している。歴史的に、道徳への寄与の点では、武士道など『徒然草』とは比較にならない。
芝居などのサブカルチャーから庶民も武士道の影響を受けたという新渡戸の主張は当時の規範に矛盾する。庶民が武士身分の道徳に惹かれたとしたら、それは秩序の解体につながりかねない。身分制の堅持が道徳の前提であるのだから、それは。
新渡戸の知識の歴史的限界をあげつらっても、陰険なだけであろう。けれども、武士の為政者としての立場の強化が藩校創設の契機になっており、南部藩士の子弟である新渡戸が慣れ親しんだ道徳はそこに基盤を置いている。江戸前期、武断政治から文治政治への移行と共に藩校が設立される。1641年、岡山藩主池田光政が創設した花(はな)畠(ばたけ)教場が最初の事例である。
全国的に藩校が設立されたのは宝暦期(1751~64)以後であり、財政危機に直面した多くの藩が幕府の文武奨励もあって、藩政改革を目的とした有能な人材を育成するために相次いで設立している。発展期には全国で255校に及び、ほぼ全藩が抱えている。この頃になると、その趣旨に応じて、人格教育から実学教育へと変容している。また、藩校の隆盛は地方文化の振興にもつながっている。こうした歴史は、現代人よりも、むしろ、新渡戸のほうが承知しているにもかからわらず、言及していない。
新渡戸は、武士道の日本的な独自性を強調し、『武士道』を次のように書き始めている。
武士道はその表微たる桜花と同じく、日本の土地に固有の花である。それは古代の得が乾からびた標本となって、我が国の歴史の押し葉集中に保存せられているのではない。それは今なお我々の間における力と美との活ける対象である。それはなんら手に触れうべき形態を取らないけれども、それにもかかわらず道徳的雰囲気を香らせ、我々をして今なおその力強き支配のもとにあるを自覚せしめる。それを生みかつ育てた社会状態は消え失せて既に久しい。しかし昔あって今はあらざる遠き星がなお我々の上にその光を投げているように、封建制度の子たる武士道の光はその母たる制度の死にし後にも生き残って、今なお我々の道徳の道を照らしている。
日清戦争に勝ったとしても、それは軍事的勝利であって、文化的なものではない。日本は東洋を代表しているわけではなく、東アジアの中国文化圏の東端にすぎない。大陸の大帝国は日清戦争まで朝貢貿易を続けている。中国は東アジア文化圏の中心であるが、それを象徴するのが皇帝である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
