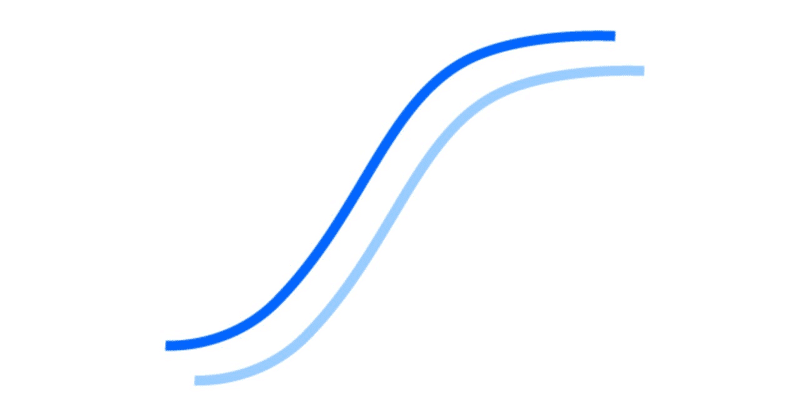
社会の中の文学(2)(2012)
第2章 ポストモダン文学以後
ポストモダン文学は、確かに、非対称線の時代をよく物語っている。1980年に発表された田中康夫の『なんとなく、クリスタル』を皮切りに、多くの挑戦的な作家が登場する。ポストモダン文学の頂点と呼べるのは清水義範だろう。彼は古今東西のありとあらゆる文章を模倣するのみならず、非常に高い娯楽性を持っている。ポストモダン文学の脱制度化・多様化・相対化の精神を最も体現している。ポストモダン文学は、モダニズムの大衆化の傾向があり、「アヴァンポップ」と呼ぶこともできよう。清水義範は作品を通じて日本語を文章から再検討することを模索している。
ポストモダン文学は何でもありのアナーキーに見えて、社会を抽象化する試みが共通している。哲学書のように必ずしもはっきりとはしていないけれど、社会に対する認識を広げる思想を語る。社会性と向き合う姿勢が認められる。
けれども、このポストモダン状況が文学の行き詰まりを招き、以後の表現者は途方に暮れることは想像するに難くない。何をしてもいいことになると、何をしていいのかわからなくなる。「何でも自由に書いてみなさい」と教師に言われて生徒が困ってしまうようなものだ。ここで書く内容と技術を分け、前者を再考する必要があったのだが、文学者は何でもありなのだからと後者に流れてしまう。社会について何を理解し、何を疑問に思い、それに関する他の意見や表現に対する自分の批判を加える。そういった社会への真摯な姿勢が見られない。
清水義範の挑戦が、実は、この段階で生きてくるはずである。彼は、文章を解体してその機能から検討・再構成することで、形式が決まると、書くべき内容が自ずと道かれることを作品で示している。内容が定まれば、その手段も見えてくる。しかし、文学者から顧みられることはない。
社会環境が激変し、漠然とした不安が社会に蔓延する。思いつきや思いこみによる恣意が表現上に横行する。外から矛盾に見えても、自分の中では一貫している。それは、激動の中、アイロニーによって自意識の優位さを確保し、心のバランスを保とうとする自己防衛策にも見える。そうした気ままで気まぐれな作品も誰かに共感されなければただ消えてしまう。そこで表現はコミュニティづくりへと向かう。システム内にエントロピー増大が進んでも、サブシステム内の要素間に相互作用が働けばエントロピーはこの内部では大きくならない。各作家・作品はコミュニティをつくり、その参加者を増やすことに存在意義を見出し始める。他のコミュニティとは、エントロピー増大が生じてしまう恐れがあるので、関係を持たないように努める。コミュニティの内と外は明確に区分される。コミュニティが発生するが、それが起点となって文学上の新たな系譜をもたらしはしない。文学は点在するコミュニティの集合体と化す。
文学作品は、こうなると、社会の抽象化ではない。コミュニティの具体化である。あるコミュニティをつくるために、文学作品が用意される。実社会に束縛されていないのだから、何でもできる。反面、それは自己完結している。社会性と向き合わない作品が数多く出現する。文学者は新たなことなど起きないと知りながら、袋小路の中を漂泊と遍歴の旅を続けることになる。
第3章 遅れてきたポストモダン文学
円城塔はこうした閉塞状況から望まれた作家である。恐ろしいほど社会・時代認識ができていない文学者たちが彼を称賛する。しかし、それは彼がレトロだと言っているに等しい。
「前衛」が時代遅れだとしても、「ジャンルの横断」という褒め言葉は有効ではないかと反論があるかもしれない。けれども、これもずれている。70年代にアカデミズムの諸領域で従来の自立した体系が行き詰まりを見せ、それを打破するために、学際的研究が本格化する。横断や越境は手段であって、目的ではない。それ自体に特に意味があるわけではない。ところが、80年代の思想・表現はこれに期待を寄せる。今日、学際的研究が常態化したため、その課題が明らかになっている。各分野で専門化・細部化・高度化も進み、学際化が進展するほど、他領域に関する知識も必要となるが、その学習はきりがない。また、特定分野の成果を一般化するには、アイデンティティを維持しつつも、汎用性が必須だが、次々に登場する用語・方法の標準化の課題もある。「協同」の困難さの克服に主眼が移っている。「ジャンルの横断」は80年代へのノスタルジーでしかない。それは円城塔が遅れてきたポストモダン文学者だと言っているだけである。
円城塔にはスタニスワフ・レムを始めとする各種のパロディが見られる。しかし、それらに必然性が読み取れない。なぜそのパロディをしているのか作者の感性的な選択以外に理由が見当たらない。横断や越境がもてはやされた80年代ならそれでもよかろう。ポストモダン文学の衰退の原因の一つに、著しく作家の感性に依存した創作が目立った点を挙げることができる。ポストモダン文学者は代表作で個性がほぼ出尽くしている。彼らの奇抜なスタイルは、概して、方法ではなく、芸風にとどまっている。円城塔はそれを繰り返している。
現在、日本語においても文章の数量分析が進んでいる。現段階では、ある程度の長さを持った文章を対象にした階層性クラスター分析などを用いた書き手の特定が主である。しかし、現代人が最も記しているのは携帯メールである。それらは、通常、短く、文章ではなく、文や語の範疇に入る。これを扱えなければ、日々やり取りされるテキストの大半が対象から外れてしまう。また、書き手の心理的な変化を分析することも今後の目標である。既存の作家のパロディであれば、コンピュータで十分可能な時代が到来しつつある。それに伴い、コンテクストへの志向が文学において今まで以上に重要になっている。パロディにも必然性、すなわち状況的理由が要る。
円城塔の作品を読むと、80年代のバカ騒ぎと浅慮を想い出し、気恥ずかしくなる。と同時に、それを無邪気に称賛している文学者を見ていると、あの意義を踏襲しつつ発展させていくことを怠り、進化していないと情けなくなる。
第4章 ロマンスの時代
円城塔は、ジャンル論で言うと、「ロマンス(Romance)」に属する。ロマンスはもう一つの世界を舞台とする。神々の物語である神話とは異なり、近代小説と神話の中間に位置する。近代以降、下位ジャンルにSFやミステリー、アドベンチャー、ファンタジー、ホラー、サスペンスなどが含まれる。歴史小説や時代小説もこのロマンスに属している。ブロンテ姉妹やウォルター・スコットなどが代表的な作家である。作者の描き出す登場人物は現実の人間ではなく、彼(女)の顕在的・潜在的意識の願望の分身、すなわちアバターであって、何かを象徴している。性格よりも個性に関心が向けられ、小説家がこの点で因習的であるのに対し、ロマンス作家は大胆である。作品の傾向は内向的・個人的であり、扱い方は主観的で、願望充足がこめられている。時折、情緒的でさえある。社会の抽象化ではなく、作者の願望の具体化がロマンスの役割である。登場人物は複数の世界を渡り歩く選ばれた者であり、しばしば英雄的・超人的であるが、精神的な深みに乏しく、作者の操り人形にすぎないことも少なくない。構成は慣習的で、秩序立てられ、安定している。元の世界への帰還という目的に向かって話が展開される円環構造をしている。そのため、始まりに終わりが提示されていることも少なくない。すべての要素はそれを実現するために従属している。作者にとって、曖昧なものや無駄なもの、意に沿わないものは除外され、ただ因果関係が叙述される。ロマンスは読む側に負担が少ないため、最も読者を獲得しやすい。ただ、願望を優先させるあまり、恣意的に書いてしまうこともあり、ばかばかしいほどの不適切に溢れていても、その願いに共感する読者は無批判的に受容する。ロマンスの短編形式は「お話(Tale)」である。
ロマンスの基本型は主人公が複数の世界を漂泊・遍歴し、最後に元へ戻ってくる円環構造である。設定を変えることで多様な物語をいくらでも生み出すことができる。中心的人物の性格や人数、彷徨い方、また世界の特徴や数、その関連性、さらに下位ジャンルの組み合わせなどを変更するだけで、物語を量産することが可能である。オブジェクト指向プログラミングのカプセル化・継承・多様性などの発想を物語の構造に応用するというのも一つの手である。これは巨大なプログラムを複数のプログラマで作成するのに適しているので、取り入れれば、壮大で複雑なロマンスが構築できるだろう。入れ子や再帰も使えるのだから、そのシステムの可能性は広がる。
世界的に、こうしたロマンスの応用作業が新しい文学の創出だという誤解が生じている。それは手段を自己目的化しているにすぎず、文学の袋小路を示しているだけで、刷新ではない。20世紀文学を支配したのはエドガー・アラン・ポーだと言ってよい。彼はロマンスの下位ジャンルのイノベーションを行っている。彼にとって、その企てはあくまで手段である。『盗まれた手紙』に端的に示されているように、人間の認知とは何かという根源的な問いがある。それに対し、今の動向は課題を持たないまま、下位ジャンルの創出が自己目的化している。文章は形式によって大枠が決定される。形式を刷新しない限り、文学的革新はない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
