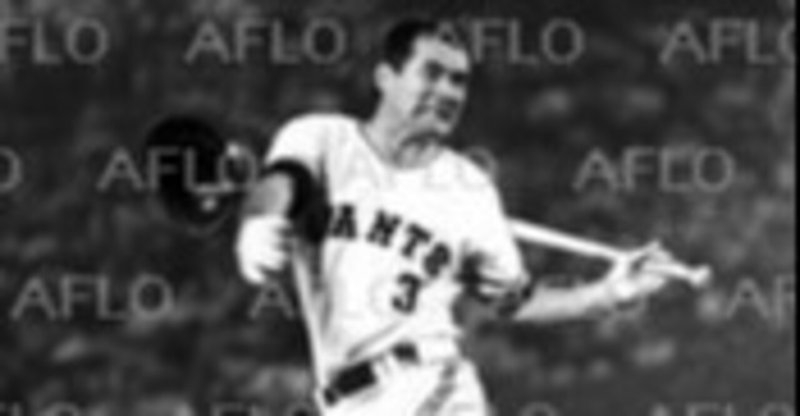
生きられた超人─長嶋茂雄(8)(1992)
註
(1) 当初、ピッチャーは腕を腰から上にあげてボールを投げることが禁止されている。一八六七年、変化球--カーブ--が投げられるようになり、八三年にサイドスロー、八四年、オーバースローが許可され、スピット・ボールも許される。スピット・ボールは、ボールを素手以外の部位で擦ってツルツルにしたり、ボールに傷をつけたり、唾液やワセリンなどの異物を擦りつけて鋭い変化を与える投球のことである。島秀之助は、『プロ野球審判の眼』の中で、アメリカ滞在中の一九三一年に見たスピット・ボーラーを次のように記している。「投手板上でグラブの中へボールを包むようにかくして、顔を近づけてかじるような格好をして唾液を塗る投球準備動作中の様子は、今までに見たこともないだけに奇異の眼を見張ったものである。相当量塗るらしく、投球した瞬間に唾液が飛ぶこともあったし、太陽光線を受けて時に光ることもあったように思った。打者の近くへ来て球に鋭く曲がったり落下したり変化するため、打者にとっては非常に打ちづらいようであった」。ベーブ・ルースもスピット・ボールには非常に手こずったという。一九一〇年代後半、スピット・ボールは条件的に禁止される。その条件は、それまでスピット・ボールを投げていたピッチャーは登録し、彼らだけは従来通りの投球を認めるというもので、スピット・ボーラーの自然消滅を狙っている。スピット・ボールが禁止された理由はカール・メイズ事件がきっかけである。一九二〇年、ニューヨーク・ヤンキースの投手カール・メイズの投球がクリーブランド・インディアンスのレイ・チャップマン頭部当たり、彼が死亡する。その際、メイズも利用していたスピット・ボールが問題視されている。なお、この事件以降、ボール交換の習慣も始まる。それ以前は、汚れようが傷つこうが、グラウンドにある限り、ボールは好感されていない。ただ、今日でもアメリカではスピット・ボールを投げている投手は多いようである。例えば、三百勝投手ゲイロード・ペリーにいたっては『私とスピット・ボール』なる本まで出版している。そういう歴史を経ているためか、日本では直球と変化球、アメリカにおいては速球と変化球という区分になっている。スライダーやシュートは日本では変化球だが、アメリカにおいては速球に分類されている。日本でも球威の衰えたベテラン投手がスピット・ボールを使っているけれども、現役の間、プロの技術として誇ってよいはずなのに、真のファンが少ないという不幸な環境のため、彼らがこのことに関して口を開くことはない。
(2) 九四年に日本プロ野球初の二百本安打を達成したイチローのバッティング・コーチとして知られる新井宏昌は次のように述べている。「名球会に入ってらっしゃるような方と自分とじゃバッティングに対する価値観が違うような気がするんです。僕はその日4打席あったら4打席、全部バットの芯で打ちたいというバッターなんです。たとえば4打席1ポテンヒットよりも、4打席全部いい当りのアウトの方が満足できる。僕のバッティングの基本は来たストライクをとにかくバットの芯で捉えること。バッターボックスというのは、送りバントやエンドランのサイン以外はすべて自分の自由にできる場所のことでしょう。だったら僕は自分のバッティングを思う存分楽しめればそれでいい。ヒットは楽しみの延長線上にあるものだと理解しています」。こうした発言は新井が長嶋以後の野球を理解していることを示している。名球会を長嶋以前の野球のアナクロニズムの極みと笑い飛ばさなければならない。新井はボールを解剖してバッティングのコツをつかんだと言ったり、バットの芯にマジックで目を描いて打ったりするなど、風貌に似合わず、ユーモラスである。それを見たあの偉大なレロン・リーも真似をしたが、空振り三振をしてベンチに戻った際、目薬をバットの目にさしていたのは楽しい。九六年のベイスターズの斎藤隆は、その意味で、素晴らしい。この豪球投手は、セ・リーグにおいて、一試合の平均も含めて奪三振王、被安打率は最小でありながら、与死球王で、本塁打配給王という最も印象深い記録を残している。こういう破天荒な選手こそ愛するのである。
(3) 「野球害毒論」とは、玉木の『プロ野球大事典』によると、東京朝日新聞に連載された「野球と其害毒」のことである。執筆者としては新渡戸稲三らがいる。それから四年後、同じ朝日新聞は全国中等学校野球大会を開催するにあたって、「野球害毒論」を否定するための自己欺瞞的な社説を掲げ、さらに、大会で試合前にホームプレートをはさんで礼をするという汚らしい儀式を制定したりなどして、野球の道徳的意義を極めて反動的に強調し、その病的な弊害は今日においてもなお続いている。
一七四四年、ロンドンで発行された『小さなかわいいポケットブック』には、「ベースボール」という言葉が使われている。野球は、アメリカに渡ってから、都市の住民の娯楽として楽しまれている。最初は、上流階級の楽しみだったものの、街中で行われていたため、窓のガラスを割るなどのトラブルがあり、野球発祥の地という伝説があるクーパーズタウンにおいては、タウンボールと呼ばれていた野球が禁止されたほどだ。ニューヨークの消防士で銀行員のアレキサンダー・カートライトがルールを編纂する。一八四六年、ハドソン川をはさんでマンハッタンの向こう側にあったエリジアン・フィールドで行われた史上初の野球の公式戦で、最初の野球チーム、ニューヨーク・ニッカボッカーズはクリケットのチーム、ニューヨーク・ナインに二三対一でボロ負けする。ところが、この試合によって、ニューヨークで野球ブームに火がつき、多くの球団が設立される。野球へのスポット・ライトの中心がニューヨークであるのは、このためでもある。チームは、主に、職業別によって編成されている。職業が問われなくなるのは、プロ化、すなわち選手に給料が払われるようになって以降である。一八五八年、全米野球選手者協会が結成され、アマチュアリズムを掲げる。「選手者」という言葉が使われているのは、まだ統一化・標準化された野球という概念が形成されておらず、ゲームの数だけ野球のルールがあるという状態だったからである。あるゲームでは帽子での捕球が認められているが、別のゲームではそれが禁止されているという有様である。組織によって統一ルールを決めるようになって以後、「プレーヤーズ」が使われる場合、オーナーに対する労働者という意味になる。ゴルフが民衆の娯楽から紳士のスポーツと変わったのとは逆に、野球は、徐々に、上流階級の気晴らしから「国民的娯楽」になっていく。ちなみに、アメリカで長らく上流階級のスポーツの地位にあったのはフットボールである。
野球は、南北戦争をきっかけに、全米中に広まる。従軍した兵士が野球を故郷に持ち帰ったからである。一八六九年、ハリー・ライトがつくったシンシナティ・レッドストッキングスがプロ球団を宣言して旗揚げすると、プロ化が進む。ハリーは新しい産業を起こし、雇用を生み出している。しかし、次第に、賭が横行し、相場師が手を出し始め、野球の人気は低下する。一八七六年、人気をとり戻すために、ナショナル・リーグが結成され、ウイリアム・ハルバート会長は選手の保留条項を設定する。FA制度はこの保留条項に対する反発である。ナショナル・リーグは中産階級以上が観客であり、一八八二年に中西部の球団が結成したアメリカン・アソシエーション・リーグは、料金が安く、日曜日も試合を開催し、客席での飲酒が認められていたため、労働者階級が足を運ぶ。一九世紀では、ブルジョアやプロレタリアートといった階級概念が中心で、家族という概念は、階級概念が崩壊し、大衆の世紀になってから見出された概念である。このころ、多くの黒人選手がリーグに在籍していたが、一八八四年、紳士協定によって、締め出される。経営者側の横暴さに耐えかねて、一八八九年の一年間だけ、大学で法律を学んだジョン・ウォードを中心に、選手の自主運営によるプレーヤーズ・リーグが存在している。一八九一年、ナショナル・リーグはほかのリーグを吸収し、大リーグを宣言する。だが、一部のチームの一方的な勝ち、選手の乱暴なプレーやスキャンダル、オーナーの拝金主義的経営により、恐慌が起こったこともあって、野球の評判は著しく悪化する。一九一九年のワールド・シリーズの八百長により、「シューレス」ジョー・ジャクソンを含む八人の選手が追放されたブラックソックス・スキャンダルも、結局、このオーナーの横暴が原因である。いくら活躍して、観客数が増しても、オーナーは選手に安い報酬しか支払わず、選手が逆らうと、トレードや解雇にしている。
二〇世紀に入っても、野球は都市のスポーツとして酒やギャンブル、いかさまの中で育っている。行儀の悪い荒っぽいものだ。スタンドの観客の喧嘩沙汰、荒れるゲーム、選手と経営陣の反目、八百長疑惑など問題が山積みしている。一九〇八年に、フロリダ州ウェブスター市では、市長が許可した場合を除いて、野球を禁止するという野球禁止条令が施行されていたほどだ。アメリカン・リーグの会長バン・ジョンソンは「家族で見にこれる健全な雰囲気の娯楽」を公約にしていたが、それが実現するのは、ベーブ・ルースがニューヨーク・ヤンキースで活躍する一九二〇年代になってからのことである。先に引用したデューイの『経験としての芸術』も、彼がニューヨークのコロンビア大学の教授だったころの作品である。
黒人たちも二〇世紀になると自分たちのプロ・リーグ、黒人(ニグロ)リーグを結成する。スチュアート・フレックスナーは、『アメリカ英語事典』において、「南北戦争後、black は奴隷時代の遺物として嫌われ、黒人は一八八〇年代後半までcolored という言い方を好んでいる。しかし、一八八〇年代後半から一九三〇年代までは、negro の方が好まれている。一九二〇年代からはNegro とNを大文字で書いた」と説明している。黒人リーグはポスト・シーズンに大リーグのメンバーと対抗戦をして勝ちこすなど、大リーグに勝るとも劣らない実力・人気を示している。ちなみに黒人リーグの選手は一九二七年、三二年、三四年の三度来日し、ハーレム・グローブ・トロッターズばりのプレーを見せている。島秀之助や佐山和夫を除くと、日本の野球史に関するほとんどの著作はこの出来事を無視している。さまざまな苦闘の中、ジャッキー・ロビンソンの大リーグ・デビュー以降、選手を大リーグにひきぬかれ、黒人リーグのチームは一九六〇年までにすべて消滅する。
(4) 戦前の職業野球で華麗な守備で人気を博した名ファーストである中河美芳は特高につけ狙われていたし、近藤貞雄は憲兵に殴られている。しかし、今やプロ野球界が最も保守的かつ反動的な考えの持ち主の住みつく世界の一つになっているのは、職業意識の欠如と言うほかない。体育会的なるものは滅びなければならない。
(5) タイトルが個人によって表彰制度として確立されたのは、本塁打王だけではない。一九六四年、オールスターまで四割で独走した歴代二位の通算五九六盗塁を記録している南海ホークスの広瀬叔功によって、盗塁王がこの年から連盟表彰になる。盗塁は、日系二世の山田伝やウォーリー与那嶺らによって、戦闘的なプレーとして持ち込まれてはいたが、それまで日本では評価されてはいない。なお、日本では、打撃三冠のうちのいずれかと盗塁王を同時に獲得したのは、このシーズンの広瀬と九二年の佐々木誠、九五年のイチローの三人だけである。大リーグではホームラン王と盗塁王を同時に記録するパワーとスピードをかねそなえたプレーヤーはウィリー・メイズなどいるが、本塁打王をとったことのあるプレーヤーで盗塁王になったことがあるのはただ一人、ライオンズ時代の秋山幸二だけである。九一年のシーズン、秋山に四冠王(イースタン・リーグでは、七七年にジャイアンツの庄司が記録している)の期待がかかったが、残念ながら、無冠に終わる。また、九五年に、イチローも惜しいところで、ホームラン王に届かず、三冠にとどまる。大リーグでも四冠王に輝いたのはタイ・カッブが、ホームランが評価されなかった時代の一九〇九年に、記録しているだけである。
(6) それゆえ、「一球入魂」や「球けがれなく道けわし」などというイデオロギーを標謗した数多くの野球漫画を書いた水島新司は、やはり、日本野球を歪めた張本人の一人として断罪されてしかるべきである。水島がそれ以前の野球漫画のアンチテーゼだった意義は認める。しかし、反宗教的・反省主義的野球こそ長嶋の目指すところなのに、彼は反動的にふるまっている。多くの日本の野球選手は水島のマンガを見て育ってきたことは確かである。だが、彼のマンガは勝つことや打つことが中心となっており、そこには美しい敗北であるとか、美しい三振といったものがない。『ドカベン』が人気を博したのは三振王岩鬼の存在のためにほかならない。唯一の例外は、長嶋を目標とする真田一球を主人公にした『一球さん』であるが、野球を知りつくした長嶋に対して、まったく知らない一球さんを主人公にするという・アイロニーをルサンチマンの解決法としてしまっている。そのため、あるがままの肯定によるルサンチマンの克服という真に長嶋的問題には至っていない。
そもそも『野球狂の詩』で、水原勇気の投げるドリーム・ボールは、その変化に対して、握りがおかしい。ゆれながら一度浮き上がって落ちるようにしたければ、縫い目に指をかけないでボールを指の股からぬき、無回転で投げないと、ゆれる変化が起きない。ほかにも、山田太郎のキャッチしたあとにミットを動かすスタイルでは、ストライクをボールにされかねないのに、水島は「山田のキャッチングでストライクをもうけた」などと書いている。大リーグでは、ボールをとったらミットを動かさず、それを審判に見えやすくし、小指がストライク・ゾーンにかかっているようにするのが基本である。こうしなければ、カンニングと見なされ、すべてボールと判定される。スワローズの古田敦也は動かす癖が時々出て、審判からはこの点は評判が悪いが、監督の野村克也も現役時代そうだったから仕方がないのかもしれない。プロ野球選手にもさまざまなヒントを与えてきた水島だけれども、『一球さん』でも、投球を速くするために鉛のボールを投げるトレーニングを平気で描いてしまうのは、あまりにもいただけない。率直に言って、あれほどプロ野球関係者との交流があるのに、不思議なことに、不備を挙げればきりがない。
実は、現在のキャッチャーミットはファーストミットの変種である。かつてのキャッチャーミットは人差し指の付け根で捕球するタイプだったが、これはすでに絶滅している。今は小指と親指でつまむように捕球するタイプで、ファーストミットから進化したものだ。すべてのグローブの中でファーストミットが最も捕球しやすいとわかったからである。大リーグで、ナックルボーラーの登板の際、キャッチャーがソフトボール用のファーストミットで守っているのはそのためだ。道具の革新は格好にも影響を及ぼす。昔のキャッチャーは左肘を下に向けて構えていたが、現代は左腕を水平にして投球を待っている。今の選手が人差し指をグローブの外に出しているのはそういう設計だからである。
(7) 試合開始状態を保存することを目的とする守りを中心とした野球が地味になるのは当然である。こうした野球はわかる人にはわかるだけ、すなわち特定多数にのみアピールするにすぎず、反動であり、長嶋以後の野球とは言えない。勝つ野球はおもしろい野球と違うのかという疑問がV9時代のジャイアンツのON以外の元選手たちから投げかけられているが、むろん、勝つ野球はおもしろい野球である。勝つ野球と彼らが呼んでいるのは、実は、負けない野球にすぎない。彼らは、勝つことはONがやってくれるから、負けないことをしていればよい。だが、ファンは負けない野球を見にボール・パークに足を運ばない。負けない野球とは守りの野球であり、宗教の野球である。犠牲(=生け贄)バントは、その名の通り、アニミズム的儀式と化している。この呪術性が日本の野球の自由主義化・個人主義化を妨げている。負けないという否定語ではなく、勝つという肯定語のもたらす意欲的・反宗教的力強さをファンは望む。森祇晶が、ライオンズの監督時代、バントを使うとブーイングが起こったのに対して、ボビー・バレンタインがマリーンズを率いて、バントを多用しても、誰も非難しない。負けない野球は、フランチャイズ制がしっかり確立していないために、はびこっているのだ。東京ジャイアンツの総監督三宅大輔は、一九二五年に発表した『野球』において、「日本では必要以上にバントが濫用されている」と批判している。こういう記述を目にすると、日本の野球はいったい何なのかという絶望感に襲われるのも当然であろう。クリーブランド・インディアンス、セントルイス・ブラウンズ、シカゴ・ホワイトソックスのオーナーとして、画期的なファン・サービス──背番号の上に選手名をつけさせたり、ホームチームの選手がホームランを打つとスコアボードから花火が打ち上げられたりなど──によって、いずれの球団でも観客動員を確実に増やしたことで知られるビル・ピークは次のように言っている。「誤解しないで欲しいんだがね。私はチームが勝てもしないのに催し物をやればお客が入るなんて言ったことは一度もないんだよ。ファンの心理ってそんなもんじゃない。ファンはホームチームと一体になって、地元チームが勝つときは、自分も勝ったと思う。生活のいらだたしさから逃れるんだ。私が関係した球団は勝ったからこそお客が入ったんで、催し物だけじゃお客は呼べませんよ」。結局、チャリティーやボランティアに関する認識不足があの不毛な考えを日本のプロ野球関係者が払拭できない原因である。「福岡のドリームゲームのときなんですよ。メジャー出身の選手たちはまったく疲れた姿を見せないんです。フランコにそれで“なんでですか”と聞いたんです。そしたら、そんなこと、なんで聞くのかって顔をされてしまいました。ファンにアピールするという前に、チャリティーに関しての考え方が違うんですね。野球でこれだけいい思いをしているのだから、野球で社会還元をするのはあたり前だろという感じです。阪神大震災のチャリティーと言えば、僕らの地元のためじゃないですか。僕がもっとがんばらなけりゃいけないとそのとき、思いましたよ。だから、少しでも自分をアピールしようと、バックホームの遠投をしたり、盗塁もしました。そうじゃないと、外国選抜チームに対して失礼だと思いましたからね。そういう意味で、僕らに比べたら、まだまだメジャーの人たちの懐の深さを感じます」(イチロー)。一九六九年七月九日の対カープ戦で史上最高のホームスチールを決めたアトムズの武上四郎は、後に、コーチとしてサンディエゴ・パドレスのナ・リーグ制覇に貢献している。その武上を長嶋はコーチに招聘する。従って、長嶋采配非難は呪術への回帰にすぎない。
一九七四年のW杯西ドイツ大会で、美しいあのジャンピング・ボレーによって「空飛ぶオランダ人」と呼ばれ、「トータル・サッカー」の象徴だったヨハン・クライフは、一九九八年六月八日付『朝日新聞』夕刊において、サッカーは美しくなければならないと次のように述べている。
「サッカーは美しくなければならない。美しいというのは、攻撃的でテクニックに優れ、3点、4点とゴールが生まれ、緊張感があり、見て楽しいサッカーだ。プロフェッショナルである以上、勝利は重要だが、美しいサッカーを追及していけば、当然勝つ可能性も高まる」。
試合では、神を相手にするわけではないから、当然、誰かがミスをする。そのミスを待っていれば、少なくとも、負けることはない。勝敗にこだわれば、勝負は、必然的に、負けない態度のほうが好結果をとれることになっている。けれども、負けない姿勢は、実は、歴史的に見て、後継者を生めない。力への意志が足りないのだ。歴史は勝つ姿勢を必要とする。勝つ姿勢は神を相手にすることを前提にしているからである。チェスの天才、ボビー・フィッシャーは、神とチェスを勝負したらどうなるかと尋ねられて、「自分が先手なら引き分けだ」と答えている。勝つ姿勢のそうした過剰さが後継者を持てる。ところが、たいていの後継者たちは原因と結果をすり替え、勝つ姿勢を負けない姿勢へとねじ曲げる。負けない姿勢というルサンチマンを勝つ姿勢という健康的な姿へと再創造することが求められる。だから、敗者だけが創造者となりうる。 七四年大会の決勝戦で、オランダは開始一分にクライフが倒され、PKで先制したものの、ベッケンバウアー有する西ドイツに逆転負けする。けれども、クライフは「いつものわれわれなら、2点目、3点目を取りにいくのに、守りに回ってしまった。美しさが足りなかったから、負けたわけだ。しかし、私はいまでも、W杯の優勝と最優秀選手賞のどちらを選ぶかと聞かれたら、迷わず、世界で一番魅力的なサッカーをした選手に贈られる最優秀選手賞が欲しい、と答える」と言っている。醜い日本人は敗因を決して「美しさが足りなかったから」と認めない。日本にはあまりに美しさが足りない。すべての、そうすべてのスポーツにたずさわるものはこのクライフの言葉に従わなければならない。これはスポーツに限らない。美しさは力への意志がもたらすものなのだ。
これはプレーヤーに限らない。スポーツに関する作品はそれ以上にひどい状態にある。大きく、故山際淳司に代表される人間ドラマ的表現と二宮清純に代表される実証主義的記述にわかれる。前者は担当記者や友人としての視点であり、後者はオタクからの視線に近い。その功績や意義を十分に認めるが、この対立が思想史にはよくあるのを知っているので、次に進みたいと考えている。前者が後者の方法論よりも先に登場したのは、コンピューターが発達するまではそのアプローチを試みようにも不可能だったからである。前者は社会現象としてスポーツを理解するファンであり、後者はマニアとしてのそれであるとしても、両者とも目の前で繰り広げられるスリリングなプレー自体からその歴史的価値を読みとることのできるファンから書かれたものがない。彼らはスポーツについて書いているかもしれないが、スポーツをするように書いてはいない。そこには文化としてのスポーツという認識が欠けている。彼らには歴史がないのだ。言葉は肉体に訴えるはずなのに、彼らの作品を読んでも、疲れもしなければ興奮もしないなど肉体がまったく無反応であるのに憤りを覚えずにはいられない。力への意志による解釈がまったく起こらない。長嶋はONについて語るとき、王が対象としての長嶋個人と自分自身に言及するのに対して、その関係に着目する。長嶋は、この関係へのまなざし、力への意志により、審美主義から遠く離れている。日本のスポーツ・ジャーナリズムは長嶋からこの姿勢を学ぶべきである。一方、アングロ・アメリカにおけるスポーツに関する作品はそれが前提になっているのである。フロレンティン・フィルムズが九四年に作制した『大リーグ─もう一つのアメリカ史─』はその典型である。九二年にカナダのトロント・ブルージェイズがワールド・チャンピオンになり、優勝旗は国境を渡る。閉鎖的で偏狭な日本人はこんなことを許さないだろう。すべてが忘れられたとしても、あの光景を決して失うことはないのだ。長嶋やイチローを文化財に指定したいくらいなのである。長嶋やイチローによって人々のプロ野球に対する態度が変わったからである。プロ・スポーツはアマチュアに先行している。アマはプロへの対抗として生まれたが、それはナショナリズムへとつらなっている。アマが非難されなければならないのはこれらの点にある。しかし、その批判にはユーモアを用いる。二〇〇〇年のシドニー・オリンピック水泳の主役は、オーストラリアの若き天才スイマー、イアン・ソープではない。主役は「オリンピック史上最も遅いスイマー」である。赤道ギニアのエリック・ムサンバニは、残り二人がフライング失格したために、男子100m自由形予選一組を一人で泳がなければならない。溺れているのではないかともがくような泳ぎで、もしかしたら足をついてしまうのではないかという不安の中、彼は世界中の声援を受けながら、泳ぎきる。タイムは1分52秒72で、200m男子自由形の世界記録より遅い。観客にスタンディング・オベーションに応えた後、押し寄せた世界中のメディアの質問に対して、片言の英語で、エリックは答ええる。それによると、赤道ギニアの水泳連盟が半年前に発足したばかりで、競泳人口は彼を含め八人しかおらず、国内にプールはリゾート用の20mプール二つしかなく、それも観光用のため、ほとんど使えず、彼自身100mを今回初めて泳ぎきったということだ。それを聞いて、エリックに対して、さまざまなスポンサーから水着・ゴーグルの提供、さらに金銭面の援助が申し出がなされている。同じく赤道ギニアのポーラ・ボローパも、エリック・ムサンバニ同様のウナギ泳法で、女子自由形50mの予選を泳いでいる。彼女は、女子サッカーの選手で、オリンピックに参加をするため、突然、白羽の矢がたてられたらしい。彼女に対しても、エリックと同じようにスポンサー契約の話が舞いこんでいる。「人生に遅すぎるということはないでしょう。私もアテネ・オリンピックを目指しますよ」と言っている。商業主義への批判は、そのユーモアによって、商業主義を追及することによって、真に可能になる。アマ・スポーツはこのようにしてとっとと滅びねばならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
